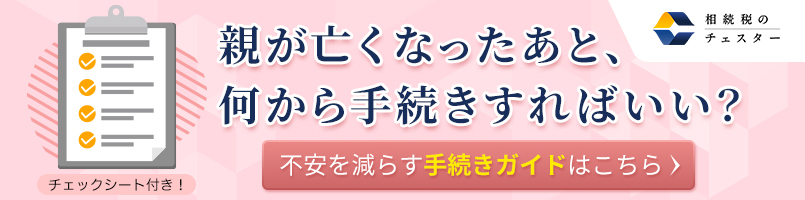四十九日法要を自宅で行う際に用意するもの一覧!マナーや注意点も紹介

四十九日法要を自宅で執り行う際、事前に用意するものに悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、自宅での四十九日法要で用意するものや法要におけるマナー、注意点について詳しく解説します。故人を偲び、心を込めた法要を行うために、準備リストをご活用ください。
四十九日法要とは

四十九日法要とは、故人の死後四十九日目に行われる追善供養です。四十九日法要は、故人が極楽浄土へ行けることを祈る仏教儀式であり、遺族にとっては日常生活に戻るきっかけとなります。
四十九日は故人の魂がさまよう期間です。七日間ごとに審判が下り、最終日の四十九日に魂の行き先が決まるとされています。
また、四十九日間は「忌中」と呼ばれ、お祝い事や遊興を避けて、故人が成仏できるように祈る期間です。四十九日法要が終われば「忌明け」となり、遺族が通常の生活に戻れる節目となります。
なお、四十九日法要の日程は通常、命日を一日目と数えて四十九日目に設定されますが、遺族や参列者の都合で前倒しになることも少なくありません。日程を変える場合は四十九日よりも前の日に行います。後ろ倒しにすると故人が成仏した後に法要を行うことになるためです。
四十九日法要の主な流れ
四十九日法要の一般的な流れは以下の通りです。
四十九日法要の流れ
- 開式
- 読経・焼香
- 法話
- 閉式
- 会食
自宅で行う場合も基本的に同じ流れですが、規模や参列者の数によって簡略化されることもあります。
四十九日法要を行う場所
四十九日法要の場所には、特に決まりはありません。通常はお寺や葬儀社等の式場で行われますが、自宅で執り行うことも可能です。参列者の数やお寺との付き合い、家族の意向など、さまざまな事情を考慮して選ぶとよいでしょう。
例えば、参列者が多い場合は式場やお寺で行うのが一般的ですが、少人数の家族や近しい親戚で集まりたいという理由で自宅が選ばれることもあります。
四十九日法要を自宅で行うメリット・デメリット

自宅での四十九日法要には、メリットとデメリットがあります。両者を比較しながら家族で相談し、最適な選択をしましょう。
メリット①コストを抑えられる
自宅で四十九日法要を行うことで、お寺や式場を借りる費用を節約できます。お布施や食事代などの必要経費は別途考慮する必要がありますが、会場費や葬儀社への人件費が不要となり、経済的な負担が軽減されます。また、自宅であれば会場探しの手間もかかりません。
メリット②慣れ親しんだ場所で故人を供養できる
故人の思い出が詰まった自宅で、リラックスして法要を執り行えることもメリットです。葬儀社の式場やお寺といった慣れない場所での四十九日法要は、時間が決められていることもあり、緊張が続いて終わる頃には疲れてしまうこともあります。
自宅は人目や時間を気にせず過ごせるため、遺族と参列者が故人の思い出を楽しく共有できる法要となるでしょう。
メリット③ 菩提寺がなくても法要を執り行える
菩提寺とは、ご先祖のお墓があり、法要の依頼やお墓の管理など仏事全般を相談できる寺院のことです。菩提寺がない方がお寺で法要を行おうとすると、どこのお寺にお願いするかと悩むことにもなりますが、自宅で行う場合は菩提寺がないことを気にする必要がありません。僧侶の派遣サービスを利用すれば、菩提寺の有無を気にせずに故人への供養を進められます。
デメリット①準備や片づけに手間がかかる
自宅で四十九日法要を行う場合、用意や片づけを全て自分たちでしなければならないことがデメリットです。座布団の用意やお供え物の設置、撤収、掃除など準備から片づけまでを家族で行うと、相当の労力と時間がかかります。
デメリット②駐車スペースが足りないことがある
自宅で法要を行う場合、参列者の駐車場の確保が課題となることがあります。特に、多くの親族や友人が参列する場合や、遠方から来る参列者が多い場合は注意が必要です。参列者の人数や交通手段を踏まえて、自宅で行うべきかどうかを検討しましょう。
デメリット③納骨の際は移動が必要となる
四十九日法要が終わった後に納骨を行うことが一般的ですが、四十九日法要を自宅で行うと、納骨の際にお墓へ移動しなければならないことがデメリットです。お寺で法要を行うと、法要後にそのまま納骨を行えるため、参列者の負担となりません。お寺が遠方の場合、四十九日法要と納骨を別日にすることになれば、二日分の予定を確保する必要があります。
自宅での四十九日法要に向けて用意するもの

自宅で四十九日法要を行う際に用意するものには、大きく分けて「必ず用意するもの」と「必要かどうかを家族で判断するもの」があります。以下の一覧を、自宅での四十九日に用意するもののリストとしてご活用ください。
必ず用意するもの
- 仏壇や仏具
- 仮位牌と本位牌
- 遺骨と遺影写真
- 座布団
- お布施
- 香典返し
必要かどうかを家族で判断するもの
- 食事
- 引き物
- お供え物
それでは、それぞれの項目を詳しく説明します。
必ず用意するもの
以下は、自宅で法要を行う上で必ず用意するものです。事前に確認し、計画的に用意を進めましょう。
仏壇や仏具
仏壇と仏具は、自宅の四十九日法要までに用意するものです。四十九日法要では、葬儀後に設置した仮祭壇をそのまま利用できますが、法要後に仮祭壇に祀ってあるものを仏壇へ移動させなくてはなりません。また、仏具は自宅での法要中に使うため、予め用意しておく必要があります。
仏具として最低限用意するものは、線香を供える「前香炉」、ロウソクを立てる「灯立て」、音を鳴らす「おりん」です。
仮位牌と本位牌
仮位牌と本位牌も、自宅での四十九日法要に必ず用意するものです。位牌とは故人の戒名や没年月日などを記した木牌で、故人の魂の依り代とされます。四十九日法要までは葬儀で使用した「仮位牌」を使用し、四十九日法要にて正式な本位牌に魂を移してもらいます。
本位牌は、お寺が用意するものではなく、遺族が自ら葬儀社や仏具屋に依頼して作成するものです。本位牌が自宅に届くまで時間がかかる場合もあるため、早めに手配しましょう。なお、浄土真宗では位牌を使用しません。
遺骨と遺影写真
遺骨と遺影写真も、自宅での四十九日法要で必ず用意するものです。遺骨は四十九日法要後にお墓に納骨することが一般的です。遺影写真は法要中や法要後に故人を偲ぶために飾られます。
葬儀社から遺骨や遺影写真を祀る祭壇を用意してもらっている場合は、そのまま使用しましょう。祭壇がない場合は、お寺に相談するか、一時的な台を用意して代用することも可能です。
座布団
四十九日法要を自宅で行う場合、座布団を用意します。法要中に僧侶や参列者に座っていただくため、関係者全員分の座布団が必要です。ホームセンターで購入することも可能ですが、一度しか使わない場合は親戚に借りて用意したり、レンタルする方法も検討しましょう。
お布施
お布施は、僧侶への感謝の気持ちを表すために必ず用意するものです。四十九日法要のお布施の金額は地域や寺院によって異なりますが、一般的な相場は3万円〜5万円です。別途お車代も用意しましょう。
香典返し
香典返しとは、お通夜や葬儀などでいただいた香典に対するお返しです。一般的に、四十九日法要終了後にお渡しするため、四十九日法要で用意するもののリストに含まれています。
ただし、昨今は遠方からの参列者に配慮して、葬儀当日に香典返しを渡す「当日返し」も少なくありません。必ず用意するものではありますが、お渡しするのが四十九日ではなく葬儀当日になる場合もあることを覚えておきましょう。
必要かどうかを家族で判断するもの
下記の項目は自宅での四十九日法要で必ず用意するものではなく、必要かどうかは状況に応じて家族で判断するものです。
食事
四十九日法要後は、僧侶や参列者に感謝し、故人の思い出を語り合う場として「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を行います。ただし、近年は従来と違い、会食は必ず用意するものではなくなってきました。感染症対策や、遠方からの参列者が多いなどの理由が挙げられます。
時間がない場合は食事の代わりに弁当をお持ち帰りいただいたり、少人数の四十九日法要の場合は近くへ外食に行ったりするなど、参列者の状況や規模に合わせて判断しましょう。
引き物
引き物とは、四十九日法要に参列者からいただいたお供え物に対するお礼の品です。香典返しと引き物は混同されがちですが、香典返しは葬儀などでいただいた香典へのお礼であるのに対し、引き物は四十九日法要でいただいたお供えへのお礼です。
香典と香典返しは家族葬でも必ず用意するものですが、家族だけで四十九日法要を行う場合、引き物は四十九日に用意するものには含まれない可能性があります。
お供え物
お供え物は参列者からいただく場合もありますが、家族が用意することもあります。お供えをする場合、故人の好物や季節の果物、お菓子などを用意するとよいでしょう。
自宅での四十九日法要に向けて行うこと

自宅で四十九日法要を行う前には、物品の用意だけでなく、各所への連絡も必要です。ここでは、特に重要な「僧侶への連絡」と「家族や参列者への連絡」について紹介します。
僧侶への連絡
家族と相談して四十九日の日程が決まったら、僧侶には早めに相談しておきましょう。ほかの法要との兼ね合いで、希望する日程に沿えないことがあります。また、日程を決める前に、僧侶の都合を予め確認し、予定に合わせて日程を調整するのも一つの方法です。
自宅での四十九日法要の日が近づいたら、改めてお寺へ連絡を入れましょう。四十九日の日時を決める際に既に連絡をしていますが、直前に確認をしておくと丁寧な印象を与えられますし、安心して当日を迎えられます。
家族や参列者への連絡
自宅の四十九日法要に参列予定の方には、案内状を用意して送ります。身内には電話やメールでお知らせする場合もありますが、それ以外は案内状を送付するのが一般的です。連絡の際は、下記のような内容を盛り込みましょう。
家族や参列者へ連絡する内容
- 法要の案内
- 法要の日時
- 自宅の場所とアクセス方法
- 会食の有無
- 服装や持ち物
- 参加の可否確認
自宅での四十九日法要におけるマナー・注意点

最後に、自宅で四十九日法要を行う際に知っておくべきマナーや注意点を紹介します。
服装のマナー・注意点
四十九日法要では、喪服を着用するのが一般的です。たとえ身内だけの自宅法要であっても、カジュアルな服装は故人や僧侶へ失礼にあたります。法要にふさわしい服装を選び、故人や僧侶へ敬意を示しましょう。施主の方針で私服にする場合、僧侶へ事前の相談が必要です。
四十九日の服装や身だしなみのマナーについて詳しく知りたい方は、下記をご覧ください。
挨拶のマナー・注意点
身内だけの自宅法要だとしても、法要の始まりや終わりの挨拶、会食の案内、会食前の挨拶はしっかりと行いましょう。忙しい中集まっていただいた方に感謝し、法要をスムーズに進めるためです。ただし、挨拶や案内は簡潔に行い、長くならないように気をつけます。
引き物・香典返しのマナー・注意点
引き物や香典返しは、感謝の気持ちを表現するものです。品物を用意する際は、以下に注意しましょう。
四十九日の引き物の選び方・注意点
- 相場(会食ありの場合):3千円〜5千円
- 相場(会食なしの場合):4千円~8千円
- 消え物(食べたり使ったりするとなくなるもの)を選ぶ
- 掛け紙をかける
- 僧侶にもお渡しする
四十九日の香典返しの選び方・注意点
- 相場はいただいた香典の3〜5割
- 消え物を選ぶ
- 掛け紙をかける
四十九日法要に用意するものや注意点を把握して早めに準備を始めましょう

この記事のまとめ
- 自宅での四十九日法要は、メリットとデメリットを比較して決める
- 必ず用意するものと家族で必要性を判断するものがある
- 法要前に僧侶と参列者へ連絡をする
- 家族だけの自宅法要であっても、基本的に喪服を着用する
- 引き物や香典返しには相場を守る
- 僧侶には、お布施とは別に引き物も用意する
四十九日法要は、故人を偲び、家族や参列者が心を一つにする大切な機会です。自宅で行う場合、故人が慣れ親しんだ場所でくつろいで過ごせるメリットがあるものの、用意には時間と労力が必要となります。用意するもののリストを参考に、早めに計画を立てて準備を始めましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。