【齋藤弘道さん特別インタビュー02】遺言による寄付の心得

相続業界で幅広く活動する齋藤弘道さんは、遺言信託業務や相続トラブル解決に長年携わりながら、遺贈寄付推進に関する勉強会を立ち上げ、遺贈寄付を日本に根付かせるために尽力しています。今回のインタビューでは、全国レガシーギフト協会の設立経緯や遺贈寄付を行う際の注意点について語っていただきました。
「遺贈寄付」という概念を正しく理解する
——全国レガシーギフト協会について教えてください。
全国レガシーギフト協会の前身となる勉強会が立ち上がったのは、2014年のことです。社会のために自分の財産を活かしたいという人々の想いを、どうすれば形にできるのか。遺贈寄付を希望される方の「想い」を最適な形で実現することを目的として、弁護士や税理士、NPO関係者が中心となり、当時信託銀行に勤務していた私も加わって スタートしました。
私たちは遺贈寄付に関する課題や論点を明らかにしようと議論を重ねてきました。その活動はおよそ2年続き、2016年11月には「一般社団法人全国レガシーギフト協会」として法人化され、組織としての体制が整いました。
——協会ではどのような活動を行っていますか?
より多くの方々に遺贈寄付についての理解を深めていただけるよう努めています。特に専門家の皆さまへは、研修会を通じて「遺贈寄付」に関する情報提供などの活動を行っています。なかでも重要なことは、「遺贈寄付」という概念を正しく理解していただくことです。その理解の対象は、寄付を希望される方だけでなく、相続に関わる士業の先生方——たとえば弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家の方々も広く含まれます。
こうした士業の方々に遺贈寄付の仕組みや意義をご理解いただくことで、相続に関する相談を受けた際に、遺贈寄付という選択肢を提案できるようになります。また、研修会の開催に加え、『遺贈寄付ハンドブック』という書籍も発行し、さらに「遺贈寄付サロン」も定期的に開催して、遺贈寄付を受け入れる団体に対しても、遺贈寄付の理解と受入体制の促進に努めています。
——遺贈に関する相談窓口もあると伺いました。
全国に19か所の相談窓口を設けており、その運営は各地域のコミュニティ財団が担っています。コミュニティ財団とは、寄付や助成金を集めて地域の小規模団体に対して公募による助成を行うなど、地域に根ざした活動を行っている団体です。
これらの財団には、全国レガシーギフト協会の社員として参画いただいており、「加盟団体」と呼んでいます。加盟団体は、それぞれの地域で無料の相談対応を展開しています。
「遺贈寄付」という言葉 を命名

——遺贈寄付には、いくつかの方法があると伺いました。
現在、遺贈寄付には6つの方法(遺言による寄付、死因贈与契約による寄付、生命保険による寄付、信託による寄付、相続財産の寄付、香典返し寄付)があると定義しています。以前から遺言によって財産を寄付するという行為自体は存在していましたが、実は「遺贈寄付」という言葉はありませんでした。そこで後に当協会となる勉強会が2014年頃に「遺贈寄付」という言葉を命名し、その概念を整理・確立していきました。
——遺贈寄付の概念を整理・確立しようと思ったきっかけを教えてください。
信託銀行に勤務していた当時、私は本部で遺言信託業務を担当しており、全国の支店からの相談を受ける立場にありました。各支店の担当者は、お客さまから寄付に関する相談を受けることが多く、「どこか推薦できる団体はないか」と尋ねられることもありました。しかし、どのような団体がどのような活動をしているのか把握しておらず、銀行側としても推薦はできないというのが実情でした。
担当者らは私のもとに相談へ来ますが、私自身も十分な情報を持っておらず、的確に答えることができませんでした。もちろん、銀行が特定の団体を推薦するのは今でも難しい面があります。しかし、「理解した上で伝えられない」と、「そもそも何も知らずに伝えられない」のとでは大きな違いがあると感じています。この点は、明確な課題だと捉えていました。
また、法律や税制に関する問題もあり、どこに、どのようなリスクがあるのかすら把握できていませんでした。こうした状況を改善するために、まず論点を整理し、課題を抽出して、段階的に解決していくプロセスが必要だと強く感じたのです。
より幅広い視野でのアドバイス
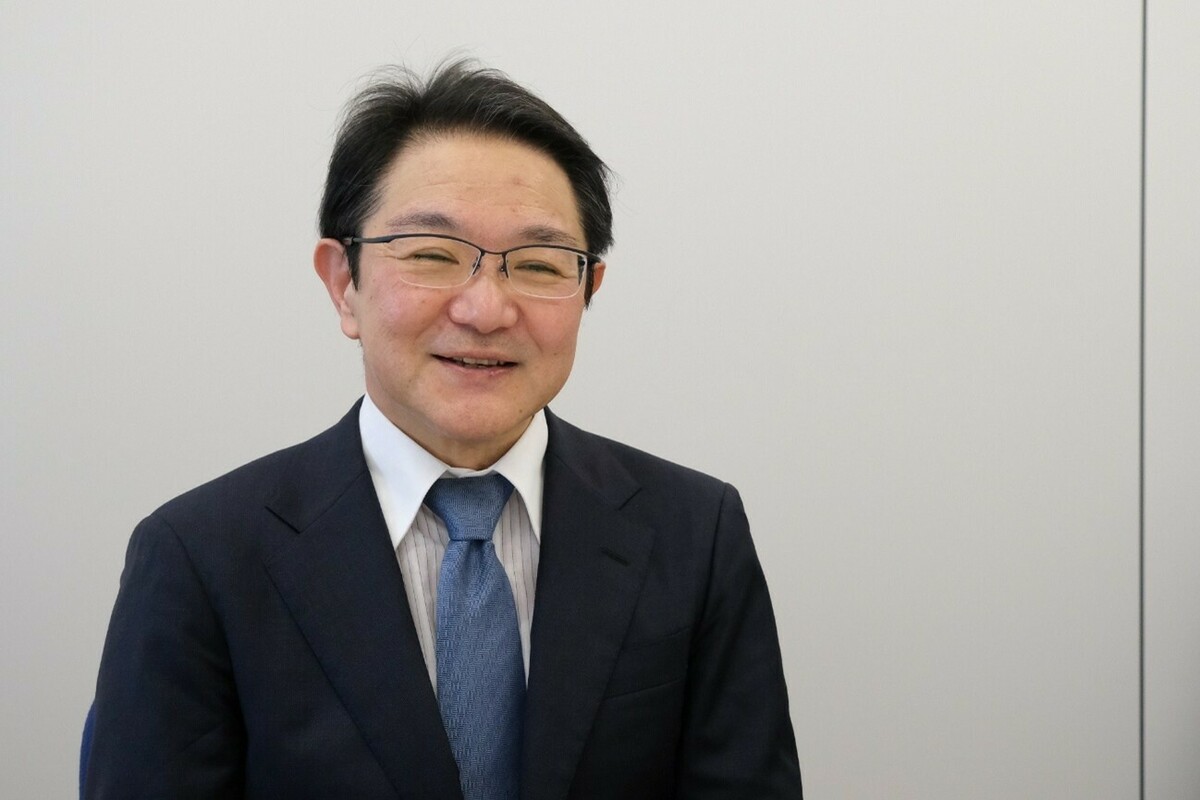
——遺贈寄付を行う際の注意点を教えてください。
すべての団体が「どんな財産」でも、受け取るとは限らない、という点に注意が必要です。受け入れる団体の体制が整っていなければ、遺言で寄付されても、対応に困ることがあります。
現金であれば受け入れやすいかもしれませんが、不動産や有価証券など、管理や処分に手間がかかる財産が含まれている場合は、団体側も慎重に判断します。
特に「包括遺贈」のように、財産の全部を一括で寄付する内容だと、処分が困難な財産が含まれることと、遺言者の債務を引き継ぐリスクもあります。
——遺言書を作成する前に、まずは寄付先の団体へ相談することが大切ですね。
そのとおりです。団体に相談せずに進めてしまうと、死後に遺言の内容が受入困難と判明しても、修正はできず、取り返しのつかない事態になるおそれがあります。
もちろん、今後の状況によっては相続人や相続財産が変わる可能性もゼロではありません。それでも、現時点で団体に「受け入れられる」という言質を取っておくことが安心だと思います。
——遺言執行時に団体が遺産を受け取らない場合のリスクとは?
団体が遺産を受け取らない(遺贈を放棄する)場合、特定遺贈であれば放棄の時期に制限はありませんが、包括遺贈の場合は遺言者の死亡を知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
このように、包括遺贈の場合は団体が債務を負う上に、放棄する際の手間もかかるため、断られるリスクが高いと言えます。包括遺贈を検討する場合には、必ず団体へ事前相談することをお勧めします。
——遺贈寄付について、全国レガシーギフト協会へ相談するメリットを教えてください。
一般的には、士業の先生は団体に関する情報が限られるため、紹介できる選択肢が少なくなりがちです。一方で協会は多くの団体とつながりがあるため、より幅広い視野でアドバイスが可能です。相談は無料です。
もうひとつは、これまで多くの事例を通じて論点を整理してきた実績があることです。寄付先団体との情報交換も積極的に行っているため、リアルな事例に基づいたアドバイスができる点も、協会ならではの強みだと考えています。
【プロフィール】
齋藤 弘道(さいとう・ひろみち)
全国レガシーギフト協会理事
遺贈寄附推進機構株式会社代表取締役。2007年より、みずほ信託銀行の本部にて営業部店からの特殊案件や1500件以上の相続トラブルと10,000件以上の遺言の受託審査に対応。遺贈寄附の希望者の意思が実現されない課題を解決するため、2014年に弁護士・税理士・NPO関係者らとともに勉強会を立ち上げる(後の全国レガシーギフト協会)。2014年に野村證券に転職、野村信託銀行にて遺言信託業務を立ち上げた後、2018年に遺贈寄附推進機構株式会社を設立。日本初の「遺言代用信託による寄付」をオリックス銀行と共同開発。

















