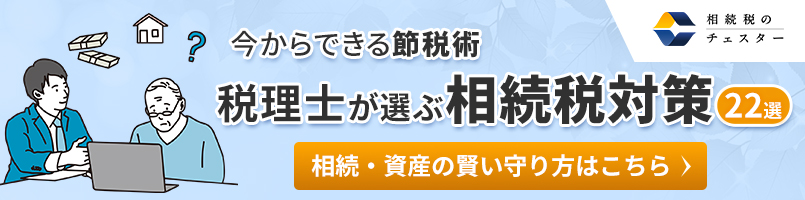相続税の基礎控除はいくらまで?控除額と相続税の計算方法

相続税は、相続する金額や法定相続人の数によって基礎控除が定められています。相続が決まった際、またはまとまった金額を相続する可能性がある場合は、相続税の基礎控除について理解しておきましょう。本記事では、相続税の基礎控除の計算方法や注意点を解説します。
相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除は、相続する財産に対して課税される前に差し引ける非課税枠のことです。相続税の基礎控除額が大きいほど課税対象となる相続財産額が少なくなり、結果として相続税の負担が軽減されます。
具体的な基礎控除額は法定相続人の数によって変わるため、正しいルールを把握した上で計算を進めることが大切です。
ただし、基礎控除が適用されるため、相続する財産の金額が基礎控除内に収まる場合は課税の対象外です。小規模な相続財産を持つ家庭の税負担を軽減するために、このような仕組みが整っています。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変動します。正確な計算方法を理解することで、相続税の有無や税額を事前にある程度把握できます。詳しい計算方法を確認していきましょう。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式で求められます。たとえば、法定相続人が2人の場合、「3,000万円+(600万円×2)=4,200万円」が控除されます。相続する財産が4,200万円未満の場合、相続税を納める必要はありません。
基礎控除額については、以下の表を参考にしてみてください。
|
法定相続人の数 |
基礎控除額 |
|---|---|
|
ひとり |
3,600万円 |
|
2人 |
4,200万円 |
|
3人 |
4,800万円 |
|
4人 |
5,400万円 |
|
5人 |
6,000万円 |
相続人が増えると基礎控除額も増える
相続税は、法定相続人ひとりにつき600万円ずつ控除額が増えるため、相続人が多いほど控除額が高くなります。控除額が高くなることで、相続人ひとりあたりの税負担が軽減されます。たとえば、子供が多い家庭ではより高い基礎控除が適用されるため、相続税の負担を抑えることが可能です。
基礎控除額は変更になる可能性があるため注意
基礎控除額は、今後法律の改正により変更される可能性がある点に注意しましょう。過去にも税制改正で控除額が引き下げられた実例があるため、常に最新の情報を確認することが大切です。税務署のホームページなどから、最新情報を確認しましょう。
相続税の計算方法

相続税の計算は、以下の流れを経ておこないます。
相続税の税額の計算方法
- 財産の評価額から相続の対象となる財産の総額を算出する
- 相続の対象となる財産の総額から基礎控除額を引く
- 法定相続分に応じた税額の総額を計算する
- 相続税の総額を実際の相続分で割る
- 最終的な税額を算出する
手順に沿って、正しい相続税額を算出しましょう。
①財産の評価額から相続の対象となる財産の総額を算出する
相続税の計算は、まず相続する財産の評価額を正確に把握することから始まります。不動産や預貯金、有価証券などの評価をおこない、相続の対象となる正味の財産の総額を算出しましょう。
現金であればその金額が評価額となりますが、不動産や車などは金額に換算する必要があります。評価方法は、資産の種類によって異なる点に注意が必要です。
相続財産の総額を算出した後は、相続の対象にならない非課税財産や、被相続人が残した負債を差し引くことで、最終的な課税対象額を求めます。例えば、生命保険の非課税枠や墓地などは相続財産に含まれません。
②相続の対象となる財産の総額から基礎控除額を引く
相続の対象となる財産の総額が算出できたら、基礎控除額を差し引いて、課税される財産の総額を算出します。基礎控除額が対象の課税財産総額を上回る場合、相続税は発生しません。
たとえば、相続される予定の財産が4,000万円で法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円のため相続税はかかりません。反対に、基礎控除額が4,200万円で相続する財産が5,000万円の場合、4,200円を差し引いた800万円が課税の対象となります。
③法定相続分に応じた税額の総額を計算する
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの相続財産の取り分の割合のことです。法定相続分を基準に各取り分や税金の計算を進めます。
法定相続分は配偶者や子、父母、祖父母などで詳しく分類されています。法定相続分の割合は、以下のとおりです。
法定相続分
- 相続人が配偶者のみ…配偶者がすべて相続
- 相続人が子のみ…子がすべて相続
- 相続人が配偶者と子…配偶者 1/2、子 1/2
- 相続人が配偶者と父母…配偶者 2/3、父母 1/3
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹…配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4
課税される財産の総額がわかったら法定相続分で課税財産総額を割り、法定相続人一人ひとりの課税される財産の金額を算出します。そこから各相続人ごとの課税財産額に対して、課税の割合をもとに課税金額を計算します。
例えば、配偶者に割り振られた課税財産額が1,000万円の場合、税率は10%で控除はないため、相続税の金額は100万円です。
相続税の税率と控除額は、以下の表を参考にしてみてください。
|
税率 |
控除額 |
|
|---|---|---|
|
1,000万円以下 |
10% |
- |
|
1,000万円超から3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
|
3,000万円超から5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
|
5,000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
|
1億円超から2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
|
2億円超から3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
|
3億円超から6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
|
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
④相続税の総額を実際の相続分で割る
相続税の金額が明確になったら、対象の相続税の総額を実際の相続分で割り振ります。法定相続分は配偶者や子、父母、祖父母などで詳しく分類されています。配偶者、または一親等の血族以外の人が相続する場合は、相続税額の2割が加算される点に注意しましょう。
遺産を相続する場合、遺言書の内容によって、法定相続分どおりに分けられないことがあります。遺産分割協議で決まらない場合でも、一旦法定相続分で計算して相続税の申告期限までに納税しなければなりません。
各種特例によっては納税額が増えてしまう可能性もありますが、納税後に正しく申告すれば修正でき、納めすぎた分を返してもらえます。
⑤最終的な税額を算出する
各家庭の環境によっては、高額な相続税の納付が難しい場合もあります。そのため、相続税には基礎控除以外にもさまざまな特例が用意されています。
各相続人の相続税がわかったら、特例を用いてさらに相続税を下げられないか確認しましょう。反対に、相続を受ける人によっては相続税が加算される可能性がありますが、その場合でも正しく申告することが大切です。
財産を相続した人が以下の条件に当てはまる場合は、相続税の加算、または控除をおこないましょう。
相続税の控除・加算が発生するケース
- 財産を取得した人が一親等の親族や配偶者以外の場合…相続税額に20%加算
- 相続時精算課税制度を利用した場合…過去の贈与税を控除した額が納付税額
- 配偶者が財産を取得した場合…配偶者の相続税額の軽減を控除した金額が納付税額
- 未成年者・障がい者が財産を取得した場合…一定額を控除した金額が納付税額
- 10年以内に複数相続を受けた場合…一定額を控除した金額が納付税額
すでに贈与税などを支払っている場合は、その金額も明確に出す必要があります。各相続人ごとの相続税を合算して、控除額や相続税額を算出しましょう。
相続税を計算する際のポイント

相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除や特例があり、正しい税額を把握するためには複数のポイントを理解しておく必要があります。相続放棄をすれば基礎控除額は変わるのか、基礎控除額以外にどんな特例や控除を使えるのかなど、相続税と基礎控除に関するポイントを確認していきましょう。
相続放棄をしても基礎控除額は変わらない
相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動し、相続人が多いほど基礎控除額は多くなります。しかし、相続放棄をした場合でも、基礎控除額の計算には影響しません。放棄した相続人も法定相続人としてカウントされるため、控除額はそのまま適用されます。
法定相続人の中に相続放棄をする人がいても基礎控除は減らないため、相続人同士でよく話し合って協議を進めましょう。
基礎控除以外にも利用できる特例や税額控除も把握する
相続税の負担を軽減するためには基礎控除だけでなく、さまざまな特例や税額控除を活用することも大切です。たとえば「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの特例を利用することで、課税対象額を減らせます。
これらの特例を正しく活用すれば、相続税の支払いの負担を減らして今後の生活に必要な財産を大切に守ることが可能です。未成年や障がい者が相続をする際も、将来や生活のことを見越した特例制度があるため、忘れずに利用しましょう。
相続税の基礎控除以外に利用できる特例・税額控除の例
- 小規模宅地等の特例
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者の税額控除
- 障がい者の税額控除
- 相次相続控除
- 贈与税額控除
相続後確定申告が必要な場合もある
財産を相続した際はその旨を申告するだけでなく、相続した内容によっては確定申告が必要な場合があります。
たとえば、相続した不動産などの財産を売却した場合は、確定申告でその譲渡益を所得税の課税対象として申告しなければなりません。また、死亡保険金を受け取ったり、収益性のある物件を相続したりといった場合にも確定申告が必要です。
上記以外にも確定申告が必要になる場合は多々あるため、不安な方は税務署などに相談しましょう。
申告漏れはペナルティがあるため注意する
相続税の申告漏れは、加算税や延滞税などのペナルティが課せられる可能性があります。申告期限を過ぎてしまうと、基礎控除や特例が使えなくなる可能性があるだけでなく、罰金が発生することもあります。申告期限は一日でも過ぎたら延滞税が発生するため、必ず期限内に申告しましょう。
また、相続額を意図的に少なく申告したり、適用できない特例を使ったりすると、発覚後に修正申告が必要になります。その際、過少申告加算税が課されて通常より多くの税金を支払うことになりかねないため、必ず正しい内容で申告しましょう。
相続税の計算が不安な場合は税理士に相談

相続税の計算に不安を感じている方は、税理士に相談した上で進めてみましょう。
相続税の計算は非常に複雑で、基礎控除以外にもさまざまな特例、控除項目があり、知識のない個人が正確に算出するのは容易ではありません。
税理士は、基礎控除や特例、控除などの知識が豊富なだけでなく、申告書の書き方なども熟知しています。税理士に相談することで、専門的な知識をもとに正しい相続税の算出が可能です。
相続税の負担を最小限に抑えるためのアドバイスも受けられ、税負担を軽減できることもあります。初回は無料で相談できる税理士サービスも多数あるため、積極的に利用してみてください。
相続税の基礎控除を計算してみましょう

この記事のまとめ
- 相続税の基礎控除とは、相続する財産に対して課税される前に差し引ける非課税枠のこと
- 相続税は、相続する財産の金額が多いほど高い税率が適用される
- 基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められる
- 相続税に関して不安な場合は税理士に相談するとよい
相続する人や家庭の負担を軽減するため、相続税には高い基礎控除額が設定されています。また、相続税には基礎控除以外にもさまざまな特例制度や控除があるため、正しく利用すれば税金の負担を軽くできるでしょう。
ただし、相続税の計算は非常に複雑で、知識がないまま正しい税額を算出するのは容易ではありません。不安な方は税理士などのプロに相談し、適切なアドバイスを受けて申告をスムーズにしましょう。
国税OB税理士(国税庁出身税理士)。
相続税を専門とする税理士法人チェスターのパートナー税理士。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、
国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。
著書に「令和6年度版相続税・贈与税コンパクトブック」、「デジタル財産の税務」など多数。
また、「相続大辞典」、「税理士が教える相続税の知識」の記事監修も務める。