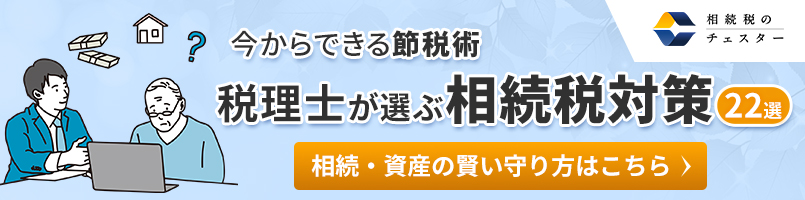不動産を生前贈与する際の手続きは?メリットや注意点もあわせて紹介

土地・建物などの不動産があれば、相続が発生する前に生前贈与するのも選択肢の一つです。本記事では、不動産を生前贈与する際の手続きやメリット・デメリット、注意点について解説します。相続における不動産の扱いについて懸念をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産を生前贈与する際の手続き

不動産を生前贈与する際の一般的な手続きの流れは、以下のようになっています。
ステップ①必要書類を取得する
まず、生前贈与の手続きに必要な書類の準備を済ませておきます。
| 生前贈与の手続きに必要な書類 | |||
|---|---|---|---|
| 書類名 | 入手先 | ||
| 登記事項証明書 | 最寄りの法務局 ※郵送、オンラインでの請求も可能 |
||
| 登記済証 (登記識別情報) | 不動産を管轄する法務局 ※郵送、オンラインでの請求も可能 |
||
| 固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の市区町村役場 | ||
| 贈与者の印鑑証明書(発行から3ヵ月以内) | 贈与者の居住地の市区町村役場 | ||
| 固定資産評価証明書 | 不動産の所在地の市区町村役場 | ||
ステップ②贈与契約書等を作成する
必要な書類が用意できたら贈与契約書を2通作成し、贈与者・受贈者が1通ずつ保管する形で契約を取り交わします。前提として、贈与に伴って不動産の名義を変更する際は、登記原因証明情報を法務局に提出しなくてはいけません。そのため「なぜ不動産の名義を変更するのか」を証明する書類が必要となり、生前贈与の場合は贈与契約書がこれに当たります。
贈与契約書には以下の情報を漏れなく盛り込んだ上で、贈与者・受贈者の署名・押印を施しましょう。なお、押印する際はなるべく実印を使ってください。
贈与契約書に盛り込むべき情報
- 当事者の情報(誰から誰に不動産を贈与するのか)
- 贈与の時期(いつ贈与するのか)
- 贈与の対象となる不動産(何を贈与するのか)
加えて、不動産の名義変更に当たっては、所有権移転登記申請書も必要になります。法務局の窓口や公式WEBサイトから入手できるため、記入例を確認の上、早い段階で仕上げておきましょう。
ステップ③所有権の移転登記を行う
提出後は、法務局にて書類の内容が確認され、問題がなければ数日から1週間程度で登記が完了します。登記が完了すると、申請時に指定した連絡先宛に「登記完了通知書」が送付されるか、もしくは法務局の窓口で受け取ることができます。
これまでに紹介した書類をすべて準備したら、対象となる不動産の住所地を管轄する法務局に提出します。なお、どこの法務局が管轄となるかは、法務局の公式WEBサイトから確認することが可能です。
オンライン申請や書面申請を問わず、登記が完了したかどうかは「登記情報提供サービス」などを利用して確認することも可能です。これにより、名義が新しい受贈者へと正式に移転されたことを確認できます。
贈与契約書の作成と確定申告を忘れないこと
前提として、贈与は贈与者および受贈者双方の合意がなければ成立しません。親子間で土地や建物などの不動産を贈与する場合でも同じです。当事者同士が合意に達した上で贈与があったことの公的な証明として、贈与契約書は必ず作成しましょう。
また、贈与の金額が1年間で110万円を超えた場合は、贈与税の確定申告をしなくてはいけません。これは、一括贈与・分割贈与を問わず必要な手続きです。贈与した翌年の2月1日から3月15日(当日が土日祝日の場合は休み明け最初の平日)の間に、所轄の税務署に確定申告書を提出する必要があります。
なお、後述する相続時精算課税制度を使う場合は、贈与の金額にかかわらず贈与税の申告をしなくてはいけません。
不動産を生前贈与する際にかかる税金

不動産の生前贈与ではさまざまな税金がかかるため、具体的な税金を種類ごとに、税率や計算式とともに紹介します。ただし、実際に納める税金の金額は個々の事例により異なるため、税理士もしくは税務署に確認するのが望ましいです。
贈与税
土地や建物などの不動産を贈与した結果、その年の1月1日〜12月31日までの贈与額が110万円(基礎控除)を超えた場合、贈与税を納める必要があります。贈与税は「(1年間に受け取った財産の価額の合計額-110万円)×税率-控除額」という式で計算することが可能です。
なお、贈与税の税率には一般税率と特例税率がありますが、「誰が誰に贈与するか」によっても用いられる税率が異なるため注意してください。
| 一般税率と特例税率 | |||
|---|---|---|---|
| 一般税率 | 特例税率が適用されない場合に用いる(兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年者の子に贈与するなど) | ||
| 特例税率 | 親、祖父母が直系の18歳以上の子・孫に贈与する | ||
不動産取得税
不動産取得税とは、生前贈与などの理由により不動産を取得した場合、都道府県に納める税金の一種です。不動産取得税の税率は、以下のようになっています。
| 不動産取得税の税率 | |||
|---|---|---|---|
| 土地、居住用の建物 | 3% | ||
| 居住用以外の建物 | 4% | ||
不動産取得税は「固定資産税評価額×3%(または4%)」という式で計算可能です。例えば、取得した不動産(土地、居住用の建物のみ)の固定資産評価額が2,000万円だった場合、不動産取得税は60万円となります。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の登記手続きにより発生する税金のことで、実際は法務局に現金もしくは印紙で支払います。
登録免許税の税率は2%であり、具体的な金額は「固定資産税評価額×2%」という式で計算可能です。例えば、取得した不動産(土地、居住用の建物のみ)の固定資産評価額が2,000万円だった場合、登録免許税は40万円となります。
専門家への報酬
税金以外にも、贈与税にかかる確定申告や名義変更に伴う所有権の移転登記を税理士・司法書士などの専門家に依頼した場合、報酬が発生します。依頼に先立って見積もりをとり、具体的な金額を確認しましょう。
不動産を生前贈与するメリット

不動産を生前贈与することには、次のメリットがあります。
希望する相手に確実に不動産を承継させられる
相続とは異なり、生前贈与は自らの意思で行えるため、配偶者や子など希望する相手に確実に不動産を承継させられます。
ただし、贈与を行う際は相手の了解が欠かせません。原則として当事者同士の合意があって初めて成立するためです。
相続税を抑えられる
生前贈与を行うと贈与税を納付する必要がありますが、結果として相続税の節税対策としても利用できます。
ただし、実際に相続税を抑えられるかは、適用できる控除や贈与時・相続時の不動産の価格などの条件に左右される部分もあるため、事前に税理士に確認しましょう。
受け取った側が家賃収入を得られる
生前贈与の対象となる不動産が収益物件であれば、不動産を受け取った側(受贈者)がその後家賃収入を得られるようになります。
贈与税の「配偶者控除の特例制度」を使える
夫(妻)が妻(夫)に自分たちが住む持ち家を贈与する場合、一定の条件を満たしていれば、贈与税における「配偶者控除の特例制度」を利用できます。
配偶者控除の特例制度を利用するための条件
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に行われた贈与である
- 贈与の対象となったのは居住用不動産またはそれを取得するための金銭である
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、受贈者が現実に住んでおり、その後も住み続ける見込みがある
この特例を使えば、最高2,000万円まで贈与税を控除することが可能です。
「相続時精算課税」の制度を使える
相続時精算課税の制度は、原則として60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫に対し財産を贈与した場合に選択できる制度です。
本来、贈与税は1月1日から12月31日までの贈与額が110万円を超えた場合、受贈者に納税する義務が生じます。しかし、相続時精算課税の制度を使えば、以下の条件下で税制上の優遇を受けることが可能です。
相続時精算課税の制度で受けられる税制上の優遇
- 毎年110万円の基礎控除が受けられる
- 基礎控除に加え、生涯で2,500万円の特別控除が受けられる
なお、基礎控除の対象となる贈与に関しては贈与税がかからず、相続財産に加算されないため、相続税もかかりません。一方、特別控除の対象となる贈与については贈与税はかからないものの、相続財産に加えられるため相続税がかかる場合もあります。
他にも使える非課税枠がある
不動産を生前贈与すると、上記で挙げた以外にも使える非課税枠があります。具体的には以下のものが挙げられますが、それぞれに利用条件が設けられているため、税理士もしくは税務署に確認しましょう。
生前贈与に当たって利用できる非課税枠の例
- 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
- 贈与税の配偶者控除の特例
- 特定障害者等に対する贈与税の非課税制度
不動産を生前贈与する際の注意点

不動産の生前贈与にはさまざまなメリットがある一方、デメリットもあることに注意が必要です。ここでは、具体的に考えられる注意点として、以下の3点について解説します。
かえって税金が高くなる可能性がある
不動産を生前贈与すると、かえって税金が高くなる可能性があります。例えば、相続により不動産を取得した場合の登録免許税の税率は0.4%であるのに対し、贈与によった場合は2%と大きく異なります。
状況次第では相続により不動産を取得するより、贈与として取得したほうが税金が高くなる可能性もあるため、節税対策として使う場合は特に注意が必要です。
税金や手続きの費用が発生する
不動産の贈与も、売買と同じく譲渡の一種である以上、受贈者は不動産取得税や贈与税を納めなくてはいけません。また、登記手続きにあたっては登録免許税が発生します。
さらに、これらの手続きを司法書士や税理士に依頼した場合、その部分についても報酬を支払わなくてはいけません。
時期によっては生前加算制度の対象となる
不動産を生前贈与する時期によっては、生前加算制度の対象となります。生前加算制度とは、不動産などの財産を贈与した贈与者が、贈与後3~7年以内に亡くなった場合、その贈与がなかったことにされる制度を指します。相続税の計算にあたっても、贈与された不動産の価格が相続財産に加算される仕組みです。
贈与者が亡くなる直前に、相続税を回避する目的で贈与が行われることを避ける目的で設けられています。ただし、このような制度がある以上、生前贈与を行う際は、なるべく早いうちに手続きをすませましょう。
利用できない制度も出てくる
土地などの不動産を生前贈与する際は、さまざまな制度が使える可能性があります。一方で、生前贈与では利用できない場合もあるため、注意しなくてはいけません。
代表例が「小規模宅地等の特例」です。これは、被相続人が自宅や事業用店舗等に使っていた宅地の相続税評価額を最大80%削減できる制度ですが、生前贈与した土地については対象外になっています。
不動産の生前贈与をしたほうが有利なケース

ここまでの内容を踏まえ、不動産の生前贈与をしたほうが有利になる場合の具体例として以下の3つについて解説します。
ケース①不動産が収益物件である
対象となる不動産が、賃貸アパート・マンションなどの収益物件であれば、生前贈与を前向きに検討しましょう。
収益物件ならではの特殊な事情として、長期間保有するほど、将来的に相続財産が膨らんでいくことが挙げられます。得られた家賃収入が現金や預貯金、他の不動産や株式などの金融商品の形で残っていれば、その分相続税は高くなるため注意が必要です。
子など家族に相続させる予定があるなら、早い段階で生前贈与すれば、相続財産を減らすことができます。また生前贈与の後に得られる家賃収入を貯めておき、相続税の支払いに充当することも可能です。
ケース②将来値上がりする可能性が高い
将来値上がりする可能性が高い不動産であれば、生前贈与により相続税の負担を抑えることができます。将来相続が発生した際に、不動産の価格が上昇・下落のどちらの傾向にあるかは正確に予測できません。
しかし、相続が発生した際に上昇傾向にあれば、相続人は相応の相続税を納める必要があります。価格次第では、相続税を払うためにその不動産を売却せざるを得ない事態も考えられるでしょう。
相続税の負担を抑えるという意味では、将来値上がりする可能性が高い不動産を評価額が低い時期に生前贈与するのは非常に効果的です。また、前述した相続時精算課税の制度を使う場合は、贈与時の評価額を用いて相続税を計算します。
このような理由があるため、将来値上がりする可能性が高い不動産であれば、生前贈与を検討しましょう。具体的には、以下の条件に該当する不動産が考えられます。
将来的な値上がりが見込める不動産の例
- 大規模再開発の予定がある地域の不動産
- 政令指定都市など都市機能が充実している地域の不動産
- 最寄り駅から近い、複数路線利用可能など利便性の高い不動産
ケース③企業の経営者で事業承継を想定している
企業の経営者であり、子など家族に事業承継させることを考えているなら、遺産相続ではなく生前に不動産を贈与するほうが円滑に進められます。
経営者が亡くなった際に、子などの家族が後継者かつ相続人として事業を引き継ぐ形だと、土地や建物などの不動産、株式などの金融資産が相続税の対象になるためです。相続税の金額次第では、所有している資産では支払い切れずに資金調達に苦慮する可能性もあります。
また、節税対策としてのみならず、相続人の間でのトラブルを防ぐためにも生前贈与を検討するのは重要です。相続は資産がからむデリケートな問題である以上、それまでは仲のよかった家族同士でも深刻な争いに発展するおそれがあります。
混乱を防ぐためにも、できるだけ早い段階で不動産をはじめとした企業の資産を把握し、税理士や弁護士などの専門家にも相談しながら対策を施しましょう。
不動産の生前贈与は専門家に相談しましょう

この記事のまとめ
- 土地などの不動産を生前贈与することにはいくつかのメリットがある
- 一方で、かえって税金が高くなる可能性があるなどデメリットもある
- 不動産が収益物件もしくは将来値上がりする可能性が高いものであれば、生前贈与を検討すべき
- ただし、どれだけの効果が見込めるかは税理士に相談すること
結局のところ、土地などの不動産を生前贈与すべきか否かは、個々人の置かれた状況によっても異なります。大幅に税金が増えるなど、あえて生前贈与をすべきでない場合もあるため、まずは税理士などの専門家に相談しましょう。
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。