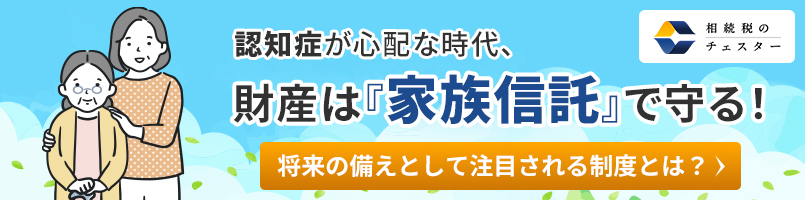歩行介助の種類や目的、コツとは?注意点を抑えて安全にサポートしよう

歩行介助は、転倒予防や自立支援のために欠かせない介護技術です。被介助者の身体状況や環境に応じた正しい方法と支え方を知ることで、安全性と安心感を高められます。本記事では、歩行介助の種類や目的、注意点、実践のコツを詳しく解説します。
歩行介助とは

歩行介助とは、歩行が困難な人に対し、転倒や事故を防ぎながら移動を支援する介助のことです。特に高齢者や病気・けがの回復期にある方は、筋力やバランス機能が低下し、自分ひとりでの歩行が不安定になる場合があります。転倒による骨折や寝たきりになるリスクも高いため、正しい方法での歩行介助が不可欠です。
歩行介助の主な目的
- 転倒を防ぎ、安全に移動する
- 残存機能を活かして生活の自立度を高める
- 外出や移動の機会を確保し、社会参加や精神的な安心感を得る
正しい方法での歩行介助は、被介助者の生活の質(QOL)の向上だけでなく、介助者の負担軽減にもつながります。介助者は、「基本を守る」「適切な支え方をする」ことが大切です。
誤った方法で支えると、被介助者の転倒や介助者の腰痛などにつながるため、正しい知識を持ち事前に練習を行ってから臨みましょう。
5種類の主な歩行介助

歩行介助は、被介助者の身体能力や環境に応じて大きく5種類に分けられます。それぞれの特徴と方法を理解し、適切な対応を行いましょう。
付き添い歩行(見守り中心)
付き添い歩行は、被介助者がほぼ自力で歩行できる場合に行う軽度の介助方法です。対象となるのは、筋力やバランス機能がある程度保たれている高齢者や回復期の方で、本格的な補助は行いません。介助者は被介助者の少し後方または横を歩き、常に視界に入れながら状況を観察します。
この方法では、転倒やふらつきが起きそうな瞬間に、即座に対応できるようにすることが大切です。たとえば、足がもつれたときは腰や肘付近を軽く支え、歩調を整える声掛けを行います。
注意点として、付き添い歩行は見守りが中心であるため、介助者が先回りしすぎて被介助者の自発的な歩行を妨げないような配慮が必要です。段差や床材の変化がある場合は具体的に事前説明を行い、安全性と安心感を両立させます。
軽介助(手すり+声掛け)
軽介助は、手すりや壁などの支えを利用して歩行する方に行う介助方法です。被介助者が自分の力である程度動けるが、不安定さやふらつきがある場合に適しています。介助者は被介助者の足腰が弱い方(患側)に立ち、軽く体を支え安全を確保します。
この方法の基本は、手すりの高さが適正であり、握りやすく安定しているかを事前に確認することです。さらに、手すり周辺に障害物や滑りやすい床材がないかを点検します。
注意点は、被介助者の歩行速度が遅くても急かさないことです。階段や段差では「ここから上ります」「もうすぐ下ります」と具体的な声掛けを行い、被介助者が安心して移動できるようにします。軽介助は、慣れていても油断せず毎回まわりの環境確認を行うことが大切です。
中介助(片麻痺・杖使用)
中介助は、片麻痺や下肢の筋力低下があり、自力歩行するには杖や歩行補助具が必要な方に行います。介助者は杖を使う側とは反対側に立ち、バランスを保ちながら歩幅や速度を合わせることが必要です。
この方法では、手順を誤ると転倒やバランス崩れの危険が大きくなります。たとえば、杖を突くタイミングと足を出す順序が合っていない場合、支持基底面が狭くなり不安定になります。そこで介助者は声掛けを使い、被介助者の動作と呼吸のリズムを合わせなければなりません。
注意点は、被介助者が安心できるペースを維持すること。急かすと不安が強まり、余計に体がこわばります。また、腰や肘付近を軽く支える程度にし、被介助者の自立性を保つことが大切です。中介助では、どのように介助するか事前に被介助者へ共有してから行うと、安全性が格段に高まります。
全介助(歩行器・歩行車)
全介助は、自力での歩行が困難な方に対して行います。歩行器や歩行車を使用し、介助者がしっかりと器具本体を安定させながら移動を補助します。対象は筋力低下が著しい高齢者や、手術後の回復期などでバランスが極端に不安定な方です。
この方法の基本は、出発前に器具のブレーキやタイヤの動き、ハンドルの固定を確認することです。ブレーキが効かない、タイヤが滑るといった状態は重大事故につながるため、必ず点検します。
注意点は、急な停止や方向転換を避け、速度をゆっくり一定に保つことです。また、被介助者の安心感を高めるため、移動中は「もうすぐ右に曲がります」など具体的な声掛けを行います。全介助では、介助者の姿勢や支え方も重要で、腰を痛めないよう膝を使って体重移動する方法を徹底することが大切です。
段差・階段介助
段差や階段の歩行介助は、平地以上に高度な介護技術と注意力が求められます。上りでは後方から、下りでは前方から支えます。この方法では、必ず立ち止まって段差や階段の有無、高さ、段数を具体的に説明することが重要です。被介助者に心構えができることで、安全性が格段に向上します。
注意点は、段差の直前でスピードを落とし、一段ごとに足を確実に置くことです。特に高齢者は視界が狭く足元が見えづらいため、決して焦らせず、両足をそろえてから次の段に進みましょう。介助者は常に被介助者より低い位置(下りなら前方、上りなら後方)に立ち、万一の転倒時に支えられる姿勢を保つことが大切です。
歩行介助を行う前のチェックリスト

歩行介助を行う前に、以下のチェック項目を確認することが安全確保の第一歩です。
歩行介助を行う前のチェックリスト
- 被介助者の体調(血圧、脈拍、めまいの有無)に異常がないか
- 歩行ルートに段差や障害物がないか
- 靴が滑りにくく、服装が動きを妨げないか
- 杖や歩行器が正しく調整・点検されているか
- 途中で休める椅子や手すりがあるか
- 照明が十分か、暗所がないか
- 緊急時の連絡方法が確保されているか
上記のチェック項目は、介助者が自分の腰や肩を痛めないためにも有効です。特に高齢者の場合は体調の変化が急に起こることがあるため、こまめな確認が欠かせません。
安全に歩行介助する7つのコツ

歩行介助を安全に行うためには、事前準備と実施時のポイントを押さえることが大切です。ここからは、歩行介助に役立つ7つのコツを具体的に解説します。
身体状況を知っているか
歩行介助の出発点は、被介助者の身体状況を正確に把握することです。筋力、関節可動域、バランス感覚、呼吸機能、持病(心疾患・糖尿病・高血圧など)、疲れやすさの程度を確認しましょう。たとえば、片麻痺の高齢者であれば、麻痺のある側と健康な側とで動きや力の入れ方が異なります。介助方法や支え方はその状態に合わせる必要があります。
また、被介助者がいつから歩行器や杖を使用しているか、最近の転倒歴はあるかも重要な情報です。これらを把握することで、被介助者に合った方法で安全な歩行介助を実現できます。
歩行動線に障害物はないか
どれほど丁寧な歩行介助を行っても、環境が整っていなければ事故は防げません。段差、カーペットのめくれ、電気コード、低い家具、ペットのおもちゃなど、障害物になり得るものは全て取り除きます。高齢者は視覚や反射神経が低下していることが多く、小さな障害物でも大きな事故の原因になります。
動線確保は歩行介助の基本であり、事前に被介助者と一緒に歩いて確認するのもよい方法です。一緒に確認することで、被介助者の安心感を高める効果もあります。
靴や服装は危なくないか
被介助者が履く靴はかかとがしっかり固定され、滑りにくい素材のものを選びます。サンダルやスリッパは転倒リスクが高いため避けましょう。靴のソールが擦り減っている場合は交換する必要があります。服装は、動きを妨げず、裾や袖が引っかからないデザインが理想です。寒暖差のある場所を移動する場合は、脱ぎ着しやすい重ね着もおすすめです。
介助者も動きやすい衣服と安定した靴を着用し、急な動きや支え方の変更にも対応できる状態を保ちます。被介助者の安全確保だけでなく、自分自身の腰痛やケガ予防にもつながります。
補助器具は壊れていないか
杖や歩行器は、歩行介助の質を左右する重要なツールです。グリップが滑りやすくなっていないか、ネジが緩んでいないか、タイヤやキャスターが正常に動くかを必ず確認します。特に杖は、高さが合っていないと逆にバランスを崩します。被介助者の肘が軽く曲がる程度の高さに調整することが大切です。
休憩できる場所があるか
体力の低下している方や長距離の歩行介助時には、休憩ポイントの設定が不可欠です。途中に椅子やベンチ、手すり付きのスペースを確保することで、被介助者が安心して移動できます。休憩は疲労を防ぐだけでなく、呼吸や脈拍の安定、姿勢のリセットにも必要です。
特に高齢者や持病のある方は、急に体調が変化する可能性があるため、無理に歩かせず、こまめに休憩を挟みましょう。
立つ位置は正しいか
介助者の立ち位置は歩行介助の支え方に直結します。片麻痺の場合は弱い側、全介助では後方や横、段差・階段では状況に応じて位置を変えます。
上り階段では後方から体を支え、下り階段では前方でバランスを見守りましょう。誤った位置に立つと、転倒時に支えきれないだけでなく、介助者自身も巻き込まれてケガをする恐れがあります。
声掛けは多くできているか
歩行介助中の声掛けは、被介助者の行動を導き、安心感を高めます。「右足を出します」「ここから段差です」「休憩しましょう」など、動作や状況を具体的に伝えることが重要です。
声掛けはただの合図ではなく、被介助者のリズムを整え、無駄な力みを防ぐ効果があります。特に高齢者は情報処理のスピードが遅くなる傾向があるため、短く分かりやすい言葉で事前に知らせる方法が有効です。
歩行介助は予防と正しい手順を確認してから行いましょう

この記事のまとめ
- 歩行介助は転倒防止と自立支援のための介護技術
- 体調確認や動線確保などの事前準備が大切
- 身体状況の把握や立ち位置など安全のコツは7つある
- 杖や歩行器は高さと状態を正しく整えて使う
- 被介助者のペースを尊重し無理なく介助を行う
歩行介助は、転倒予防と身体機能維持のための重要な介護技術です。
被介助者が「安心して歩ける」という状態は、日常生活の質の向上にもつながります。具体的な場面を想定しながら、安全で効果的な方法を実践していきましょう。
介護職員として介護老人保健施設に勤務。
ケアマネジャー取得後は、在宅で生活する高齢者や家族をサポートする。
現在はWebライターとして、介護分野に関する記事を中心に執筆している。