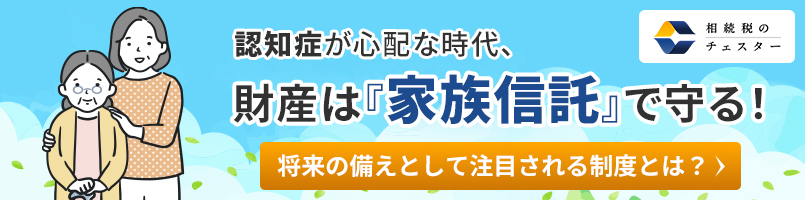【介護用品】歩行器の種類は三つ!機能の違いやタイプの選び方をご紹介

歩行器には機能的に複数の種類があるのを知っていますか?歩行器は、歩行時の転倒リスクを軽減する福祉用具です。使用する人の身体状況に応じて、全三種類の中からその人に合ったものを使用しましょう。本記事では歩行器の種類による違いや選び方について紹介しますので、目を通してみてください。
歩行器とは

歩行器は、身体機能の低下によって不安定になった歩行をカバーする介護用品です。使用者の安全確保に役立つと共に自立の促進につながるため、介助者の負担を軽減する効果も期待されています。デザインや形状は多種多様ですが、有する機能によって大きく三種類に分けられます。
歩行器の定義
厚生労働省では、歩行器を下記のように定義しています。
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る
- 車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目
引用元 | 平成11年3月31日 厚生省告示第93号
一般的に、歩行時の使用者の体重を支えられる構造のものを歩行器と呼んでいます。また、その中でも両手で持ち上げて使用する形状か、車輪付きで身体の前と左右をフレームで包むような形状であるものを歩行器と定義しています。
歩行器には、歩行が不安定になった人の身体を支えることで、転倒を予防する目的があります。歩行を安定化させることによって使用者の自立を促進し、心身状態の悪化を防ぎます。また、歩行時に見守りが必要な人が歩行器を使用することで、付き添いが不要になり、介護者の負担が軽減されるという二次的な効果も期待されています。
歩行器とシルバーカーの違い

ここからは、歩行器とシルバーカーの違いについて紹介します。
使用目的の違い
歩行器は全三種類ありますが、主な使用目的は使用者の歩行支援と転倒予防、自立の促進で、これらは種類を問わず共通です。一方シルバーカーは、高齢者が外出するときの利便性を高めるために作られた器具です。
このように、歩行器とシルバーカーは目的が異なっています。
外見や構造の違い
歩行器は使用者の体重を支える必要があるため、ハンドルやグリップを握ったときにフレームが身体を囲むような「コの字」の形状になっています。タイヤがついている種類も四方に張り出すことで、体重を支えるつくりになっているのが特徴です。このため、歩行時の安定性が低い人にとって必要な介護用品といえます。
一方シルバーカーは、上から見るとハンドルが横一文字になっており、フレームも体重を支える構造にはなっていません。三つの異なる種類に分かれる歩行器とは違い、基本的に荷物を入れるカゴと座って休憩できる機構からなっています。シルバーカーは介護というより、利便性を追求した作りが特徴です。
対象者の違い
歩行器の対象者は、歩行時に支えがないと転んでしまう恐れがある人です。一方シルバーカーは、歩行は安定しているが「物を持って歩く」「疲れやすい」などの理由で移動時の利便性を高めたいと考えている人が対象となります。
歩行器は福祉用具貸与の対象
歩行器は、福祉用具貸与の対象となっています。福祉用具貸与とは、要支援1以上の認定を受けた人が利用できる介護保険サービスです。安価で介護用品をレンタルでき、心身状況に応じて種類や品目を交換できます。
歩行器の種類と特徴

歩行器は、その形状や機能から下記の三つに分けられます。
歩行器の種類
- 固定式歩行器(ピックアップ式・持ち上げ式)
- 交互式歩行器
- キャスター付き歩行器(歩行車)
同じ種類でも形状や機能が細分化されており、対応する環境や使用方法もさまざまです。そのため、種類ごとの特徴を理解した上で、使用者が求めているものに合った歩行器を選びましょう。
ここからは、三種類ある歩行器の大まかな特徴について紹介します。
固定式歩行器(ピックアップ式・持ち上げ式)

固定式歩行器はパイプ型のフレームに足が四本ついていて、三つの歩行器の種類の中では最も安定性が高いです。軽量で折り畳みできるものもあるため、車で移動するときの持ち運びも簡単です。
使用する際は歩行器を持ち上げて一歩前に置き、追従するように一歩ずつ歩きます。三種類の歩行器の中で固定式が向いているのは、下記のような人です。
固定式歩行器が向いている人
- 上半身の筋力が維持されている人
- 歩行姿勢が比較的安定している人
- 杖では歩行が不安定になってきた人
固定式歩行器は持ち上げて使用するため、上半身の筋力とある程度のバランス能力が必要です。歩く姿勢が比較的安定し、自力で歩行する力が残っている人におすすめです。
交互式歩行器

交互式歩行器は固定式歩行器と形が似ていますが、左右の足に可動性があることが特徴です。歩行時に手を振って歩くように歩を進めると同時に、左右の足を交互に前方に動かして使います。前進するときに持ち上げる必要がないため、歩行時にバランスを崩す恐れも少ないでしょう。三種類の歩行器の中で交互式が向いているのは、下記のような人です。
交互式歩行器が向いている人
- 上半身の筋力が多少衰えている人
- 支えがないとバランスを崩してしまう人
- リズミカルに歩みを進めたい人
交互式歩行器は歩行時に持ち上げる必要がないため、上肢が衰えている人でも安全に使用できます。また、必ず左右の足のどちらかが地面に接地している状態になるため、バランスを崩しやすい人でも安定感があります。
キャスター付き歩行器(歩行車)

キャスター付き歩行器は、前方の二本もしくは四本全ての足にタイヤがついています。三種類の歩行器の中でも商品のバリエーションが豊富で、固定式歩行器の足にキャスターがついたものから、シルバーカーのように多機能なもの、バッテリー内蔵で電動アシスト機能がついたものまでさまざまです。
使い方は、キャスターを活かして進行方向に押しながら進みます。ただし、操作が難しく思わぬ事故の原因になる可能性もあるため、使う際は慣れも必要です。折り畳みができるタイプを選んでも比較的大きく重量もあるため、持ち運ぶときには介助者が必要になる場面もあるでしょう。三種類の歩行器の中でキャスター付きが向いているのは、下記のような人です。
キャスター付き歩行器が向いている人
- 上半身の筋力が衰えている人
- 足腰の痛みや筋力低下があり、歩行自体に不安がある人
- 身体を支える以外の便利機能も欲しい人
キャスター付き歩行器は、上肢の筋力が衰えている人向けの歩行器です。足腰の痛みや筋力低下によってふらつきがある人でも、前方に押し出しながら進むため安定感のある歩行が期待できます。シルバーカーのように荷物を入れるカゴや座面がついているものもあるため、便利な付加機能が欲しい人にもおすすめです。
歩行器の選び方

先述したように歩行器にはさまざまな種類や形状、機能があります。ここから紹介する選び方を参考に、最適な歩行器を見つけましょう。
歩行器の選び方
- 使用する場所や目的から選ぶ
- 自分の体格に合ったものを選ぶ
- 身体の状態に適したものを選ぶ
- プロや専門職の人に相談する
使用する場所や目的から選ぶ
歩行器は、種類によって適した場所や目的が異なります。例えば自宅の中だけであれば、どの種類の歩行器を使っても基本的に問題ありません。持ち運んで外出先でも使用したい場合は、軽量な固定式や交互式を選択するという方法もあります。中には電動アシスト付きの種類もあるため、起伏がある屋外を歩くときはおすすめです。
歩行器は、種類によって得意とする場所や場面が異なります。「自宅だけなのか、外出先でも使うのか」「歩行器を使って何をしたいのか」などを考えて選びましょう。
自分の体格に合ったものを選ぶ
歩行器は体格や身体の特徴に合わせて調整ができる介護用品ですので、実際に使用する人の体格に適した種類を選びましょう。具体的には、下記の点について確認することをおすすめします。
体格に合った歩行器選びの主なポイント
- 身長や体重に対して、大きすぎたり小さすぎたりしないか
- グリップや上腕を乗せる位置を適した高さに調整できるか
- 円背の場合、実際の身長より低く調整できるかどうか
- しっかりと体重を支えることができるか
体格が小さいのに歩行器が幅広すぎたり、大柄なのに高さが足りなかったりすると、適切に身体を支えることができません。使用者の身長・体重や変形部位などをしっかり確認した上で、身体に合った歩行器を選びましょう。
身体の状態に適したものを選ぶ
歩行器は、身体機能の低下を補うための介護用品です。使用する方の筋力やバランス能力に適した種類を選びましょう。
身体状態に適した歩行器選びの主なポイント
- 自身の力で歩行器を持ち上げたり動かしたりできるか
- ブレーキをしっかり握り込むことができるか
- 使用時、左右へのブレや歩行器だけが突出するなどの状況はないか
歩行器は、使用者の身体状況によって種類や形状・機能を選択する必要があります。歩行に直接影響する足腰の状態だけでなく、歩行器を操作する上半身の筋力やバランス保持能力も確認が必要です。
細かい使用感は実際に使ってみないと分からない部分もあるため、可能な限り実際の歩行器で試してから決めましょう。
プロや専門職の人に相談する
使用者に最も適した歩行器を選ぶためには、専門知識が必要です。これは、心身状況や持病の予後、生活環境等に応じ、専門的かつ総合的な視点で選定する必要があるためです。適切な歩行器を選ぶのが難しい場合は、福祉用具専門相談員や理学療法士、作業療法士といった専門家に相談するのもよいでしょう。
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与事業所に配置が義務付けられている専門職です。心身状況や歩行器が必要な理由などを確認しつつ、他職種と連携しながらアドバイスしてくれます。入院や通院でリハビリをしている場合は、受診先のリハビリ専門職(理学療法士や作業療法士)に相談するのも一つの方法です。
最もおすすめな相談相手は、介護保険制度のケアマネジャーです。要介護認定を受けて担当のケアマネジャーに相談すれば、福祉用具専門相談員やリハビリ専門職の方ともつながることができ、自宅の環境を見た上で選んでもらえるでしょう。
歩行器ごとの違いを理解し、身体に合った歩行器を使用しましょう

この記事のまとめ
- 歩行器は身体機能の低下によって不安定になった歩行をカバーする介護用品で、介護保険の対象
- 歩行器とシルバーカーは使用目的・対象者が大きく異なる
- 歩行器は大きく三種類あり、それぞれに対応する環境や使用方法が異なる
- 歩行器は使用目的や身体状況によって使い分ける必要があるが、選定する際は専門家に相談するのよい
歩行器を利用することで、転倒不安がある人の自立促進と介助者の負担軽減が期待できます。本記事で紹介した三種類の違いを理解し、使用者に合った歩行器を選択しましょう。
適切な歩行器の選定には専門知識が必要なため、どれがよいのか分からない場合はケアマネジャーや福祉用具専門相談員などの専門家に相談しましょう。
東北公益文科大学卒業。その後、介護保険や障害者総合支援法に関する様々な在宅サービスや資格講座の講師を担当した。現在は社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの生活相談員として、入居に関する相談に対応している。在宅・施設双方の業務に加えて実際に家族を介護した経験もある。高齢者介護分野のみならず、障がい者支援に関する制度にも明るい。