賃貸物件での孤独死、ご遺族と管理者がまず確認すべき「3つの対応」とリスクを回避するための方法

「賃貸物件に住んでいる親族が亡くなった」
「管理している物件で、入居者が孤独死された」
一生に一度あるかないかの出来事は、ある日突然やってきます。
孤独死という予期せぬ別れに直面したとき、そのお住まいが「賃貸物件」であるかどうかによって、ご遺族や物件管理者がとるべき対応は大きく異なります。
遺品の整理や清掃、原状回復、費用負担の整理、そして契約の処理など、いずれも感情的にも実務的にも重いテーマですが、「最初にどの順番で対応すべきか」を知っているかどうかで、その後の負担やトラブルのリスクは大きく変わってきます。
本記事では、賃貸物件での孤独死という状況において、ご遺族と管理者がまず押さえるべき3つの対応ポイントを、具体的かつ分かりやすく整理してお伝えします。
「賃貸物件で孤独死が発覚したとき」ご遺族と管理者がとるべき3つの対応
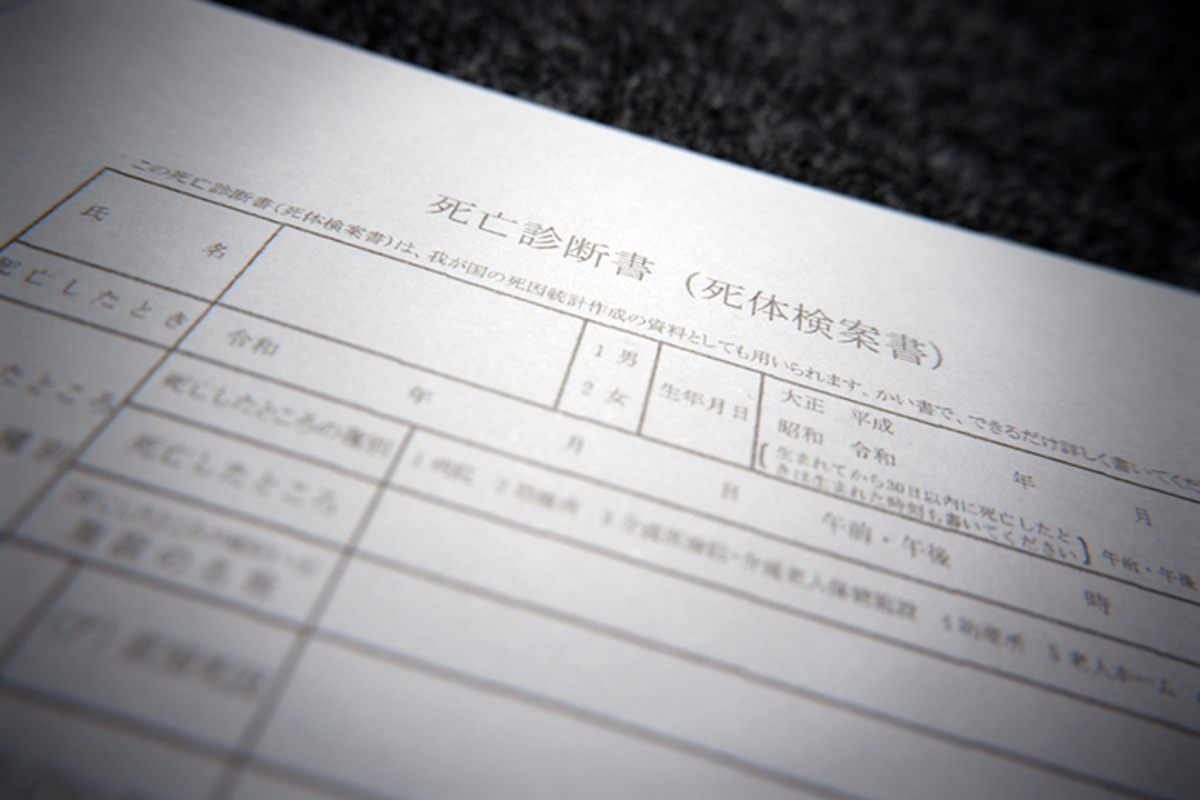
賃貸物件で孤独死が発覚した場合、事態は一気に動き出します。
ご遺族にとっても、賃貸物件を管理する立場の方にとっても、すぐに判断・対応しなければならないことが数多く発生します。
しかも、賃貸契約という性質上、関係者は法的・実務的な義務をそれぞれ異なるかたちで担うことになるため、初動を誤ると責任の所在や費用負担をめぐってトラブルになる恐れもあります。
ここでは、ご遺族と賃貸物件管理者が最初に押さえておくべき3つの対応について、それぞれの立場からの視点と、連携時のポイントも交えて整理していきます。
①賃貸物件での孤独死の発見直後にやるべき「連絡」と「記録」の基本
賃貸物件で孤独死が発覚した際、まず求められるのは迅速かつ冷静な通報と、状況の正確な記録です。
この初動が、その後の対応全体に大きく影響します。
ご遺族の場合
ご遺族が最初に孤独死を発見した場合は、迷わず119番(または110番)への通報が最優先です。
すでに死亡が確認されているような状況でも、医師または警察官による死亡の確認が必要であり、自分の判断で遺体に触れることは避けなければなりません。
あわせて、賃貸契約書や入居時の書類が手元にある場合は確認しておきましょう。
どのような契約形態か、連帯保証人や緊急連絡先が誰かといった情報は、今後の対応や費用負担の整理に大きく関係してきます。
スマートフォンなどで部屋の状態を記録(写真・動画)しておくことも重要ですが、精神的に厳しい場合は無理をする必要はありません。
賃貸物件管理者(オーナー・管理会社)の場合
賃貸物件管理者側が通報を受けて最初にすべきことも、警察や消防との連携確認です。
すでに警察が介入している場合は、現場に勝手に立ち入らず、警察の指示に従う必要があります。
その後、契約者の親族・緊急連絡先への連絡を行うことになりますが、プライバシー保護の観点から慎重な対応が求められます。
また、発見当時の室内の状況や設備への影響などは、後の原状回復や損害保険申請に関わるため、記録を必ず残しておくべきです。
可能であれば、第三者(同席者・立ち会い業者等)の存在を確保し、証拠を担保しておくとより安心です。
②ご遺族・賃貸物件管理者それぞれの立場で必要な初動対応
孤独死が発覚した直後、ご遺族と賃貸物件管理者には、それぞれに異なる「初動対応の役割」が求められます。
ここでは、関係法令や慣例に基づきながら、両者の対応内容と注意点を整理します。
ご遺族の初動対応:まずは「死亡の確認」と「賃貸契約の把握」
ご遺族が行うべき初動対応は、まず死亡の事実確認と、その後の法的手続きへの備えです。
- 死亡診断書または死体検案書の取得(※通常は警察経由で発行)
- 警察による事情聴取・現場検証への対応(身元確認など)
- 葬儀社や特殊清掃業者への連絡準備
- 故人が住んでいた部屋の賃貸契約の確認(借主か、連帯保証人の有無など)
孤独死が発生した部屋が「原状回復の対象」となるかどうか、費用負担の可能性があるかどうかを判断するには、契約内容の確認が不可欠です。
また、急いで部屋を片付けたくなるお気持ちも理解できますが、損害保険の申請や賃貸契約の整理、さらには相続手続きにおいても、居室の状態を維持したまま確認すべき点が多くあります。
不用意に整理を始めてしまうと、「退去手続き」や「相続放棄」の妨げになる可能性もあるため、まずは賃貸物件管理者と連絡を取り、必要な確認を済ませてから対応することをおすすめします。
賃貸物件管理者の初動対応:入居者の孤独死をめぐる「法的・契約的な整理」
一方で、物件を管理する側(オーナー・管理会社)は、賃貸借契約上の義務や今後の手続きに備えて、法的整理を進めることが求められます。
- 警察・消防との対応記録(立ち入り時の記録保持)
- 緊急連絡先・ご遺族への連絡(本人確認と慎重な配慮が必要)
- 死亡に伴う賃貸契約の扱いの確認(相続か終了か)
- 孤独死損害保険などの適用可否の確認
- 現場保存と原状回復に関する計画立案
特に重要なのが、「契約終了の時点」をいつと見なすかです。
相続人が契約を承継するか放棄するかによって、原状回復義務や家賃債務の範囲が変動するため、専門家(弁護士や司法書士等)への相談が必要になるケースが多いです。
③警察・消防・自治体との連携の注意点
孤独死が発覚した際には、第一報を受けた行政機関との連携が重要になります。
ここでは、それぞれの役割と連絡時の注意点を簡潔に整理します。
警察との連携
警察は、遺体の発見時に「事件性の有無」や「死因」を確認するため、現地調査(いわゆる検視・現場検証)を行います。
この際、建物の管理者(オーナーまたは管理会社)が、警察の要請に応じて鍵を開けたり、部屋への立ち入りを補助する場面も少なくありません。
調査中は、ご遺族や管理者ともに許可なく室内に立ち入ったり、遺品を持ち出したりすることは禁止されています。
死因が明確になるまでは、室内の状態を保全することが、後々の保険申請や契約整理において重要な証拠保全にもつながります。
消防との連携
消防は、119番通報によって第一発見時に警察とともに出動するケースが多く、「異臭」「応答がない」「意識不明の疑い」などの通報に対して救急搬送または現地確認を行います。
室内に立ち入る際、ドアを開ける必要がある場合には、賃貸物件管理者が鍵を提供することで立ち入りを補助することが一般的です。
また、異臭や腐敗が進行している状況では、消防隊員が安全確認を行った上で、警察に引き継ぐ形となるのが通常の流れです。
消防の役割は、主に生命反応や安全確認の初動対応であり、その後の衛生対応や片付けに関しては、賃貸物件管理者やご遺族が専門業者に手配を行う必要があります。
自治体との連携
自治体によっては、「身元不明」「引き取り手不在」などの状況において、福祉的措置や遺体の火葬埋葬手続きを行うことがあります(※死亡届や火葬許可申請も含む)。
また、孤独死の実態を把握している部署(高齢福祉課など)との連絡が、今後の対策や情報共有の起点になる場合もあります。
賃貸物件の「原状回復」と費用負担の考え方

賃貸物件で孤独死が発覚したあとは、適切な初動対応が行われたとしても、その後に問われるのが「原状回復」の問題です。
とくに、死後の発見が遅れたケースでは、体液の染み込みや臭気、害虫の発生などにより、床や壁の張り替え、消臭・消毒といった高度な処置が必要になる場合もあり、状況によっては数十万円〜100万円を超える費用がかかることもあります。
こうした原状回復費用が、誰に・どこまで請求できるのかは、契約内容や法律の解釈によって変わるため、安易に判断するとトラブルになるリスクもあります。
ここでは、「原状回復とは何か」「誰が負担すべきか」といった基本的な考え方について、実例や判例を交えながら整理していきます。
①孤独死は“原状回復義務”の対象になるのか?
原状回復とは、「通常の使用によって生じた劣化や損耗を除いた範囲で、部屋を元の状態に戻すこと」とされています。
これは国土交通省のガイドラインにも明記されており、経年劣化や通常損耗は借主の責任ではないとされています。
しかし、孤独死が発生した場合は、この原則だけでは判断がつきません。
とくに死後の発見が遅れたケースでは、体液の染み込み、強い臭気、害虫の繁殖などにより、室内に深刻な汚損が発生することが多く、こうした損耗は「通常の使用の範囲」を明らかに超えるものとして、原状回復の対象と判断されるのが実務上の一般的な対応です。
実際には、消臭・除菌・内装材の交換などに高額な処置が必要となり、原状回復費用が数十万円以上に達することも珍しくありません。
ただし、こうした費用が誰に請求されるのか、どこまでが妥当とされるのかについては、契約の内容や状況によって大きく異なります。
この点については、この後順番に解説していきます。
②費用を巡るトラブル事例と裁判所の判断
孤独死に伴う原状回復費用については、ご遺族・管理者・保証人の間でトラブルに発展するケースが少なくありません。
とくに争点となりやすいのは、「どこまでが通常損耗で、どこからが特別損耗なのか」「請求された金額が妥当かどうか」といった点です。
たとえば、東京地方裁判所の平成27年の判例では、孤独死に伴って発生した消臭・内装補修などの費用について、相続人に一部負担義務があるとしつつも、請求額のうち説明が不十分な部分は減額すべきと判断されました。
また、設備の全交換や過剰な脱臭対応について、契約上に明記されていない場合には、オーナー側が費用を負担すべきとする裁判所の判断も出ています。
こうしたトラブルを防ぐためには、請求の根拠を明確にすること、そして賃貸借契約において事前に対応方針を整理しておくことが重要です。
それでは、こうした費用は実際に誰が負担することになるのでしょうか。
次に、その点について整理していきましょう。
参考:心理的瑕疵の有無・告知義務に関する裁判例について|不動産適正取引推進機構
③ご遺族・オーナーどちらに負担が発生するのか?
孤独死にともなう原状回復費用が発生した場合、その負担者は契約内容と状況によって変わります。
基本的には故人が借主であるため、原則として相続人が責任を引き継ぐことになります。
ただし、ご遺族が相続放棄を行えば、その費用負担義務も放棄されるのが民法の原則です。
一方で、故人の契約に連帯保証人が設定されていた場合には、相続とは無関係に、契約上の義務として請求対象になる点に注意が必要です。
さらに、「ご遺族が連帯保証人も兼ねている」ケースでは、相続放棄をすれば原則として保証人としての責任も消滅しますが、放棄前に支払い行為があった場合や、放棄が認められないと判断された場合には、請求が残る可能性もあります。
また、物件の損傷が著しい場合や、近隣からの苦情が発生するケースでは、管理者側(オーナー)が自費で対応を余儀なくされるケースもあります。
このように、責任の所在が複雑になりやすいからこそ、費用請求の判断や作業の実施にあたっては、対応実績のある専門業者の選定が極めて重要となります。
ここからは、そうした「特殊清掃」の正しい理解と業者選びのポイントについて見ていきます。
専門業者の選定と「特殊清掃」の正しい理解

賃貸物件で孤独死が発生した際に、意外と見落とされがちなのが、近隣住民への配慮と対応です。
特に発見が遅れた場合には、強い臭気や害虫の発生が原因で、周囲からクレームが寄せられるケースも多く、対応が遅れることで物件や管理者への信頼が損なわれることも少なくありません。
こうしたケースにおいては、通常の清掃では対応が困難です。
感染症対策、臭気除去、汚染物の撤去といった専門的な工程を含む「特殊清掃」という領域での処置が求められます。
また、作業の質だけでなく、誰に依頼するか(=業者選び)によっても、その後のトラブルの有無が大きく変わることが実務上の事実としてあります。
ここでは、専門性の高い清掃が必要な理由、業者選定の注意点、そして“依頼者・入居者・近隣”すべてに配慮した対応とは何かについて整理していきます。
①清掃・消臭・感染症リスクへの対応は専門性が必要
賃貸物件で孤独死が発生した場合、対応には単なる掃除や片付けを超えた専門的な処置が必要になります。
とくに死後の発見が遅れたケースでは、体液や汚染物の除去、臭気の拡散防止、感染症対策といった高度な作業が不可欠です。
こうした作業は、作業手順・資機材・防護対応を含めた“段階的な工程管理”のもとで行われなければなりません。
例えば、事前の養生や封じ込めを行わずに残置物を先に撤去してしまったことで、廊下やエレベーターなど共用部に汚染が広がってしまったという実例も報告されています。
また、臭気は目に見えないため、空気中の浮遊物や表面材に付着した汚染物質を見逃すと、再発や苦情の原因になります。
さらに、C型肝炎や結核菌など、感染症リスクのある体液に対しては、適切な消毒方法と防護体制が求められるのも重要なポイントです。
このような清掃は、一般的なハウスクリーニングや遺品整理とは異なり、物件構造や被害状況を正確に判断できる技術と経験を持つ専門業者でなければ対応できません。
②悪質業者とのトラブルを避けるための選び方
特殊清掃は高度な専門性が求められる分野である一方で、その知識や作業内容が一般には知られていないため、依頼者の不安につけ込む悪質な業者も存在します。
実際に多く寄せられているトラブル事例をふまえ、依頼前に特に注意すべき3つのポイントを整理しました。
- 「即日対応」「最安値」などをうたいつつ、作業内容が不明確なまま契約を進める
- 残置物の搬出だけを先行し、臭気や感染リスクへの対策を一切講じない
- 専門資格や実績の確認ができないまま作業を始めようとする
こうした対応は、作業後に費用トラブルや近隣からの苦情につながる可能性もあるため、注意が必要です。
清掃作業は、単なる「片付け」ではなく、依頼者・入居者・近隣に安心を届ける信頼形成の一歩でもあります。
次は、その観点から、すべての関係者にとって納得のいく進め方について考えていきましょう。
③依頼者・入居者・近隣、“三方よし”で進める賃貸物件の清掃対応とは?
賃貸物件の特殊清掃において重要なのは、単に部屋を綺麗にすることではありません。
依頼者(ご遺族や管理者)にとって納得のいく対応であること、次に住む入居者にとって安心できる状態が整っていること、そして、近隣住民に不安や不快感を与えないことが重要です。
これらすべてが揃って、はじめて本当の意味での「清掃完了」といえます。
例えば、臭気や害虫の再発を防ぐには、目に見えない汚染源まで確実に処理する必要があり、その工程を丁寧に説明・共有することで、依頼者や管理会社との信頼関係も深まります。
また、近隣への配慮(貼り紙や作業時間の調整など)も、クレーム予防として不可欠です。
作業そのものだけでなく、“誰のために行うのか”を意識した清掃対応こそが、プロの仕事といえるでしょう。
今後のために検討すべき孤独死トラブルの予防策と賃貸契約内容の見直し

ここまでで、賃貸物件で孤独死が発覚した際の対応方法について整理してきました。
しかし、本質的に重要なのは、孤独死が発生したあとに慌てて対応するのではなく、あらかじめ安心できる環境を整えておくことです。
実際、契約時点での条項整理や保険の活用、入居者とのコミュニケーションの積み重ねによって、孤独死後のトラブルや混乱を未然に防げるケースは数多く存在します。
最後に、「孤独死リスクへの備え」として今からできる3つの対策を取り上げていきます。
①孤独死リスクを想定した契約条項とは?
孤独死が発生した場合のトラブルを未然に防ぐために、近年では「孤独死リスク」を想定した契約条項をあらかじめ盛り込むケースが増えており、以下のような内容が実務上取り入れられつつあります。
- 室内で死亡事故(自然死・病死を含む)があった場合の費用負担区分を明記
- 原状回復や特殊清掃に関する費用を、保証会社の保証範囲に含める契約構成
- 孤独死を含む死亡事故についての報告義務・立ち会い義務の規定化
- 相続人または緊急連絡先が不明・対応不能の場合の残置物処理の同意条項
こうした条項は、法的拘束力を持たせるためには、入居者の事前同意をきちんと得ることが前提となります。
一方的に追記するのではなく、契約時に内容を説明し、署名・押印を得ておくことがトラブル回避につながります。
また、特約として孤独死に関する対応方針を記載する場合でも、条文の曖昧さや過剰な免責内容には注意が必要です。内容が不透明だと、かえってトラブルの火種になりかねません。
リスクを回避しつつ、ご遺族や保証人との後々の交渉を円滑にするには、弁護士などの専門家に契約書の整備を相談することも一つの手段です。
②保険の活用(孤独死保険・原状回復費用補償)
孤独死に備える手段として、「孤独死保険」「原状回復費用補償」などの少額短期保険に加入する物件も増えています。
これにより、オーナー側は高額な特殊清掃や原状回復の費用を最小限に抑えることができ、一方でご遺族側も、実質的には一般的な退去時費用のみで済むケースが多くなります。
ただし、注意が必要なのは、これらの保険は補償上限が高くても100万円程度である点です。
死後の発見が大幅に遅れた場合や、建物全体に被害が及ぶようなケースでは、補償範囲を超えてしまう可能性もあります。
そのため、保険加入は有効な備えである一方で、契約内容や上限額の確認、必要に応じた複数年更新など、運用する上でも注意が必要です。
また、ご遺族や連帯保証人の立場からは、加入状況を事前に確認しておくことが望ましく、まだ保険に未加入のオーナーや管理者にとっても、今後のトラブル予防の観点から検討に値する手段といえるでしょう。
③入居者との関係性づくりが孤独死の未然防止の鍵
孤独死への備えとして最も本質的な対策は、そもそも孤独死を発生させないことにあります。
そのためには、物件の設備や契約内容以上に、入居者との日頃の関係づくりが重要な役割を果たします。
実際、孤独死にはいくつかの予兆が見られるケースがあり、ゴミ出しが滞っている、郵便物が溜まっている、室内から異臭がするといった生活の変化が、「何かあったのでは」と早期に異変に気づくきっかけになることもあります。
日常的な連絡手段を確保しておく、定期巡回を行う、近隣住民とも緩やかに情報共有できる体制をつくるなど、“誰かが気にかけている”という環境づくりが、孤独死の未然防止に直結します。
入居者を“契約上の存在”としてだけでなく、“生活者として見守る”姿勢こそが、結果的にご遺族・管理者・近隣、すべての人にとっての安心に繋がるのです。
「突然の孤独死」に直面しても、冷静に“順序立てて”対応するために

孤独死は、誰にとっても突然の出来事です。
特に賃貸物件で起きた場合、ご遺族や管理者の立場では、感情的な動揺だけでなく、契約や費用といった現実的な対応も迫られます。
だからこそ、冷静に「順序立てて」対応していくことが何より重要です。
初動での連絡と記録、原状回復の整理、専門業者の手配、そして費用や契約の確認など、一つひとつを落ち着いて進めていくことで、不要なトラブルを防ぎ、関係者すべてにとっての負担を最小限に抑えることができます。
そして、万が一に備えた保険や契約条項の整備、日頃の入居者との関係づくりも、「安心の準備」として非常に有効です。
孤独死というテーマは重く感じられるかもしれませんが、関係者が安心して対応できる環境は、あらかじめ整えることができます。
その現実的な視点と備えこそが、今を生きる私たちに求められている姿勢ではないでしょうか。
ブルークリーン株式会社 代表取締役
1992年 東京生まれ。奄美諸島出身の父とメキシコ人の母の間に生まれる。都立雪谷高校を卒業後、IT企業(東証グロース上場企業)やリフォーム業を経て起業。米国バイオリカバリー協会から認定を受けた、日本人唯一のバイオリカバリー技術者。
[資格&修了]
・米国バイオリカバリー協会 公認バイオリカバリー技術者
・全米防疫技術研究所(NIDS)マスターズコース修了認定
・公益社団法人日本ペストコントロール協会 1級技術者

















