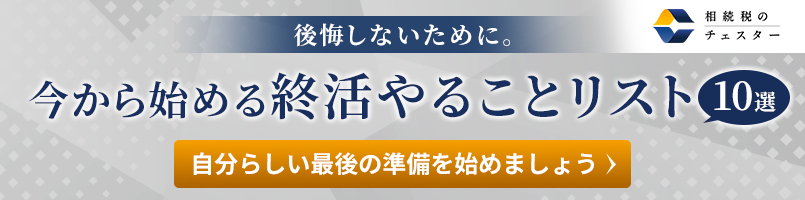孫に遺産相続はできる?受取人となるための注意点や方法を解説

自分の遺産を孫に相続させたいと考える人も多いのではないでしょうか。孫は原則的に相続人ではないため、孫に遺産を相続させるには事前に対策をしておく必要があります。本記事では、孫に遺産相続させる方法や、孫が遺産を受け取る際の注意点などを解説します。
孫に遺産相続はできる?

相続させたい孫がいても、何もしなければ孫は遺産相続できません。遺産相続できる親族の範囲は民法で定められていますが、その中に孫は含まれていないためです。ただし、自分の子が自分より先に亡くなっていたら、子の子である孫が遺産相続できるという例外があります。
孫は原則的に遺産相続できませんが、生きているうちに対策しておくことで、孫に遺産相続させることは可能です。孫に遺産相続させる方法にはいくつかありますが最適な方法を選びましょう。
孫に遺産相続させるには事前の準備が必要

孫に遺産を承継すると相続を1回分飛ばせるため、相続税を抑えられることもあります。
ただし、前述したとおり、孫に遺産を相続させるには、あらかじめ準備が必要です。ここでは、孫への遺産相続に事前の準備が必要な理由について説明します。
孫は原則的に相続人ではない
亡くなった人の遺産を相続できる親族は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。先述のとおり、孫は通常は相続人にはなりません。なお、配偶者は常に相続人ですが、配偶者以外の親族には優先順位があり、先順位の人がいない場合に相続人になります。
| 配偶者 | 常に相続人 | ||
| 子 | 第1順位の相続人 | ||
| 直系尊属 | 第2順位の相続人 | ||
| 兄弟姉妹 | 第3順位の相続人 | ||
孫が相続人になるのは代襲相続の場合
代襲相続とは、本来相続人になる人が被相続人(相続される人)よりも先に亡くなっている場合に、その次の世代が代わりに相続する仕組みです。孫は通常は相続人になりませんが、代襲相続により相続人になることがあります。
被相続人の子(第1順位の相続人)が既に亡くなっている場合、亡くなった子の子(被相続人の孫)がいれば、孫が代襲相続します。孫が相続人になって遺産を相続できる事例はそれほど多くないのです。
相続人でない孫にも遺産相続させることは可能
孫が相続人ではない場合でも、孫に遺産を相続させることはできます。ただし、相続人でない孫に遺産を相続させるには、事前の準備が必要です。孫に遺産を相続させるには、次の四つの方法があります。
孫に遺産を相続させる方法
- 孫と養子縁組をする
- 孫に遺産を相続させる旨の遺言書を書く
- 孫に生前贈与をする
- 孫を受取人に指定した生命保険に入る
孫に遺産相続させる4つの方法

ここからは、孫に遺産を相続させる方法について、具体的な内容や注意点を説明します。
① 孫と養子縁組する
養子縁組をして孫を自分の養子にすれば、孫を法律上自分の子にできます。養子縁組とは、法的な親子関係を作るための手続きのことです。孫と養子縁組の合意をした上で役所に届け出れば、孫を養子にできます。
養子になった孫は、相続についても実子と同じ扱いになるため、第1順位の相続人となります。養子と実子では、相続できる割合(法定相続分)にも差はありません。孫は他の子と平等に遺産を相続します。
未成年者との養子縁組には通常家庭裁判所の許可が必要ですが、孫の場合には未成年でも許可なく養子にできます。ただし、未成年の孫と養子縁組する場合、親権者(通常は自分の子)の承諾が必要です。
② 遺言書を書く
遺言書を作成すれば、法定相続人でない孫にも遺産を相続することが可能になります。遺言書に書いた内容は、民法上の相続のルールよりも優先されるからです。なお、遺言書により遺産を取得させることを「遺贈」といいます。
遺贈する際の注意点として、遺留分(民法で保障されている最低限の相続割合)を持った相続人の権利を奪えない点があります。なお、遺贈には特定遺贈と包括遺贈の二つの方法があり、どちらの方法で遺贈してもかまいません。
遺贈の種類
- 特定遺贈…不動産、預貯金など特定の財産を指定して遺贈する方法
- 包括遺贈…「遺産の4分の1」など、割合を指定して遺贈する方法
遺言書は民法で定められた方式で書く必要があり、要件を満たしていない遺言書は無効となってしまいます。手書きの遺言書でも、要件を満たしていれば有効です。
③生前贈与する
孫に資産を残したい場合、自分が生きている間に贈与する方法(生前贈与)もあります。生前贈与は、財産を譲る側と受け取る側が合意すれば可能です。つまり、孫と話し合って了承が得られれば、孫に確実に財産を渡すことができます。なお、孫が未成年者の場合には、親権者の承諾が必要になります。
生前贈与では贈与税がかかりますが、贈与税には年間110万円の非課税枠があります。年間110万円を限度に生前贈与すれば、贈与税もかからず、税務署への申告義務もありません。110万円の非課税枠を活用する方法は「暦年贈与」と呼ばれます。暦年贈与をすれば、贈与税の負担なく、孫に少しずつ財産を移すことも可能です。
④孫を生命保険の受取人にする
生命保険を活用して孫に遺産を残すこともできます。生きている間に生命保険に入り、孫を受取人に指定しておけば、自分が亡くなったときに孫が保険金を受け取れます。
生命保険金は民法上の相続財産ではなく、受取人固有の財産です。遺産分割の対象ではないため、他の相続人に分ける必要もありません。ただし、生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になるため、孫が相続税を負担しなければならない場合があります。
孫が遺産の受取人になる場合の注意点

さまざまな方法により、孫に遺産を取得させることは可能です。ただし、孫が遺産を受け取る場合には、注意しておかなければならないこともあります。ここからは、孫が遺産の受取人になる際の注意点について説明します。
親族間でトラブルになる恐れがある
孫は本来相続人ではないため、孫に遺産を相続させることで他の相続人に影響が出てしまい、親族間でトラブルになる恐れがあります。
たとえば、孫を養子にした場合、他の子達の相続分が減ってしまいます。もし養子縁組に不満を持つ人がいれば、遺産分割がスムーズに進まないでしょう。遺言書や生前贈与で孫に財産を取得させた場合も同様に、他の親族が相続できる財産が減ってしまうため、トラブルに繋がる場合があります。
親族間で対立が生まれると、孫が肩身の狭い思いをすることになってしまいます。孫に遺産を譲りたいなら、事前に他の相続人の了承を得ることがおすすめです。
他の相続人の遺留分に注意する
孫へ遺贈や生前贈与を行う場合、他の相続人の遺留分に注意しておかなければなりません。遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分です。遺留分の割合は相続人の組み合わせによって、次のように変わります。
| 相続人の組み合わせ | 相続人全員での遺留分 | 各相続人の遺留分 | |
| 配偶者のみ | 1/2 | - | |
| 配偶者と子 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 | |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2 | 配偶者2/6、直系尊属1/6 | |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | 配偶者1/2、兄弟姉妹なし | |
| 子のみ | 1/2 | - | |
| 直系尊属のみ | 1/3 | - | |
| 兄弟姉妹のみ | なし | - | |
たとえば、亡くなった人の残した財産が4,000万円、相続人が妻と長男、次男の3人である場合、妻の遺留分は1,000万円、長男と次男の遺留分はそれぞれ500万円ずつです。相続人の遺留分2,000万円を確保すると、孫に譲れる遺産は2,000万円までとなります。
孫が遺産を受け取ったことで他の相続人が遺留分を取得できなくなった場合には、孫に対して遺留分侵害額請求ができます。孫が遺留分侵害額請求を受けた場合には、遺留分を金銭で返さなければなりません。
孫に遺産を渡し過ぎると、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。孫へ遺産を譲るときには、他の相続人の遺留分を奪わないよう限度額を考えて行いましょう。
孫の相続税は2割加算になる
一定の規模以上の遺産がある場合には、遺産を受け取った人に相続税がかかります。相続税額は取得した財産額に比例しますが、被相続人に近い一部の親族を除き、納税額が2割加算されるルールがあります。孫は原則的に相続税の2割加算の対象です。
相続税が2割加算されないのは、配偶者と1親等の親族(父母、子)です。ただし、孫を養子にしている場合には、養子は1親等ですが、2割加算の対象になります。なお、代襲相続により孫が相続人となった場合には、2割加算の対象にはなりません。
| 2割加算にならない人 | 2割加算になる人 | ||
| ・配偶者 ・子 ・父母 ・子を代襲相続した孫 ・養子(孫である人を除く) |
・兄弟姉妹 ・祖父母 ・甥・姪 ・上記以外の親族(孫も含む) ・孫養子 ・親族以外 |
||
登録免許税や不動産取得税の負担が増える
不動産を相続する場合は法務局で不動産の名義変更(相続登記)を行う必要があり、相続登記の際には登録免許税がかかります。相続人でない孫への相続登記では、相続人への相続登記よりも登録免許税が高くなります。
相続及び遺贈を原因とする相続登記の登録免許税は、次のとおりです。
| 登録免許税の税率 | |||
|---|---|---|---|
| 「相続」の場合 | 固定資産税評価額の0.4% | ||
| 「遺贈」の場合 | 固定資産税評価額の2% (ただし、法定相続人への遺贈は0.4%) |
||
相続人が遺産を承継する「相続」に対し、遺言書により遺産を承継させる「遺贈」は登録免許税が5倍高くなります。通常、相続人でない孫に死亡時に不動産を譲るには、遺言書を書いて遺贈しなければなりません。そのため孫が不動産をもらう場合には、登録免許税の負担が大きくなってしまうのです。
不動産を取得したときには、不動産取得税もかかります。相続による取得の場合には、不動産取得税は非課税です。一方、相続人以外が特定遺贈により不動産を取得する場合には、不動産取得税が課税されます。相続人でない孫が不動産をもらう場合、不動産取得税がかかる場合も多くなっています。
生前贈与では贈与税対策をする
生前贈与をする際の注意点の一つが、贈与税がかかることです。贈与税は受け取った側の孫が負担することになるため、なるべく負担のない方法で贈与する必要があります。
孫への年間の贈与額を110万円以下に抑えれば、贈与税はかかりません。また、特定の目的で孫へ金銭を贈与する場合には、一定の限度額まで非課税になる特例もあるため活用しましょう。
贈与税の非課税特例
- 教育資金贈与の特例(孫ひとりにつき1,500万円まで非課税)
- 結婚・子育て資金贈与の特例(孫ひとりにつき1,000万円まで非課税)
- 住宅取得資金贈与の特例(省エネ住宅の場合孫ひとりにつき1,000万円まで非課税)
孫に遺産相続させるなら親族間のトラブルや税金に注意しましょう

この記事のまとめ
- 通常は孫は相続人にならない
- 孫に遺産を相続させるには養子縁組や遺言書を書くなどの方法がある
- 孫に遺産を相続させるときには他の相続人の了承を得ておく
- 孫が遺産を相続する場合には相続税が2割加算になる
- 孫に生前贈与するなら暦年贈与や非課税特例を活用する
孫に遺産を相続させたい場合、事前にすべき準備や注意点について知っておくことが大切です。孫に遺産を相続させると、他の相続人が相続できる遺産が少なくなります。孫が将来トラブルに巻き込まれないよう、他の相続人の理解を得るようにしましょう。税金についても知識を持っておき、孫の負担を軽くすることも大切です。
神戸大学法学部卒業。鉄鋼メーカー、特許事務所、法律事務所で勤務した後、2012年に行政書士ゆらこ事務所を設立し独立。メインは離婚業務。離婚を考える人に手続きの仕方やお金のことまで幅広いサポートを提供。法律・マネー系サイトでの執筆・監修業務も幅広く担当。