「三途の川を渡る」言葉の意味とは?六文銭や石積みなどとの関係も解説

死者があの世へ旅立つ際の表現として用いられる「三途の川を渡る」という言葉は、どのような意味があるのでしょうか。本記事では、三途の川の意味や由来、六文銭や石積みとの関係についても解説します。また、世界における三途の川と似た言い伝えも紹介するため、ぜひご覧ください。
「三途の川を渡る」とは?言葉の意味や由来

「三途の川を渡る」は、人が亡くなったときによく使われている言葉です。ここではその意味や由来、死を表す理由について解説します。
「三途の川を渡る」の意味
「三途の川を渡る」とは、人が亡くなった後に、この世からあの世に旅立つことを意味する言葉です。三途の川は仏教の死生観に由来し、この世(此岸)とあの世(彼岸)を隔てる川を指しています。
また、命の危機に瀕している状態などを示す際、比喩的に使われることもある言葉です。大病を患ったり事故で瀕死の状態になったりしたが、一命を取り留めたという意味で「三途の川を渡りかけた」と表現されることもあります。
三途の川の由来
三途の川の由来は、仏教の「六道輪廻」という思想です。仏教では、人は亡くなってから「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」「修羅道」「人間道」「天道」の六つの世界への生まれ変わりを繰り返すとされています。
この六つの世界のうち地獄道、餓鬼道、畜生道の三つを「三悪道」と呼びます。仏教における「三途」とは、この三悪道を指す言葉です。つまり、3つの世界を分ける川ということから三途の川と呼ばれるようになったとされています。
ほかにも、「川の渡り方が三通りあるため」という説もあります。
三途の川が死を表す理由
仏教における三途の川は、この世とあの世の境界です。三途の川を渡ってしまうと、二度と引き返すことはできないとされています。この、決して引き返せない状況が「人生の終わり」を意味するという解釈から、三途の川が死を表すようになったのです。
また、死は必ず訪れるものですが、その瞬間や死後にどうなるかについては分かりません。そのため、川を渡るという誰もが理解しやすい情景に例えることで、死の瞬間や死後の世界がイメージしやすくなったとされています。
このように、三途の川は生と死の境界を表す象徴として、日本文化に根付いてきました。死をより深く考え、日頃の行いを振り返るきっかけにしていたとも考えられます。
三途の川の渡り方の違い

三途の川の渡り方は、生前の行いによって異なるとされています。渡り方の違いについては諸説ありますが、ここでは一般的な考え方を紹介します。
善人の場合
生前に悪行をせず善行を積んできた人は、金や銀、七宝でできた橋を渡れるといわれています。善人は、美しく安全な道を楽に渡れるのが特徴です。生前によい行いを重ねたことへの報いでもあるのでしょう。
仏教ではこうした教えを、人々が善悪を判断する基準としています。正しい行いをすることが、よい結果につながると信じられているためです。
軽い罪を犯した場合
特別な悪行を行わず、軽い罪を犯した場合は、「山水瀬(さんすいせ)」と呼ばれる三途の川の浅瀬を渡るとされます。
橋を利用するほど楽ではありませんが、あまり苦労することなく自分の足で渡れるとされています。善悪の判断は非常に厳格で、わずかな罪であっても苦しみが加わると考えられています。
重い罪を犯した場合
重い罪を犯した場合は、三途の川の下流にあるとされる「強深瀬(ごうしんせ)」あるいは「江深扶(こうしんえん)」と呼ばれる場所を自力で渡らなければなりません。
流れが激しく水深の深い場所であるため、流されたり溺れたりする危険があります。三つの渡り方の中でも、最も苦痛を伴うものです。
三途の川と六文銭の関係

三途の川の渡り方は生前の行いによって違いがあると解説しましたが、平安時代末期になると、三途の川を渡る際に、渡し船に乗るという考え方に変化しました。その際に必要とされているのが六文銭です。ここでは、三途の川と六文銭の関係について詳しく解説します。
六文銭とは
三途の川は亡くなった人がこの世からあの世へ旅立つときに渡るとされる川ですが、その渡し船に乗る際に、渡し賃として必要になるのが六文銭です。
三途の川には番人として鬼の夫婦がいるとされ、六文銭を持っていないと衣服を奪われるといわれています。そのため、納棺の際にお金を一緒に収める慣習が生まれました。
現代の葬儀での扱われ方
棺に収める六文銭は、かつては本物のお金が使われていました。しかし、現代の葬儀では、法律上の問題や硬貨の燃え残り観点などから、本物のお金を収めることができません。
代わりに六文銭を模したプラスチック製のものや、紙に六文銭を印刷したものなどが使われており、葬儀の際に葬儀社から購入する、あるいは葬儀の料金に含まれている場合もあります。
三途の川と石積みの関係
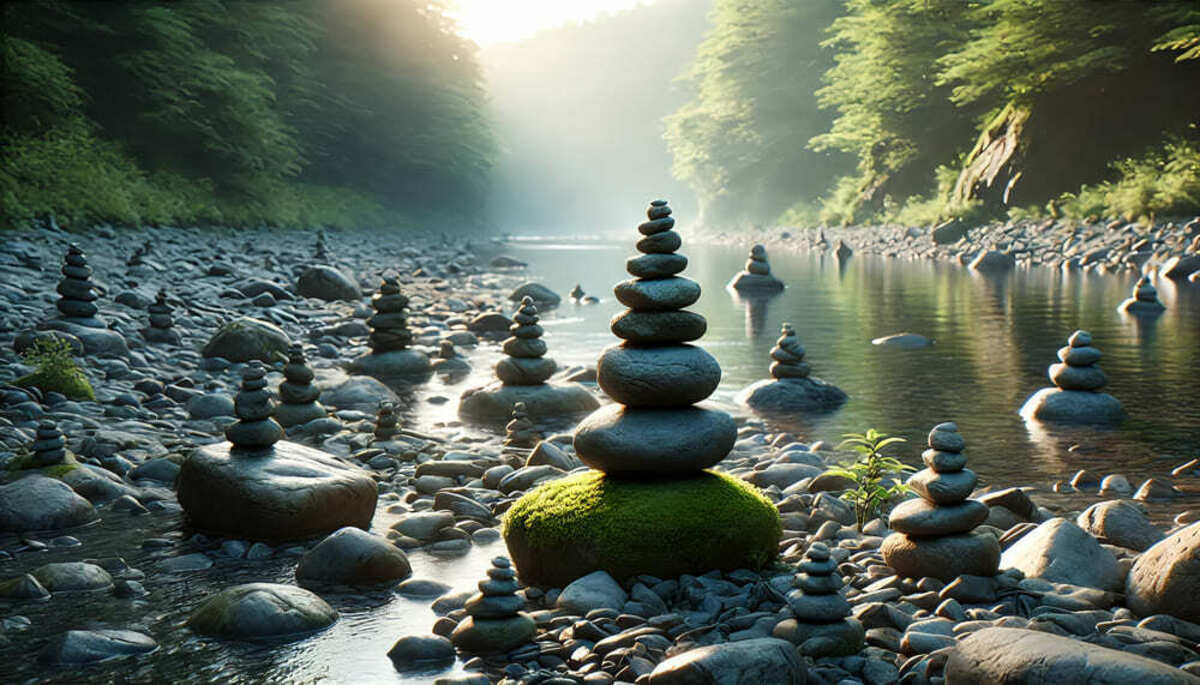
ここからは、三途の川と石積みの関係について解説します。
石積みとは
石積みとは、仏教の教えに由来する物語に登場する行為で、親より先に亡くなった子供たちが親不孝の罪を償うための苦行です。小石を積んで塔を作ろうとするのですが、完成間近になると鬼がやってきて壊してしまいます。そのため、子供たちは何度も繰り返し石を積み続けるのです。
この苦行は親が子供の死を悲しみ、苦しんでいる間は続くとされています。しかし、いつの日か地蔵菩薩が現れて、その苦しみから子供たちを解放し、成仏させてくれるとも信じられていたのです。
賽の河原とは
賽の河原とは、三途の川の手前にあると伝えられる河原です。親よりも先に亡くなった子供たちが、その罪を償うために石積みをしている場所とされています。 この場所では、子供たちが積み上げた石の塔を崩されるだけでなく、「奪衣婆(だつえば)」や「懸衣翁(けんえおう)」といった鬼の夫婦にも責め立てられるといわれています。
奪衣婆は、亡くなった人の衣服をはぎ取る老婆の鬼です。懸衣翁は奪衣婆と同様に三途の川のほとりにいる老人の鬼で、はぎ取った衣服を三途の川のほとりにある大木、衣領樹(えりょうじゅ)の枝にかけて、枝の垂れ具合によって生前の罪の重さを計るとされています。
現代の供養と賽の河原の関係
現代において、賽の河原の信仰が儀式として表現されることはほとんどありません。賽の河原の物語は子供に先立たれた親の悲しみや罪悪感から生まれたもので、仏教の正統な教義ではないためです。
ただし、子供が亡くなった家庭ではお地蔵様を祀ったり、流産や死産などで亡くなった場合は水子地蔵を建立して供養したりすることもあります。
また、墓地やお地蔵様が祀られている周りに小石を積む行為は、賽の河原の石積みの名残といえるでしょう。亡くなった子供たちに代わって石を積み、彼らの苦しみを和らげたいという願いの表れとも考えられます。
世界における三途の川と似た言い伝え

世界には三途の川と似た言い伝えがあります。ここでは、「インド」「エジプト」「ギリシャ」の3つの国の言い伝えを紹介します。
インド
インドにおける三途の川とされているのが、ガンジス川です。ヒンズー教では、ご遺体を火葬した後の遺骨をガンジス川に流すことにより、よい人生に生まれ変わるとされてきました。
三途の川を渡ることにより輪廻転生で生まれ変わるという、仏教の教えにも似ています。
また、古代インドのヒンズー教の神話では、亡くなった人が死後に渡る川として「ヴァイタラニー川」が登場します。この川の水は熱くて臭く、人の髪の毛や血、遺骨なども流れており、地獄の入り口とされているのです。
かろうじて細い橋が架かっており、渡り切った後にヤマ神(死と正義を司る神)による審判を受けるといわれています。
エジプト
古代エジプトでは、人は亡くなった後にその魂が厳しい旅に出ると考えられていました。死後の世界の旅では、「死者の書」を頼りにして冒険を行うとされていたのです。
ナイル川はあの世にもあると信じられており、亡くなった人は太陽神ラーの船に乗り、あの世にある天空のナイル川を渡るとされていました。
渡し守が漕ぐ船での旅を終えると、冥界の王オシリス神による審判を受けるとされています。生前の行いが死後の運命を左右するのも、仏教の死生観と似ている点です。
ギリシャ
ギリシャ神話の中にも、この世とあの世の境界となる「スティクス川」が登場します。冥界を七重に取り巻く川であり、その冥界の入り口にあるのが支流の「アケローン川」です。
渡し守のカロンに船賃を払うと、亡くなった人の魂が川を渡れるとされています。このことから、古代ギリシャでは「オボロス貨」と呼ばれる硬貨を亡くなった人の口に入れて埋葬する慣習がありました。日本における六文銭ともよく似ています。
三途の川の意味を理解し、日頃の行いを振り返りましょう

この記事のまとめ
- 「三途の川を渡る」とは、人が亡くなった後この世からあの世に旅立つことを意味する言葉である
- 三途の川の由来は仏教の「六道輪廻」の思想を起源とし、三途とは「地獄道」「餓鬼道」「畜生道」の三つの世界を意味する
- 三途の川の渡り方は生前の行いによって異なり、善人は橋、軽い罪を犯した人は浅瀬、重い罪を犯した人は激流を渡るとされる
- 三途の川の渡し賃として「六文銭」が必要で、現代では六文銭を模したプラスチックか、紙に印刷されたものを棺に入れる
- 賽の河原は三途の川の手前にあり、親より先に亡くなった子供が石を積む苦行で親不孝の罪を償っている
- インド・エジプト・ギリシャなどにも三途の川と似た言い伝えがある
三途の川とは、この世とあの世を隔てる川で、生前の行いによって渡り方が異なります。善人は橋を使って簡単に渡れますが、重罪人は激流を渡らなければならないとされています。三途の川を渡るという意味を理解し、日頃の行いを振り返ってみるのもよいでしょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。




















