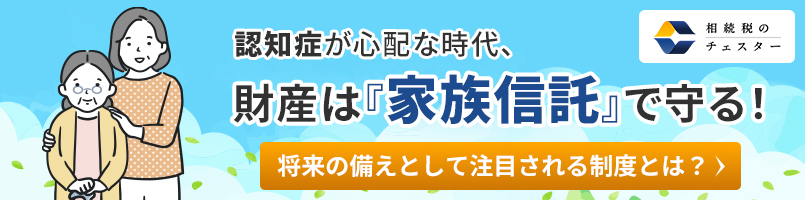【死期が近い人の特徴】表情や身体的症状、精神面での変化について解説

死期が近くなると人は表情や身体、精神面でも変化が現れます。どのような変化が起こるかを理解することは、大切な人の最期に寄り添うために重要です。本記事では、死期が近い人の表情の特徴や身体的症状、精神面での変化などを詳しく解説します。また、死期が近い人に対して家族ができることにも触れているため、参考にしてみてください。
死期が近い人の表情の特徴

死期が近い人は、表情に特徴的な変化が現れることがあります。特に目元は人の身体や意識の状態が映し出される部分でもあり特徴が現れやすいため、死期が近い人のサインの一つとなるでしょう。ここでは、死期が近い人の表情の特徴を三つ紹介します。
目の力が弱くなる
死期が近い人の特徴として、身体機能の低下により目の力が弱くなることがあります。さらに、筋肉も衰えていくため、まぶたの開閉がうまくできず、目を開けたまま眠ることもあります。
これは、身体のエネルギーを温存するための自然な現象でもあるため、無理に目を閉じるような対応はせずに見守ってあげるのがよいでしょう。
目の焦点が合わなくなる
目の焦点が合わなくなるのも、死期が近い人の特徴の一つです。ご家族が目を見つめても、死期が近いご本人の意識が朦朧としていて目が合う感覚がなくなることもあります。
また、遠くを見つめるようになったり、黒目がぐるぐると動いたり、白目をむいたりすることがあることも特徴です。ただし、死期が近いご本人と目の焦点が合わなくなっても、周囲にいる人の声は聞こえている可能性もあります。
目の色が濁る
死期が近い人は、目の色が濁って見えるという特徴もあります。例えば、白目の部分が黄色っぽくなったりどんよりとした色になったり、目の潤いが失われた状態です。
一般的に、まばたきをすることで目に潤いを与えますが、死期が近い人は筋肉が衰えたり意識が低下したりしてまばたきの回数が減るため、目が乾きやすくなるのも原因の一つでしょう。
死期が近い人の身体的症状

死期が近い人は、表情の変化だけでなく身体的症状にも変化があります。ご本人が安らかに過ごせるように、症状の特徴を理解しておけば心の準備をすることもできるでしょう。ここでは、死期が近い人の身体的症状を五つ挙げています。
身体のにおいが変化する
死期が近いと身体のさまざまな機能が低下し、身体のにおいが変化する場合があります。甘酸っぱいにおいや線香のようなにおいがすることが多くありますが、これは体内の代謝機能が低下し、老廃物が体内に蓄積することが原因とされています。
食事や水分摂取量が減る
死期が近いと食欲がなくなることも多いため、食事や水分摂取量が減ってしまいます。消化機能も低下するため、栄養を摂取させようとして無理に食べさせると、かえって身体に負担をかける可能性もあります。
本人が欲しいと望むものを少量ずつ与えたり、口を湿らせてあげたりして、無理に食べさせないようにするのがよいでしょう。
呼吸が変化する
呼吸の変化も、死期が近い人のサインの一つです。心肺機能も低下してしまうため、呼吸が浅く速くなったり不規則になったりします。また、死期が近い人は「下顎呼吸(かがくこきゅう)」や「死前喘鳴(しぜんぜいめい)」という症状が起こるのも特徴です。
下顎呼吸は、下顎を上下にパクパクと動かし大きく呼吸します。呼吸中枢と呼ばれる機能が衰え、自動的に呼吸するのが難しくなっているためです。
一方、死前喘鳴は、呼吸するときにゴロゴロという音がします。喉や気官に分泌物が溜まるのが原因です。どちらも死期が近い人の生理的なサインとされています。
死期が近い人の呼吸が変化した際の家族の対応として、体勢を変えたり、部屋の湿度を調整したり、声掛けをするといった方法でケアするのもよいでしょう。
手足が冷たくなる
死期が近い人のサインの一つとして、心肺機能や血液の循環機能が低下により手足が冷たくなるという症状もあります。
さらに、血液の循環が悪くなることで、肌の色や爪の色などが紫色や青色っぽくなる「チアノーゼ」という症状が現れる場合もあります。
死期が近いと起こる現象なため恐ろしいことではありませんが、ご本人が安心して過ごせるように、優しく手足をさすってあげるのもよいでしょう。
意識が混濁する
死期が近いと脳機能も低下していき、意識が混濁するという特徴もあります。うわ言を発したり過去の話をしたり、支離滅裂なことを言ったりして意思疎通が難しくなることもあるでしょう。
脳の働きが低下することで、幻想や妄想を抱く場合もあり、呼びかけに反応しないこともあります。会話中に眠ってしまったり、意識がぼんやりとしたりといった症状が続くのも特徴です。
また、死期が近い人は話している途中に眠ってしまい、会話が成り立たなくなる場合もあります。ただし、意識がはっきりしている時間が減り、目をつむっている時間が長くなっても、聴覚は最後まで残るとされているため安心させてあげる対応をとることも大切です。
死期が近い人の精神面での変化

死期が近い人は、表情や身体的症状の変化のほかに、精神面でも大きく変化が現れる場合があります。これは、ご本人が死を受け入れて、最期のときを迎えるための心の準備をしているサインともいわれています。ご家族は精神面での変化を理解し、見守ることも大切です。
消極的になる
死期が近い人の特徴として、消極的になることが挙げられます。日中の行動や活動量が減り、口数も少なく、テレビや新聞など外部のものに興味を示さなくなる傾向があり、それまで楽しんでいた趣味に関心がなくなるなども死期が近い人のサインです。
これは、肉体的な衰えに加え、生命への執着が薄れていることが原因ともいわれています。一方で、死期が近い人が安らかな状態へと移行していくための自然な過程でもあるのです。
その際は、励ましたり無理に活動を促したりせず、そばに寄り添ってあげるのがよいでしょう。死期が近い人の中には、痛みや苦しみなどから早く解放されて、最期のときを静かに迎えたいと願っている人もいます。死期が近い人の思いを尊重し、心静かに過ごすのもご家族のケアの一つといえます。
お迎え現象が起こる
お迎え現象とは、死期が近い人がすでに死亡しているご家族や友人を見たり、その声を聞いたりする体験を指します。また、人によっては仏様や天使などを見る場合もあるといわれている現象です。
医学的や科学的な証明はされていませんが、死期が近い人の多くが経験するともいわれています。死期が近い人がこの経験をすることは、死に対する恐怖を和らげて、心安らかに旅立つための準備とも考えられるでしょう。
死期が近い人にお迎え現象が起きたときは、否定をせずに優しく相槌を打ってあげるのが、安心させるのによい方法です。
中治り現象が起こる
中治り現象とは、死亡する数日前から数週間前に一時的に体調が回復する現象です。それまで食欲がなく食べられない日が続いていたのに急に食欲が出たり、朦朧として意思疎通が難しかったのに家族との会話が弾んだりします。
家族にとっては嬉しい出来事ですが、その後体調が急激に悪化することが多いです。中治り現象が起こったら、ご家族は心の準備をしておくことも必要でしょう。
「病気が治るのでは?」などという過度な期待をしたり、ご本人に無理をさせたりせず、静かに語り合ったりそばに寄り添ったりして、穏やかな時間を過ごすことが大切です。
死期が近い人のために家族ができること

死期が近いと感じると、人は不安や恐れを抱くことも多いです。そんなときにご家族がそばにいれば、死期が近い人の不安や恐れも和らぐでしょう。ここでは、死期が近い人のために、家族ができることについて紹介します。
できるだけ話しかける
人が持つ五感の中でも、聴覚は最後まで残るといわれているため、死期が近い人にはできるだけ話しかけるようにすることをおすすめします。意識が混濁していたとしても、話しかけたり好みの音楽をかけたりするのは安心感を与えるのによい方法です。
特にご家族が優しく話しかけることで、返事はなくても安らぎを感じてくれるでしょう。話す内容は特別なことでなく、その日にあった出来事のようなささいな事でも構いません。また、家族で過ごした楽しい思い出や感謝の気持ちなどを伝えるのも、安心感を与えられる可能性が高いです。
さらに、言葉に加えて、ご家族が手を握るといったスキンシップも温もりが伝わりやすくなります。
顔や枕を綺麗にする
死期が近い人は寝たきりになることも多く、身体を清潔に保つのが難しくなります。そのため、蒸しタオルで顔や口元を拭いてあげると、不快感を軽減できるでしょう。顔や頭の触れる枕も枕カバーをこまめに交換するなど、清潔に保つよう心掛けることが大切です。
髪を梳かしたり身だしなみを整えたりすることは、死期が近い人の尊厳を守ることにもつながります。大切にされていると感じ、最期のときまで心安らかに過ごせるでしょう。
死後の話や不満を言わない
死後の話や不満などは、死期が近い人の前で言うのは避けましょう。ご本人が家族の負担になっていると感じて、胸を痛めてしまう可能性もあります。
自分のせいで家族に迷惑をかけているという思いを抱いてしまうと、肉体的にも精神的にも不必要な苦痛を与えてしまうかもしれません。
介護の不満や死後の手続き、相続の話などはさまざまな話し合いや連絡が必要ですが、死期が近い人のいない場所で行うことが大切です。親戚や葬儀社への連絡など話し合いが必要なときは、ご家族のみで行うようにしましょう。
死期が近い人の特徴を知り、悔いのない時間を過ごしましょう

この記事のまとめ
- 死期が近い人は、目の力が弱まったり焦点が合わなくなったり色が濁ることがある
- 死期が近いと身体の代謝機能が低下するため、独特のにおいが発生するのも特徴の一つ
- 消化機能も衰えるため食欲もなくなるが、無理に食べさせるのは避ける
- 下顎呼吸・死前喘鳴など呼吸の変化も見られるようになる
- 中治り現象で、一時的に回復したように元気になることもある
- 消極的になる、お迎え現象など精神面での変化も見られる
- 聴覚は最後まで残るため、意識が混濁しても話しかけることが大切
- 死期が近い人の前で死後の話や葬儀社への連絡などを行わない
死期が近い人には表情や身体的症状、精神的な変化などさまざまな特徴があります。死期が近い人が死を受け入れて穏やかに過ごし、安らかに旅立つ準備期間でもあるため、変化の特徴を知って悔いのない時間を過ごすためにお役立てください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。