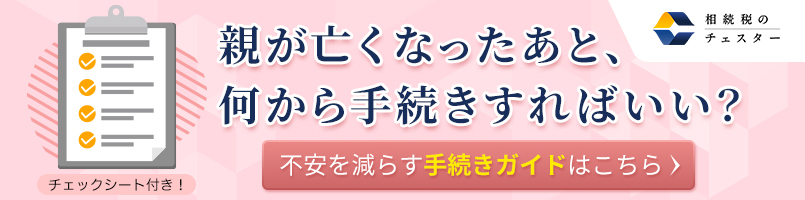身内だけの新盆の服装は何を選ぶ?参列のマナーとあわせて解説

故人が亡くなって忌明け後に初めて迎えるお盆を「新盆(にいぼん)」といいます。新盆の法要を身内だけで執り行う場合、どのような服装で参列したらよいのか迷う方もいるでしょう。本記事では身内だけの新盆の服装を、男女と子供に分けて紹介します。新盆の準備や流れについても解説しますので、参考にしてください。
新盆とは

「新盆(にいぼん・はつぼん・あらぼん)」は、故人が亡くなって四十九日を過ぎたあと、つまり忌明けに初めて迎えるお盆のことをいいます。また新盆は「初盆(はつぼん・ういぼん)」とよぶ場合もあります。
新盆は忌明けに故人の魂が初めて帰ってくるお盆とされており、故人を偲ぶために家族だけでなく親戚や友人などを招いて行う法要です。しかし近年では感染症の予防や遠方の方への配慮などから、身内だけで新盆の法要を執り行うことも増えてきています。
2026年の新盆期間は?
新盆は通常のお盆と同じ期間に行われることが多いです。
2026年のお盆期間は、ほとんどの地域が8月13日(木)から16日(日)です。
東京をはじめとする一部の地域では、7月13日(月)〜7月16日(木)をお盆期間としています。
身内だけの新盆の服装

新盆は、法要や会食があるので喪服で参列するのが一般的です。身内だけで執り行う新盆の場合、服装は施主の意向に従うのがマナーですが、一般的には男性女性ともに「平服(略喪服)」が望ましいとされています。ここからは、身内だけの新盆の服装について解説します。
【男性】身内だけの新盆の服装
身内だけで執り行う新盆での男性の服装は、「ダークカラーのスーツ」が望ましいでしょう。黒や濃紺、暗めのグレーのスーツを選びます。できるだけストライプなどの柄のないシンプルな服装を選び、裏地のデザインが華美なものや光沢のあるものは避けましょう。
またワイシャツは白がふさわしく、ボタンダウンなどカジュアルな服装を避けましょう。男性の服装の足元は黒の靴下と革靴を着用し、ネクタイも黒や濃紺、暗めのグレーで、地味なデザインを選ぶのがマナーです。
【女性】身内だけの新盆の服装
身内だけで執り行う新盆での女性の服装は、ダークカラーのワンピースやスーツがふさわしいとされています。女性の服装のスカート丈は膝下を選び、露出しすぎないように注意しましょう。シャツを着用する服装の場合は、白の無地で胸元が開きすぎない露出の少ないものを選びます。
服装は一般的に無地がふさわしいとされていますが、シンプルであればチェックやストライプなど柄があるものでも構いません。また女性の服装は、パンツスーツでも問題ないでしょう。足元は黒の薄手のストッキング(30デニール程度)と、安定感のあるダークカラーのパンプスが一般的とされています。
【子供】身内だけの新盆の服装
身内だけで執り行う新盆での子供の服装は、幼稚園や学校の制服がふさわしいです。子供の制服は平服としてだけでなく、大人が喪服を着用する場面でも正式な服装としてみなされます。子供の制服の中に、赤いネクタイやチェック柄のスカートなど、派手な印象のアイテムがあっても問題ありません。
制服がない場合の子供の服装は、ダークカラーでシンプルなデザインを選びます。男の子の服装は、白のシャツにダークカラーのボトムスがよいでしょう。女の子の服装は、ダークカラーのワンピースやジャンパースカートがおすすめです。大学生の場合は、大人と同じ服装で参列しましょう。
華美なアクセサリーは避ける
特に女性の場合、華美なアクセサリーや露出のし過ぎといった服装にならないよう注意しましょう。アクセサリーを身に着ける服装の場合は、フォーマル度の高い真珠の一連ネックレスをおすすめします。男性の服装の場合も、結婚指輪と腕時計以外の装飾品は身に着けないのがマナーです。派手なものや目立つものは、身に着けないよう心掛けてください。
身内だけの新盆だとしても、カジュアルすぎる服装は避けましょう。たとえダークカラーであっても、Tシャツにジーンズのようなカジュアルな服装は新盆の法要にふさわしくありません。
殺生をイメージさせる服装を避ける
身内のみの新盆であっても、殺生をイメージさせる服装を避けるのがマナーです。毛皮や蛇革、オーストリッチなど、動物の革と分かる服装は新盆の法要にふさわしくありません。
フェイク品の製品であっても誤解を招く可能性があるため、避けましょう。バッグや靴、ベルトなどに殺生をイメージさせるアイテムはないか、準備の段階で服装の確認をおすすめします。
▶︎参考:新盆(初盆)の服装を男女別に紹介!細かいマナーや家族のみの場合も紹介
身内だけの新盆のマナー

たとえ身内だけの新盆であっても服装はもちろん、身内以外の関係者や僧侶などへの配慮も必要です。ここからは、身内だけで執り行う新盆のマナーについて解説します。
僧侶を呼ぶ場合は事前に連絡する
僧侶を新盆法要に呼ぶ場合は、遅くとも1ヶ月前には連絡しておきましょう。
身内のみで、僧侶を呼ばずに新盆を迎えたいと考える方もいるでしょう。故人を思う気持ちが大切ですので、身内のみで僧侶を呼ばない新盆でも問題はありません。
身内以外の関係者に連絡する
身内のみで新盆を迎える場合は、親族や友人など関係者に連絡するのも忘れないようにしましょう。身内以外にも、故人の新盆に参列したいと考えている方もいるでしょう。新盆だからと訪ねてくる方もいる可能性はあるため、事前に連絡しておく必要があります。
身内だけで新盆を行う場合の準備

新盆は通常のお盆よりも、丁寧な供養を行うのが一般的です。ここからは、身内のみで迎える新盆の準備について解説します。
新盆法要の日程を決める
まずは、身内のみの新盆法要の日程を決めましょう。一般的にお盆は、8月13日〜16日に執り行われます。地域によっては、旧暦の7月13日〜16日の場合もあるでしょう。
新盆法要の日程に決まりはないため、お盆期間中であれば問題ありません。身内のみであるため、全員の都合を確認して日程を決めればよいでしょう。
白提灯や精霊棚の飾りつけをする
次に、白提灯(しろちょうちん)や精霊棚(せいれいだな・しょうりょうだな)の飾りつけをします。白提灯とは玄関先や軒下、窓際、仏壇の前などに飾る、新盆のときに故人の魂が迷わずにたどり着くための目印の提灯です。
精霊棚とはお盆のときに特別に作られる棚のことをさし、故人の魂が滞在する場所とされています。きゅうりや茄子で作った精霊馬、精霊牛やほおずきなどを飾りつけします。
お供え物や花を用意する
精霊棚に飾る、お供え物や花も用意しましょう。一般的に精霊棚には「香り(お線香)・花(生花)・灯り(灯燭)・お水・ご飯」の「五供(ごくう)」をお供えします。
ご飯は、生前故人が好きだった食べ物やお菓子などを用意しましょう。水羊羹やゼリー、缶詰など後々身内で分け合えて、日持ちしやすい食べ物も好まれています。
会食の準備・予約をする
身内のみの新盆でも、会食の準備を忘れないようにしましょう。身内が少人数の場合は自宅で用意したり、仕出し弁当などを注文しておいたりするのがおすすめです。料亭やレストランを予約する場合は、新盆の会食であることを伝えましょう。
身内だけの新盆の流れ

新盆の供養方法は施主の意向に従うのが基本ですが、一般的な流れもおさえておきましょう。ここからは、身内だけで執り行う新盆の流れについて解説します。
お墓参りに行く
新盆には、身内でそろってお墓参りに行くのが一般的です。昔から故人のお迎えは早いほうがよいといわれており、13日の午前中に行くのが望ましいとされています。しかし新盆のお墓参りに決まりはないため、身内で話し合って日程を決めるとよいでしょう。
新盆のお墓参りも、通常のお墓参りと同様に執り行います。お墓の掃除をしてお供え物をしましょう。お供え物はそのままにしておくと、動物が食べ荒らしたり墓石を傷める原因になります。お供えした食べ物や飲み物は、身内でその場で食べるか持ち帰るのがマナーです。
迎え火を焚く
お盆入りの8月13日の夕方に「迎え火」を焚くのが一般的です。迎え火とは、故人の魂が迷わずたどり着けるように焚く火のことをいいます。「焙烙(ほうろく)」という素焼きの小皿に「おがら(麻の茎)」を乗せて火を焚きます。
白提灯にあかりを灯す
迎え火の火を使って白提灯を灯しましょう。先述のとおり、白提灯は故人の魂が迷わずにたどり着くための目印になります。おがらが燃え尽きたら、水をかけて火の始末をします。しかし近年では防火上の理由などから火を焚くことが減り、LEDの盆提灯などを使用することが増えています。
送り火を焚く
新盆の最終日である8月16日の夕方には「送り火」を焚くのが一般的です。送り火とは、故人の魂が迷わず元の場所に戻れるように焚く火のことです。迎え火の順序とは逆で、盆提灯の火を使って火を焚きます。火を焚くことが難しい場合は、迎え火同様LEDの盆提灯などを使用してください。
送り火のお見送りが終了したら、白提灯や精霊棚の片付けをします。16日のうちに片付けるのが好ましいとされていますが、難しい場合は翌日でも問題ありません。
身内のみの新盆でも服装に注意して参列しましょう

この記事のまとめ
- 「新盆」とは、故人が亡くなって四十九日の忌明け過ぎ、初めて迎えるお盆のこと
- 身内だけの新盆の服装は、男性女性ともに「平服(黒や濃紺、暗いグレーなどの地味な服装)」でよい
- 子供の服装は幼稚園や学校の制服が正式。ない場合はダークカラーの服装を選ぶのが一般的
- 派手な装飾品を控えるなど、身内だけの新盆であっても服装のマナーに注意する
- 身内だけの新盆でも、日程や精霊棚の飾りつけ、会食の準備などが必要
- 身内だけの新盆の流れはお墓参りや白提灯などがあるが、一般的には施主の意向に合わせる
身内だけで執り行う新盆であっても、故人への供養であるため落ち着いた服装を心掛けることが大切です。本記事で解説した新盆の服装や流れなどを参考にして、準備を整えてみてください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。