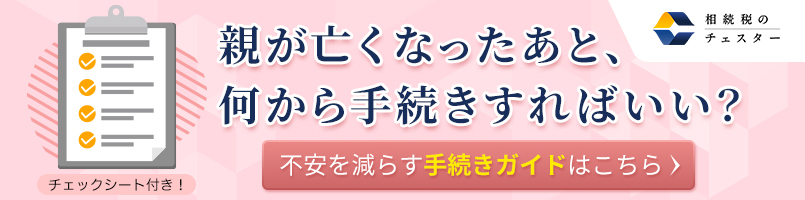お盆の迎え火と送り火のやり方!注意点もあわせて解説

お盆の時期になると、各家庭で迎え火・送り火を行う地域も少なくありません。しかし、迎え火や送り火を焚いたことがないと、具体的なやり方が分からない人も多いでしょう。本記事では、お盆の迎え火・送り火のやり方について行う理由とともに紹介します。注意点もまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
お盆に迎え火・送り火をする意味とは?

お盆の時期になると、各家庭の玄関などで火を焚いている様子を見たことがある人は多いのではないでしょうか。お盆が始まる時期に焚く火を「迎え火」、終わり際の時期に焚く火を「送り火」と呼びます。
宗派によって多少の違いはありますが、お盆は仏教において「極楽浄土へ旅立った故人・ご先祖が現世へ帰ってくる時期」と考えられています。迎え火は現世へ帰ってくる故人やご先祖の魂が、迷わずに自宅へ帰って来られるための目印という意味を持つものです。
送り火については、法事やお供えなどでご先祖を丁寧に供養した上でお盆の終わり際に焚く火です。お盆が終わって再びあの世へ旅立つご先祖の魂が、無事に極楽浄土へ帰れるようにという願いを込めるために行います。地域によっては大々的に迎え火・送り火を行うところもあり、特に京都の五山送り火(=大文字焼き)が有名です。
お盆の迎え火・送り火はいつ行う?

同じお盆に行う儀式ですが、迎え火と送り火では行うタイミングが異なります。ここからは、お盆の迎え火・送り火を行う日や時間について解説します。
迎え火は7月または8月の13日
迎え火は、一般的に「盆の入り」とされるお盆の初日に行います。具体的には8月13日ですが、地域によっては7月13日に行う場合があります。この違いは、旧暦と新暦のどちらに基づくかによるもので、7月に行う「新盆(新暦のお盆)」と、8月に行う「旧盆(旧暦に近いお盆)」というように分かれています。関東の一部や都市部では新盆が多く、その他の地方や西日本では旧盆が一般的です。
また、外がまだ明るい時間帯に火を焚いてもご先祖から見えにくいとされているため、日が沈む夕方から夜の時間帯に執り行うのが一般的です。
少しでも早く故人やご先祖をお迎えできるようにという理由で、日中の時間帯に迎え火をする家庭もあります。地域や家庭によって考え方が異なるため、迎え火をする時間帯については菩提寺や親族に確認しておくことも大切です。
送り火は7月または8月の16日
送り火については「盆明け」にあたる8月16日(地域によっては7月16日)に行います。時間帯に厳格なルールはありませんが、迎え火と同じく夕方から夜間に行うことが一般的です。しかし、法事やお墓参りなどの予定によっては、午前中に送り火を行う場合もあります。
地域や宗派によっては迎え火・送り火を焚かないこともある
地域や宗派によっては、お盆に迎え火・送り火を焚かない場合もあります。例えば「五山送り火」で有名な京都や「精霊流し」を行う九州などでは、大規模な送り火を行うため、自宅の玄関で送り火を焚かないという家庭もあります。
また、浄土真宗では、故人は死後すぐに極楽浄土にて仏様になると考えられているため「お盆の時期にご先祖の霊が現世へ帰ってくる」という考え方がありません。そのため、お盆の時期には仏壇にて仏様へ感謝を伝え、迎え火・送り火はしないのが一般的です。
迎え火・送り火に必要なもの

お盆に行う迎え火・送り火は、昔ながらのやり方に沿って行うことで、より丁寧にご先祖を供養できるでしょう。ここからは、お盆の迎え火・送り火をするにあたって用意するものを紹介します。
おがら
おがらとは、皮を剥いた麻の茎を乾燥させた「麻ガラ」のことです。古くから照明として使われてきた道具であり、仏教ではおがらから出る煙は死者の魂を現世へ導く目印になると考えられています。また、麻は古くから清らかな植物とされており、燃やして煙を出すことでご先祖の魂が帰ってくる場所を清める意味もあります。
迎え火・送り火の時期になると花屋やスーパーなどでおがらが売られていることがあります。おがらが入手できない場合は、松明または短くカットした割りばしでも問題ありません。
焙烙
焙烙(ほうらく)とは、おがらを焚くための皿のことで、一般的な迎え火・送り火では浅めで厚みのある土器の皿が用いられます。お盆の時期になるとホームセンターなどで購入できますが、迎え火・送り火の当日に用意できない場合は自宅にある耐熱皿で代用しても問題ありません。
マッチ・水を張ったバケツ
送り火・迎え火をする際には、着火に必要なマッチや消火用の水入りバケツも必要です。マッチを使い慣れていない場合は百円ショップなどで購入できるライターでも問題ありません。ターボライターであれば、迎え火・送り火をする際に風が吹いても火が消えにくいため、スムーズに着火できるでしょう。
精霊馬・お供え物
迎え火・送り火をする際には、仏壇にお供えする精霊馬とお供え物も用意しましょう。精霊馬とは、お盆の時期にご先祖の霊があの世とこの世を行き来する際に使う乗り物で、キュウリ馬とナス牛の二つがあります。
キュウリ馬は足の速い馬を模したもので、盆の入りに飾ることで「ご先祖が少しでも早く家へ帰って来られるように」と願いを込める意味があります。対してナス牛は盆明けに飾るもので、足の遅い牛に乗ることで「現世の景色を楽しみながらゆっくりあの世へ帰ってください」という気持ちを表すものです。
お供え物については花やお水、食品などが一般的です。お供え物にお菓子を選ぶ場合は、常温かつ長期での保存がきく落雁やようかん、せんべいなどを選ぶことが望ましいです。
しかし、お供え物はあくまでご先祖を丁寧に供養するためのものです。ご先祖が生前に好きだったものをお供え物にしても問題ありません。
迎え火・送り火のやり方・手順

迎え火・送り火はお盆という短い期間の中で、法事やお供えとともにご先祖へ丁寧に感謝を伝える上で必要な儀式です。しかし、具体的にどのようなやり方で行えばよいか分からない人も多いでしょう。ここからは、お盆の迎え火・送り火のやり方を手順に沿って解説します。
迎え火のやり方
迎え火は、積んだおがらに火を灯して盆提灯に移す方法が一般的です。本来はお墓参りの際に灯したロウソクの火を盆提灯に灯し、自宅に持ち帰って仏壇に移す方法で行われていました。
しかし、近年はお墓や菩提寺が遠かったり、火を自宅まで持って帰るのが難しかったりといった理由で、自宅の玄関で火を焚くというのが一般的になっています。
迎え火のやり方
- 焙烙の上に少量のおがら(または短く折った割りばし)を重ね、玄関などに置く
- おがらにマッチやライターで火を灯し、迎え火を焚く
- 火を灯したら手を合わせ、迎え火で盆提灯に火を灯す
- おがらが燃え尽きたら、水に浸して完全に消火する
送り火のやり方
迎え火はおがらに灯した火から盆提灯を灯したのに対して、送り火は盆提灯の火を使って焚くのが一般的な方法です。地域によっては、送り火の際に精霊馬を一緒に燃やすこともあります。
送り火のやり方
- 焙烙の上におがら(または短く折った割りばし)を重ね、玄関などに置く
- 盆提灯の火をおがらに付け、送り火を焚く
- 送り火の煙が上がったら手を合わせ、火が消えるまで見守る
- 火が燃え尽きたら、燃えカスに水をかけて完全に消火する
お盆の迎え火・送り火をするときの注意点

実際にお盆で迎え火・送り火をする際には、あらかじめ注意点を理解しておかないと火傷やトラブルにつながる可能性もあります。ここからは、迎え火・送り火をする際の注意点を紹介します。
火事に注意する
迎え火・送り火では実際に火気を扱うため、火事には十分に注意してください。万が一火が広がった際にすぐ消火できるように、水を溜めたバケツを火のそばに置いておきましょう。
特におがらの量が多すぎると火が大きくなりやすいため、少量のおがらを使うことと、周囲に飛散しないように対策を立てておくことをおすすめします。また、小さな子供がいる家庭では子供が火に触れないように、火を焚いている間は大人がしっかり見守ってください。
風が強い日は十分に注意して行う
風が強い日に迎え火・送り火をする場合は、周囲に十分注意して行いましょう。風によって火が付いているおがらが飛んでしまう危険性もあります。迎え火・送り火を焚く時間帯に風が強い場合は、火を付けずに形だけで行うか、缶の中で火を焚いておがらが外へ飛ばないようにするとよいでしょう。
場所に配慮する
迎え火・送り火をする際には、火を焚く場所にも注意しましょう。特にマンションなどの集合住宅や都市部などでは、火を焚くと煙や臭いによる近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。周辺の人の迷惑にならない場所で行うようにしてください。
自宅でお盆の迎え火・送り火が焚けない場合はどうする?

マンションやアパートなど、自宅で迎え火・送り火が焚けない場合はどのように対処すればよいのでしょうか。ここからは、自宅で迎え火・送り火が焚けないときの方法について解説します。
電気式のロウソク・盆提灯を使う
実際に火を焚けない場合は、電気式のロウソク・盆提灯で代用しても問題ありません。電池式や電気式のものであれば火がなくても使えるため、火事の危険性がありません。使用中も煙や臭いが出ないことから、近隣住民の迷惑になりにくいでしょう。
ロウソクで代用する
迎え火・送り火に使うおがらの代わりに、ロウソクを使用するのもおすすめです。ロウソクはおがらに比べて火の勢いが弱く、臭いも目立たないためマンションやアパートでも使いやすいでしょう。しかし、火気であることは変わりないため、周囲に引火しそうなものがないか確認した上で使ってください。
お墓で迎え火・送り火を焚く
自宅ではなく、ご先祖のお墓で迎え火・送り火をするというやり方もあります。臭いや煙で周囲に迷惑をかける心配がない上、消火に必要な水や桶なども現地で用意できます。お墓参りの際に一緒に迎え火・送り火ができるのもメリットといえます。
お盆は迎え火・送り火でご先祖を丁寧に供養しましょう

この記事のまとめ
- 迎え火・送り火は、故人の霊がお盆にあの世とこの世を行き来する際の目印
- 迎え火は7月または8月の13日の夕方~夜に行うのが一般的
- 送り火は7月または8月の16日の夕方~夜に行うのが一般的
- 地域や宗派によっては迎え火・送り火をしないこともある
- 迎え火・送り火はおがらと器、消火用のバケツが必要
- 火が焚けない場合は、電気式の盆提灯やロウソクで代用しても問題ない
お盆に行う迎え火・送り火は、ご先祖の霊が無事にあの世とこの世を行き来できるようにするための目印となる儀式です。適切なタイミングと正しいやり方で行うことが大切です。お盆の時期には、本記事で紹介したやり方や注意点を踏まえて、迎え火・送り火でご先祖を丁寧に供養しましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。