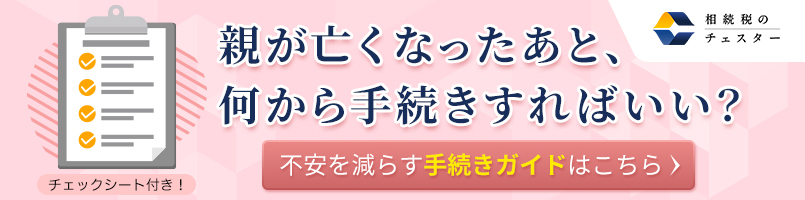送り盆とはどんな儀式?日程・準備物・お迎えの仕方・費用を徹底解説

お盆では「送り盆」が行われますが、何をすればよいか分からない人も多いのではないでしょうか。本記事では、送り盆の意味や日程、準備するものなどを紹介します。これから送り盆を予定している人は、ぜひ参考にしてください。
送り盆とは

「送り盆」という言葉を聞いたことがあっても、内容や意味までは分からないという方もいるでしょう。まずは、送り盆とは何かを解説します。
送り盆の意味
送り盆とは、お盆の最終日に故人やご先祖をあの世に見送る儀式です。まず、お盆の初日に故人やご先祖を自宅にお迎えする「迎え盆」が行われます。お盆中に故人と共に過ごした後、お盆が終わる頃にあの世へ送り出すのです。送り盆はとても古くからあり、明確な起源は分かっていません。送り盆が定着したのは、江戸時代以降だとされています。
送り盆を行う目的
送り盆には、故人やご先祖の魂が迷わずあの世へ帰れるようにお見送りする、という目的があります。送り盆では見送りのため、おがらを燃やす「送り火」を行うのが一般的です。
送り盆を行う日時
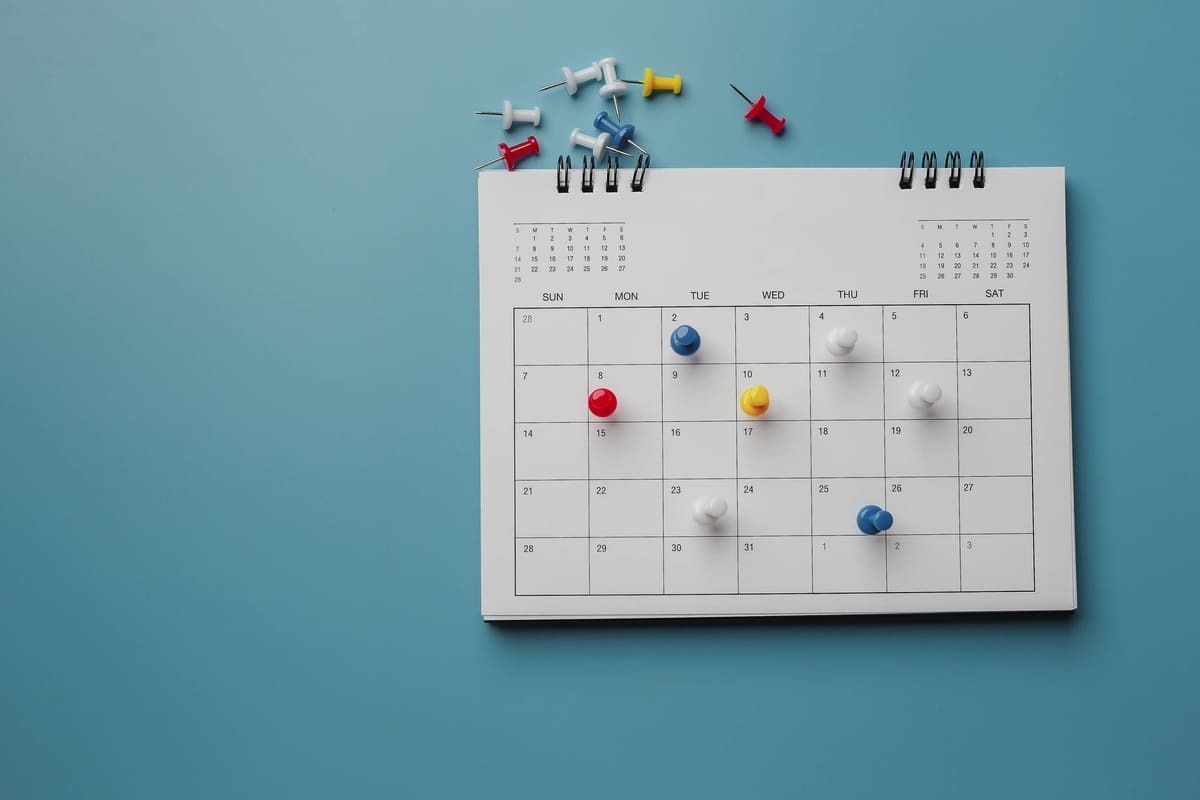
送り盆の準備をする上で気になるのが、行われる日時ではないでしょうか。送り盆の日にちや時間帯は、住んでいる地域によって異なります。間違えないよう、事前に確認しておきましょう。
お盆最終日に行う
送り盆は、お盆の最終日に行われるのが一般的です。お盆初日に迎え盆で故人の魂を自宅まで導き、お盆中は共に過ごします。その後、お盆最終日に送り火をして故人を送り出します。
お盆の日程は新盆の場合は7月13〜16日頃、月遅れ盆では8月13〜16日頃です。大半の地域では月遅れ盆にお盆を行いますが、新盆が採用されている地域もあります。送り盆を行う際は、お住まいの地域でのお盆の日程を確認しておきましょう。
2025年のお盆期間は?
2025年のお盆期間は、ほとんどの地域が8月13日(水)から16日(土)です。送り盆は最終日の16日(土)に行いましょう。
東京をはじめとする一部の地域では、7月13日(日)〜7月16日(水)をお盆期間としています。
地域によって行う時間が異なる
送り盆は、お盆最終日の夕方から夜にかけて行うのが一般的です。お盆の最後の日、日中は故人やご先祖と一緒に過ごし、夕方に送り火をたいてあの世へ送り出します。これは、現世を訪ねてきた故人の魂が迷わずあの世へ帰れるよう、暗い中で火をたいて道筋を作るという意味があります。
ただし、お盆最終日の前夜から朝にかけて送り火をたく地域や、午前中のうちに送り盆をすませる地域もあります。お住まいの場所によって送り盆が行われる時間帯は異なるため、前もって確認しておきましょう。
迎え盆・送り盆で準備するべきもの

ここからは、迎え盆と送り盆で家族が準備するべきものを紹介します。何を手配すればよいか分からない方は、こちらを参考にしてみてください。
お盆飾り
迎え盆・送り盆で準備するものとして、お盆飾りが挙げられます。盆提灯や位牌、盛花、霊前灯などを準備します。盆棚の飾り方は宗派や地域などによって異なるため、菩提寺やお寺に確認しておきましょう。一般的には、盆棚の最上段に位牌、最下段に精霊馬、左右に霊前灯や盛花などを飾ります。
盆提灯
迎え盆・送り盆に向けて、盆提灯を準備しておくとよいでしょう。盆提灯は、故人やご先祖が迷わず自宅に帰ってこれるように飾るもので、植物や家紋などが描かれています。盆提灯には置いて飾るタイプと吊るすタイプの2種類があるため、住宅環境や菩提寺の意向などに合わせて選びましょう。
葬儀を終えて初めて迎えるお盆のことを新盆と呼び、新盆では一般的な盆提灯ではなく白紋天という白い提灯を使用します。白い提灯を使用するのには、初めて彼岸から戻ってくる故人の魂が迷わないようにという意味があります。白紋天は自宅の外に吊り下げて飾るのが一般的ですが、難しい場合は室内に飾っても問題ありません。
 はせがわのお盆提灯|お仏壇のはせがわオンラインショップ| Amazon.co.jp
はせがわのお盆提灯|お仏壇のはせがわオンラインショップ| Amazon.co.jp
まこも・蓮の葉
まこもや蓮の葉も、迎え盆・送り盆で家族が用意するものの一つです。まこもや蓮の葉には、お釈迦様が上に座って病気の人を治したという言い伝えがあります。盆棚の上にまこもを敷き、その上に蓮の葉を乗せて野菜や果物などをお供えするのが一般的です。
精霊馬
精霊馬とは、キュウリで馬を、茄子で牛をかたどった飾りです。彼岸から故人が帰ってくる際はなるべく早く帰ってこれるように馬を、あの世へと戻る際はゆっくり進むために牛を準備します。キュウリや茄子で作るのが一般的ですが、市販されている精霊馬を使用することもあります。
十三仏
十三仏とは、お盆や彼岸、法要などの仏事に使用される掛け軸です。十三仏とは、地蔵菩薩、阿弥陀如来、勢至菩薩、不動明王、阿閦如来、釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩、弥勒菩薩、薬師如来、大日如来、虚空蔵菩薩、観音菩薩のことです。十三仏は故人を浄土に導くと共に、三十三回忌まで故人を守ってくれる存在とされています。
十三仏は床の間やお仏壇に飾りますが、お盆には盆棚の上に飾るのが一般的です。
ほおずき
ほおずきも、迎え盆・送り盆で準備するお盆飾りの一つです。ほおずきは鮮やかな色味と提灯のような形状が特徴で、仏事に飾る植物として好まれています。お盆を迎えるにあたって欠かせない飾りの一つであり、仏壇や盆棚に張られたまこもの縄に吊り下げたり、お供え物と並べて飾ったりするのが一般的です。
お供え物
お盆の際は、盆棚にお供えするお供え物を準備します。仏教では五供(飲食、花、香、蝋燭、浄水)をお供えするのが一般的ですが、そのほかにも故人が好きだった食べ物や飲み物、季節の果物などをお供えすることもあります。
▶︎参考:2025年のお盆のお供えはいつからいつまで?品物の相場や選び方も紹介
おがら
おがらとは、麻の茎の皮を剥いて乾燥させたもので、送り火の火をつける際に使用します。おがらを準備できない場合は、割り箸で代用しても構いません。また、おがらを乗せて火をつけるための焙烙(ほうろく)や耐熱皿も準備しておきましょう。
 はせがわのお盆用品|お仏壇のはせがわオンラインショップ| Amazon.co.jp
はせがわのお盆用品|お仏壇のはせがわオンラインショップ| Amazon.co.jp
送り盆を行う流れ

ここからは、送り盆を行う流れを紹介します。初めて送り盆を行う場合は、こちらを参考にしてみてください。
①お供え物を供える
送り盆当日は、故人の仏壇や盆棚にお供え物をします。仏壇には、五供(ごく)と呼ばれる香、花、飲食、浄水、蝋燭や、季節の果物をお供えするのが一般的です。そのほかにも、家族の食事と同じものや生前故人が好きだったものなどをお供えすることもあります。夕方から送り盆を行う場合は、午前中までにお供え物を供えておきましょう。
ただし、アルコール類や殺生をイメージさせる肉・魚、トゲや毒のある花などはお供え物にはふさわしくないため避けてください。故人が好きだったとしても、仏壇にはお供えしないのが無難です。
②送り火の準備をする
次に、送り火の準備を始めます。迎え火を行った玄関や庭先などに焙烙を置き、その上におがらを積み重ねるように乗せます。山の形や井形のように交互におがらを組むことで、火がつきやすくなります。なかなか燃えない場合は、新聞紙などを下に敷いて使いましょう。おがらが長い場合は、焙烙からはみ出さないように折ってください。
送り火が灯ったら、故人があの世へ無事に帰れることを祈って合掌します。そのまま、送り火が消えるまで見守りましょう。火が燃え尽きたら水をかけて消化し、おがらはしばらく水に浸けておきます。地域によっては、送り火を提灯に灯して故人のお墓に持って行ったり、仏壇の蝋燭に灯したりすることもあるため、あらかじめ周囲に確認しておきましょう。
③お墓参りを行う
地域によっては、送り火の後にお墓参りを行うところもあります。提灯に火を灯し、故人やご先祖の魂と共にお墓を訪れてお見送りします。お墓参りを行う際は、お盆を共に過ごせたことの感謝を伝えるとよいでしょう。
④お供え物やお盆飾りを片付ける
送り火をすませたら、お供え物やお盆飾り、精霊馬などを片付けます。精霊馬は菩提寺に持参してお焚き上げを依頼したり、庭に埋めたりして片付けます。
送り火が終わった時間によっては、当日ではなく翌日に片付けを行うこともあります。ただし、火事にならないよう翌日に片付ける場合でも火の始末は当日に行いましょう。
送り盆にかかる費用

送り盆には、お盆飾りやお供え物、おがら、精霊馬などを準備する費用がかかります。費用の相場は3千円〜5千円ですが、新盆法要を行う場合は別途お布施の料金がかかります。
新盆法要のお布施は3万円〜5万円が相場ですが、適切な金額のお布施を用意するためにも、周囲に確認しておくのがおすすめです。
送り盆とは何かを理解し、正しくご先祖を見送りましょう

この記事のまとめ
- 送り盆とは、お盆の最終日に故人やご先祖の魂をあの世へ見送るための儀式
- 送り盆はお盆最終日に行うことが多いが、地域によっては実施する時間帯が異なる
- 送り盆や迎え盆で準備するべきものとして、お盆飾り、お供え物、おがらなどが挙げられる
- 送り盆は、お供え物をする、送り火の準備をする、お墓参りを行う、お供え物やお盆飾りを片付けるという流れで行う
- 送り盆にかかる費用の相場は3千円〜5千円
送り盆とは、故人やご先祖の魂を現世から彼岸へと見送るための儀式です。送り盆はお盆最終日に行われることが多いですが、地域によって実施する時間帯が異なることがあります。本記事で紹介した送り盆で準備するべきものや手順などを参考にして、家族でご先祖を見送りましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。