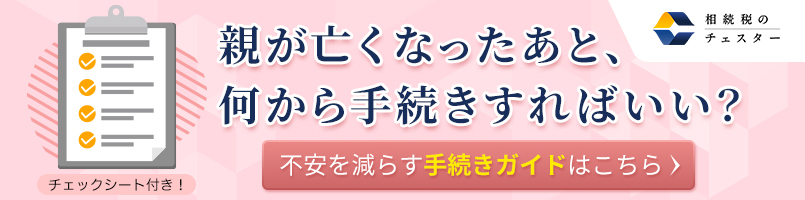一周忌法要と納骨式を一緒にできる?一般的な流れや用意することを紹介

喪が明ける区切りにあたる一周忌法要ですが、遺族の都合によっては納骨式も一緒に行いたい人もいるのではないでしょうか。本記事では、一周忌法要と納骨式を一緒に執り行うことはできるかを解説します。まとめて行う際の流れも紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
一周忌法要と納骨式を一緒にできる?

結論からいえば、一周忌法要と納骨式は一緒に行っても問題ありません。そもそも納骨式とは、火葬した故人の遺骨をお墓などに納めることであり、明確な期限がないため、納骨をするタイミングは遺骨を保管している人が自由に決められます。
四十九日法要や一周忌法要をはじめとした、故人の供養の区切りとなるタイミングで納骨式を一緒に行う人も少なくありません。
一周忌法要と納骨式を一緒にするメリット
一周忌法要と納骨式を一緒にする最大のメリットは、遺族や参列者の負担を軽減できる点にあります。一周忌法要と納骨式を別で執り行う場合、遺族は何度も法事の準備をしなくてはいけません。また、何度も参列者へスケジュール調整してもらう必要もあります。
一周忌法要と納骨式を一緒に行うことで、参列の回数を減らせるため、準備や参列における負担を軽減できるでしょう。
また、気持ちが落ち着いてからお墓を決められるのもメリットです。葬儀やお通夜、火葬などが終わった直後に納骨式を行うとなると、葬儀の参列者への対応などで忙しくなり、遺骨の管理場所やお墓をじっくり考えて決められない可能性があります。
一周忌と納骨式を一緒に行う場合、四十九日法要後から納骨場所やお墓を考えても一周忌法要に十分間に合います。家族から受け継いできたお墓がない人にとっては、時間をかけて納骨する方法を考えられるでしょう。
一周忌法要と納骨式を一緒にするデメリット
一周忌法要と納骨式を一緒にするデメリットは、当日のスケジュールが多忙になる点にあります。まとめて執り行う場合は、一周忌法要の後で納骨式を行うのが一般的です。そのため、一周忌法要当日はそれぞれの法事の準備をしたり場所を移動したりなどで忙しくなります。
一周忌法要自体の時間も長くなることから、特に高齢の遺族や参列者にとっては身体的な負担がかかる可能性もあります。実際に参列者を呼んで執り行う場合には、あらかじめ一緒に行うことを連絡しておくことが大切です。
一周忌法要と納骨式を一緒にするときの流れ

一周忌法要と納骨式を一緒にする場合、当日はかなり忙しくなるため、あらかじめおおまかな流れを把握しておくことが大切です。ここからは、一周忌法要と納骨式を一緒に執り行うときの一般的な流れを解説します。
①施主による挨拶
参列者の受付が終わり、僧侶と参列者が会場に揃ったら、一周忌法要を始める前に施主が挨拶を行います。忙しい中故人の供養に来てくれた参列者や、読経を執り行ってくれる僧侶へのお礼を伝えます。
また、お礼だけでなく、遺族側の近況報告なども伝えます。納骨式の後で会食を行う場合には、一緒に連絡します。一周忌法要や納骨式の時間があるため、挨拶は1分程度に留めるのが一般的です。
②僧侶の読経・焼香
挨拶が終わったら、僧侶の読経を行います。読経が始まってから10分~15分ほど経つと、参列者による焼香が始まります。焼香は施主、遺族と故人との関係が深い人から順番に行います。読経自体は30分~1時間程度かかります。
③僧侶による法話
読経を終えた後は、僧侶が法話を行います。法話とは、僧侶が仏教の教えに関する話を一般の人にも分かりやすいように伝えることを指します。一周忌法要と納骨式を一緒に行う場合、スケジュールの都合上10分以内で終わるのが一般的です。僧侶の法話が終わると、一周忌法要は終了となります。
④納骨式
一周忌法要を終えたら、お墓や納骨堂など納骨予定の場所へ移動して納骨式を行います。場所によって多少流れは異なりますが、僧侶が読経を行い、遺骨を納めるカロートと呼ばれる安置スペースや納骨室を開けて納骨します。
なお、骨壷ごと納骨するのが一般的ですが、地域によっては骨壷から遺骨を取り出して納骨する場合もあるため、地域の納骨方法を確かめておきましょう。
⑤施主による簡単な挨拶
納骨式を終えたら、施主が簡単な挨拶を行います。無事に一周忌法要と納骨式を終えたお礼を伝えます。一周忌法要と納骨式の後に会食がある場合は、会食の会場についての案内を行います。会食へ参加しない参列者に対しては、一周忌法要と納骨式を終えた後に返礼品を渡します。
⑥会食
会食会場へ移動したら、施主が乾杯の挨拶をし、会食を行います。会食が終わったら、お開きの挨拶をし、参列者へ返礼品を渡して解散となります。
なお、僧侶が会食に参加するか否かによって御膳料をお渡しするかどうかが異なります。僧侶が会食に参加する場合は、お布施とお車代を渡すのが一般的です。参加しない場合は、加えて御膳料を渡しましょう。
一周忌法要と納骨式を一緒にするときの準備

一周忌法要と納骨式を一緒に執り行う場合、当日のスケジュールだけでなく事前の準備や手続きも重要です。ここからは、一周忌法要と納骨式を一緒に行うときに用意することや手続きについて解説します。
一周忌法要の日程・会場の決定
一周忌法要と納骨式を執り行う日程・会場を決めましょう。日程については、故人の死後から一年後の祥月命日に行うのが一般的ですが、参列者や遺族の都合がつかない場合には、祥月命日より前の土曜日や日曜日に設定しても問題ありません。
一周忌法要は、葬儀社のホールやお寺などで行います。家族のみで一周忌法要を行う場合は自宅で行うことも可能です。納骨式も一緒に行うため、できるだけ納骨場所に近い場所で行うとよいでしょう。
僧侶への依頼
ご先祖のお墓を管理しているお寺(=菩提寺)の僧侶へ、一周忌法要での読経の依頼を行います。お寺のスケジュールによっては希望日に予約を取れない場合もあるため、早めに依頼しておきましょう。僧侶のスケジュールも踏まえた上で、一周忌法要を行う日を決めるようにします。
菩提寺がない場合は葬儀社に僧侶を紹介してもらうか、派遣サービスを利用する方法があります。
納骨に必要な書類の準備
納骨式を行うためには、納骨に必要な書類を揃える必要があります。一般的には火葬後に発行される「埋葬許可証」が必要です。納骨の手続きは原本のみ可能でコピーは使えない場合もあるため、受け取った許可証の保管方法には注意しましょう。
卒塔婆の依頼(お墓に納骨する場合)
お墓の場合、納骨の手続きとともに卒塔婆の依頼もします。卒塔婆とは題目や経文が描かれた木札です。仏教においては、卒塔婆を立てることも善行の一つとされており、故人の追善供養を行う意味で立てられます。
卒塔婆は一般的に菩提寺に直接依頼すれば問題ありませんが、懇意にしているお寺がない場合には納骨するお墓の墓地や霊園に相談してみるとよいでしょう。
石材店への依頼(お墓に納骨する場合)
お墓に納骨するなら、石材店への依頼も行います。お墓に納骨する場合、墓石に故人の名前・戒名などを彫ってもらう必要があります。お墓の完成にはある程度の日数がかかるため、一周忌法要と納骨式の日程を決めたら早めに依頼しておきましょう。
石材店に依頼する際には、納骨費用と彫刻料などを用意します。また、納骨を終えた業者へ寸志を渡すこともありますが、近年は工事費用に含まれている場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
参列者への連絡
納骨や一周忌法要の依頼が完了したら、参列者に参加の可否についての連絡を行います。連絡の際は法要を行う会場名や開始時間も一緒に伝えます。一般的には案内状を出しますが、家族や身内のみで行う場合は電話やメールなどで連絡しても問題ありません。
案内状を出す場合には、会場の地図や連絡先なども一緒に記載しておくと安心です。連絡する際には「一周忌法要と納骨式を同時に行う」という旨を伝えておくと、当日のトラブルを防げるでしょう。
会食の手配
参列者の人数が明確になったら、会食の手配を行います。場所が決まったら当日のメニューや席次(席順)も決めていきます。メニューを決める際には、参列者の中に食物アレルギーがある人はいないかを確認しておきましょう。
会食の席次については、施主が上座に座り、施主以外の親族が下座に座るのが一般的です。ほかの参列者の席順は自由に決められますが、故人に近しい親戚から年齢順で上座に近い場所に座ることが多いです。
一周忌法要を行う会場と会食の場所が別になる場合は、事前にどのような交通手段で移動するかを確認しておくと安心です。
返礼品の準備
当日に参列者へ渡す返礼品の準備もしておきましょう。一般的には「消え物」と呼ばれる、洗剤やお茶、海苔などの消耗品が選ばれますが、近年は参列者が好きなものを選べるようにカタログギフトを選ぶ人も少なくありません。
 大丸・松坂屋の返礼品
大丸・松坂屋の返礼品「消えもの」や和風カタログギフトなど
返礼品には表書きとして「志」と記載したのしをつけ、水引きは黒と白の結び切りを使うのが一般的です。
一周忌と納骨式を同時に行う前に、必要な準備を確認しておきましょう

この記事のまとめ
- 納骨の時期は自由に決められるため、一周忌法要と同日に行っても問題ない
- 一周忌と納骨式を同時に行うと、遺族や参列者の負担を軽減できる
- 一周忌と納骨式を同時に行うデメリットは、当日のスケジュールが多忙になること
- 菩提寺や石材店への依頼・埋葬許可証の準備をしておく
一周忌法要と納骨式を同時に行う場合、トラブルなく執り行うためにも事前準備はしっかりしておく必要があります。本記事で紹介した当日の流れや必要な準備を参考にしながら進めていきましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。