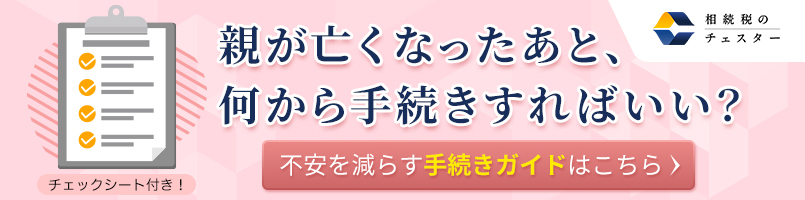香炉とは何かを簡単に解説!使い方や選び方、お手入れの方法まで紹介

香炉とは、故人の供養に欠かせない重要な仏具の一つです。しかし、香炉がどのようなものなのかを詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、香炉の種類や使い方、選び方、お手入れの方法などを簡単にご紹介していきます。
香炉とは

香炉とは、お香を焚いたり線香をあげたりする際に使用する器のことです。香炉は仏具の中でも重要とされる「三具足(みつぐそく)」の一つであり、毎日の供養やお参りに欠かせません。日々の供養だけでなく、お通夜や葬儀、法要の際にも必ず使用されます。
香炉には、仏壇で使用するものと焼香で使用されるものの2種類があります。仏壇で使う場合は、線香を寝かせたり立てたりしやすいように丸型で口が大きい香炉が使われます。焼香で使う場合は、香料が調合された抹香を入れて使用します。
香炉の種類

「香炉」と一口に言っても、さまざまな種類があることをご存知でしょうか。ここからは、香炉の種類と特徴について詳しく解説していきます。
前香炉
前香炉(まえこうろ)は、多くの宗派で使用されている香炉です。口が丸く金属の材質でできているのが特徴で、地域によっては「机用香炉」「線香炉」と呼ばれることもあります。前香炉の中に灰をしきつめ、線香を立てて使用します。仏具店での取り扱いが多く、仏壇のサイズに関わらずに使用できるため、最も一般的に使用されている香炉といえるでしょう。
ただし、浄土真宗では前香炉は使われません。
透かし香炉
透かし香炉とは、浄土真宗大谷派で使われるものです。材質は青磁で、外郭が透かし模様になっているのが特徴です。美しい模様が入っていますが、値段はリーズナブルなものが多く、手に入れやすい種類でもあります。外郭の中には、「なかご」と呼ばれる金属製の灰入れが収められています。線香は灰の上に立てずに折り、寝かせて焚くのが特徴です。
土香炉
土香炉(どこうろ)とは、浄土真宗本願寺派で使われている香炉です。透かし香炉と同じく青磁で作られており、宗紋が入っているものと無地のものがあります。どちらの模様を使用すべきか迷ったら、お寺に相談するとよいでしょう。
また、土香炉でも線香は立てずに折り、寝かせて焚くのが一般的です。
長香炉
長香炉(ながこうろ)とは、名前の通り横に長い形状が特徴で、線香を折らずに寝かせて使います。紫壇調や黒壇調のシックで落ち着いたデザインのものが多く、伝統的なデザインの仏壇にも合わせやすいです。シンプルなデザインのものだけでなく、柄の入った華やかなデザインのものもあり、好みに合わせて選ぶことが可能です。
長香炉は、北陸地方の浄土真宗を中心に使用されることが多い香炉でもあります。同じ浄土真宗でも使用できる香炉の種類が異なるため、前もって確認しておきましょう。
玉香炉
玉香炉(たまこうろ)は、浄土真宗の焼香で使用されることが多い香炉で、浄土真宗本願寺派の仏壇で使用されることもあります。丸みのある形状が特徴で、材質は青磁です。
線香は立てずに寝かせて焚くのが基本で、線香を折る場合もあります。
火舎香炉
火舎香炉(かしゃこうろ)とは、浄土真宗の大谷派や本願寺派で使用されている種類の香炉です。大谷派では金色のものを、本願寺派では黒をはじめとする焼き色のものが使われます。
火舎香炉は焼香で使われるものであり、蓋に煙を出す穴がついているのが特徴です。こちらは仏壇では使われません。
焼香炉
焼香炉(しょうこうろ)とは、焼香をするために使われる香炉であり、自宅の仏壇やお墓では使われません。葬儀や法要の焼香の際、参列者に回して使うことから「回し香炉」と呼ばれることもあります。右側のスペースにはお焼香を、左側には灰と炭を入れて使用するため、準備をしておく必要があります。
香炉を使用する場所

香炉はどのような場所で使用されるものなのでしょうか。ここからは、香炉を使う場面について解説します。
仏壇で使用する
香炉を使う場面として、仏壇での使用が挙げられます。普段のお参りで線香をあげる際は、灰を入れた香炉を使用する必要があります。宗派や好みに合わせた香炉を準備して、故人を弔いましょう。
また、日々の供養では香炉の他にマッチや花立て、燭台といった仏具を準備しておく必要があります。仏壇を新しく購入する場合は、香炉とともに他の仏具も準備しておくのがおすすめです。
お墓で使用する
香炉を使用する場面として、お墓が挙げられます。お墓参りをした際は、故人やご先祖に来訪を伝えるために線香をあげる必要があります。お墓で使用できる香炉には、屋根がついているものや重量があるものなどさまざまな種類があるため、好みに合わせて選びましょう。ただし、焼香専用の香炉はお墓では使えないため、注意が必要です。
部屋で使用する
これまでに紹介した前香炉や土香炉などを、部屋でお香を楽しむ際に使っても構いません。お部屋のインテリアに合わせて香炉を選び、好きな香りを楽しみましょう。仏壇ではなく部屋に遺影や思い出の品を置いた供養スペースを作る場合も、香炉を使用できます。供養スペースの広さや雰囲気などに合わせて、サイズやデザイン、材質などを選ぶとよいでしょう。
葬儀・法要会場で使用する
香炉を使用する場面として、葬儀・法要会場も挙げられます。参列者が祭壇の前に立ち、焼香を行う際に香炉が使用されます。葬儀や法要で使用されるのは焼香炉であり、他の種類の香炉は使われません。
香炉の使い方

香炉の正しい使い方が分からない、今までなんとなく使っていたという方も多いのではないでしょうか。ここからは、香炉の使い方を詳しく紹介していきます。
香炉灰を準備する
香炉で線香を焚く際は、香炉の中に入れる灰(香炉灰)が必要です。灰を入れないと線香がまっすぐに立たない上、火事になるリスクが高まります。線香が安定するよう、灰を香炉の6〜7分目まで厚めに敷きましょう。香炉灰には珪藻土灰や籾灰、藁灰などさまざまな種類があり、それぞれ特徴が違います。
以下は灰の種類別の違いや特徴をまとめた表ですので、参考にしてみてください。
| 香炉灰の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 珪藻土灰 (けいそうどばい) |
珪藻土から作られた天然素材の灰。安価で手に入れやすく、最も多く使用されている。調湿性が高く、灰が舞い上がりにくい。 | ||
| 藁灰 (わらばい) |
藁を燃やして作る灰。通気性が高く軽量であるため、線香が燃え残りにくい。 | ||
| 籾灰 (もみばい) |
籾を燃やして作られる灰。他の灰に比べて柔らかく、線香が最後まで燃えやすい。 | ||
| 藤灰 (ふじばい) |
樹皮を剥いだ藤を焼いて作る灰で、白い色味から化粧灰とも呼ばれる。やわらかい質感で線香が最後まで燃えやすい。 | ||
香炉石を使うこともある
香炉灰ではなく、小さな香炉石(こうろせき)を使用することもあります。灰のように舞い上がることがない上、洗って汚れを落とせば何度でも繰り返し使用できます。天然石やガラスが使用された香炉石も多く、さまざまな色味の石を組み合わせて香炉を華やかに彩ることも可能です。おしゃれなデザインの香炉や、モダンな雰囲気の仏壇には香炉石を使うのがおすすめです。
ただし、香炉石に接している部分は線香が燃えにくくなってしまいます。線香を寝かせて使う浄土真宗では、香炉石は不向きです。
宗派によって使い方が異なる
信仰している仏教の宗派によって、香炉の使い方は異なります。例えば、浄土真宗では線香は寝かせて使用しますが、他の宗派では線香を立てるのが一般的です。また、宗派によっては線香を折って香炉に入れることもあります。香炉の使い方をあらかじめ確認した上で、どの香炉が適しているか検討するとよいでしょう。
香炉の選び方

香炉にはさまざまな種類があるため、どれを使用すればよいか迷ってしまう方もいるのではないでしょうか。ここでは、香炉を選ぶ際に重要になる点をまとめましたので、参考にしてみてください。
デザインや大きさで選ぶ
香炉の選び方として、デザインや大きさで選ぶことが挙げられます。シックで落ち着いたものや華やかな雰囲気のものなど、香炉のデザインはさまざまです。香炉を置くスペースのことも加味しつつ、好みに合わせて香炉を探してみてください。
 はせがわの香炉|お仏壇のはせがわオンラインショップ|Amazon.co.jp
はせがわの香炉|お仏壇のはせがわオンラインショップ|Amazon.co.jp
宗派に合わせて選ぶ
宗派によって、使用できる香炉は異なります。特に、浄土真宗は宗派によって使える香炉が決まっています。香炉を選ぶ際は、自身が信仰している宗派を確認しましょう。
香炉のお手入れ方法

仏壇に線香をあげるために使われる香炉は、他の仏具と比べても使用頻度が高めです。香炉を長く使い続けるためには、正しい方法でお手入れする必要があります。最後に、香炉のお手入れ方法について紹介していきます。
灰と線香を分ける
最初に、灰と線香を分ける必要があります。専用の道具を使用するのがおすすめですが、手元にない場合はピンセットや割り箸で代用しても構いません。灰が舞ったりこぼれたりしても大丈夫なように、新聞紙や布を敷いて作業するとよいでしょう。
灰の中に溜まっている線香の燃え残りを取り除いたら、灰をふるいにかけて細かい燃えカスを取り除きます。
香炉を洗う
灰と線香の燃え残りを取り分けたら、一度灰を出して香炉を洗います。灰がこびりついていたとしても、水洗いだけで簡単に落とすことが可能です。金属製の硬いたわしや研磨スポンジを使うと色落ちや傷の原因になるため注意してください。
また、金属製の香炉は水気が残っているとサビの原因になるため、洗った後はしっかりと水気を拭き取ることが大切です。
香炉灰を交換する
香炉灰が塊になっていたり、固くなって変色していたりした場合は、交換のサインです。香炉に入っていた灰を全て捨て、新しいものに入れ替えましょう。使用済みの灰は新聞紙に入れ、可燃ごみとして処理します。
灰の状態がよければ、再利用しても問題ありません。灰の中に空気を入れつつ、押し付けすぎずにふんわりと灰を盛りましょう。灰を入れたら軽く表面をならして完成です。
香炉とは何かを理解し、使い方やお手入れ方法を知って大切に扱いましょう

この記事のまとめ
- 香炉とは、お香を焚いたり線香をあげたりする際に使う器のことで、重要な仏具の一つ
- 香炉には、前香炉、透かし香炉、土香炉、長香炉、玉香炉、火舎香炉、焼香炉などさまざまな種類がある
- 香炉はお墓や部屋、仏壇などで使用される
- 香炉の使い方は宗派によって異なる
- 香炉はデザインや大きさ、宗派に合わせて選ぶ
- 香炉をお手入れする際は、まず灰と線香を分けてから香炉を洗い、灰を交換する
香炉とは、お香を焚いたり線香をあげたりといった用途で使用される仏具です。前香炉や長香炉などさまざまな種類があり、宗派によって使える香炉が異なります。本記事で紹介した香炉の選び方や使い方を参考にしながら、大切に香炉を扱いましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。