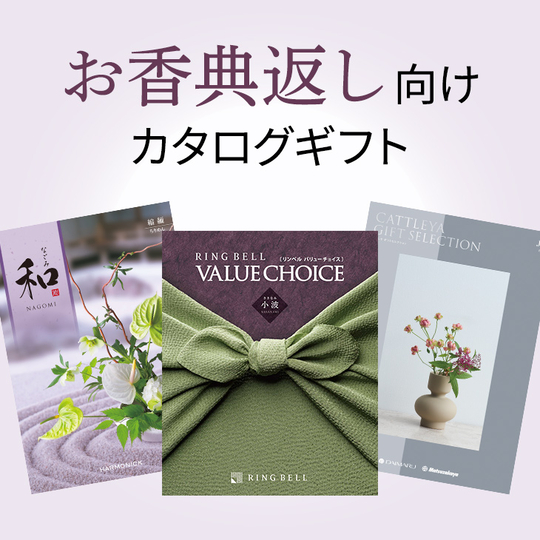葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉とは?伝え方・例文・注意点を解説

お通夜や葬儀が終わったら、来てくれた人にお礼の手紙を出すのが一般的です。本記事では、葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉の例文や注意点について紹介します。
葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉の大切さとタイミング

葬儀に来てくれた人へのお礼は葬儀当日だけでなく、後日改めてお礼の言葉を伝えるのが一般的です。葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉は「お礼状(挨拶状)」として手紙で送ります。
お礼状は、葬儀当日会場で香典返しと一緒に渡す「会葬礼状」とは別物であるため、注意しましょう。本来香典返しは四十九日を過ぎてから送るのが一般的ですが、近年では葬儀当日に手渡すことが増えてきています。そのため、混同しないよう注意が必要です。
またお礼状を送るタイミングは、四十九日を過ぎた忌明けが一般的です。四十九日の法要を終えてから、遅くとも1ヵ月以内には送りましょう。最適なタイミングで送るためにも、お礼状を送る人を事前にまとめておくと安心です。
葬儀に来てくれた人へお礼の言葉を送る方法

葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉は手紙で送るのが一般的ですが、他の方法で伝える場合もあります。ここからは友人や親族、近所の方など直接会える人や、葬儀に参列せず香典を送ってくれた方へのお礼の言葉など、状況別に解説します。
挨拶回り
友人や親族、近所の方など直接挨拶できる人へのお礼の言葉は、挨拶回りの際に伝えましょう。友人や親族は葬儀後、次に会ったときに、会社の関係者の場合は出社のときがよいでしょう。近所の方の場合は、葬儀の翌日または1週間以内に挨拶に向かいます。
しかし、直接会える関係の相手であってもなかなか挨拶にいけるタイミングがない、連絡が取りづらいなど、挨拶の機会がない場合は忌明けの際に手紙を書くとよいでしょう。
香典返し
葬儀に来れずとも香典や弔電、供花を送ってくれた人にもお礼状を送りましょう。また香典を送ってくれた人には、香典返しも一緒に送ります。
本来であれば香典返しとお礼状だけでなく、直接お礼を伝えるのがベストです。しかし参列者が多い場合や遠方から参列した人には、お礼状のみで伝えることが多いです。お礼状のみで伝える場合は、直接挨拶できないことへのお詫びの言葉を記載するのを忘れないようにしましょう。
法要の案内状
四十九日や一周忌など、法要の案内状を送る相手の場合は一緒にお礼状を送りましょう。葬儀に来てくれた人に次の法要の案内状を送る際は、感謝の気持ちを込めて簡潔にお礼の言葉を添えます。
葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉の書き方&マナー

葬儀に来てくれた人へのお礼状を書く際は、書くべき内容や注意すべき点があります。ここではお礼状の書き方を解説します。
葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙の内容と順序
通常、手紙を書く際は始めに時候の挨拶を書きますが、葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙の場合は不要です。また「謹啓」や「謹言」といった書き出し(頭語)や結びの言葉を記載することがありますが、省略しても構いません。
また、葬儀に来てくれた人が友人や親族などの親しい関係であっても、丁寧な言葉を心掛ける必要があります。本文は、伝えたい内容があっても、必ずお礼の言葉から書き始めましょう。そしてお礼の言葉の後に「葬儀を無事終えたこと」や「書面でのお礼になってしまったことのお詫び」を書きます。
葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙の書き順
- 書き出しの言葉(謹啓、拝啓)
- 故人の続柄と名前
- お礼の言葉
- 結びの言葉(謹白、敬具)
- 日付
- 喪主の名前
忌み言葉や重ね言葉を使わない
葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙には、忌み言葉や重ね言葉を使わないよう注意しましょう。忌み言葉は「終わる」「倒れる」「絶える」といった、死や不幸を連想させるような言葉のことを指します。不幸が続くことを連想させる重ね言葉は「しばしば」「たびたび」「くれぐれも」といった同じ言葉が重なった言葉のことです。
| 忌み言葉・重ね言葉の一例 | |||
|---|---|---|---|
| 忌み言葉 | 重ね言葉 | ||
| 死ぬ | 重ね重ね | ||
| 生きていた頃 | たびたび | ||
| とんだこと | 次々 | ||
| めっそうもない | またまた | ||
| 生存中 | だんだん | ||
| 四(死) | 続いて | ||
| 九(苦しむ) | 再び | ||
句読点を使わない
葬儀に来てくれた人に送るお礼状には、句読点を使わないよう注意しましょう。葬儀や法要が滞りなく執り行えるよう、文章の区切りを意味する句読点を使わないのが一般的です。
また、本来は書状に句読点を用いないことから、お礼状にも句読点は不要であるという考えもあります。どちらの意味においても、葬儀に来てくれた人へのお礼状には、句読点を使わないよう注意しましょう。
縦書きで書く
横書きはカジュアルな印象を与えかねないため、弔電のお礼状は縦書きで書きます。
お礼状は手書きと印刷のどちらでも構いませんが、手書きの方がより丁寧です。また手書きの際に縦書きに慣れていない場合は、時折全体を見ながら書き進めていくと縦のラインがズレることなく、きれいに仕上がるでしょう。
【例文】葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉

書き方はわかっても、実際に書く文章に悩む人もいるのではないでしょうか。ここではお礼状の例文を紹介します。葬儀当日に来てくれた人だけでなく、香典や供花を送ってくれた人へのお礼の例文も取り上げているため、参考にしてみてください。
葬儀参列のお礼の言葉
謹啓
亡母 東博花子(故人の俗名)儀 葬儀に際しましては ご多用中にもかかわらず 会葬いただき ありがとうございました
生前母が何かとお世話になりましたこと 心から厚く御礼申し上げます
お陰様で母も 心置きなく旅立つことができたと存じます
生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願いいたします
本来であれば拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書面をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます
謹言
令和〇〇年〇〇日
〇〇市~(差出人の住所)
喪主 東博一郎
香典に対するお礼の言葉(葬儀に参列できなかった人へ香典返しと一緒に送る場合)
亡父 東博太郎(故人の俗名)儀 葬儀に際しましては 過分なお心遣いを承りまして 誠にありがとうございました。
おかげさまで〇月〇日に 無事葬儀をすませることができました
供養のしるしとしてささやかな品をお届けいたしますので ご受納いただければ幸いです
本来であれば直接お会いしてお礼をお伝えすべきところを 略儀ではありますが書状にて失礼いたします
令和〇〇年〇〇日
〇〇市~(差出人の住所)
喪主 東博一郎
供花に対するお礼の言葉
亡父 東博太郎(故人の俗名)儀 葬儀に際しまして 立派なご供花を賜りまして 誠にありがとうございました
謹んでお受けし 父の霊前に飾らせていただきました
庭仕事が好きな父でしたので 〇〇様からのお花にさぞ喜んでいたことでしょう
またおかげさまで〇月〇日に 無事に葬儀をすますことができましたことも 併せてご報告いたします
本来であれば直接お会いしてご挨拶申し上げるべきところではございますが 略儀ながら書状にて失礼いたします
令和〇〇年〇〇日
〇〇市~(差出人の住所)
喪主 東博一郎
葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉に関するよくある質問

葬儀に来てくれた人のなかで、普段メールで連絡をとっている人にもお礼の手紙を書くべきなのかなど、疑問に思う人もいるでしょう。ここでは、葬儀に来てくれた人へのお礼状についてのよくある質問をまとめました。
質問①お礼の言葉はメールやLINEで送ってもよい?
友人や親族、会社の関係者など、普段からメールやLINEで連絡を取り合っている参列者であれば、葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉をメールやLINEで送っても問題ありません。しかし、メールやLINEでお礼の言葉を送るのは略式になるため、葬儀に来てくれた人との関係によっては注意が必要です。葬儀に来てくれた人が目上の方の場合は、お礼状や電話での挨拶がよいでしょう。
質問②お礼の手紙は手書きでないと失礼?
葬儀に来てくれた人へのお礼状は、必ずしも手書きではいけないというわけではありません。ひな形があったり例文を参考にしたりする場合は、パソコンで打ち込んで印刷すると便利です。しかし葬儀に来てくれた人へのお礼は、やはり手書きの方が丁寧な印象にはなるでしょう。
特に参列者が目上の方の場合は、手書きでお礼の手紙を書くことをおすすめします。葬儀に来てくれた人へのお礼状を書く時間がなかなか取れない場合は、印刷したものに手書きで一言添えましょう。
質問③お礼の手紙の便箋や封筒はどんなものがよい?
葬儀に来てくれた人へのお礼状の封筒や便箋は無地、または筋模様の白を使うのが一般的です。派手な柄の入った便箋や封筒は失礼にあたります。普段連絡を取り合っている友人などの場合は多少柄の入ったものでも許容されますが、目上の方の場合は無地の便箋と封筒を選びましょう。
 お礼状の封筒・便箋|Amazon.co.jp
お礼状の封筒・便箋|Amazon.co.jp
葬儀に来てくれた人にはお礼の手紙で感謝を伝えましょう

この記事のまとめ
- 葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉は、手紙で送るのが一般的
- 葬儀に来てくれた人へ手紙でお礼の言葉を送るタイミングは、四十九日を過ぎた頃
- 葬儀に来てくれた人へのお礼の方法は「挨拶回り」「香典返し」「法要の案内状」という形もある
- 葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙には忌み言葉や重ね言葉、句読点を使わない
- 普段連絡を取り合っている相手であれば、葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉をメールやLINEで送っても問題ない
- 葬儀に来てくれた人へのお礼の手紙は「無地または筋模様の白」の封筒・便箋を使うのが一般的
葬儀に来てくれた人へのお礼の言葉は、お礼状という形で手紙で伝えるのが一般的です。しかし、お礼の言葉は必ずしも手紙でなくてはならないというわけではなく、状況に応じてほかの手段もあります。大事なのは参列してくれた人や、参列できずとも香典や供花を送ってくれた人に対する感謝の気持ちです。状況にあった、丁寧なお礼を心がけましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。