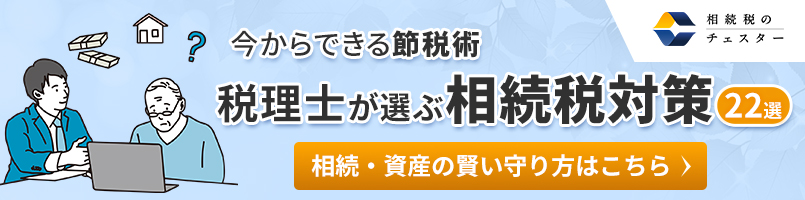持ち家がない人の老後は不安?賃貸のメリットや生活費の貯め方も解説

老後に持ち家がない人は、家族と同居する場合を除き、自分たちで賃貸住宅を借りて住み続けることになります。しかし、収入がない状態で家賃を払うのに対し、不安を感じる人もいるかもしれません。本記事では、持ち家がない人の老後について、賃貸に住むメリットや生活費の貯め方などの観点から解説します。
持ち家がない人の老後はどうなる?

老後に持ち家がない人の1ヵ月の生活費の平均額は、その人の生活スタイルや暮らしている場所によっても異なります。ここでは、公的なデータを用いて詳しく解説します。
老後の生活費の平均額は25万円
「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)」によれば、65歳以上の夫婦2人では、月に25万円ほどの生活費がかかることが示されています。
なお、同調査によれば主な生活費の内訳は以下の通りです。
| 1ヵ月あたりの生活費の内訳 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 1ヵ月あたりの金額 | 構成比 | |
| 食料 | 72,930円 | 29.1% | |
| 住居 | 16,827円 | 6.7% | |
| 光熱・水道 | 22,422円 | 8.9% | |
| 家具・家事用品 | 10,477円 | 4.2% | |
| 被服及び履物 | 5,159円 | 2.1% | |
| 交通・通信 | 30,729円 | 12.2% | |
住居が約1万7千円となっていますが、持ち家がない人の場合、家賃を払わなくてはいけない以上、実際はこれよりも支出が多くなる可能性があります。
持ち家がない人は老後も家賃を払う必要がある
持ち家がない人は、家族や知人と同居するのでない限りは、老後も賃貸住宅を借り自分たちで家賃を払い続ける必要があります。賃貸住宅を借りた場合の月額家賃と共益費の平均値は以下のようになっていました。
| 賃貸住宅を借りた場合の月額家賃と共益費の平均値 | |||
|---|---|---|---|
| 月額家賃 | 78,737円 | ||
| 共益費 | 4,614円 | ||
約8万5千円といったところですが、あくまで平均値であり、間取りや物件によってはこれよりもかかることを留意しておきましょう。
生活費以外の出費も考慮する必要がある
さらに、暮らしていくためには生活費以外の費用もかかるため、これらの費用もあわせて考えなくてはいけません。具体的には以下の費用が考えられるため、1ヵ月あたりの平均額と合わせて紹介します。
| 生活費以外の費用の平均額 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 1ヵ月あたりの金額 | ||
| 保健医療 | 16,879円 | ||
| 教養娯楽 | 24,690円 | ||
| 諸雑費 | 19,835円 | ||
| 交際費 | 24,230円 | ||
| 直接税 | 13,090円 | ||
| 社会保険料 | 18,435円 | ||
| 合計 | 117,159円 | ||
1ヵ月で12万円程度かかる計算です。趣味を満喫したいと思っていたり、持病があって医療機関に定期的にかかったりしている場合は、これよりも多くなることが考えられます。
さらに、自分や家族に介護が必要になった場合、その分の費用もかかるため、1ヵ月あたりの出費も大幅に増えることから、相応の資金を用意しておかないといけない点に注意が必要です。
老後に持ち家がない人が賃貸に住むメリット

老後に持ち家がない人は、家族や友人、知人と同居するか、自分たちで賃貸住宅を借りて住むことになります。ここでは、老後に持ち家がない人が賃貸住宅に住むメリットについて詳しく解説しましょう。
住み替え・引っ越しがしやすい
持ち家がない人ならではのメリットとして、住み替えや引っ越しがしやすいことが挙げられます。持ち家であっても住み替えや引っ越しはできますが、まずは持ち家を売らなくてはいけません。
物件がある場所や物件自体の状態によってはなかなか買い手がつかず、引っ越しや住み替えに時間がかかる場合もあります。しかし、賃貸住宅に住んでいるなら、賃貸契約を更新しない旨を伝え、次に住む家を探すだけで引っ越しや住み替えができるため、はるかに手軽です。
税金、修理代がかからない
持ち家がない人は、家について税金や修理代を負担しなくてすむというのもメリットです。持ち家の場合、自分が所有している限りは毎年固定資産税を払わなくてはいけません。また、家は住んでいる以上傷んでいくため、外壁の塗りなおしなどの修理が必要となります。
家を大事に使うことである程度修理費用は節約できますが、節約できる額にも限界があります。持ち家がない人の場合、これらの家に関する諸費用を負担する必要がないため、その分節約ができます。
相続トラブルを避けられる
相続トラブルを避けられるのも、持ち家がない人ならではのメリットです。仮に、遺産が持ち家しかない状態で亡くなった場合、子供などの相続人は持ち家をどうするかの判断を迫られます。
相続人がひとりであればその相続人の裁量だけで、家を売るか、そのまま保有し賃貸に出すか、自分が住むかの判断が可能です。しかし、子供が3人兄弟など複数の場合、家を売るか、誰かが引き継ぐかといった扱いは、当事者間で話がまとまらないと決められません。
なお、誰かひとりがその家に住む場合は、代償分割といって残りの相続人に代償金として金銭を払う必要が出てきます。そのため、ある程度まとまった現金が用意できないと話がとん挫するでしょう。
いずれにしても、持ち家がある以上、自分が亡くなった後の家の扱いについては考えなくてはいけません。持ち家がない人であれば、このような心配をしなくて良いのも大きなメリットといえます。
老後に持ち家がない人が賃貸に住むデメリット

老後に持ち家がない人が賃貸に住むことには、メリットがある一方、デメリットもあることに注意しなくてはいけません。具体的にどのようなデメリットがあるのか、詳しく解説します。
家賃を払い続けないといけない
持ち家がなく賃貸住宅を自分で借りて住む人は、住んでいる限り家賃を払い続けなくてはいけません。十分な資産がある、もしくは老後もある程度の収入があるなら家賃を払い続けられるでしょう。
しかし、そうでない場合は家賃をどう工面するかが問題になります。また、自分や家族の病気・けがなどで想定以上に医療費や生活費がかかったり、資産が不足した場合、家賃が払えなくなる可能性もある点に注意しなくてはいけません。
物件をバリアフリー化できない
持ち家がない人が直面しうる問題として、物件をバリアフリー化できないことが挙げられます。持ち家であれば、基本的には自分や家族の好きなように改装できるため、自分や家族の都合でリフォーム工事をしても問題ありません。
一方、持ち家がない人が住む賃貸住宅の場合、あくまで家は借り物である以上、自由にリフォームをすることはできません。高齢になり今までの家に不便さを感じたとしても、そのまま住み続けるか、別の物件に引っ越すかして対応することになります。
入居を断られる可能性がある
持ち家がない人が直面する問題で、非常に深刻なものの一つが「入居を断られる可能性がある」ことです。以下の理由により、高齢者に対して家を貸すのをためらう大家は一定数います。
高齢の持ち家がない人が賃貸住宅への入居を断られる理由の例
- 事故や病気による孤独死のリスクがある
- 十分な収入が見込めないため家賃滞納のリスクがある
定年後など、ある程度の年齢になってから家を借りる場合は、不安を解消するためにも「シニア向け」と銘打っている物件を選ぶか、高齢者向けの賃貸住宅に力を入れている不動産会社に依頼するとよいでしょう。
持ち家がない人の老後に向けた生活費の貯め方

持ち家がない人が老後の生活に対し不安をなくすためには、せめて貯金や資産などお金のことでは不安を抱えない状況を作るのが効果的です。貯金を上手に貯められるようにすれば、不安を解消することにもつながります。
具体的な生活費の貯め方について解説するので、ぜひ参考にしてください。
できるだけ長く働く
持ち家がない人に限ったことではありませんが、老後でもできるだけ長く働くことで、貯蓄が減っていくスピードを抑えられます。また、仕事をきっかけに身体を動かしたり、人と関わったりすることで、体力面・精神面での不安の解消にもつながります。
勤務先に再雇用制度など、定年後も働ける制度があるなら有効活用しましょう。また、現役のうちから資格を取ったり、趣味や特技を磨き上げたりして、定年後に起業するのも一つの方法です。
無駄な出費を省く
無駄な出費を省き、減った資金を貯金に回すのも、生活費を貯めるという意味では有効です。たとえば、今住んでいる家が最寄り駅から遠くて車が必要だった場合、あえて最寄り駅から近いコンパクトな物件に住み替え、車を手放せば便利な上に節約にもつながります。
ほかにも、子供がすでに独立している場合、保険を見直して必要がない保障を省くなど、工夫次第で節約して余った資金を貯金に回せるはずです。ただし、無駄な出費を省くといっても、生活の質が必要以上に落ちる方法を取るのは好ましくありません。無理がない程度に取り組みましょう。
資産運用をする
生活にある程度余裕がある場合、貯金の一部を資産運用に回して増やしていくのも生活費に回す資金を増やすためには有効です。定年後でも、NISA(少額投資非課税制度)を使って少額ずつ投資を続けていけば、資産を増やせる可能性は十分にあります。
ただし、資産運用である以上、損失を出し、資金が目減りしてしまう可能性があることに注意が必要です。まずは生活防衛資金として生活費の半年分程度の貯金を確保した上で、最初は少額の資金から資産運用を始めていきましょう。
持ち家がない人は老後を迎える前に十分な資金を確保しましょう

この記事のまとめ
- 老後に持ち家がない人の1ヵ月の生活費は、持ち家がある人に比べ高い可能性がある
- 老後に持ち家ではなく賃貸に住むことは、住み替えや引っ越しがしやすいなど一定のメリットがある
- その一方で、入居自体を断られたり、家賃を払い続けないといけなかったりなどデメリットもあることに注意が必要
- 家賃のほかに生活費もかかるため、お金のことに不安を抱えない状況を作るのが重要
- 定年後も働き続けたり、無駄な出費を省いたりして余剰資金を作り、その一部を資産運用に回すのも効果的
持ち家がない人は、引っ越しや住み替えがしやすい一方で、家賃を払い続け、状況に応じて引っ越せるだけの資金を確保する必要があるのも事実です。健康に注意してできるだけ長く働くとともに、資産運用で少しずつ手元のお金を増やすなど、無理のない範囲で工夫して十分な資金を確保しましょう。
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。