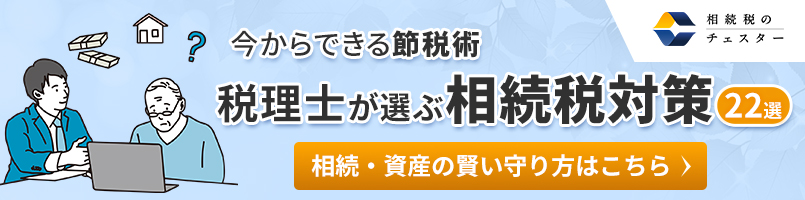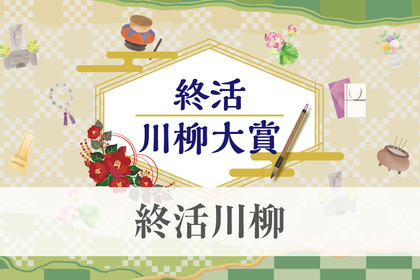50代からのお金の増やし方!平均貯蓄額と老後に必要な資金も解説

50代は老後が視野に入ってきますが、一体どの程度老後資金を用意すればよいのか知りたい方もいらっしゃるでしょう。本記事では、50代からのお金の増やし方について、50代の平均貯蓄額と老後に必要な資金を解説します。
50代の平均貯蓄額は1,773万円

まず、50代の平均貯蓄額はどのぐらいなのか、公的なデータを使って検証してみましょう。金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)」によれば、50代(厳密には、世帯主が50代の世帯)の平均貯蓄額(金融資産保有額)は1,773万円でした。
引用元 (参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)統計表 3 金融資産保有額(金融資産保有世帯)(金融広報中央委員会)
1割強が100万円未満
前述したように、50代の平均貯蓄額は1,773万円であるものの、貯蓄額は人それぞれです。同じく、金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)」によれば、調査に参加した50代の貯蓄額は、以下のように分布していました。
| 50代の貯蓄額の分布 | |||
|---|---|---|---|
| 貯蓄額 | 割合(%) | ||
| 100万円未満 | 13.8 | ||
| 100万円超200万円未満 | 8.8 | ||
| 200万円超300万円未満 | 5.1 | ||
| 300万円超400万円未満 | 5.5 | ||
| 400万円超500万円未満 | 5.5 | ||
| 500万円超700万円未満 | 7.6 | ||
| 700万円超1,000万円未満 | 7.8 | ||
| 1,000万円超1,500万円未満 | 11.2 | ||
| 1,500万円超2,000万円未満 | 6.0 | ||
| 2,000万円超3,000万円未満 | 7.3 | ||
| 3,000万円超 | 15.4 | ||
| 無回答 | 6.0 | ||
引用元 (参考)家計の金融行動に関する世論調査[総世帯](令和5年)統計表 3 金融資産保有額(金融資産保有世帯)(金融広報中央委員会)
上記のデータから、3,000万円超とかなり高額に達している人が約15%いる一方で、約14%の人は貯蓄額が100万円未満であることが分かります。
【年金編】50代からのお金の増やし方

実際のところ老後資金がどのぐらい必要になるかは、人それぞれである上に、その時を迎えてみないと分からない部分もあります。
しかし、老後資金に不安を感じているなら、50代であってもなるべくお金を増やして老後を迎えられるよう、できる工夫は取り入れましょう。以下のように、年金の支払い方、受け取り方を工夫するだけでも、老後資金においてはプラスになります。
年金を繰り下げ受給する
2024年12月現在、公的年金は65歳から受給が開始される仕組みになっています。しかし「繰り下げ受給」という制度を利用する方法もあります。繰り下げ受給とは、受給する時期を1ヵ月繰り下げれば、年金が月額で0.7%増加する仕組みです。65歳から5年遅らせて70歳から受給を開始すれば42%アップすると考えましょう。
参考として、令和6年度の老齢基礎年金は月額68,000円であるため、同じ金額のまま70歳まで受給を繰り下げたとすると、96,560円まで増える計算になります。
付加保険料を上乗せして払う
自営業(法人の代表者である場合は除く)、フリーランスなど、国民年金保険の第一号被保険者の場合、年金保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして払うと、将来受け取れる老齢基礎年金の額を増やせます。
具体的には「200円×納付した月数」の金額が、付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされる仕組みです。一例として、50歳から60歳までの10年間、付加保険料を納めた場合、24,000円(年額)が老齢基礎年金に上乗せされます。
定年後も会社員として働き続ける
定年後も会社員として働き続けることも、将来受け取れる年金を増やし、老後を充実させるという意味では有効です。会社員が勤務先で加入する厚生年金は、原則として70歳まで加入できるため、65歳で定年した後も働き続けて厚生年金を支払えば、将来受け取る年金を増やすことが可能です。
お金の増やし方としてだけではなく、老後も社会とのつながりを持ち、元気で過ごすためにも有意義な方法であるため、前向きに検討する価値はあるでしょう。なお、正社員としてだけでなく、パート・アルバイトでも条件を満たせば厚生年金に加入することが可能です。
未納・免除・猶予分の追納をする
国民年金保険料の未納・免除・猶予分があれば、できる範囲で追納しましょう。未納・免除・猶予分があると、その分将来受け取れる年金額は減ってしまうためです。なお、追納できる期間について、表にまとめました。
| 国民年金保険料を追納できる期間 | |||
|---|---|---|---|
| 分類 | 追納できる期間 | ||
| 単なる未納期間 | 原則、過去2年間 | ||
| 免除、学生納付特例、納付猶予 | 過去10年間 | ||
【資産運用編】50代からのお金の増やし方

お金の効率的な増やし方という意味では、資産運用も有効です。ここでは、50代からでもお金を増やすために使える資産運用の方法を紹介します。
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、毎月掛金を拠出して運用すると、60歳以降に元本と運用益の合計を一時金もしくは年金の形で受け取れる制度です。iDeCoは、税制上の優遇が豊富であることが大きなメリットです。
iDeCoの税制上の優遇
- 掛金は全額所得控除される
- 利息および運用益は非課税
- 年金で受け取るなら公的年金等控除、一時金で受け取るなら退職所得控除の対象となる
ただし、あくまで老後資金の準備を目的とした制度であるため、原則として60歳になるまで資金を引き出せません。また、掛金の金額の変更は年1回のみ、職業(厳密には国民年金保険の加入状況)によって拠出できる掛金の上限額が異なるなど、一定の制約があるため、理解してから始めましょう。
NISA
NISAとは、少額投資非課税制度のことで、専用口座を通じて一定の条件を満たす形で資産運用を行った場合、運用益および売却益が非課税になる制度を指します。
制度自体は2014年から始まっていましたが、2024年1月から制度が恒久化され、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる上に、無制限で非課税保有できるようになりました。両者の違いは以下のとおりです。
| つみたて投資枠と成長投資枠 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 240万円 | |
| 非課税保有限度額 | 1,800万円(成長投資枠との合計額) | 1,200万円 | |
| 対象商品 | 公募株式投資信託等 | 上場株式・公募株式投資信託等 | |
不動産投資
不動産投資とは、マンション・アパートなど不動産を購入し、希望者に貸しだすことで賃料収入を得る投資を指します。「大家業を営む」と考えると分かりやすいでしょう。物件の管理を管理会社に委任すればある程度手間や時間は節約できる上に、会社勤めの傍ら副収入を得る手段としても使えます。不動産投資には賃料収入以外に、売買利益(キャピタルゲイン)もあります。
ただし、入居者が現れないと収入が得られない上に、物件自体が火事や地震などの災害で滅失するリスクがあることに注意が必要です。ある程度の資金を用意し、無理のない計画で運用することと、信頼できる不動産会社の担当者を見つけることが重要になるでしょう。
FX(外国為替証拠金取引)
FX(外国為替証拠金取引)とは、米ドルと日本円など、通貨と通貨を交換し、為替差益により利益を得ることを目指す資産運用の一手法です。1万円など少ない資金から始められる上に、平日であれば24時間いつでも取引ができるため、仕事の傍ら取り組むのにも向いています。
また、「レバレッジ」といって、自己資金を担保にして自己資金以上の取引ができる仕組みが取り入れられているため、やり方次第では大きな利益を出すことも可能です。その反面、わずかな価格変動でも大きな損失が発生する可能性があることに注意しなくてはいけません。
純金積立
純金積立とは、毎月一定額の金を長期間続けて購入していく投資方法を指します。「毎月1,000円分」など金額を決めて購入する「定額積立」、「毎月1グラム」など数量を決めて購入する「定量積立」に分類されます。
購入した金額に比べ、売却した金額が大きければ利益が出ます。仕組みが簡単な上に、少額から始められるため、資産運用の経験が乏しい場合でも取り組みやすい方法といえます。
ただし、金の価格が暴落した場合損失が出る可能性があることに注意が必要です。また、口座を開設する金融機関や地金商によっては手数料が高く、売却益が出ていたとしても、手数料により大幅に目減りすることがある点にも気を付けないといけません。
REIT(不動産投資信託)
REIT(不動産投資信託)とは、不動産投資に特化した投資信託の一種で、投資家から集めた資金を元手に不動産に投資し、家賃収入や売却益などの収益を投資家に分配する仕組みの金融商品を指します。
不動産投資の一種ではあるものの、少額から始められる上に、証券取引所に上場されているため、いつでも売却することが可能です。また、一般的な不動産投資とは異なり、複数用途型リートでは異なるREITを組み合わせて購入できるため、分散投資によりリスクも軽減できます。
ただし、投資対象となる不動産からテナントの退出が増えたなどの理由で家賃収入が下落した場合は、価格や分配金が下落する恐れもあるため注意しなくてはいけません。また、投資対象である不動産が火災や地震などの災害で被害にあったり、法改正や規制の強化によって価値が下落したりした場合も同様です。
外貨預金
外貨預金とは、文字通り日本円を米ドルやユーロなどの外貨に換えて預ける預金のことを指します。具体的な数値は個々の国・通貨により異なりますが、外国のほうが金利が高いことが多いため、受け取れる利息が大きいのがメリットです。
また、円高の時期に外貨預金を始めて、円安に転じたタイミングで日本円に換金すれば、為替差益を得ることが可能です。ただし、為替手数料や利息がかかるため、その分得られる為替差益は減ることに注意しましょう。
逆に、円安の時期に外貨預金を始めて、円高に転じたタイミングで日本円に換金すると為替差損を出してしまいます。また、外貨預金は預金保険制度の対象外です。つまり、日本円建ての普通預金とは異なり、口座を開設している金融機関が万が一破綻した場合、すべての資産を失うおそれがあります。
個人年金保険
個人年金保険とは、生命保険の一種で、公的年金に上乗せする保険です。毎月保険料を支払うと、契約で定めた受け取り開始時期を迎えたら、一定期間もしくは終身にわたり、年金もしくは一時金の形で金銭を受け取れます。
基本的には毎月保険料を払えばよいため仕組みが簡単で、貯蓄が苦手でも計画的に老後資金を準備できるのがメリットです。また、保険料については、個人年金保険料控除を受けられるため、節税にもなります。
ただし、受け取り開始時期を迎える前に解約すると元本割れを起こしがちになるため注意してください。また、保険料払込期間中にインフレが起きると、契約時よりお金としての価値が目減りする「インフレリスク」も伴います。
【生活の見直し編】50代からのお金の増やし方

固定費を減らして貯金に回す
家計簿をつけて毎月の収入・支出を把握できるようになれば、自然と家計の見直しにもつながっていきます。見直しの一環として取り入れてほしいのが「固定費を減らして貯金に回す」ことです。固定費は一度減らせば節約効果が長く続くため、貯蓄できる額も徐々に増えていきます。
定年後のいわゆる「老後」の時期に入ると、収入が激減する以上、早いうちからできる範囲で節約を心がけるのは非常に重要です。固定費を見直すために、具体的に取り入れてほしい方法をいくつか紹介しましょう。
固定費の見直しの具体例
- 電力会社・ガス会社のプランを切り替える
- 固定電話をあまり使っていないなら解約し、携帯電話でやり取りをする
- 賃貸住宅に住んでいるなら家賃の安い物件に住み替える
- 使わないサブスクサービスは解約する
ただし、貯蓄を増やしたいがために無理に固定費を含めた支出を減らそうとすると、生活の質が大幅に落ち、ストレスが溜まりがちになることに注意が必要です。あくまで無理のない範囲で取り組み、固定費を含めた支出を減らしていくのを心がけましょう。
家計簿をつける
もし家計簿をつけていない場合は、家計簿をつけてお金の流れの見える化に取り組んでみましょう。お金を増やしたくても、毎月どれだけの収入・費用が発生しているのか把握できなくては、なかなか難しいのも事実です。また、家計簿をつけることで、自分や家族のお金の使い方の特徴も見えてきます。
家計簿のつけ方は、自分の好みに合わせて構いません。ノートに手書きをするのが面倒だと感じるなら、パソコンやアプリを使って家計簿をつけることもできます。数ヵ月は続けないと意味がないため、できるだけ負担のない方法で取り組んでみましょう。
副業で収入を増やす
50代からのお金の増やし方として取り入れてほしい方法に、副業で収入を増やすことが挙げられます。本業で収入が増えればそれに越したことはありませんが、なかなか難しいのも事実です。
具体的にどのような副業をすべきかは、その人が置かれた状況や得意なこと、趣味によっても異なります。50代におすすめの副業の例をいくつか紹介します。
50代におすすめの副業の例
- ブログや動画配信を使った広告収入
- ハンドメイド作品の販売、受託製作
- 育児・家事代行
- 試験監督などの短期アルバイト
- フードデリバリー
- 覆面調査員
なお、副業をする際は勤務先の就業規則に照らし合わせて問題がないか、必要な手続きはないかを確認しておきましょう。
先取り貯金を意識する
老後資金に限らず、何らかの目的のために貯金をする場合の増やし方のコツとして重要なのが、「先取り貯金を意識する」ことです。
貯蓄を増やしたいと思っても、毎月やりくりをして余った分を貯蓄に回すといったやり方は非効率的であり、好ましくありません。やりくりが非常に上手であれば話は別ですが、大半の人は、やりくりがうまくいかず、なかなか貯蓄も増えないという悪循環に陥りがちなためです。
しかし、毎月の収入の中から、自分で決めた金額先に貯蓄に回し、残った部分でやりくりをして生活する方法であれば、効率的にお金を増やせます。この考え方は、50代に限らず何歳からでもできるお金の増やし方として意識しておくとよいでしょう。
健康に気を付ける
一見、お金の増やし方とは関係ないように思えるかもしれませんが、意外と重要なのが「健康に気を付ける」ことです。病気になると働けなくなるのに加え、医療費もかかるため注意しなくてはいけません。
厚生労働省「医療給付実態調査」によれば、がん(悪性新生物)で入院した場合の1日当たりの診療費は83,405円(協会けんぽおよび組合健保の場合)でした。
実際の自己負担割合は3割である上に、高額療養費や傷病手当金など、療養中の負担を減らす制度があるため、すべてを自分たちで負担しなくてはいけないわけではありません。
しかし、働けない時期があればその収入は減る上に、自分や家族の身体的・精神的な負担も大きくなります。まずは、健康に気を付けるべく、以下の点に配慮して生活しましょう。
健康のために取り入れるべき工夫
- 適度な運動を続ける
- 禁煙する
- 塩分、脂分はできるだけ控える
- 野菜を食べる習慣をつける
- 1週間に1回は休肝日を設ける
- 毎食後歯を磨く
- 睡眠不足に気を付ける
- 自分に合った方法でストレス解消をする
50代からのお金の増やし方の注意点

50代など比較的年齢層が高くなってから資産運用などでお金を増やそうとする場合、注意すべき点がいくつかあります。ここでは、具体的な注意点として以下の3点について解説します。
生活防衛資金を確保する
まず、生活防衛資金として、生活費の半年分程度を確保しておくようにしましょう。生活防衛資金とは、自分や家族の病気・事故など、トラブルに備えて貯めておくお金のことを指します。
一例として、毎月の生活費の平均が30万円程度である場合、その半分にあたる年間180万円程度を生活防衛資金として確保しておくのが望ましいでしょう。
勉強を欠かさない
50代に限らず、資産運用に取り組む人が気を付けるべき点として「勉強を欠かさない」ことが挙げられます。どのような方法で資産運用をするにせよ、基本的な仕組みや価格が上下するロジック、利益が出た場合の税金の扱いなど、基本的な知識を学んでから始めるのが望ましいでしょう。
また、始めた後も日本を含めた世界における政治、経済の動きに留意するなど、相応の勉強は必要です。昨今は初心者でも理解しやすいよう配慮がなされている解説書やWEBサイトが多く出回っています。
証券会社や銀行といった金融機関、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会などのNPO法人などが主催するセミナーに参加するのも、効率よく勉強できるという意味で非常に有意義です。
「うまい話」はない
これは全ての年代に言えることですが、資産運用をする際は「うまい話」はないという意識を持ち、不審な点がないか常に注意を払いましょう。
SNS等で知り合った人から「絶対に儲かるから」と薦められて投資をしたものの、相手は行方をくらまし、返金も出金もできないという投資詐欺は後を絶ちません。投資をする際は、投資先が関連法規に基づき、金融庁に正式な登録をすませているかを必ず確認しましょう。金融庁のホームページにある、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」から確認できます。登録がなかった場合は、きっぱりと断るのが無難です。
また、勧誘を受けて断ったにもかかわらず、しつこい勧誘が続く場合は、金融庁「金融サービス利用者相談室」に相談し、解決を図るのが現実的な選択肢となります。
いずれにしても、やり取りをしていて不審な点を感じたら、それ以上はやりとりをしないなど、自衛することも重要です。
50代からのお金の増やし方を複数組み合わせて実践しましょう

この記事のまとめ
- 50代の平均貯蓄額は1,773万円だが、100万円未満の層も一定数いる
- 50代からでも正しいお金の増やし方をすれば老後資金は増やせる
- 年金の受け取り方・支払い方、自分に合った資産運用を検討する
- 家計簿をつける、健康に気を付けるなども有効
- 生活防衛資金を確保し、常に勉強を欠かさないようにする
50代からでもできるお金の増やし方はたくさんありますが、重要なのは自分にできそうなものを複数組み合わせて実践することです。すべてを一度に実践するのは難しいかもしれませんが、まずはできそうなところから始めてみましょう。