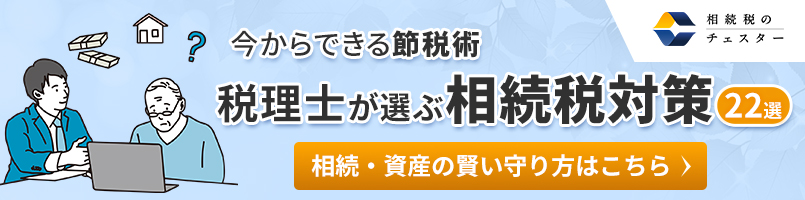夫婦の老後資金はいくらあれば安心?目安と準備方法を紹介

夫婦の老後資金はいくらあれば安心なのか考えたことはあるでしょうか。「老後2,000万円問題」など、老後資金の準備に関する話題は定期的に人々の注目を集めます。それだけ、老後資金はいくらあればよいのか不安に思う人が多いのかもしれません。本記事では、夫婦の老後資金はどれだけあれば安心なのか、その目安と準備方法について解説します。
夫婦の老後資金の考え方

最初に、夫婦2人で老後を迎える場合、老後資金はどれだけあれば安心なのかについて考えてみましょう。
生活スタイル次第で必要な老後資金は変わる
夫婦の生活スタイル次第で必要な老後資金は変動します。
老後に夫婦でやりたいことがあるなら、その分の予算も計上した上でシミュレーションしましょう。たとえば、老後にクルーズ船で旅行したいという場合、乗る船や選択するプランにもよりますが、1名につき300万円程度はかかります。
老後に夫婦でやりたいと考えていることがあるなら、事前に話し合いをした上で、どれぐらいの予算がかかるか把握しておきましょう。
現実的には、やりたいことを全てかなえるのは、予算の面で難しいこともある点に注意しなくてはいけません。老後資金がいくらあっても足りない、という事態にならないよう、夫婦で話し合い、優先順位を付けて希望をかなえていく形にするとよいでしょう。
やりたいことをリストアップしたら、「どうしてもやりたいこと」「できたらやりたいこと」というように、思い入れの強さなどを基準に優先順位を付けてみるとよいでしょう。
金額だけでなく、早くから準備することが重要
また、老後資金の準備に関しては早くから準備することが重要です。
同じ2,000万円を用意するのでも、40年かけて準備するのと20年かけて準備するのとではどちらが負担が大きいかは明らかです。
子育てやマイホーム購入など、お金のかかるライフイベントが続くとなかなか貯金ができないかもしれませんが、少しづつ取り組みましょう。
夫婦で準備すべき老後資金の目安

準備すべき老後資金の目安ですが、夫婦がどのような生活を送りたいかによって異なります。ここでは4パターンを想定し、準備すべき老後資金の目安を紹介するので参考にしてください。
最低日常生活費だけで暮らす場合
まず、最低日常生活費だけで暮らす場合を考えてみましょう。公益財団法人生命保険文化センターによれば、老後における夫婦の最低日常生活費は月額で23.2万円となっています。
一方、2024年4月からの夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は、230,483円となっていました。
最低日常生活費だけで暮らすと仮定し、1ヵ月で必要な生活費を少し余裕を持って24万円と考えた場合、毎月約1万円の赤字が生じると考えられます。1年間で12万円、65歳から85歳までの20年間で約240万円赤字が生じる計算です。
なお、詳しくは後述しますが、一人分の10年間の介護費用は約1,200万円といったところなため、先ほどの240万円と合計した約1,440万円は最低限でも用意するのが望ましいでしょう。実際は夫婦のやりたいことのための費用やこまごまとした雑費が必要になりますが、貯金がない場合はまずはこの水準を目標にしてみましょう。
ゆとりある生活を送る場合
公益財団法人生命保険文化センターが行った調査によれば、夫婦2人の「ゆとりある老後生活費」は平均37.9万円という結果になりました。約38万円といったところです。
毎月必要な生活費が38万円、夫婦2人の標準的な年金額を23万円と仮定すると、毎月15万円の赤字が生じる計算になります。65歳で定年を迎え、85歳になるまでの20年間を想定した場合、生活費の不足額は3,600万円にものぼる計算です。
また、介護費用についても考えなくてはいけません。公益財団法人生命保険文化センターの統計によれば、介護費用にまつわる費用は以下のようになっています。
介護費用を考える際に参考になるデータ
- 一時的な費用:平均74万円
- 毎月の介護費用:平均8.3万円
- 平均介護期間:5年1ヵ月
ただし、いざ介護が始まったものの、想定より長期化し資金が足りないという事態は避けるに越したことはありません。必要な費用を見積もる際は、期間を多少長めに計算しておくとよいでしょう。
仮に10年介護した場合、合計額は1,190万円(=8.3万円×120ヵ月+74万円)と試算できます。約1,200万円といったところです。先ほどの生活費の必要額と合わせると、夫婦2人に必要な老後資金の額は約4,800万円と考えられます。
持ち家がある場合
持ち家がある場合、生活費に加えて、リフォーム費用に充当できるお金があることが望ましいです。
一般社団法人住宅リフォーム推進協議会「2023年度住宅リフォームに関する消費者(検討者・実施者)実態調査」によれば、リフォーム費用の平均は以下のようになっています。
|
一戸建て |
381.5万円 |
|---|---|
|
マンション |
301.7万円 |
令和6年2月 2023年度住宅リフォームに関する消費者(検討者・実施者)実態調査(一般社団法人住宅リフォーム推進協議会)
この数値を元にすると、一戸建ての場合は1回あたり約400万円、マンションの場合は1回あたり約300万円と考え、定年後2回(10年に1回のペース)行うことを見越して予算を立てましょう。
仮に、最低限の生活費でよいと考えるなら、一戸建ての場合は約2,240万円、マンションの場合は約2,040万円が必要になります。
また、ゆとりある生活を送りたいと考えるなら、一戸建ての場合は約5,600万円、マンションの場合は約5,400万円が合計の生活費として必要な計算です。
賃貸の場合
賃貸に住み続ける場合、家賃を払い続けられるかが問題になります。
参考までに、国土交通省がまとめた賃貸住宅の月額家賃および共益費の平均は以下の通りです。
|
月額家賃 |
78,737円 |
|---|---|
|
共益費 |
4,614円 |
約84,000円と考えると、仮に15年住めば1,512万円が必要な計算になります。
もちろんこれはあくまで一例であり、間取りや築年数、地域によってはこれよりも高くなる点に注意しなくてはいけません。
生活費に加えてこれだけの金額を用意できるかが問題になるでしょう。
計算しやすくするために約1,500万円必要と考えた場合、最低限の生活を前提にするなら約2,940万円、ゆとりある生活を送りたいなら約6,300万円必要な計算となります。
なお、実際は平均生活費の中にリフォーム代を含めた修繕費、家賃は含まれているため、これだけの金額を必ず用意する必要があるとまでは言い切れません。ただし、ある程度まとまった金額が必要であることは意識しておきましょう。
夫婦の老後資金を計算する流れ

実際に夫婦で老後資金を計算する際にはどうすればよいのか、具体的な流れを解説します。シミュレーションをする際に活用してください。
①老後にいくら必要かを調べる
まず、老後資金はいくら必要になるかを調べましょう。支出額と年金支給額を把握した上で、必要額のシミュレーションを行います。毎月の支出額に含まれる項目は以下の通りですが、これら以外にも必要だと思う費用も含めた上でシミュレーションすると安心です。
毎月の支出額に含まれる項目の例
- 食費
- 住居費
- 水道光熱費
- 家具・家事用品費
- 被服・履物費
- 保険医療費
- 交通・通信費
- 教育費
- 教養娯楽費
- 税金
- 社会保険料
例えば、持ち家があるなら、リフォーム費用を毎月少しずつ積み立てておくのが望ましいため、その分も計上する必要があります。また、旅行をしたいなど、費用のかかる余暇を楽しみたい場合は、その分も考慮しておきましょう。
②いくら貯めればよいか目標額を決める
次に、いくら貯めればよいか目標額を決めていきましょう。現状の金融資産残高と老後資金としての必要額を比べ、不足があるならその分が目標額になるはずです。
また、「ほかの人たちは実際どれぐらい貯めているのか」が気になる方もいらっしゃるかもしれません。ここで60代、70代の夫婦2人以上の世帯は、どれだけ金融資産を保有しているのか、公的なデータを用いて紹介します。
世帯主が60代、70代の夫婦2人以上の世帯における金融資産保有額の分布は以下のようになっています。
| 世帯主の年齢別・金融資産保有額の分布 | |||
|---|---|---|---|
| 金融資産保有額/世帯主の年齢 | 60代(%) | 70代(%) | |
| 100万円未満 | 7.4 | 7.0 | |
| 100万円以上~200万円未満 | 5.7 | 6.3 | |
| 200万円以上~300万円未満 | 5.5 | 5.4 | |
| 300万円以上~400万円未満 | 3.8 | 5.8 | |
| 400万円以上~500万円未満 | 2.4 | 3.1 | |
| 500万円以上~700万円未満 | 9.2 | 7.7 | |
| 700万円以上~1,000万円未満 | 8.4 | 7.2 | |
| 1,000万円以上~1,500万円未満 | 8.7 | 12.7 | |
| 1,500万円以上~2,000万円未満 | 6.8 | 8.2 | |
| 2,000万円以上~3,000万円未満 | 12.0 | 9.1 | |
| 3,000万円以上 | 26.0 | 24.3 | |
| 無回答 | 4.1 | 3.2 | |
令和5年 家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査] 各種分類別データ(令和5年) 統計表3「金融資産保有額(金融資産保有世帯)」(金融広報中央委員会)
3,000万円以上の世帯は、4世帯に1世帯といったところです。しかし、100万円未満など保有額が非常に少ない世帯も一定数ありました。
なお、いくら貯めるか目標額を決める場合は、公的年金がいくら受け取れるかも加味して考えないといけません。前述したように、2024年4月からの夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は、230,483円となっています。
ただし、実際の年金額は現役時代に受け取っていた給与や勤続年数によっても異なるため、日本年金機構「ねんきんネット」で確認しましょう。
夫婦の老後資金の準備方法

目標額を決めたら、老後資金の準備方法を決めていきましょう。老後は仕事を辞めるなどして収入が減る一方、一定額の支出が生じるため、足りない部分を賄う方法を考えなくてはいけません。ここでは、夫婦2人の老後資金の準備方法について、具体的な例を挙げつつ解説します。
NISA
NISAとは、一定額までの投資にかかる税金が非課税になる少額投資非課税制度のことです。本来、株式や投資信託などの金融商品の運用益や配当には、所得税や住民税がかかります。しかし、専用の口座を通じて一定の条件を満たす形で運用すれば、これらの税金がかからなくなるという制度と考えましょう。
資産運用において重視される「長期・積立・分散」投資を行える制度であるため、長い期間をかけて資産を形成するのに向いている制度です。早い段階から始めることで少ない負担で老後資金を準備できますが、投資である以上損をするリスクもあることに注意しましょう。
また、NISAは後述するiDeCoとは違い、老後資金の確保に特化した運用方法ではありません。しかし、まとまったお金が必要になった場合、いつでも引き出せるという利点を有しています。
一例ですが、老後の生活費や介護費用はiDeCoで確保し、持ち家のリフォーム資金や旅行などの余暇にかかる資金はNISAで確保するといった形で活用しても構いません。夫婦によって適した活用方法を金融機関で相談してみてもよいでしょう。
iDeCo
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことです。毎月一定額の拠出金を支払っていくと、60歳以降に一時金または年金、もしくは両方を併用する形で、掛金と運用益の合計額を受け取れます。
老後資金の準備に活用することを目的とした制度であるため、早い段階から始めれば、ある程度まとまった金額を用意できるでしょう。ただし、拠出金の額を自由に変更できない、原則として途中で解約できないなど、デメリットはあります。
そのため、まずは毎月の収入と支出を考え、無理のない額で拠出金を設定し、少しずつ始めていくとよいでしょう。証券会社などのWEBサイトでシミュレーションもできるため、一度試してみるのをおすすめいたします。
個人年金保険
個人年金保険とは、老後資金を貯めることに特化した保険商品の一種です。契約時に定めた年齢まで保険料を払うと、一生涯もしくは一定期間年金が受け取れる仕組みになっています。
仕組みが分かりやすく、着実に老後資金を貯めていけるのが大きなメリットです。ただし、早い時期に解約すると、受け取れる解約返戻金の額が解約までに支払った保険料の合計額を下回る「元本割れ」を起こす恐れもあります。基本的には途中で解約しない前提で契約するのが望ましいでしょう。
リバースモーゲージ
持ち家はあるものの、金融資産が少なく、老後資金の準備が困難な場合は、リバースモーゲージを検討しましょう。リバースモーゲージとは、持ち家など不動産を担保にして借り入れを行い、契約者が亡くなった際に担保不動産を売却して返済に充てる融資の一種です。
存命中は返済がないか利息分だけを支払っていき、亡くなったときに家を売却するか、相続人が資金を出すかして残債を一括返済します。持ち家さえあれば生活費を確保する手段として使えるのがメリットですが、以下のデメリットもあるため注意が必要です。
リバースモーゲージのデメリット
- 契約者が死亡しても、夫婦の一方や子供は家を相続できない
- マンションなど集合住宅では使えない場合が多い
- 生きているうちに契約期間が終了すると家を失う
- 金利上昇により返済負担が増える
- 担保評価額の下落により融資限度額も下がる可能性がある
【番外編】働き続けること
老後資金との関連では、働き続けることも貯金が減るスピードを抑えるという意味で重要になります。働くことで収入が得られる上に、老後生活のよい刺激になるはずです。また、夫婦2人のうちどちらか一方に万が一のことがあったとしても、仕事を続けることで社会とのつながりを保てます。
夫婦が安心して老後を送るには、早くから老後資金の準備を始めましょう

この記事のまとめ
- 夫婦2人がゆとりある生活を送るために必要な老後資金の目安額は4,800万円
- 老後にやりたいことがあるならさらに上乗せする必要がある
- 老後資金の準備は現状の把握とシミュレーションが重要
- 老後資金の準備方法は自分たちに合ったものを活用すべき
- 早い段階から少しずつ準備することで負担を軽減できる
夫婦2人に必要な老後資金がいくらになるのか正確に計算することはできません。どちらか一方が早世してしまったり、逆に長生きしたりすることはあり得るからです。
しかし、長生きすればするほど老後資金はかかる以上、できるだけ多めに確保しておくに越したことはありません。老後資金は、早い段階から無理のない範囲で老後資金の準備を始めてみましょう。