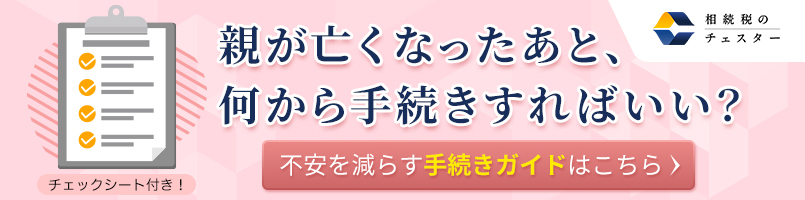喪中に「良いお年を」は言ってよい?代わりに使える年末の挨拶も紹介

喪中に新年を迎える場合、年末の挨拶として「良いお年を」と言っても問題ないのでしょうか。本記事では、喪中に「良いお年を」と言ってもよいのかや、代わりに使える挨拶などを解説します。喪中の年末年始に控えるべきことについても解説しますので、参考にしてみてください。
喪中に「良いお年を」と言ってもよいのか

喪中の場合、年末の挨拶として「良いお年を」と言ってもよいのでしょうか。喪中は普段と年末年始の過ごし方が異なるため、どのような年末の挨拶をするべきか迷う方も多いでしょう。まずは、喪中に使う年末の挨拶について解説していきます。
自分が喪中の場合は言ってもよい
自分が喪中の場合は「良いお年をお迎えください」と挨拶をしても問題ありません。喪中は、故人を偲んで派手な行動やお祝い事などを慎む期間です。
「良いお年を」という挨拶には「神様を無事に迎えて良い年を過ごせますように」といった意味が込められています。この意味からわかる通り「良いお年を」に、新年を祝う意味はありません。そのため、喪中の期間中に「良いお年を」と挨拶をしても構わないと考えられているのです。
相手が喪中の場合は言うのを控えた方がよい
相手が喪中の場合は、「良いお年を」という挨拶は控えた方がよいでしょう。前述した通り「良いお年を」にはお祝いの意味はなく、喪中の相手に使っても問題はありません。
しかし、中には「良いお年を」という挨拶を不快と感じる方もいます。その理由として喪中の間は、まだ大切な人を亡くした深い悲しみから抜け出せず、気持ちを切り替えられない方が多いという理由が挙げられます。また「良いお年を」に「良い」という言葉が入っていることから、お祝いの意味があると考えている方もいます。そのため、喪中の方には「良いお年を」とは言わず、他の挨拶で対応した方がよいでしょう。
喪中に使える年末の挨拶

上述した通り、自身が喪中の際は「良いお年を」と言っても問題ありませんが、相手が喪中の場合は控えた方がよいでしょう。では、喪中の相手にはどのように挨拶をすればよいのでしょうか。ここからは、喪中に使える「良いお年を」の代わりの年末の挨拶を紹介します。
今年もお世話になりました
「良いお年を」の代わりに使えるのは「今年もお世話になりました」という挨拶です。お祝いと勘違いされる文言を含んでおらず、相手に不快な思いをさせる心配がありません。できるだけ挨拶はシンプルにして、喪中の相手を気遣いましょう。
来年もよろしくお願いいたします
喪中の相手に対して「来年もよろしくお願いいたします」という挨拶も使用できます。「今年は大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいたします」のように、両方の挨拶を使っても問題ありません。また、こちらの挨拶は挨拶状でも使用可能です。
喪中の年末年始に言ってはいけない言葉

上述した通り「良いお年を」は自分が喪中でも問題ありません。しかし、喪中で使ってはいけない言葉もあるため注意が必要です。ここからは、喪中の年末年始に言ってはいけないことを解説します。
あけましておめでとうございます
喪中の年末年始に言ってはいけないこととして「あけましておめでとう」という新年の挨拶があります。「あけましておめでとう」という言葉には、新年を迎えたお祝いの意味があります。故人を偲んで身を慎む喪中には、お祝い事は避けるべきであるため「あけましておめでとう」という新年の挨拶は控えましょう。自身が喪に服している期間はもちろん、喪中の相手にも言わないようにしてください。
喪中であることを知らない相手から「あけましておめでとう」と言われた場合でも「おめでとう」とは返しません。代わりに「本年もよろしくお願いいたします」と言い換えるとよいでしょう。
忌み言葉
喪中の年末年始では、忌み言葉を使わないように注意しましょう。忌み言葉とは、同じ言葉を続ける重ね言葉や、不幸を連想させる言葉のことです。例えば「重ね重ね」「再三」「追って」などの言葉が当てはまります。忌み言葉の中には、普段何気なく使っている言葉も多数含まれているため、使わないよう注意してください。
死を連想させる言葉
喪中には、死を連想させるような言葉を使わないのも注意すべき点です。例えば「死ぬ」「あの世へ行く」といった直接的な表現は避けるべきです。他にも、「去る」「永眠」「他界」「逝去」などの言い方も控えましょう。
喪中の年末年始で控えるべきこと

喪中の年末挨拶の他に、喪中の年末年始には控えるべきことがあります。ここからは、喪中の年末年始で控えるべきことについて解説していきます。年越しやお正月をどのように過ごしたらよいのかわからない場合は、こちらを参考にしてみてください。
年賀状を出す
喪中の年末年始に控えるべきこととして、年賀状を出すことが挙げられます。年賀状は、新しい年を迎えられたことを祝うという意味を持ちます。そのため、お祝いを控えるべき喪中に年賀状を出すのは避けるべきとされています。
喪中の場合は、年賀状の代わりに喪中はがきを投函しましょう。喪中はがきとは、服喪中であることや新年の挨拶を控える旨を伝えるためのものです。喪中はがきは、11月中旬から12月上旬までに手配しましょう。
 喪中はがき印刷|Yahoo!ショッピング
喪中はがき印刷|Yahoo!ショッピング
喪中に年賀状をいただいた場合は、寒中見舞いを出して返事をします。寒中見舞いとは、松の内が明けてから立春までに出す挨拶状のことです。何も返事をしないのは相手に失礼となるため、必ず返信しましょう。
 寒中見舞いはがき|Yahoo!ショッピング
寒中見舞いはがき|Yahoo!ショッピング
正月飾り
喪中の年末年始では、正月飾りを飾ることは避けましょう。正月飾りとは、門松や鏡餅、しめ縄などです。これらの正月飾りは新年のお祝いを表すものであるため、喪中には控えるべきとされています。
おせち料理を食べる
おせち料理も、喪中の期間中に控えるべきことの一つです。おせち料理には、紅白かまぼこやエビ、鯛、昆布といった慶事の食材が入っているため、喪中にはふさわしくありません。
お正月のお祝いをするおせち料理の代わりに、「ふせち料理」という精進料理が基になった料理を食べるとよいでしょう。ふせち料理にはお祝いの意味を持つ食材が使われていないため、喪中でも問題なく食べられます。
休みを利用した旅行
年活年始の休みを利用した旅行も、一般的には避けるべきと考えられています。ただし、喪中となる前から旅行を予定していた場合、家族での了承が得られれば旅行をしても問題ありません。
相手が喪中の場合は「良いお年を」を他の挨拶に言い換えましょう

この記事のまとめ
- 自分が喪中の場合、「良いお年を」と挨拶をしても問題ない
- 喪中の相手に対しては「良いお年を」という挨拶は控えた方が無難
- 「良いお年を」の代わりに、「今年もお世話になりました」や「来年もよろしくお願いいたします」といった挨拶をするとよい
- 「あけましておめでとう」といった賀詞や忌み言葉、死を連想させる言葉は控える
- 喪中の年末年始に控えるべきこととして、年賀状を出すこと、正月飾り、おせち料理を食べること、休みを利用した旅行などが挙げられる
相手が喪中の場合は、「良いお年を」という挨拶は控え、「今年はお世話になりました」「来年もよろしくお願いします」といった言葉に置き換えましょう。「あけましておめでとう」の挨拶や、忌み言葉、死を連想させる言葉などは控えてください。本記事で紹介した挨拶に留意し、喪中の年末年始にやってはいけないことなどを参考にして、喪中の過ごし方を考えてみましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。