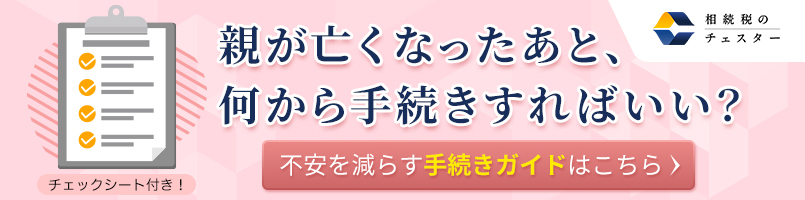一周忌の挨拶例文集!挨拶のタイミングやマナー・注意点も解説

一周忌法要では、施主または喪主による挨拶や、参列者による挨拶があります。しかし、具体的に何を話せばよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。本記事では、一周忌法要の挨拶例文やマナー、注意点について詳しく解説します。本記事を参考に準備を行い、一周忌法要をスムーズに進めましょう。
一周忌法要の挨拶とは

一周忌法要とは、故人が亡くなってから一年後に行われる年忌法要を指します。故人の逝去後、三回忌や七回忌といった年忌法要が執り行われますが、一周忌は特に重要な法要です。
大切な人が亡くなると、故人の死と向き合って悲しみを乗り越えるために喪に服す「喪中」という期間があります。喪が明けて、故人の死を受け入れ通常の生活に戻る節目が一周忌法要です。したがって、一周忌法要には一般的に身内だけでなく親族や友人など大勢の方が参列します。
一周忌の挨拶は法要中に何度か行われます。施主から参列者へ感謝の気持ちを伝えたり、参列者からご遺族へ思いを伝えたりする大切な機会となります。
一周忌法要の挨拶の目的
一周忌法要の挨拶の主な目的は以下の二つです。
一周忌法要の挨拶の目的
- 参列者や遺族に感謝を伝える
- 法要を円滑に進行する
施主または喪主が参列者に挨拶をする場合、参列者が遠方から足を運んでくれたことや、生前の故人と親しくしていただいたことに感謝の気持ちを示します。一方、参列者によるご遺族への挨拶は、招待に感謝を示し、ご遺族を気遣うためのものです。
また、施主や喪主による挨拶は、法要の流れをスムーズに進めるための大切な役割も担っています。法要の始まりや終わりを告げ、滞りなく儀式を進めるために不可欠です。
一周忌法要で挨拶を行う人
一周忌法要では、施主または喪主、参列者がそれぞれさまざまな場面で挨拶を行います。
全体に向けて挨拶を担当するのは、基本的に施主または喪主です。施主や喪主は、儀式全体を取り仕切り、参列者をお迎えする役割を担います。法要を円滑に進めるためには、代表者である施主や喪主による挨拶が必要です。
ただし、施主や喪主が高齢で挨拶が困難な場合や、人前でどうしても話せない場合は、施主や喪主に代わって故人の家族が挨拶を行うこともあります。
参列者が挨拶を行うのは、受付時や帰宅時です。また、会食で献杯(杯を捧げ、敬意を示すこと)を頼まれた場合は献杯の挨拶も行います。参列できない場合は、弔電や手紙で挨拶をしましょう。
一周忌法要の流れと挨拶のタイミング

一周忌の法要は、以下の流れで進行します。
一周忌法要の流れ
- 僧侶の入場
- 施主または喪主による法要開始の挨拶
- 読経・焼香
- 法話
- お墓参り(場所が近い場合)
- 施主または喪主による法要終了の挨拶
- 会食
- 施主または喪主による締めの挨拶
一周忌法要を円滑に進めるためには、各場面での挨拶のタイミングが重要です。それでは、法要の流れと挨拶のタイミングについて詳しく見ていきましょう。
①僧侶の入場
参列者が着席し、開始時間になったら僧侶が入場します。落ち着いた状態で始められるように、全員の着席を確認してから僧侶を案内しましょう。
②施主または喪主による法要開始の挨拶
一周忌法要が始まる前に、施主または喪主が参列者に向けて挨拶を行います。参列に対して感謝の意を示すとともに、僧侶を紹介し、法要の始まりを告げます。
③読経・焼香
僧侶の読経が始まると同時に、参列者による焼香が行われます。故人と近しい遺族から焼香を始め、親族全員の焼香が終わった後、友人や知人が焼香を行う流れです。
④法話
法話とは、僧侶が大切な人との別れや生きることについて教えを伝えることです。亡き人を偲び、参列者と想いを共有することで悲しみを乗り越える準備をします。この場面では挨拶は行われません。僧侶の言葉に耳を傾けて過ごしましょう。
⑤お墓参り
一周忌法要の会場からお墓が近い場合、法話後にお墓参りが行われます。一周忌法要と納骨式を同時に行うときは、お墓参りの前に納骨式を行います。
⑥施主または喪主による法要終了の挨拶
一周忌法要終了後、施主または喪主は参列者に法要の終わりと感謝の意を述べる挨拶を行います。法要後に会食を予定している場合、施主または喪主は会食が行われる場所や移動手段もお伝えしましょう。
⑦会食
一周忌法要の後は、お斎(おとき)と呼ばれる会食が行われることが多いです。お斎は参列者や僧侶をもてなすための会食のことで、故人の思い出について語り合い、和やかに過ごします。会食の始まりや献杯をする際、施主や喪主による挨拶が必要です。
献杯の挨拶を身内や友人へ依頼する場合は、施主または喪主が依頼した方の紹介をします。その後、依頼された方は献杯の挨拶を行います。
⑧施主または喪主による締めの挨拶
会食終了後、施主または喪主は、法要の締めとなる挨拶を行います。参列者へ感謝を示し、法事が終了したことを伝えましょう。
一周忌法要の挨拶例文集【施主または喪主による挨拶】

ここからは、一周忌法要の挨拶の例文を紹介していきます。まずは、施主または喪主による挨拶です。
法要前の挨拶例文
お礼:皆様、本日はご多用の中、父・故 東博 太郎の一周忌法要にご参列いただき、誠にありがとうございます。
法要の開始を告げる:これより、一周忌の法要を始めさせていただきます。
僧侶の紹介:本日の法要は◯◯寺の◯◯様にお願いいたしました。それでは◯◯様、よろしくお願いいたします。
法要後の挨拶例文
お礼:本日は、皆様のおかげで無事に一周忌法要を迎えられました。故 東博 太郎に代わり、深く感謝申し上げます。父も、きっと喜んでいることと思います。
会食のお知らせ:この後、ささやかではございますが、お食事の用意がございます。お時間の許す限りおくつろぎいただき、故人の思い出をお聞かせいただけると幸いです。
締め:本日はご多用のところ、お時間をいただき誠にありがとうございました。
納骨式と一周忌法要をセットで行う場合の挨拶例文
お礼:本日は故 東博 太郎の一周忌及び納骨式にお越しいただき、ありがとうございました。私たちもようやく前を向いて生活できるようになり、無事にこの日を迎えることができました。皆様のお力添えに心より感謝申し上げます。
会食のお知らせ:この後、ささやかなお食事の場をご用意しております。お時間がある方は、ぜひおくつろぎください。
会食前の挨拶例文
お礼:本日はご多用の中、故 東博 太郎を偲ぶ席にお付き合いいただき、御礼申し上げます。懐かしい方にお集まりいただき、きっと父も喜んでいることでしょう。
参列者への気遣い:お時間の許す限り、ゆっくりとおくつろぎください。
献杯の挨拶を行う人を紹介する例文
紹介:献杯の挨拶を〇〇様にお願いいたしました。〇〇様、どうぞよろしくお願いいたします。
一周忌法要の締めとなる挨拶例文
お礼:本日は、長時間お付き合いいただき、誠にありがとうございました。
法事の終了を告げる:なごりはつきませんが、そろそろお開きの時刻となりました。皆様の温かいご支援に心より感謝申し上げます。故人も皆様と過ごせて、さぞかし喜んでいることでしょう。
返礼品のお知らせ:ささやかではございますが、お礼の品をご用意しております。お帰りの際に、お受け取りいただければ幸いです。
締め:どうかお足元にお気をつけてお帰りくださいませ。本日は、誠にありがとうございました。
会食をしない場合の挨拶例文
お礼:本日はご多用のところ、故 東博 太郎の一周忌法要にご参列いただき、誠にありがとうございます。たくさんの方にお越しいただき、父もきっと喜んでいることと思います。
会食のない旨の説明:皆様と粗宴を囲みたいところではありますが、遠方よりお越しの方もいらっしゃるため、これにてお開きとさせていただきます。
返礼品のお知らせ:お帰りの際は、返礼品と折詰をお持ち帰りくださいませ。
締め:この度は、誠にありがとうございました。
一周忌法要の挨拶例文集【参列者による挨拶】

続いて、参列者による一周忌法要の挨拶例文を紹介します。
受付での挨拶例文
到着時:本日は一周忌法要に参列させていただき、ありがとうございます。
香典を渡す:こちら、御仏前にお供えください。
献杯の挨拶例文
名乗り:故人の友人の〇〇でございます。
お礼:本日はお集まりいただきありがとうございます。今日は皆様と思い出を語らい、亡き友を偲びたいと思います。
献杯の挨拶:それでは、献杯をさせていただきます。献杯。
法要後に帰るときの挨拶例文
招待へのお礼:本日は参列させていただき、誠にありがとうございました。
ご遺族への気遣い:どうか、お身体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
一周忌法要の挨拶例文集【弔電・手紙での挨拶】

遠方に住んでいるなどのやむを得ぬ事情で一周忌法要に参列できない場合、弔電や手紙で挨拶を行いましょう。取り急ぎ参列できない旨をお伝えする場合は弔電、時間に余裕があるときは故人との簡単なエピソードを添えて手紙を送るのがおすすめです。
弔電の例文
哀悼の意:東博太郎様の一周忌法要にあたり、衷心より哀悼の意を表します。
参列できない旨の説明:当日は都合がつかず、お伺いできない失礼をお許しください。
ご遺族への気遣い:遠方より故人のご冥福とご家族の皆様のご健康をお祈りいたします。
手紙の例文
招待へのお礼:この度は一周忌法要のご案内をいただき誠にありがとうございます
参列できない旨の説明:本来なら参列してお悔やみを申し上げるべきところですが やむを得ぬ事情によりお伺いできず誠に申し訳ありません
故人との思い出:生前東博太郎様には職場でお世話になり 困ったときには励ましていただきました
ご香料を送る旨をお知らせ:東博太郎様のご冥福を祈り 心ばかりですが 御仏前にお供えしていただきたく御香料を送らせていただきます
ご遺族への気遣い:ご家族の皆様におかれましてはどうかお身体にお気をつけてお過ごしください
一周忌法要の挨拶に関する基本マナーと注意点

最後に、一周忌法要の挨拶を行う際に気をつけるべきポイントを紹介します。
忌み言葉や重ね言葉を避ける
一周忌法要の挨拶では、忌み言葉や重ね言葉を避けましょう。例えば、「死ぬ」「終わる」などの死を連想させる言葉や、「重ね重ね」「再度」などの不幸が重なることを連想させる表現は避けましょう。
短く簡単にすませる
一周忌法要の挨拶は、長くなりすぎず簡単に行うことが大切です。施主または喪主は、参列者や僧侶をあまり長く待たせないように配慮しましょう。ゆっくりと語り合いたい場合は、会食の場を利用します。
法要に関する話題以外は慎む
一周忌法要の挨拶では、法要に関する話題に集中し、それ以外の話題には触れないことが大切です。一周忌法要の時間は限られており、世間話や個人的な話題まで挨拶に盛り込んでしまうと進行に影響します。法事の進行や故人への追悼に関連した内容を話すように心掛けましょう。
故人に関する悪い印象を与える内容を避ける
一周忌法要の挨拶では、故人に関する失敗談などの悪い印象を与える話題に触れるべきではありません。たとえ親しい仲だったとしても、不快に思う方もいるかもしれません。心穏やかに故人を偲ぶ場となるように、どなたが聞いても問題のない内容を心掛けましょう。
一周忌法要を円滑に進められるように事前に挨拶を準備しましょう

この記事のまとめ
- 一周忌法要の挨拶は、施主または喪主、参列者によって行われる
- 一周忌法要の挨拶には感謝を伝え、法要を円滑に進める役割がある
- 忌み言葉や重ね言葉を避け、簡潔に述べる
- 一周忌法要の挨拶は、長くなりすぎないようにする
- 故人に関する失敗談などの話題は避ける
一周忌法要の挨拶は、参列者やお招きいただいた遺族へ感謝の気持ちを伝える機会であり、一周忌を滞りなく進めるためにも重要です。挨拶を行うタイミングや内容を把握し、例文を参考に適切な挨拶を準備して、故人を偲ぶ場にふさわしい法要にしましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。