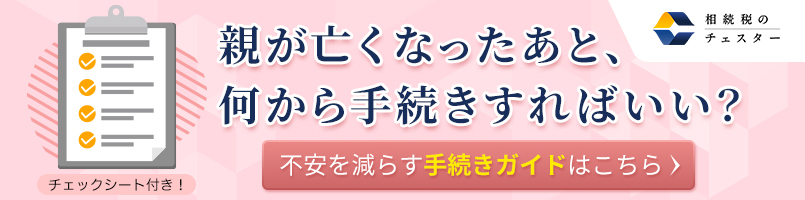一周忌のお供えの選び方は?金額の相場や渡し方のマナーも解説

親族や親しい方の一周忌には、お供えを持参する方も多いでしょう。しかし、どんなものがよいのか、相場はどの程度なのかと悩むものです。本記事では、一周忌のお供えの選び方や相場、おすすめのものを紹介します。渡し方のマナーや渡す際の注意点も解説するため参考にしてみてください。
一周忌にお供えをする意味

一周忌とは、故人が亡くなってから一年後の同月同日である祥月命日(しょうつきめいにち)のことです。年忌法要の中でも重要とされており、遺族や親族、親しい友人が集まり一周忌法要が行われます。
一周忌は故人を偲び慶事を避け、慎んで暮らしてきた遺族や親族の節目となる喪明けの日でもあります。これ以降の年忌法要は家族のみで行われる場合もあるため、一周忌法要に招かれた際は、故人への感謝や供養の意味を込めてお供えを持参するのが一般的です。
ただし、地域によっては一周忌のお供えを必要としない場合もあるため、事前に周囲の方に確認し、慣習に合わせるのがよいでしょう。
一周忌のお供えの選び方

一周忌のお供えを選ぶ際には、「消え物を選ぶ」と「日持ちするものを選ぶ」の2点に気をつけることが大切です。
消え物を選ぶ
一周忌のお供えには、消え物を選ぶのが一般的です。食べたり飲んだりしてなくなるものや、使ってなくなる消耗品などが多く選ばれています。
地域によっては、一周忌法要後に参列者でお供えを分け合う場合もあります。そのため、かさばらず、分けやすいかという点も考慮して選ぶとよいでしょう。
日持ちするものを選ぶ
一周忌のお供えは、日持ちするものを選ぶ必要があります。賞味期限の短いお供えは消費が追いつかず、腐らせてしまう場合もあるでしょう。
日持ちするお供えであれば、ある程度の期間保存できるためおすすめです。
一周忌のお供えの相場

ここでは、一周忌のお供えの相場を紹介します。
品物だけを渡す場合は5千円~1万円
香典は渡さず品物だけを渡す場合の一周忌のお供えは、5千円~1万円が一般的です。故人との関係や地域の慣習によっても異なるため、親族間や周囲と相談して金額を決めることをおすすめします。
香典も渡す場合はなくてもよい
仏教において、香典は故人にお供えする「香」の代わりにお金を包んだもので、供物や供花と同じ意味を持っています。そのため、一周忌に香典を渡す場合は、お供えはなくてもよいとされています。
一周忌のお供えにおすすめのもの

仏教では仏壇や祭壇にお供えするものとして、「五供・御供(ごくう)」という考え方があります。五供とは、「香・花・灯明・水・飲食」の五つです。これらを意識して一周忌のお供えを選ぶのがよいでしょう。
ろうそく・線香
灯明はろうそくを指し、「明かりを灯し闇を照らすことにより迷いや煩悩を払う」という意味があります。また、香とは線香や白檀などの香りが出るものを指し、「仏様の食事や現世と死後の世界を繋ぐもの」とされています。
どちらも仏壇のある家庭では毎日使うもののため、五供の中でも特に実用的です。一周忌のお供えとして特別感を出したい場合は、香りのよいものや煙が少ないものなど、高級感のある線香を選んでみてください。
花(生花・ブリザーブドフラワー)
五供の花は、供花や仏花と呼ばれるものを指します。故人の冥福を祈るとともに、仏壇や祭壇を飾るためのものです。また、ご遺族を慰める意味もあります。
お通夜や葬儀で供花に使用される花は、仏事に用いられる菊や百合、白い花が一般的です。一方、一周忌からは花の種類が限定されておらず、故人が好きだった色の花を取りれてもよいとされています。
ただし、香りの強い花や、赤や濃い紫などの派手な色合いの花は避けた方が無難です。トゲや毒がなく、ピンクやブルー、ラベンダーなどの淡い色合いをおすすめします。
花をお供えする際は花束ではなく、フラワーアレンジメントされているものを選ぶとご遺族が花瓶を準備することなく、そのまま仏壇にお供えできるためおすすめです。
近年では、生花だけでなくプリザーブドフラワーも増えてきました。長期間綺麗な状態を保てる上にお手入れの手間もかからないため、ご遺族にも負担をかけにくいでしょう。
お菓子
飲食はお供えして同じものを食べることにより、故人と繫がりが持てるとされています。お菓子は一周忌のお供えとして定番で、仏壇に供えた後にご遺族や参列者と一緒に食べたり、分け合ったりできるのが利点です。
賞味期限が長く、常温で保管できることはもちろん、幅広い年代に好まれる種類のお菓子を選ぶのがよいでしょう。和菓子ならせんべいや饅頭、洋菓子ならクッキーやバームクーヘン、ゼリーなどがおすすめです。
飲み物
飲み物もお菓子と同様におすすめです。
親族や友人など参列者と分け合えるように、小さいサイズのペットボトルや紙パックのものがよいでしょう。
一般的にお茶やジュース、健康飲料などが一周忌のお供えとして選ばれています。アルコールは宗派や地域によって禁止されている場合もあるため、避けた方がよいでしょう。
果物
五供の飲食として、果物が選ばれることも多いです。仏教では魂の形が丸いといわれているため、一周忌にお供えする果物も丸いものがよいとされています。
そのため、リンゴやメロン、梨やスイカなど丸くて日持ちしやすく、季節に合った旬の果物を選ぶのがよいでしょう。ただし、地域によって好まれる果物の種類が異なる場合もあります。沖縄では丸い果物ではなく、バナナやサトウキビが一周忌のお供えの定番です。
また、果物の数を奇数にすることも大切です。仏教では偶数は割り切れるため、故人との縁が切れることを連想されるとして避けられています。
一周忌のお供えの渡し方のマナー

ここからは、一周忌のお供えの渡し方のマナーを解説します。掛け紙や渡すタイミングについて触れているため、参考にしてみてください。
掛け紙を使う
お供えに使う掛け紙とは、贈り物や金封に掛ける紙全般を指します。熨斗(のし)のある掛け紙と水引だけが印刷されたものがありますが、一周忌のお供えには水引だけのものを使用するのがマナーです。熨斗が付いた掛け紙は慶事の際に使用されるものであり、弔事には不向きのため注意してください。
さらに、一周忌法要に参列しお供えを手渡しする際は「外掛け」に、郵便や宅急便などで一周忌のお供えを送る場合は「内掛け」にします。外掛けは包装紙の上から掛ける方法で、内掛けは箱に直接掛けて包装紙で包む方法です。渡し方に合わせて掛け紙を使い分けましょう。
施主に手渡しする
一周忌のお供えを渡すタイミングは、玄関などで施主と挨拶した時です。その際に「御仏前にお供えください」と一言添えて渡すのがよいでしょう。
施主以外の方に渡したり、勝手に仏壇にお供えしたりするのはマナー違反にあたります。
一周忌のお供えを持参する際に紙袋を使用することも多いでしょう。渡す際は事前に紙袋から取り出し、お供えのみを渡してください。使用後の紙袋は自分で持ち帰ります。
一周忌のお供えを渡す際の注意点

一周忌のお供えを渡す際には、注意しなければならないこともあります。最後に、お供えに避けた方がよいものや手配する際に気をつけたいことを解説します。
殺傷・慶事をイメージさせる物を避ける
殺生を禁じている仏教では「四つ足臭物(よつあしなまぐさもの)」をお供えするのは禁止されています。生ものは日持ちしないという点でも、以下のものは避けた方がよいでしょう。
四つ足生臭物の例
- 肉類(四足歩行の動物の肉)
- 生魚 など
また、慶事の際に用いられる以下のような品物も、一周忌のお供え物には相応しくないとされています。
慶事に用いられるものの例
- 昆布
- かつおぶし
- お酒
高価すぎる物は避ける
一周忌のお供えは高すぎるものを選ぶと、ご遺族に気を遣わせたりお返しを準備する負担をかけてしまったりする場合もあります。
そのため、親族間や周囲と相談して、相場を理解しておくのがよいでしょう。
欠席する際は法要の3日前までに届くように手配する
一周忌法要を欠席する際は、3日前までにご遺族の自宅にお供えが届くように手配しましょう。当日や前日などギリギリになると、法要の準備でご遺族が受け取れない可能性もあるためです。
お供えの選び方は法要に参列する際と同様で、消え物で日持ちするものを選んでください。その際は、出席できないことのお詫びや故人を偲ぶ気持ち、ご遺族の方への挨拶などを書いた手紙を添えるのがよいでしょう。
選び方や金額の相場を踏まえて、一周忌のお供えを選びましょう

この記事のまとめ
- 一周忌のお供えは、消え物・日持ちするものを選ぶ
- 品物だけを渡す場合のお供えの相場は、5千円~1万円
- 香典を渡す場合はお供えがなくてもよい
- お供えは、香・花・灯明・水・飲食の「五供・御供(ごくう)」から選ぶ
- 四つ足生臭物と慶事に用いられるものは避ける
- 法要を欠席する際は、手紙を添えて3日前までに届くように手配する
一周忌のお供えは五供を考慮し、消え物や日持ちするものを選ぶことが大切です。金額は親族や周囲に確認し、相場に合わせるのがよいでしょう。殺生や慶事をイメージさせるものは避け、故人が好きだった食べ物や好きな色の花を選ぶのもおすすめです。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。