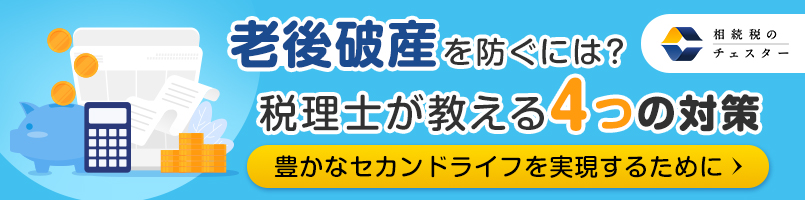熟年夫婦の過ごし方!生活や趣味で仲良くいるコツも紹介

熟年夫婦は、これまでの不満やわだかまりが原因で良好な関係を続けるのが難しいことが多々あります。好きで結婚したはずのパートナーに不満を抱えてばかりの生活を続けたくないと思う方も多いでしょう。本記事ではこれからの人生を夫婦で充実したものにするために、熟年夫婦に実践してほしい過ごし方を紹介します。
熟年夫婦が不仲になりやすい原因

熟年夫婦がこれからの人生を充実したものにするためにも、まずは熟年夫婦が不仲になる原因を知っておくことが大切です。不仲になりやすい原因はさまざまですが、しばしば原因とされるものを以下で紹介します。
価値観や生活スタイルの不一致
例え長年連れ添ってきた夫婦でも、もとは他人同士です。年月を重ねる中で、価値観や生活スタイルのずれが目立ってくることもあります。
「昔は笑ってすませていたことが、最近は気になるようになった」など、ささいな違和感が積み重なり、夫婦の距離が少しずつ広がってしまうこともあります。
例えば、一方が浪費家でもう一方が節約志向だったり、定年後の過ごし方について意見が食い違ったりするなど、これまでと生活のリズムや優先順位が変わり摩擦が生じることもあります。こうした価値観の違いを放っておくと、不仲の原因になることもあるため、お互いの考え方を尊重しながら歩み寄る姿勢が大切です。
コミュニケーション不足
熟年夫婦は、長年連れ添ってきたからこそコミュニケーション不足に陥ってしまいがちです。ずっと一緒に生活してきたからこそ話す内容がなくなってしまったり、相手の反応が薄くなりコミュニケーションをとりたいと思わなかったり、喧嘩になるのが嫌で相手に近付くことを避けたりと、コミュニケーション不足になってしまう要因は多くあります。
ライフステージの変化による不満
熟年夫婦は、定年退職や子供の独立などさまざまなライフステージの変化を経験します。ライフステージの変化が起こった際、上手く順応できない場合には不満がたまりがちです。
例としては「夫が定年退職して自宅にずっといるのに家事も手伝わず文句ばかり言ってくる」「夫婦の潤滑油のような存在だった子供が独立して夫婦二人の生活になったけれど、今更話すこともなく二人きりの空間が苦痛に感じる」などが挙げられるでしょう。
介護問題
熟年夫婦は「自分たちの親の介護」や「自分たちの介護」など、介護問題に向き合わなくてはいけない状況も多くなります。介護問題に直面したとき、夫婦のどちらか一方に介護の負担が大きくなっているとストレスがたまり、不仲の要因となることが多いです。
卒婚とは?離婚とどう違う?

熟年夫婦の中には「卒婚」を考えている方もいるかもしれません。卒婚とは、法律上の婚姻関係を維持したまま、互いに干渉を減らしてそれぞれが自由に暮らすことをいいます。
卒婚と離婚の大きな違いは法律上の婚姻関係の有無です。離婚は、法律上の婚姻関係を解消するため、相続権などの権利を失いますが、卒婚では法律上の夫婦の権利を失うことはありません。
したがって、卒婚は婚姻関係から成る権利を維持したい方や離婚手続きの手間を省きたい方、前向きな気持ちで互いの干渉を減らし自由に過ごしたい方などにおすすめです。
卒婚には「同じ家で一緒に暮らすが互いに干渉せず自由に過ごす」「別居して自由に暮らす」「週末だけ同じ家で一緒に過ごす」などさまざまなパターンがあります。
卒婚を実現するためには、卒婚が前向きに婚姻関係を続けつつストレスフリーに生きることを目的とした形であることを念頭に置き、お互いが納得するルールを作ることが大切です。
熟年夫婦の日常生活の過ごし方

熟年夫婦が仲良く過ごすためには、日常生活における意識的な行動が大切です。以下では、良好な関係を築くために熟年夫婦が意識したい日常生活の過ごし方を紹介します。熟年夫婦になっても仲良しでいたい方や、現在熟年夫婦で冷え切った関係を解消したい方などはぜひ参考にしてください。
会話を増やす
熟年夫婦は長年一緒に生活しているため、会話が少なくなってしまいがちです。意識的に夫婦での会話を増やして、コミュニケーションを取りましょう。
普段あまり夫婦で会話をしていない場合には、どんなことを話していいか分からない場合もあるかもしれません。その場合は、以下の内容で会話をしてみることをおすすめします。
何を話していいか分からない熟年夫婦におすすめの話題
- 今日あった出来事
- テレビで見たおもしろい話
- 最近話題のニュース
- 最近食べた美味しいもの
- 今度一緒に食べたいもの
- 今度一緒に出かけたい場所
会話が増えると相手のことをさらに知れるようになり、相手に対する興味や愛情が湧いてきます。熟年夫婦だからこそ、些細なことでもたくさん会話するように心がけましょう。
反対に、仲良しな熟年夫婦でいたいときに避けた方がいい会話もあります。「何か話す内容がほしい」という場合にも、以下の会話は意識的に避けましょう。
仲良しな熟年夫婦でいたいときに避けた方がよい会話
- 愚痴や不満などネガティブな会話
- 相手が話したくない内容についての会話
- 自慢話や自分だけが興味のある話など自分だけが楽しい会話
- 自分だけがひたすら喋る一方通行の会話
ネガティブな会話に関しては、長年連れ添った熟年夫婦だからこそ弱音を話したいこともあるため、絶対に話してはいけないわけではありません。しかし、会話のほとんどがネガティブな会話になってしまうと相手が辛く感じるため、注意が必要です。
協力して家事をする
熟年夫婦が抱えやすい問題として、どちらか一方に家事の比重が偏っていることが多くあります。家事の負担が大きい方が不満を抱いて不仲につながることもあるため、協力して家事をすることはとても大切です。
熟年夫婦の場合、仕事を退職してこの先一緒に家事を担える状況も増えてくることが考えられるため、常日頃から家事を分担して、さまざまな家事をスムーズにこなせるように慣れておきましょう。
家事を協力する場合、やり方が気に入らなくて喧嘩が起こることもあります。服はどういうたたみ方がいいのか、食器はどこにしまうかなど、長年家事の負担が大きかった方のアドバイスを聞きつつ、夫婦の両方が納得するやり方で家事を分担することも重要です。
休日を一緒に過ごす
熟年夫婦の場合、休日を一緒に過ごすのもおすすめです。熟年夫婦だと各々のコミュニティが確立されていることも多く、別々に過ごす休日がほとんどかもしれませんが、休日の中で一緒に過ごす瞬間を増やすよう意識してみましょう。
些細なことでいえば「テレビを一緒に観る」「自宅でお茶を一緒に飲む」などといった瞬間です。もっと長時間過ごす方法としては「一緒に散歩をする」「一緒に食材の買い物に行く」「一緒にカフェで過ごす」「映画を一緒に観る」などが挙げられるでしょう。
熟年夫婦が一緒に楽しめる趣味

コミュニケーション不足の熟年夫婦の場合、共通の趣味を見つけて一緒に楽しむのが仲良しな熟年夫婦になるための一歩です。以下では、熟年夫婦が一緒に楽しめる趣味を紹介します。
料理
料理は、どこかへ出かける必要もなく自宅にいながらにして一緒に楽しめる趣味です。普段料理をしている家庭であれば、調理道具や調味料はすでに揃っているため食材以外に大きな出費がないのも嬉しい点です。
また、家事の一つでもあるため、お互いができるようになっておくことで家事を分担することにもつながります。準備や後片付けまでを含めて、夫婦二人で行うことを意識しましょう。この機会に、ひとりでは手間がかかって作れないような料理に挑戦してみるのもおすすめです。
グルメ
美味しい飲食店をめぐったり話題の食べ物を取り寄せたりと、グルメを共通の趣味にすれば、夫婦で食事を一緒にする機会が増えます。
同じものを食べるということは、例えば飲食店に行く場合、飲食店までの行き帰りや食事が出てくるまでのなど、食事中以外に過ごす時間も増えることが多くコミュニケーションの時間も生まれます。どんなものを食べたいかや、食べた感想などを話せば会話の内容にも困りません。
熟年夫婦の場合、お互いに行きつけの飲食店があることも多いでしょう。たまにお互いの行きつけを紹介し合う日を作ると、相手の新しい一面を知れたり、夫婦そろってコミュニティに参加できたりと仲が深まるきっかけが作れるかもしれません。
旅行
子育てもひと段落し、仕事や金銭にも余裕ができやすい熟年夫婦だからこそおすすめしたい共通の趣味が旅行です。温泉旅行や海外旅行など、子育てや仕事が忙しかったときに行きたくても行けなかったような場所に出かけてみるとよいでしょう。
宿泊を伴う旅行にハードルを感じる場合は日帰り旅行を選んだり、旅行計画を立てるのが面倒な場合はツアーに参加したりと、さまざまな選択肢があるのも旅行の利点といえます。旅行先や観光スポット選びは、どちらか一方だけが楽しい場所を選ぶのではなく、夫婦二人が一緒に楽しめそうな場所を選ぶことも大切です。
一緒にいる時間がかなり長くなるため、お互いの存在が鬱陶しいと感じていたり、普段一切話していなかったりする夫婦は、もう少し仲良くなってから共通の趣味とする方がいいかもしれません。
スポーツ・運動
スポーツや運動は、熟年夫婦の健康づくりにも役立つ趣味です。これからも夫婦ともども健康に過ごすことを共通の目的とすれば、一緒に切磋琢磨してスポーツや運動に励めます。夫婦二人が無理なく楽しんで行えるスポーツや運動を選び、長く続けることを意識しましょう。
体力があまりなく、スポーツや運動に抵抗がある熟年夫婦の場合は、ラジオ体操や近所の散歩を一緒に行うことから始めてみてはいかがでしょうか。
アウトドア
釣りやキャンプ、ハイキング、天体観測などといったアウトドアは自然が好きな熟年夫婦におすすめの趣味です。日常から少し離れて自然の景色に癒され、リフレッシュする機会にもなります。
アウトドアでは特別な道具がいるものも多いですが、最初はレンタルをするなどして気軽に始めてみましょう。夫婦のどちらかがすでに行っているアウトドアを一緒に楽しむだけでなく、二人とも初めてのアウトドアに挑戦してみるのも、団結力が生まれ夫婦仲が深まります。
熟年夫婦になっても仲良しでいられるコツ

最後に、熟年夫婦になっても仲良しでいられるコツを紹介します。どれも、熟年夫婦だからこそ行うのが難しい行為かもしれませんが、人生の最後の瞬間まで幸せな結婚生活を送りたい方、夫婦仲を改善したい方はぜひ参考にしてください。
何かあったらすぐ話し合う
熟年夫婦になっても仲良しでいるコツのひとつは、何かあったらすぐに話し合うことです。報告・連絡・相談を密に行うことで会話が増え、夫婦に連帯感が生まれます。「仕事の状況に変化が起こりそう」や「新しい習い事を始めたい」など、些細なことでも話し合ってみましょう。
夫婦のどちらかが相手に不満を抱いた際にも、我慢して胸の内に抑えずその都度話し合うことで、解決の糸口が見つかることも多々あります。喋ってみればお互いのことを勘違いしていただけで不満がすぐに解消する可能性もあるため、前向きな気持ちで話し合うことが大切です。
「ありがとう」と「ごめんね」をしっかりと伝える
熟年夫婦が仲良く暮らすためには、「ありがとう」と「ごめんね」はしっかり言葉と態度の両方で伝えなくてはいけません。
夫婦の日常はどちらかが家事をしたり仕事をしたりと、お互いの助け合いで成り立っています。また、毎日を共に過ごす限り、どちらか一方に負担をかけることがあったり不満を募らせてしまったりすることも当然あるでしょう。その際にしっかりと感謝や謝罪の言葉を伝えるのが夫婦仲を保つコツです。
熟年夫婦だからこそ言葉と態度に出さなくても相手に伝わっているはず、と考えてしまう方もいるかもしれませんが、実際には伝わっていないことが多くあります。仮に伝わっていたとしても、改めて言葉と態度の両方で気持ちを伝えることで相手も気持ちが救われるため、ぜひ実践してみてください。
お互いに居心地のよい距離感を保つ
お互いに居心地のよい距離感を保つのも、仲のよい夫婦関係を目指すコツのひとつです。夫婦だからといっていつも近い距離で一緒にいるとしんどさを感じることはもちろんあるため、干渉し過ぎず適度な距離を保ちましょう。
これまで日常の過ごし方や一緒に楽しめる趣味などを上述してきましたが、必ずしも常に一緒に行動するべきというわけではありません。あくまでお互いに居心地のよい距離感を保ちながら、一緒に楽しめるものを実践してください。
誕生日や記念日などのお祝いをする
夫婦仲を保つために、お互いの誕生日や結婚記念などといった記念日のお祝いをするのもおすすめです。必ずしも高額なプレゼントや旅行などといった盛大なお祝いをする必要はなく、花やケーキを買って一緒に楽しんだり、近所の飲食店に出かけるなど些細なお祝いでも喜んでもらえるでしょう。
夫婦どちらかのリクエストがあれば、節目の誕生日や記念日には少し豪華なお祝いをしても楽しめるかもしれません。
熟年夫婦だからこそ過ごし方を工夫して仲良く暮らしましょう

この記事のまとめ
- 熟年夫婦が不仲になりやすい原因には価値観の不一致などが挙げられる
- 卒婚とは婚姻関係を維持しつつ互いの干渉を減らし自由に過ごすこと
- 卒婚は婚姻関係を維持するが離婚は婚姻関係を解消する点に違いがある
- 熟年夫婦は会話を増やす、家事を協力するなど日常の過ごし方に工夫が必要
- 熟年夫婦が一緒に楽しめる趣味には料理や旅行、アウトドアなどがある
- 仲良しな熟年夫婦になるためには感謝や謝罪を伝えるなどのコツがある
熟年夫婦だからこそ、意識的に互いを想い合って過ごさないと仲のよさを保つのは難しいものです。これまで過ごしてきた大切なパートナーと人生の最後まで楽しく過ごすためにも、本記事で紹介した日常の過ごし方を意識したり、共通の趣味に挑戦して、できるだけ良好な関係を築けるよう努めてみましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。