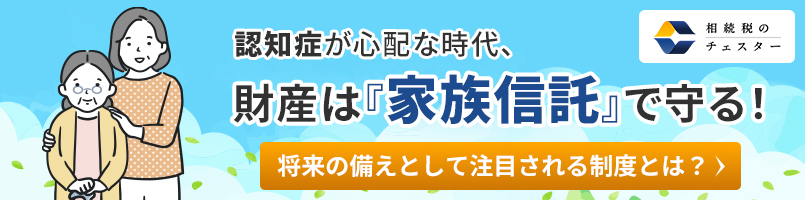親の介護費用はどのくらい?誰が負担するかや利用できる保険・制度も紹介

親の介護費用は、多くの家族が直面する重要な課題です。介護には愛情や時間に加えて、相当な費用も必要です。本記事では、親の介護にかかる費用について詳しく解説します。子供や親族が知っておくべき内容も紹介するため、ぜひ参考にしてください。
親の介護についての考え方

高齢の親の介護には一定の費用が必要になります。一般的には親自身が費用を負担しますが、足りない場合は子供が負担することもあるでしょう。まずは、親の介護費用の考え方を詳しく解説します。
親の介護費用は親が支払うのが一般的
親の介護費用は、親自身の資産や収入から支払うのが一般的です。これは、親が自身の生活費や療養費を負担する責任があるという考え方に基づいています。親の年金や貯蓄、資産などの収入を介護費用に充てます。
親の介護費用が足りない場合は子供が負担することもある
親の資産や収入だけでは介護費用をまかなえない場合、子供が費用を負担することがあります。
重要な点として、子供は親の介護を拒否することはできません。民法では、親族間で助け合う義務が定められており、特に親子間では扶養義務があるとされています。ただし、この義務は経済的な負担だけでなく、精神的なサポートも含まれます。
親の介護にかかる費用の平均

親の介護にかかる費用については、生活する場所や利用するサービスの種類、要介護度によって変わってきます。ここから、親の介護にかかる費用について詳しく解説します。
親の介護費用の月額平均
親の介護費用は、介護の必要度や利用するサービスによって大きく異なります。公益財団法人生命保険文化センターが実施した「2021年度 生命保険に関する全国実態調査」によると、介護にかかる費用は月額平均8.3万円という結果が出ています。施設で介護を受ける場合は、月額平均12.2万円です。
月額費用には、介護サービス利用料や食費、日用品費、医療費などが含まれます。金額は目安であり、生活費や介護保険の利用条件によっても変わります。
要介護度別の介護費用の違い
介護費用は、介護保険の要介護度によっても大きく異なります。要介護度が高くなるほど必要なサービスが増え、費用も高くなる傾向があります。要介護度別の介護費用は以下の通りです。

要介護度別の介護費用
- 要支援1:4.1万円
- 要支援2:7.2万円
- 要介護1:5.3万円
- 要介護2:6.6万円
- 要介護3:9.2万円
- 要介護4:9.7万円
- 要介護5:10.6万円
これらは平均的な金額のため、実際の費用は個々の状況や利用するサービスによって変動します。
在宅と施設での介護費用の違い
在宅介護と施設介護では、かかる費用に以下のような大きな差があります。
在宅と施設の費用の違い
- 在宅:4.8万円
- 施設:12.2万円
費用の内訳は以下のとおりです。
在宅介護の場合
- 介護サービス利用料
- 食費(自宅での食事)
- 日用品費
- 医療費
- 住宅改修費(必要な場合)
施設介護の場合
- 介護サービス利用料
- 居住費(家賃)
- 管理費
- 食費(施設での食事)
- 日用品費
- 医療費
在宅介護では、家賃や管理費は既存の費用として介護費用に含まれません。ただし、介護のための家のリフォーム費用は一時的な追加支出となります。対照的に、施設入居の場合は居住費が別途必要であり、自宅が空き家となる場合には維持管理費も含めた二重の居住費用が発生する場合があります。
一般的に、施設介護の方が在宅介護よりも高額になる傾向です。しかし、24時間のケアが必要な場合は、在宅介護の方が高額になる場合もあるでしょう。
親の介護費用を誰が負担するか決める流れ

親の介護費用を誰が負担するかを決めるのは、家族全体にとって非常に重要です。ここからは、親の介護費用を誰が負担するのか決める際の、具体的な流れについて詳しく説明します。
①親の資産を把握する
まずは親の資産を把握しましょう。親の資産状況の正確な把握は不可欠であり、介護費用を計画的に管理するための第一歩です。親の資産には、以下のものが挙げられます。
親の資産の例
- 預貯金
- 不動産
- 年金収入
- 保険契約
- 株式・債券等
- 負債
資産をすべてリストアップして詳細に確認すると、どの程度の介護費用をまかなえるのかを見極められます。
特に不動産や投資などの流動性の低い資産は、売却や担保に入れることが可能か検討しましょう。親がどの資産をどのように運用しているかについても家族や親族と共有しておくと、将来的なトラブルを避けられます。
②介護方針を決める
親の希望や健康状態、日常生活の環境を考慮しながら介護の方針を決定しましょう。在宅介護と施設介護のどちらにするかを判断する必要があります。親が自宅での生活を希望する場合、どのようなサポートが必要かを具体的に検討し、在宅介護が可能かどうかを判断します。
24時間のケアや専門的な医療が必要な場合、施設介護の選択肢も考慮しなければなりません。介護にかかる費用についても家族や親族で話し合い、親の希望を尊重しつつ現実的なプランを立てることが重要です。
③主な介護者を決める
家族の中で誰が主に介護を担当するのか決めると、介護がスムーズに進行しやすくなります。介護者を決定する際には、家族や親族の仕事や生活環境、住居の距離などを考慮する必要があります。介護者の負担が過度にならないように、サポート体制の構築が大切です。
介護者の休息やリフレッシュを支援するために、ほかの家族や親族が交代でサポートしたり、介護サービスの利用を検討したりする場合が考えられます。介護者を支える体制を整えると、介護が長期にわたって続く場合でも介護者の負担が軽減され、親に対して質の高いケアを提供できるようになります。
④費用が不足する場合は分担を決める
親の資産だけでは介護費用をまかなえない場合、子供たちや親族で費用を分担する必要があります。分担方法を決める際には、各家庭の経済状況や生計、介護への関わり方の考慮が必要です。公平な分担方法を話し合いで決める際には、家族間で丁寧にコミュニケーションを図りましょう。
収入に応じて負担金額を決めたり、介護にかかる時間や労力を分担したりすることも考えられます。親の資産や収入の一部を活用しつつ、家族や親族が無理のない範囲で協力することが大切です。費用分担についての話し合いは、将来的な家族内のトラブルを避けるためにも、しっかりと時間をかけておこなうとよいでしょう。
⑤資産を管理する人を決める
親の資産を適切に管理し介護費用を負担する人を決めることは、介護をスムーズにおこなうための重要なステップです。管理を担う人は、親の資産の運用や管理に透明性を持つ必要があります。家族間の信頼関係を維持するためにも、定期的に資産の状況や介護費用の支出について家族に報告する仕組みを作るとよいでしょう。
資産管理者がひとりに集中すると負担が大きくなるため、可能であれば複数の家族での役割分担もひとつの方法です。日常的な収支管理はひとりが担当し、大きな資産を動かす際は家族全員で協議するなどの方法があります。
⑥入院や入所の際の保証人を決める
親が入院や施設入所をする際の保証人を決める必要があります。保証人を選ぶ際には、単に金銭的な責任だけでなく、緊急時の対応や医療的な判断をおこなう役割も含まれます。そのため、家族全員で慎重に話し合い、最も適任と思われる人の選出が大切です。
保証人となる人が責任を果たせるよう、事前に必要な手続きや対応方法について確認しましょう。親の健康状態や施設の選択によっては、複数の保証人の設定も考慮する必要があります。
親の介護費用を軽減するための保険や制度

親の介護費用を軽減するために利用できる、さまざまな保険や制度があります。適切に活用すると、経済的負担を軽減できる可能性があります。
介護保険
介護保険は40歳以上の全員が加入する公的制度で、65歳以上の高齢者や40歳以上65歳未満の特定疾病のある人が対象です。利用時は1~3割の自己負担でサービスを受けられ、家庭の経済的負担を軽減します。
利用には市区町村への介護認定申請が必要で、認定結果に基づきサービスの範囲が決まります。訪問介護やデイサービスなど多様なサービスがあるため、親のニーズにあわせて選択が可能です。
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の年間自己負担額が一定の限度を超えた場合、超過分が払い戻される仕組みです。同一生計の世帯内で合算する必要があります。医療と介護の費用が同時にかかる場合に特に有効で、家計の負担軽減に役立つでしょう。
利用には加入している健康保険組合や居住している市区町村の介護保険担当窓口での申請が必要で、払い戻し額は所得により異なります。自動的に返還されるわけではないため、申請を忘れずにおこないましょう。制度を活用すると、より安心して介護を継続できます。
高額介護サービス費
高額介護サービス費は、月々の介護サービス利用料の自己負担額が一定の上限を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。頻繁なサービス利用や長期介護に効果的で、所得に応じて自己負担上限額が設定されています。同一生計内に複数の利用者がいる場合は合算されます。
条件に当てはまる場合は居住している市区町村から通知が届くため、市区町村窓口で手続きをしましょう。制度を活用すると長期的な介護費用負担が軽減し、親の生活の質を維持しながら介護を継続できます。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費は、介護保険施設利用時に食費と居住費の負担を軽減する制度です。所得に応じて自己負担額の上限が設定されているため、経済的に厳しい家庭でも適切な施設でのケアを受けられます。
利用には一定の条件を満たし、利用者が居住する市区町村への申請が必要です。この制度により、家計の負担を軽減しながら安心して施設生活を過ごせるでしょう。
社会福祉法人による利用者負担軽減
社会福祉法人による利用者負担軽減制度は、社会福祉法人が運営する介護サービスを利用する低所得者に対して、利用者負担を軽減するための制度です。制度の利用により、経済的に困窮している家庭でも必要な介護サービスを受けやすくなります。
利用者負担軽減制度を利用するには、利用者が居住する市区町村に対して申請をおこない、所得に関する書類を提出する必要があります。社会福祉法人による利用者負担軽減制度を活用すると、低所得の家庭でも親が必要とする介護サービスを受けられるようになり、家庭全体の経済的な負担を軽減できます。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者世帯向けに介護サービス費用等を低利または無利子で貸し付ける制度です。都道府県の社会福祉協議会が運営し、生活費など生活維持に必要な資金も対象となります。
利用には居住している市区町村の社会福祉協議会での相談と申請が必要で、所得や資産審査があります。使用用途の制限もあるため、事前確認が重要です。この制度により経済的に厳しい家庭でも必要な介護資金を確保できるため、親の生活環境を整えられます。
親の介護費用の負担を少なくするためには保険や制度を利用しましょう

この記事のまとめ
- 親の介護費用は親が支払うのが一般的である
- 親の介護費用が足りない場合は子供が支払う場合もある
- 親の介護費用の月額平均は8.3万円
- 親の介護費用を誰が負担するのかは家族で話し合う
- 親の介護費用を軽減するために、保険や制度を利用する
親の介護費用は決して少なくありません。本記事で紹介したさまざまな保険や制度を適切に利用すると、経済的な負担を軽減できる可能性があります。早い段階から親の介護について家族で話し合い、計画を立てることが重要です。経済的な面だけでなく、介護者の精神的・身体的負担にも配慮しながら、家族全体で支え合う体制を作りましょう。
介護職員として介護老人保健施設に勤務。
ケアマネジャー取得後は、在宅で生活する高齢者や家族をサポートする。
現在はWebライターとして、介護分野に関する記事を中心に執筆している。