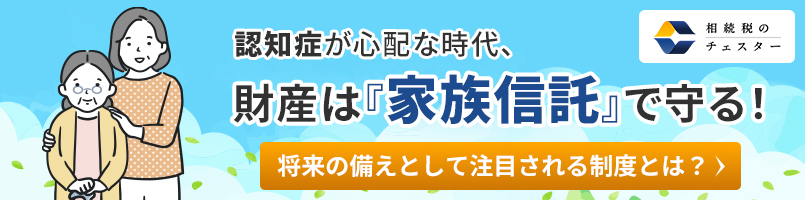老人ホームの費用が払えないときの選択肢は?予防策や費用が安い施設を見つけるコツも

老人ホームの入居中に費用が払えない状況になった場合、どのような対処法があるか知っていますか?老人ホームの費用は在宅介護と比べると費用がかかるため、支払いが困難になる場合もあるでしょう。本記事では、老人ホームの費用が払えないときの対策や安い施設選びのポイントを解説します。払えなくなる前の予防策も紹介しますので、参考にしてみてください。
老人ホームの費用が払えない主な原因

老人ホームの費用は、社会情勢等によっても変動します。入居当初は問題なくても後々払えない状況になることもあるでしょう。まずは、老人ホームの費用が払えない原因について解説します。
利用料の値上がり
老人ホームの費用は、全国的に上昇傾向です。日本全体で物価やエネルギー価格等が上昇しているのが原因で、入居当初は予算内でも値上がりによって払えない状態になる可能性があります。
近年、どの施設も値上がりが続いているため入居者の負担となっており、実際に払えないと感じ始める人も増えています。(2023年12月現在)
要介護度の悪化
老人ホームの種類によっては、介護サービスの費用が別途かかることもあります。公的な介護保険サービスの多くは、要介護度によって単価が決まっています。介護度が悪化すれば必然的に利用回数も増え、重度化するほど介護費用は増加するため、老人ホームの費用が払えないという状況につながります。
医療費の増大
令和3年度現在、日本の総人口に占める高齢者人口(65歳以上)の割合は28.9%です。一方、年齢階級別国民医療費の割合では、高齢者の費用が全体の60.6%を占めています。
加齢と比例して医療費がかかるため、老人ホームの費用を払えない状態になる可能性があります。
令和4年版 高齢社会白書
引用元 | 令和4年版 高齢社会白書 (内閣府)
令和3年度 国民医療費の概況
引用元 | 令和3年度 国民医療費の概況 (厚生労働省)
収入の減少
老人ホーム入居者の中には、自宅を貸したり不動産に投資をしたりして費用の足しにしている人もいるでしょう。このような不労所得が予定外に減少するようなことがあれば、老人ホームの費用を払えない状態につながるでしょう。
資金援助の減少
老人ホームの費用を家族などが支援している場合も、払えない状態になる可能性があります。例えば、資金援助をしてくれている家族が入院した場合、入院費用がかかって老人ホームの費用を援助することが困難になる場合もあるでしょう。
老人ホームの費用が払えないときの選択肢

ここからは、老人ホームの費用が払えないときの選択肢を紹介します。
老人ホームの費用が払えないときの選択肢
- 施設に支払い方法を相談する
- 費用が安い施設に転居する
- 生活保護を申請する
- 在宅介護に切り替える
施設に支払い方法を相談する
費用や手間が最も少ない方法が、入居先の老人ホームと費用の支払い方法について相談することです。現状のままでは払えないことを理由とともに伝え、支払い方法について施設に相談しましょう。
金銭援助が可能な近親者などと一緒に相談に行ったり、次の年金支給日や資産を現金化するまで待ってもらう等の具体策をもって相談に臨むと、解決に向けて前向きな相談ができるでしょう。なるべく早めに相談することがポイントです。
費用が安い施設に転居する
老人ホームの費用が払えない場合、現在入居している場所より安い施設に転居することも一つの方法です。老人ホームの種類によっては、今より安くなる場合があります。
一般的に、民間施設よりも、介護保険サービスで利用が可能な公的施設である介護保険施設の方が費用を抑えられます。老人ホームの担当者やケアマネジャーと一緒に、転居先を考えるのがおすすめです。
生活保護を申請する
本人の収入が少なく財産もない場合、生活保護の対象になる場合があります。生活保護を受けると医療費や介護サービス利用料の自己負担がなくなり(現物給付)、住宅扶助によって家賃の補助も受けられます。
ただし、生活保護は財産がある場合や他に利用できる公的支援がある場合は受給できないことも多いため、注意しましょう。
在宅介護に切り替える
老人ホームの費用が払えない場合、在宅介護への切り替えも検討しましょう。在宅介護は支援体制の面で多少不便ですが、毎月かかる金額の面では在宅介護の方が安くすむ場合が多いです。
公益財団法人生命保険文化センターが実施した調査では、介護施設の月額費用は平均12.2万円だったのに対し、在宅介護は4.8万円という結果でした。日常生活の支援方法を別途検討する必要があるものの、在宅介護も十分な選択肢となるでしょう。
令和3年度 生命保険に関する全国実態調査
老人ホームの費用不足に活用できる予防策

老人ホームの費用が払えない状態になる前の予防策として、公的な制度を活用して支出を減らすことも重要です。ここでは、老人ホーム入所者が利用できる各種減免制度を紹介します。
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定証)
特定入所者介護サービス費は食費と居住費の一部が割引になる制度で、所得に応じて段階的に費用の上限が設定される仕組みです。利用には、自治体窓口への事前申請が必要です。
認定要件
- 本人が介護認定を受けている
- 本人を含む同一世帯全員が住民税非課税
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税
- 預貯金等の合計金額が段階ごとに設定された所得要件・資産要件以下(下表参照)
| 負担限度額及び段階ごとの要件 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
負担段階 |
所得要件 |
資産要件 |
利用者が払う居住費の限度額 |
食費の利用者負担限度 |
|
第1段階
|
下記のいずれかに該当する場合 ・老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
単身:1,000万以下 夫婦:2,000万以下 |
0~820円/日 |
300円/日 |
|
第2段階 |
本人の公的年金+年間所得の合計が80万円以下 |
単身:650万以下 夫婦:1,650万以下 |
370~820円/日 |
390円/日 |
|
第3段階① |
本人の公的年金+年間所得の合計が80~120万円以下 |
単身:550万以下 夫婦:1,550万以下 |
370~1,310円/日 |
650円/日 |
|
第3段階② |
本人の公的年金+年間所得の合計が120万円超 |
単身:500万以下 夫婦:1,500万以下 |
370~1,310円/日 |
1,360円/日 |
※令和3年8月1日現在
※居住費の限度額は、施設や部屋タイプにより異なる
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
こちらの制度は、老人ホームの費用を払えない低所得者が対象です。社会福祉法人などの介護保険サービスを使った場合に、費用の一部を軽減する制度となります。具体的には、下記の要件を満たした上で生計が困難であると自治体から認められる必要があります。
軽減の対象者
- 住民税非課税
- 年間収入が単身世帯で150万円以下、世帯員ひとり増えるごとに50万円を加えた合計額以下であること
- 預貯金等の金額が単身世帯で350万以下、世帯員がひとり増えるごとに100万円を加えた合計額以下であること
- 日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと
- 親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
また、制度の利用には事前申請が必要です。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、介護保険サービスの自己負担額が一定以上になった場合、差額が後日給付される制度です。上限額は対象者の所得額や課税状況により異なります。利用にあたって事前の手続きは不要で、制度の対象になった場合は自動的に居住する市区町村から手続きの案内が届きます。
| 高額介護サービス費の所得区分及び負担上限額 | |||
|---|---|---|---|
|
所得区分 |
負担上限額(月額) |
||
|
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上) |
世帯:14万100円 |
||
|
課税所得380(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 |
世帯:9万3,000円 |
||
|
課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
世帯:4万4,400円 |
||
|
世帯の全員が市町村民税非課税 |
世帯:2万4,600円 |
||
|
市町村民税非課税かつ公的年金収入+その他の合計所得が80万円以下 |
個人:1万5,000円 世帯:2万4,600円 |
||
|
生活保護受給者 |
世帯:1万5,000円 |
||
※令和3年8月現在
高額療養費制度(限度額適用認定証)
高額療養費制度(限度額適用認定証)は、1ヶ月間の医療費の合計が自己負担限度額を超えた場合に、自己負担額限度額と実際にかかった費用の差額が給付される制度です。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。条件が揃えば、世帯全員の自己負担額を合算できる場合もあります。
また、事前に交付を受けた「限度額適用認定証」や「高齢受給者証」を提示することで、窓口負担を限度額までに限定することもできます。これにより医療費の支出を最小限にし、老人ホームの費用が払えないときに現金を回すことが可能となります。
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、介護保険と医療保険の自己負担額の合計が所定の自己負担限度額を超えた場合に、差額が支給される仕組みです。自己負担限度額は所得に応じて異なります。なお、この制度は介護保険と医療保険の両方に自己負担が発生している方が対象です。
該当する方に対しては、自治体から手続きに必要な案内が届きます。指示に従って所定の書類を提出しましょう。詳細は各自治体の介護保険担当窓口か、加入する公的健康保険の窓口にお問い合わせください。
自治体が実施する減免制度
先述した制度以外にも、自治体ごとに独自の減免制度を実施している場合があります。例えば、常時失禁状態の方を対象にしたオムツ支給制度や、「特定入居者介護サービス費」の対象外施設であるグループホーム(認知症対応型共同生活介護)に入所している方の食事代・居住費を減免する制度などがあります。
自治体独自の減免制度は、高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センターや市区町村の高齢者福祉担当窓口で確認できます。老人ホームの費用を払えない場合は、利用できる制度がないか確認しましょう。
費用の安い老人ホームを見つけるコツ

ここからは、費用の安い老人ホームを見つけるコツを紹介します。
ケアマネジャーに相談する
ケアマネジャーは介護保険制度の専門家で、地域に所在する老人ホームの種類や費用、各種減免制度適用の可否などの情報を持っています。ケアマネジャーに1ヶ月あたりの予算を伝えておくと、条件に見合った施設を紹介してくれるでしょう。
公的な施設から選ぶ
特別養護老人ホームをはじめとした公的な介護保険施設(全3種類)は、一般的に安く入居できます。これは、入居一時金が不要で所得に応じて費用が減免されるためです。また、自立度が高くそこまで手厚い介護は必要ないという方は、月額4万円程度から入れる軽費老人ホームもおすすめです。
入居の際にかかる一時金が不要な施設から選ぶ
老人ホームの費用には主に月額費用と入居一時金があり、一時金は一般的に数十~数百万円と高額です。昨今は、民間の施設でも一時金が不要な施設が増えてきています。老人ホームを探すときは月額費用だけでなく、一時金の有無もチェックしてみましょう。
費用相場が安い地域を探してみる
老人ホームの費用は、地域ごとに相場が異なります。現在入居している老人ホームの費用が払えないときは、近隣地域の施設も検討してみましょう。どのように探したらよいか分からない場合、所定の地域の相場観を確認できる比較検討サイトの活用もおすすめです。
老人ホームの費用が払えないときは、サービス制度の活用や転居を考えてみましょう

この記事のまとめ
- 老人ホームの費用が払えなくなる原因は、施設利用料や医療費の増大、収入の減少、資金援助の滞りなど
- 老人ホームの費用が払えないときは、支払い相談や別の老人ホームへの転居、生活保護の申請、在宅介護への切り替えを検討するとよい
- それ以外にも減免制度や軽減制度を活用するのがおすすめ
- 費用の安い老人ホームを見つけるコツは、①ケアマネジャーに相談する②公的な施設から選ぶ③入居の際にかかる一時金が不要な施設から選ぶ④費用が安い地域を探してみる
老人ホームの費用を払えない場合、活用できる減免制度がないか見直したり施設担当者に相談したりするのがおすすめです。各種減免制度は事前に申請できるものもあるため、自身が対象になるかどうかは施設入居前に確認しておくとよいでしょう。
それでも払えないときは、現在入居している老人ホームよりも費用がかからない施設へ転居するのも一つの選択肢です。本記事で紹介した内容を参考に、老人ホームの費用が払えなくなる前に対策を行いましょう。
東北公益文科大学卒業。その後、介護保険や障害者総合支援法に関する様々な在宅サービスや資格講座の講師を担当した。現在は社会福祉法人が運営する特別養護老人ホームの生活相談員として、入居に関する相談に対応している。在宅・施設双方の業務に加えて実際に家族を介護した経験もある。高齢者介護分野のみならず、障がい者支援に関する制度にも明るい。