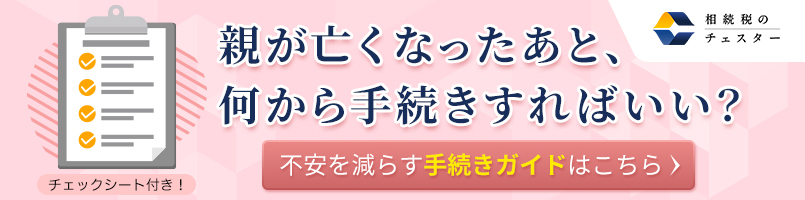喪中に年賀状が届いたら?具体的な対処法や未然に防ぐための方法を解説

喪中の期間中は、年賀状での新年の挨拶を控えるのが一般的です。しかし、喪中に年賀状が届いた場合はどのように対応すればよいのでしょうか。本記事では、喪中に届いた年賀状に対する具体的な対処法や、喪中に年賀状が届かないようにする方法などを紹介します。
喪中に年賀状が届いたときの対処法

喪中に年賀状が届いた場合の対応方法をご存知でしょうか。喪中に年賀状が届く場合としては「喪中を知らせた人から届いた」ケースと「喪中を知らせていない人から届いた」ケースの二つがあります。どちらの状況なのかによって対応が変わるため、正しい対処法を把握しておきましょう。
挨拶状や寒中見舞いを出す
喪中の期間に年始の挨拶として年賀状が届いた場合は、挨拶状や寒中見舞いを出します。挨拶状や寒中見舞いでは、喪中であることを伝えて故人を明らかにします。年賀状に対するお礼もきちんと述べましょう。日付には元旦ではなく、ポストへ投函した日にちを書くことが一般的です。
故人に対する年賀状が届いた場合も同様に、挨拶状もしくは寒中見舞いを出します。故人が亡くなっていることを伝え、生前の付き合いに対する感謝を述べてください。
喪中に年賀状が届いたときに出す寒中見舞いの書き方

喪中の期間中に年賀状が届いた場合は、寒中見舞いで対応します。ここからは、寒中見舞いの書き方について詳しく解説します。寒中見舞いに何を書くべきか迷っている、どういった形式で書いたらよいか分からないという方は、こちらを参考にしてください。
①季節の挨拶
喪中の期間中に出す寒中見舞いに書くべき内容として、最初に季節の挨拶を書きます。寒中見舞いの場合、時候の挨拶ではなく「寒中お見舞い申し上げます」「寒中お伺い申し上げます」といった挨拶が使われます。「謹賀新年」や「あけましておめでとう」といったお正月をお祝いする年始の挨拶は使えません。
②相手への気遣いの言葉
季節の挨拶の後に、相手を気遣う文言を入れます。「厳しい寒さが続きますが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか」といった文言がよく使用されます。寒中見舞いを送るのが遅くなった場合は「ご通知が遅れましたこと深くお詫び申し上げます」などのお詫びも添えるとよいでしょう。
③喪中であることの報告
次に、身内がなくなり喪中であることを記載します。
④結びの挨拶
最後に、結びの挨拶を記載します。「今後も変わらぬお付き合いのほどよろしくお願いいたします」「まだまだ厳しい寒さが続きますので、皆様におかれましてもご自愛ください」といった言葉を入れましょう。はがきにて寒中見舞いを出す場合は、結びの挨拶の後にポストに投函した日付を記載します。メールで寒中見舞いを出す場合、日付を記載する必要はありません。
喪中に寒中見舞いを書く際の注意点

喪中に届いた年賀状の返信に寒中見舞いを送る際、いくつか注意するべきポイントがあります。ここからは、喪中に寒中見舞いを書く際の注意点について解説していきます。
賀詞は使わない
喪中に寒中見舞いを書く際の注意点として、賀詞を使わないことが挙げられます。賀詞とは「寿」「謹賀」「あけましておめでとうございます」「賀正」「迎春」といったお祝いの言葉で、祝賀ともいわれます。喪中は亡くなった人を思いながら身を慎むべき時期とされているため、お祝い事は控えるべきと考えられています。新年を祝うおめでたい言葉は使用せず、「寒中見舞い申し上げます」といった挨拶のみにとどめましょう。
控えめなデザインにする
喪中の年賀状への返信として寒中見舞いを書く場合、デザインは控えめにしましょう。派手な色柄やキャラクターなどが印刷された華美なものは、喪中に送る寒中見舞いとしてはふさわしくありません。干支や日の出といったお正月のモチーフが使われているものも避けた方がよいです。
新春の季節に合わせた植物や風景が印刷された、色柄が控えめなシンプルな通常はがき、もしくは私製はがきを使用しましょう。
弔事用切手は使わない
喪中に寒中見舞いを出す場合は、弔事用の切手を使う必要はありません。寒中見舞いはあくまで季節の挨拶状であり、弔事をお知らせするものではありません。弔事用の切手ではなく、普通切手を使って寒中見舞いを送りましょう。また、弔事用切手だけでなく慶事用の切手を使うのも避けてください。
故人の死因や経緯には触れない
喪中に出す寒中見舞いであっても、故人の死因や経緯に触れる必要はありません。寒中見舞いには、季節に合わせた挨拶状という役割があります。故人が亡くなった理由や経緯などを記載する必要はなく、一般的な寒中見舞いで記載する内容を書くのが一般的です。
寒中見舞いを出す期間に注意する
喪中に寒中見舞いを出す場合、期間に注意が必要です。寒中見舞いは、1月7日の松の内が明けた日から立春までの間に出せる挨拶状です。喪中の年賀状への返事として寒中見舞いを出す場合は、1月8日から2月3日までに相手に届くように手配しましょう。もし寒中見舞いが届くのが立春より後になってしまう場合は、寒中見舞いではなく「余寒見舞い」として返事を出します。
 寒中見舞いはがき|Yahoo!ショッピング
寒中見舞いはがき|Yahoo!ショッピング
喪中に届いた年賀状に対する寒中見舞いの文例

ここからは、喪中に届いた年賀状に対する寒中見舞いの文例を紹介します。寒中見舞いに書くべき内容は、状況によって異なります。自身の状況に合わせてこちらの文例を活用し、寒中見舞いを書きましょう。
すでに喪中を知らせた相手への寒中見舞いの場合
喪中を既に知らせた相手から年賀状が届いた場合は、改めて喪中である旨を伝えます。季節の挨拶や相手の体調を気遣う言葉も記載しましょう。
喪中を知らせた相手への寒中見舞いの文例
寒中お伺い申し上げます
向寒の折、皆様におかれましてはお変わりございませんか
昨年〇〇月に〇〇(享年〇歳)が他界し、服喪中のため年頭の挨拶を差し控えさせていただきました
ご挨拶が遅くなりましたことお詫び申し上げます
本年もご厚誼のほどよろしくお願いいたします
時節柄体調など崩されませんようご自愛ください
喪中の報告を兼ねた寒中見舞いの場合
喪中の報告を兼ねて寒中見舞いを送る際は、故人の命日や故人との続柄、享年などを記載します。通知が遅れたことへのお詫びや、年賀状をいただいたことへの感謝も伝えましょう。故人が生前お世話になったことに対するお礼も忘れずに述べます。
喪中の報告を兼ねた寒中見舞いの文例
寒中お見舞い申し上げます
この度はご丁寧な年頭のご挨拶をいただきましてありがとうございました
昨年〇月に〇〇が〇〇歳で他界いたしましたため、新年のご挨拶を控えさせていただきました
ご通知が遅れましたことを深くお詫びするとともに故人が生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます
皆様の一層のご多幸とご健康をお祈り申し上げます
喪中に年賀状が届かないようにするための対応

喪中に年賀状が届くことはよくあることです。しかし、送った相手が「喪に服している人へ年賀状を送ってしまった」と気にしてしまう場合があります。相手に年賀状を準備してもらう手間もかかってしまいます。
喪中に年賀状が届かないようにするためには、普段年賀状を交換している相手に訃報を伝える、喪中はがきを送るといった対応が必要です。喪中はがきとは、年始の挨拶を控える旨を伝えるための欠礼状です。
喪中はがきを送る時期
年賀状が届かないようにするためには、喪中はがきを送る時期に注意が必要です。喪中はがきは、年賀状を手配し始める前に相手に届くようにする必要があります。そのため、11月中旬から12月初旬までに届くように手配しましょう。
喪中はがきに書く内容
喪中はがきでは、喪中のために年始の挨拶を控える旨を伝えます。年賀欠礼の挨拶と故人が亡くなった日付、今後の変わらないお付き合いをお願いする言葉を述べましょう。
喪中に年賀状が届いたときは、状況に合わせて対応しましょう

この記事のまとめ
- 喪中に年賀状が来た場合は、挨拶状や寒中見舞いを出して対応する
- 喪中の年賀状に対する寒中見舞いには、季節の挨拶、相手への気遣いの言葉、近況報告、結びの挨拶を書く
- 喪中に寒中見舞いを書く際は、賀詞を使わない、控えめなデザインにする、弔事用切手は使わないといったことを注意する
- 寒中見舞いは1月8日から2月3日までに相手に届くようにを出す
- 喪中に年賀状が届かないようにするためには、事前に喪中はがきで喪中であることを知らせる
喪中に年賀状が届いた場合は、寒中見舞いを送って返事をするのが一般的です。本記事で紹介した注意点を踏まえて、喪中に届いた年賀状に対応しましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。