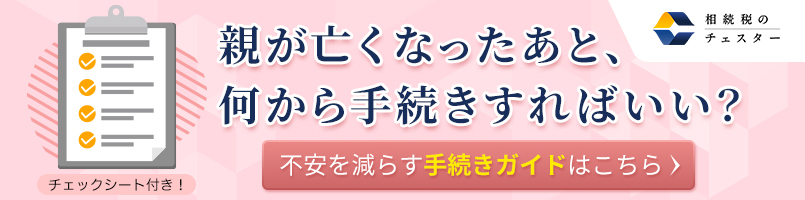御供物料の封筒の書き方は?相場や香典との違いも紹介

法要の際などに渡す「御供物料(おくもつりょう)」ですが、お金を入れる封筒の正しい書き方をご存知でしょうか。本記事では、御供物料の封筒の書き方・作法について紹介します。封筒に包む金額の相場も解説しているため、御供物料に関するマナーで迷ったらぜひ参考にしてみてください。
御供物料とは?

香典や御供物料、御線香代をはじめ、葬儀や法要などの際にご遺族へ渡すものにはさまざまなものがあります。中でも香典とともに弔事でよく使われる「御供物料」とはどのような意味なのでしょうか。具体的な封筒の書き方を紹介する前に、まずは御供物料の意味について解説します。
法要でお供え物の代わりに渡すお金のこと
御供物料とは、法要においてお供え物の代わりとしてご遺族へ渡すお金のことです。御供物料には、故人に対するお悔やみの気持ちを表したり、ご遺族への支援や哀悼の気持ちを示す意味があります。
本来は故人の魂を慰めるためのお供え物として、仏教における「五供(ごくう)」に基づき、果物などの食べ物や花などを渡すことが一般的でした。しかし、お供え物となる食べ物や花を選んだり、ご遺族の自宅まで持ち運んだりすることが参列者にとって負担になるという考え方があります。
また、お供え物として貰った食べ物の保管を考えるなど、ご遺族側にとっても負担になる可能性もあります。葬儀や法要における参列者・ご遺族の双方の負担を減らすために、近年では食べ物の代わりにお金を包んだ封筒を渡すことが主流になっています。
香典とは渡す場面が異なる
御供物料と同様に、弔事でご遺族へ渡すお金が入った封筒の一つに「香典」がありますが、二つの違いは渡す場面です。香典は葬儀や告別式などでご遺族へ渡しますが、御供物料は法要や法事の際に渡します。
また、御供物料はお菓子や果物などのお供え物の代わりであり、香典は故人の霊前にお供えする香(=線香)の代わりとして渡すことが一般的です。
なお地域によって、お供え物の食べ物を参列者同士で持ち寄り、法要後に全員で分け合う場合、お金が入った封筒は御供物料ではなく香典と呼ぶ場合があります。
御供物料の封筒の書き方

御供物料のお金は一般的に封筒に入れて渡すため、ご遺族や故人に失礼がないよう正しい書き方で表書きを記して用意することが大切です。ここからは、御供物料の封筒の正しい書き方について解説します。実際に御供物料の封筒を用意する際に困らないよう、事前に確認しておきましょう。
薄墨または濃墨を使う
御供物料の封筒の書き方では、薄墨または濃墨のどちらかを使って表書きなどを記載します。薄墨は忌中(故人が亡くなってから四十九日までの期間)における法要へ参列するときに渡す場合に使います。薄墨は涙で薄くなった墨を連想させることから、故人に対する悲しみの気持ちを表すとされています。
それに対して、忌中以外の法要で御供物料を渡す場合は濃墨を使うことが一般的です。忌明け以降は、故人を亡くした悲しみを乗り越える時期にあたると考えられているため、薄墨は使いません。
封筒の表面上部に表書きを書く
封筒の表面には、中に入っているものが何かをご遺族が分かるように表書きを記載します。表書きについては、四十九日より前の法要では「御霊前」、四十九日を過ぎてからの法要であれば「御仏前」を使用します。
しかし、浄土真宗では故人は死後すぐに極楽浄土で仏様になると考えられているため、四十九日より前の法要であっても「御仏前」と記載するのが一般的です。宗派によって表書きのルールに違いがあるため、表書きの書き方に迷った場合は「御供物料」や「御供物」という言葉を使うとよいでしょう。
表書きの下部には、御供物料の差出人名を記載します。差出人の書き方は名前を書くことが一般的ですが、家族で一つの御供物料を渡す場合は「○○家」と書きましょう。
封筒の中袋には包んだ金額と差出人の情報を書く
御供物料の封筒にお金を入れる中袋がある場合は、中袋に包んだ金額と差出人の情報を書きます。金額は中袋の表側中央に、差出人の情報は裏面の左側に記載するのが一般的な書き方です。中袋がない封筒の場合は封筒の表面のうち、水引の下に差出人の名前を書き、裏面の左側に差出人の住所と御供物料の金額を記載することが一般的です。
連名で渡す場合は目上の人から順番に名前を書く
友人や会社などといった複数人が連名で御供物料を渡す場合、差出人名の書き方は目上の人から順番に書くのが一般的です。連名で渡す人の中で一番目上の人の名前から順番に、封筒の右側から左側に向かって並べて書きましょう。
なお、大人数の名前を書くと見づらくなるため、封筒に記載する差出人名は三人までにしてください。四人以上の連名で送る場合は、封筒の中央に代表者一人の名前を書き、左側に「他一同」と書くことが一般的です。「他一同」とした場合は、誰が含まれているかがわかるように、全員の氏名を記載した紙を封筒の中に同封しましょう。
御供物料の封筒に包む金額の相場は?

故人やご遺族に対するお悔やみの気持ちとして渡す御供物料ですが、実際に渡す際の相場はどれくらいなのでしょうか。ここからは、御供物料の封筒に包む金額の相場について解説します。
故人との関係によって相場は変わる
御供物料の封筒に包む金額は「香典の半額〜七割程度」が望ましいとされており、相場は故人との関係によって変わります。一般的に故人との血縁関係が近いほど金額が高くなり、親戚の場合で5千円〜1万円が相場です。未成年や新社会人で収入が少ない場合には例外とされることが多いため、無理のない範囲で用意しましょう。
血縁関係がない人の場合は、3千円〜5千円が相場です。故人が会社の上司や友人などといった親しい関係の人の場合の相場は、5千円〜1万円と少し高くなる傾向があります。また、御供物料と一緒にお菓子などのお供え物を用意する場合は、お供え物にかける金額は少なめでも問題ないとされています。
重要な法要では多めに包むことが一般的
御供物料として封筒に包む金額は、法要によっても相場が変わります。特に四十九日までの法要は故人が亡くなって間もない時期にあたります。また一周忌などでは法事の規模が大きくなる傾向にあることから、ご遺族の負担を軽減するために多めに包むことが一般的です。
四十九日以降をはじめ、故人が亡くなってから時間が経ってから行う法要については、規模が小さくなる傾向にあることから、少なめの金額でも問題ないとされています。御供物料はあくまでお悔やみの気持ちとして渡すものであるため、状況に合わせて無理のない金額を用意しましょう。
お盆における御供物料の相場は3千円~5千円
お盆に行う法要において御供物料を渡す場合の相場は、3千円~5千円が相場です。故人が亡くなってから初めて迎えるお盆(=初盆)については、大規模に法要を行うことも多いため、少し金額を多めに用意しておくことが望ましいとされています。
お供え物と御供物料の両方を用意する場合は、両方を合算した金額が相場と同額程度になるように用意するとよいでしょう。
御供物料の封筒に関する正しい作法

御供物料を用意する際には、金額や封筒の書き方以外にも作法において注意すべき点があります。ここからは、御供物料の封筒に関する正しい作法・注意点を解説します。故人やご遺族に失礼がないよう、あらかじめ確認しておきましょう。
御供物料の封筒の種類は包む金額に合わせる
御供物料を用意する際に使う封筒は、包む金額に合ったデザインを選んでください。封筒には水引がプリントされているものや本物の水引が使われているもの、高級和紙で作られたものなどがあります。
一般的に包む金額が高いほど、正式かつ豪華なデザインの封筒を使います。包んだ金額と封筒のグレードに違いがあると、ご遺族に失礼にあたるため注意しましょう。以下の表を参考にしながら、自分が用意する金額に合った封筒を選んでください。
|
封筒のデザイン |
入れる金額の目安 |
|---|---|
|
水引が印刷されている封筒 |
3千円~5千円 |
|
本物の水引が付いている封筒 |
1万円~2万円 |
|
あわじ結びの水引が付いている封筒 |
3万円~5万円 |
御供物料の封筒には新札を入れない
御供物料の封筒に入れるお札には、できるだけ新札を使わないように注意してください。香典においては新札を使うことが「故人の不幸を予期していた」とみなされると考えられているため、御供物料も香典と同じように古いお札を入れておくと安心です。新札しか用意できない場合は、お札に折り目を付けておけば問題ありません。
御供物料を渡すタイミングは法事の前
持参した御供物料を渡すタイミングは、法事が始まる前に渡すのが一般的です。施主やご遺族へ挨拶をする際に渡して、仏壇にお供えしてもらいましょう。自分で仏壇にお供えするのは、ご遺族に対して失礼にあたるため注意してください。また、封筒に汚れが付かないように、持ち歩く際には袱紗に包んでおくことが大切です。
御供物料の封筒の正しい書き方を理解しましょう

この記事のまとめ
- 御供物料は、法要にてお供え物の代わりに渡すお金のこと
- 香典は葬儀や告別式、御供物料は法要や法事で渡す
- 御供物料として包む金額は5千円~1万円が相場
- 封筒の表書きは四十九日までであれば「御霊前」、以降は「御仏前」を使う
- 御供物料を渡すのは、法事が始まる前のタイミングが一般的
御供物料は法要で故人やご遺族に対するお悔やみの気持ちを表すためのものであるため、失礼がないように正しい書き方・渡し方を理解しておくことが大切です。本記事で紹介した封筒の書き方や注意点なども参考にしながら、御供物料の用意をしましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。