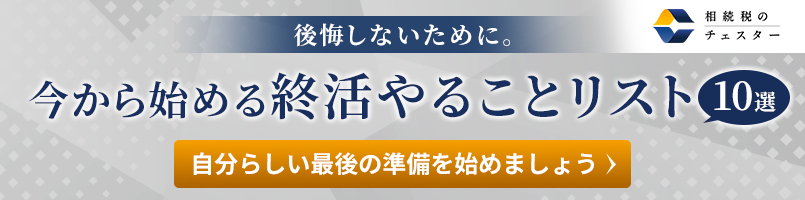公正証書遺言の証人に資格は必要?依頼費用や手続きの流れを解説

公正証書遺言を作るときには、証人が必要です。しかし証人として誰に依頼したらよいか分からない方も多いのではないでしょうか。本記事では、公正証書遺言の証人に資格が必要かどうかや依頼にかかる費用、手続きの流れについて説明します。
公正証書遺言の証人とは?

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。公正証書遺言作成時には、証人が必要になります。証人の役割やどのような人がなれるかを知っておきましょう。
公正証書遺言には2人以上の証人が必要
遺言書が残されている場合、遺言書に従って財産の相続が行われます。遺言書は誰に財産を譲るかを指定できるため、不正が行われる場合も考えられます。公正証書遺言の証人は、遺言書が確実に本人の意思で作成されていることを証明するために必要です。
民法では、公正証書遺言を作成するときに証人2人以上の立ち会いが必要であると定められています。遺言をする本人だけでなく、証人も一緒に公証役場に行って手続きを行うことになります。
公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、有効な遺言を残しやすいです。ただし、公正証書遺言も必ず有効とは限らず、有効性が裁判で争われることもあります。もし裁判になった場合、証人として立ち会った人は裁判で証言を求められる可能性もあります。
公正証書遺言の証人に必要な資格
公正証書遺言の証人になるために、特別な資格は必要ありません。ただし、証人になれない欠格事由が法律に定められています。以下のような欠格事由に該当する人は、公正証書遺言の証人になれません。
公正証書遺言の証人の欠格者
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者や4親等内の親族、書記及び使用人
未成年者は公正証書遺言の証人になれません。推定相続人(将来相続人になるであろう人)や受遺者(遺言で財産をもらう人)については、本人だけでなく配偶者や直系血族(親、子など)も証人になれないとされています。
また公証人の家族や関係者も証人にはなれません。詳しくは後述します。
公正証書遺言の証人を選ぶ際の注意点
公正証書遺言の証人を家族や親戚に頼みたいと考える人は多いでしょう。しかし、家族や親戚の多くは「推定相続人」か、「推定相続人の配偶者及び直系血族」となり、証人になることはできません。遺言書の証人は、利害関係のない第三者に依頼する必要があります。
遺言書には、財産について他人に知られたくない内容を書くことがほとんどです。遺言書の内容が漏れて、秘密を知られてしまうのは避けたいと考えるのが自然でしょう。
そのため、遺言書の証人には信頼できる人を選ぶことが大切です。適切な人がいない場合には、守秘義務のある専門家などに証人を依頼するとよいでしょう。
公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成したいが、どのように作るのかが分からないという人も多いのではないでしょうか。ここからは、公正証書遺言の作成手続きの流れや費用について説明します。
公正証書遺言の作成手続きの流れ
公正証書遺言を作成する場合、公証役場に依頼する必要があります。全国どこの公証役場に依頼してもかまいません。
病気等の事情で外出が困難な場合、公証人に出張してもらうことも可能です。ただしその場合には公証役場の管轄地域内での依頼となるため注意しましょう。
公正証書遺言を作成するまでの大まかな流れは、次のとおりです。
公正証書遺言を作成するまでの流れ
- 遺言書の内容を決める
- 必要書類を準備する
- 公証人と打ち合わせを行う
- 予約した日時に証人立ち会いのもと公証役場にて公正証書遺言を作成する
必要書類としては、本人確認書類や戸籍謄本のほか、財産に関する資料を提出します。不動産がある場合には登記事項証明書と固定資産税評価証明書、預貯金がある場合には通帳のコピーを用意します。また、遺言の内容によっては受遺者の住民票も必要になる場合があります。証人についても、住所、氏名、生年月日が分かる書類(運転免許証のコピー等)の準備が必要です。
公正証書遺言作成当日は、次のような流れで手続きが進みます。
公正証書遺言作成当日の流れ
- 遺言者の本人確認及び意思確認
- 遺言書の内容を遺言者と証人の前で読み聞かせて内容確認
- 遺言者及び証人が遺言書に署名捺印
- 公証人が遺言書に署名捺印
公正証書遺言作成にかかる費用
公正証書遺言を作成するときには、公証役場に支払う手数料が発生します。手数料は遺言書に記載する財産の価額によって下記の表のように変わります。
| 目的の価額 | 手数料 | ||
| 100万円以下 | 5,000円 | ||
| 100万円超200万円以下 | 7,000円 | ||
| 200万円超500万円以下 | 11,000円 | ||
| 500万円超1,000万円以下 | 17,000円 | ||
| 1,000万円超3,000万円以下 | 23,000円 | ||
| 3,000万円超5,000万円以下 | 29,000円 | ||
| 5,000万円超1億円以下 | 43,000円 | ||
| 1億円超3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算 | ||
| 3億円超10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円ごとに11,000円を加算 | ||
| 10億円超 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 | ||
公正証書遺言の手数料を計算するときには、財産を受け取る人ごとに上記の表にあてはめて算出した額を合計します。さらに、全体の財産が1億円未満の場合には11,000円を手数料に加算します。このほかに遺言書の枚数によって、謄本手数料が加算されることがあります。
公正証書遺言の作成手続きは、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼して進めてもらうことも可能です。この場合には、専門家に支払う報酬が追加で発生します。
公正証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言の証人になれない人は、法律で定められています。どのような人が当てはまるのか、具体的に見ていきましょう。
未成年者
未成年者は公正証書遺言の証人にはなれません。法律の改正により、2022年4月より成人年齢が18歳に引き下げられたため、現在は18歳未満が未成年者として証人対象外となります。
推定相続人・受遺者等
推定相続人・受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、証人になれないとされています。推定相続人とは、将来相続人になる予定の人のことを指します。
遺言者が亡くなったときに相続人になるのは、配偶者と血族の一部の人です。配偶者は常に相続人になりますが、血族については次のような優先順位が法律で定められています。
血族相続人の法律上の優先順位
- 子(※亡くなっていれば孫など)
- 直系尊属(※最も世代の近い人)
- 兄弟姉妹(※亡くなっていれば甥・姪)
たとえば、子供がいれば子供が推定相続人であるため、公正証書遺言の証人になれません。子供の直系血族である親や孫も証人にはなれないことになります。遺言者に子供がいれば兄弟姉妹は推定相続人にならないため、兄弟姉妹は証人になれる可能性があります。
なお、受遺者とは遺言書によって財産を受け取る人を意味します。遺言書の公正さを保つために、受遺者も証人にはなれません。
公証人の親族等
不正を防止するために、公証人の配偶者や4親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれないとされています。公証人と証人は、お互いに親族ではない必要があるということです。
公正証書遺言の証人の選び方と依頼費用の目安

遺言書には財産に関する重大な内容を書くことになります。秘密が厳守されるよう、証人は信頼できる人に依頼しましょう。公正証書遺言の証人の選び方やかかる費用について、説明します。
友人・知人に頼む場合
親族以外で頼みやすい第三者といえば、友人や知人です。信頼できる友人・知人がいれば、証人として立ち会ってもらえないか相談してみましょう。
友人・知人に証人を依頼する場合には、費用がかかりません。しかし大事な役割を引き受けてもらうことには変わりないため、何らかのお礼をするとよいでしょう。なお、友人・知人に遺言書で財産を譲る場合、譲る相手は受遺者となるため証人になれません。
弁護士・司法書士・行政書士等に依頼する場合
公正証書遺言の証人は、弁護士、司法書士、行政書士等の専門家に依頼できます。ただし、専門家に依頼する場合、証人のみを依頼するのではなく、通常は遺言書作成の手続き全体を依頼することになります。専門家に遺言書作成を依頼する場合には、証人依頼費用も含め5万円~10万円程度の費用がかかるのが一般的です。
国家資格のある専門家であれば、守秘義務があるため、遺言書の秘密も守られます。各専門家が対応できる相続手続きは以下の通りです。
| 専門家の種類 | 主な業務 | 対応できる相続手続き | |
| 弁護士 | ・紛争の解決 | ・裁判所での手続き全般 ・他の相続人との交渉 ・相続人調査 ・相続財産調査 |
|
| 司法書士 | ・登記手続き全般 ・裁判所提出書類の作成 |
・登記手続き全般 ・相続人調査 ・相続財産調査 |
|
| 行政書士 | ・官公庁に提出する書類の作成 ・権利義務に関する書類の作成 |
・遺産分割協議書作成 ・自動車の相続手続き |
|
遺言書作成を依頼する場合、将来のトラブルが予想されるなら弁護士に相談するのがおすすめです。財産として不動産がある場合には、司法書士に依頼すれば、相続発生時の登記申請までスムーズに対応してもらえます。それほど複雑でない場合で費用を抑えたいなら、行政書士に依頼する方法があります。
公証役場で手配してもらう場合
公正証書遺言の証人を自分で用意できない場合、公証役場に証人の手配をお願いすることも可能です。この場合、証人ひとりにつき1万円程度の費用がかかります。
トラブル防止のため公正証書遺言の証人は慎重に選びましょう

この記事のまとめ
- 公正証書遺言を作成するには証人2人以上の立ち会いが必要
- 公正証書遺言の証人になるための資格はないが、法律で欠格事由が定められており、未成年、推定相続人・受遺者等、公証人の親族は証人になれない
- 公正証書遺言の証人は裁判で証言しなければならない可能性もある
- 公正証書遺言の証人を専門家に依頼した場合には、遺言書作成の手続きも引き受けてもらえる
- 公正証書遺言の証人は公証役場で手配してもらうことも可能
相続対策のために公正証書遺言の作成を検討している場合は、証人の手配についても考えておきましょう。証人として立ち会いをしてもらうために、特別な資格は必要ありません。しかし、親族は証人になれない人に該当することが多く、第三者に依頼する必要があります。証人は信頼できる友人等に依頼するか、専門家に任せるのがおすすめです。
◆公正証書の作り方についてはこちらも参考にしてみてください。
公正証書とは?公正証書の作り方を初心者にも分かりやすく弁護士が解説|カケコム(事業対象:法律 事務所:東京都港区六本木5-9-20)
神戸大学法学部卒業。鉄鋼メーカー、特許事務所、法律事務所で勤務した後、2012年に行政書士ゆらこ事務所を設立し独立。メインは離婚業務。離婚を考える人に手続きの仕方やお金のことまで幅広いサポートを提供。法律・マネー系サイトでの執筆・監修業務も幅広く担当。