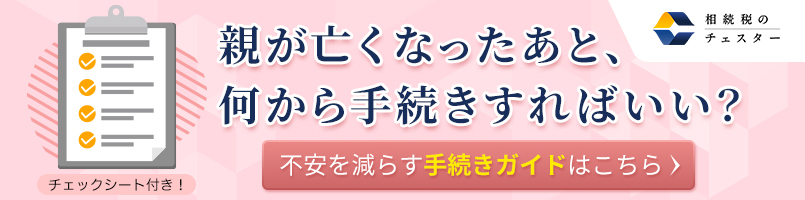デジタル遺品とは?生前整理の方法と注意点、相続トラブルを回避するための対策もご紹介

皆さんは「デジタル遺品」という言葉を知っていますか?生前整理を行う際は、デジタル遺品の存在を忘れてはいけません。本記事では、デジタル遺品の意味や生前整理の方法、処理する際の注意点について解説していきます。トラブルを回避するための対策と合わせて確認しましょう。
デジタル遺品とは?

デジタル遺品とは、故人が所有していたデジタル端末に保存されているデータや写真、インターネットで契約したサービスなどの情報のことです。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末本体もデジタル遺品に含まれます。
デジタル遺品はパソコンやスマートフォンの普及にともない、近年生まれたものです。そのため、まだ十分な法整備は進められていません。トラブルに巻き込まれないためにも、前もって対策を確認しておきましょう。
デジタル遺品の種類

「デジタル遺品」といっても、その種類はさまざまです。故人の死後に何がデジタル遺品となるのか確認しておくことで、生前整理や処理をスムーズに進められるでしょう。ここからは、デジタル遺品の種類について解説していきます。
デジタル機器内のデータ
デジタル遺品の種類として、デジタル機器内に保存されているデータが挙げられます。パソコンやスマートフォンの中に保存されている写真や画像、ファイルなどのデータがデジタル遺品です。
その他、インターネットサービスで利用しているアカウント情報も、デジタル遺品に含まれます。生前整理を行う際は、画像やファイルなどのデータの整理を行う必要があるでしょう。
ブログやSNS
デジタル遺品の種類として、ブログやSNSなども挙げられます。また、クラウドストレージ上のデータなどもデジタル遺品の一種です。
ブログやSNSに人名や住んでいる場所の情報、顔写真などが残っていると、第三者に悪用される恐れがあります。ブログやSNSなどを活用している場合は、自分が亡くなった後の取り扱いや処理についてしっかり考えておきましょう。
インターネット口座
インターネット口座も、デジタル遺品の一つです。具体的にはインターネット銀行の口座やFX口座、仮想通貨口座、ネット証券口座の情報などがデジタル遺品に当てはまります。これらのインターネット口座で取引をしたり残高を確認したりするのには、IDとパスワードが必須です。
IDとパスワードを誰にも伝えないまま亡くなった場合、残された家族がインターネット口座にログインできず相続関係の手続きに手間取る恐れがあります。ログイン情報の開示請求をするのには時間がかかるため、相続税の申告期限までに開示が間に合わない可能性も出てきてしまいます。
また、遺族が故人のインターネット口座の存在を知らず相続できなかったということも珍しくありません。インターネット口座に関する相続対策はきちんと行っておきましょう。
デジタル遺品の生前整理の方法

ここからは、デジタル遺品の生前整理や処理方法について詳しく解説していきます。デジタル遺品の処理が適切にできていないと、大きなトラブルに発展する恐れがあるため、ぜひ参考にしてください。
定期的に写真や動画を整理する
デジタル遺品の生前整理の方法として、定期的に写真や動画を処理・削除することが挙げられます。毎日のように写真や動画を撮り、そのまま画像データを整理せず放置している方も多いのではないでしょうか。
撮影に失敗した写真はその場ですぐに消す、定期的に写真を見直して気に入ったもの以外は削除するだけでも十分な生前整理になります。
また、撮影した写真や動画をクラウドサービスを利用して保管している方もいるでしょう。しかし、クラウドサービスの中には本人以外のログインを禁止しているものもあります。
あなたが亡くなった後、残された家族がデータを確認できないというトラブルが起こる可能性もあります。家族に残しておきたい画像やデータは、ハードディスクなどに保存しておくとよいでしょう。
ネット口座や契約しているサービスをまとめておく
ネット口座や契約しているサービスを一覧にまとめるというのも整理方法として有効です。特に、証券口座や銀行口座は相続に関わる情報ですので、忘れずにまとめておいてください。口座が大量にあると相続手続きに手間と時間がかかるため、使っていない口座は解約して、少しでも数を減らしておくことをおすすめします。
アカウント情報とパスワードをリスト化する
デジタル遺品の整理方法として、アカウント情報とパスワードのリスト化が挙げられます。使用していたサービス名やネット口座が分かっていても、ログインIDやパスワードが分からないとデジタル遺品の整理が進められません。
IDやパスワードの情報を残しておかないと、残された家族が業者にロック解除を依頼しなければならず、余分な費用がかかってしまいます。また、月額制のサブスクリプションサービスを利用している場合は、解約方法なども詳しくまとめておくとよいでしょう。
見せたくないデータにはロックをかける
人によってはデジタル遺品の中に、他人に見せたくないデータが入っている場合もあるでしょう。自分が亡くなったあとに見られたくないアプリや画像データ、ファイルなどにはパスワードを設定してロックをかけ、開けられないようにしましょう。家族に「ロックがかかっているデータは中身を見ずに削除して」と伝えておくことも大切です。
また、前もってデバイス内に自動削除ソフトを導入するのもおすすめです。自動削除ソフトはファイルやフォルダに一定期間アクセスがなかった場合に、データを削除してくれます。
SNSの取り扱いについて希望を残す
デジタル遺品の生前整理の方法として、SNSの取り扱いについての希望を残すことも大切です。「InstagramやFacebookなどは残して欲しい」のか「削除して欲しい」のか、しっかり伝えておきましょう。
「SNSを活用して欲しい」「死亡告知をして欲しい」などの具体的な要望も伝えておくことをおすすめします。また、SNSの種類ごとに取り扱いを変えて欲しい場合は、SNSごとの希望をリストにまとめておくとよいでしょう。
専門業者に依頼する
自分でデジタル遺品の生前整理をする自信がない方は、専門業者に対応を任せると安心です。業者には、あなたが亡くなった後のデータ削除やSNSアカウントの停止、サービスの解約などを依頼できます。これらのサービスも活用しながら、生前整理を進めていきましょう。
デジタル遺品で起こりやすいトラブル

ここからは、デジタル遺品で起こりやすいトラブルについて説明します。どのような問題が起こりやすいのかを確認し、対策を考えましょう。
デジタル機器がロックされ開けない
デジタル遺品に関するトラブルとして多いのが、機器内のデータを確認できないことです。スマートフォンには、パスワードを何度も間違えるとロックをかける機能が備わっています。
携帯電話のキャリアでは、パスワードの解除サービスは行っていません。そのため、スマートフォンへのログインパスワードが分からない場合は、専門業者に解除を依頼することになります。
しかし、パスワードのロック解除には時間がかかる上、20〜30万円ほどの費用がかかる場合も多いです。遺された家族に手間と費用をかけさせないためにも、スマートフォンのログインパスワードは控えておきましょう。
故人の知り合いに訃報の連絡ができない
故人の知人に訃報を知らせられないというのも、デジタル遺品に関するトラブルの一つです。近年はスマートフォンの普及により、故人の知り合いの連絡先は本人のスマートフォンでしか確認できない場合も多くあります。
スマートフォンのロックが解除できなかったために故人の知り合いの連絡先が分からず、葬儀の連絡ができなかったというトラブルも珍しくありません。きちんと訃報を知らせてもらうためにも、知り合いの連絡先をメモ帳にまとめておくなどの対策を講じましょう。
遺影にする写真がない
遺影にする写真がないというトラブルも起こりやすいため、十分注意が必要です。近年は画像データを現像する機会が減り、写真はパソコンやスマートフォンに保存することが大半です。
そのため、パソコンやスマートフォンにログインできず、遺影になる写真が取り出せないというトラブルが多発しています。もし遺影にして欲しい写真が決まっているのなら、事前に画像を親族へ渡しておくとよいでしょう。
定額サービスが解約できない
デジタル遺品のよくあるトラブルとして、定額サービスが解約できないことが挙げられます。漫画の読み放題サービスやサブスクリプションといった定額サービスは、解約手続きをしない限り支払いが止まりません。
故人がきちんとログイン情報をまとめていないとサービスの解約ができず、そのまま料金を支払い続けることになります。
ネット証券などの遺産の実態が分からない
ネット証券などの遺産の実態が掴めないというのも、デジタル遺品で多く見られるトラブルの一つです。故人が生前ネット証券での投資を行っていた場合、残高は相続の対象になります。
しかし現状は、ネット上での資産運用について故人が家族に知らせていない場合が多く、実態が分からないことがほとんどです。きちんと遺産を相続してもらうためにも、遺産の実態を分かるようにしておきましょう。
デジタル遺品の相続トラブルを回避するための対策

上記で説明した通り、デジタル遺品に関してはさまざまなトラブルが起こっているため注意が必要です。ここからは、デジタル遺品のトラブルを回避するための対策について詳しく解説します。
パスワードを共有しておく
デジタル遺品のトラブルを防ぐ対策として、パスワードの共有が挙げられます。配偶者や家族、兄弟・姉妹などにデジタル機器のパスワードを共有することで、データが初期化されたり写真が取り出せなかったりといったトラブルを回避できます。
アカウント情報のリストを共有しておく
アカウント情報のリストを共有しておくのも、デジタル遺品のトラブルを防ぐのに有効な対策です。契約しているサービスや口座、SNSごとにIDやパスワードなどの情報をまとめ、リストにしておきましょう。このリストを家族と共有しておけば、いざという時に対応してもらえます。
トラブルを避けるため、デジタル遺品は生前に整理しておきましょう

この記事のまとめ
- デジタル遺品とは、故人が所有するデジタル機器の中に入っているデータや情報のこと
- デジタル遺品は、デジタル機器内のデータ、インターネット口座、SNSなどを指す
- デジタル遺品は定期的に整理したり、アカウント情報などをまとめておくことが大切
- デジタル遺品では、定額サービスが解約できないなどのトラブルが起こりやすいため注意が必要
近年、デジタル機器やインターネットの普及に伴って「デジタル遺品」が誕生しました。生前整理をする際は、デジタル機器やネット上のデータ整理もきちんと行う必要があります。デジタル遺品の処理方法や、トラブルを予防する対策などを参考にして、悔いが残らないよう生前整理を進めましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。