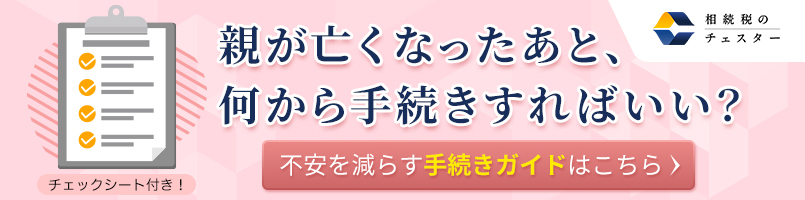繰り上げ法要とは?行う意味やメリット、事前準備から当日の流れまで詳しく解説

一般的な方法とは違った手順で葬儀・法要を行う「繰り上げ法要」をご存じですか?繰り上げ法要は、仕事などでなかなか都合がつかない方でも法要に参列しやすく、近年では多く行われています。本記事では、繰り上げ法要の意味やメリット、準備・当日の手順について解説します。
繰り上げ法要とは?

繰り上げ法要とは、四十九日までに行われる忌日法要のうち、初七日法要の日程を葬儀当日に繰り上げることです。
本来、逝去後の忌日法要は「亡くなってから四十九日までの期間は故人が成仏していない」という考え方から、死亡後七日ごとの周期で行うことが一般的です。繰り上げ法要は一般的な法要とは異なり、葬儀の当日に初七日の法要を執り行います。
現代では、法要を行う遺族側の負担や、仕事の都合で予定を合わせることが難しいといった理由から、繰り上げ法要が多く行われています。
繰り上げ法要のメリット・デメリット

ここからは、繰り上げ法要のメリット・デメリットについて解説していきます。
繰り上げ法要のメリット
繰り上げ法要のメリットは、主に日程の短縮による遺族・参列者の負担を軽減できる点にあります。まずは、繰り上げ法要のメリットを確認していきましょう。
日程調整がしやすい
繰り上げ法要は、遺族と親族・参列者間で日程調整がしやすい点が大きなメリットです。一般的な初七日法要は、葬儀(お葬式・告別式)・火葬を行う日と初七日法要が別の日に設定されているため、あらためて日程調整しなくてはなりません。
しかし、繰り上げ法要であれば、葬儀・火葬を行う日に初七日法要もまとめて執り行えるため、より多くの方に参列してもらいやすくなります。
遺族・参列者の負担を軽減できる
葬儀や火葬と一緒に初七日の法要も行える繰り上げ法要では、遺族や遠方に住んでいる参列者の身体的・金銭的負担を軽減できるのもメリットの一つです。
法要を別日に設定した場合、法要の度にあらためて休暇を取ったり、遠方の方は何度も電車や飛行機で移動することになります。しかし、繰り上げ法要であれば初七日の法要もまとめて行えるため、休暇取得や移動の手間が省けます。
繰り上げ法要のデメリット
続いて、繰り上げ法要のデメリットについてもご紹介します。
スケジュールが詰まって忙しくなりやすい
繰り上げ法要の最大のデメリットは、葬儀当日が忙しくなりやすい点です。葬儀の形式や流れによって異なりますが、一般的に葬儀にかかる目安時間は、お通夜で1~2時間、お葬式と告別式で1時間程度、火葬は1時間~1時間30分とされています。
加えて、各儀式の準備もあるため、葬儀を行う喪主や遺族は一日中忙しくなってしまいます。さらに初七日の法要まで加わるとなると、一日の拘束時間が長くなる点は注意しておいた方がよいでしょう。
周囲に理解されない可能性がある
繰り上げ法要は、住む地域や親族の考え方などによっては理解されない場合があります。
また、忌日法要はきっちり7日ごとに実施するべきという昔からの考えを持つ親族がいる場合は、繰り上げ法要に納得してもらうことは難しいかもしれません。
このように、繰り上げ法要には周囲から理解を得にくいデメリットがある点も十分理解しておきましょう。
繰り上げ法要を行うにあたって必要な準備

繰り上げ法要を行う際には、一般的な葬儀と同様にさまざまな準備が必要です。ここからは、繰り上げ法要を行うにあたって必要な準備とは何かを順番に説明します。
①葬儀社・寺院との打ち合わせ
まずは、繰り上げ法要を行うことについて葬儀社・寺院と打ち合わせをします。どのように繰り上げ法要を行いたいのかを説明し、承諾をもらいましょう。
繰り上げ法要には、葬儀(お葬式・告別式)・火葬の後に初七日法要を行う「戻り初七日」と、火葬の前に初七日法要を行う「式中初七日」という二つのやり方があります。中でも式中初七日は、対応していない寺院・葬儀社があるため、あらかじめ確認しておいてください。
②参列者への連絡
繰り上げ法要を執り行う日程が決まったら、参列者へ連絡し、出欠確認をとりましょう。とくに戻り初七日を行う場合は、会場も忘れずに参列者へ伝えてください。
③会食の準備
繰り上げ法要で会食を行う場合は、法要後の会食の場所・料理を予約するといった準備も必要です。法要を行った寺院・自宅で会食をする場合は、仕出し料理の予約をしておきましょう。
④お布施
繰り上げ法要にて読経をする僧侶に渡すお布施も早めに用意しておきましょう。表書きには「お布施」と記載し、封筒の下部に家の名字または喪主のフルネームを記入します。また、自宅で法要を行う場合は「お車代」、会食に僧侶が同席しない場合は「御膳料」も別で用意します。
お布施に包む金額は一回の読経につき3~10万円が相場です。お車代は3~5千円、御膳料は5千~1万円がそれぞれの相場になります。
⑤返礼品
繰り上げ法要の参列者に渡す会葬の返礼品も準備しておきましょう。返礼品は2~5千円が相場であり、使ったら後に残らない「消えもの」を選ぶことがよいとされています。
返礼品に付けるのし紙の表書きは「志」と書くことが一般的です。表書きの書き方は地域や宗派によって異なるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
繰り上げ法要の当日の流れ

繰り上げ法要を行う場合、当日は忙しくなるため、事前準備だけでなく当日の流れもしっかりおさえておくとよいでしょう。ここからは、繰り上げ法要を行う場合の当日の流れについてご紹介します。
「戻り初七日」の場合の流れ
戻り初七日とは、葬儀から火葬までを執り行った後、遺骨と一緒に葬儀会場へ戻り、初七日の法要を行うスタイルです。繰り上げ法要を行う場合、戻り初七日を指すことが一般的です。会場と火葬場を移動するため、体力面では負担が大きい点には注意しましょう。
「戻り初七日」の当日の流れ
- 葬儀会場にて葬儀・告別式を行う
- 火葬場へ移動し、火葬・収骨をする
- 遺骨を持って葬儀会場へ戻り、初七日法要を行う
- 会食(精進落とし)を行う
「式中初七日」の場合の流れ
式中初七日とは、葬儀の過程で初七日の法要も一緒に行うことで「繰り込み初七日」とも呼ばれています。戻り初七日のように何度も場所を移動しないため、参列者への負担は少ない傾向にあります。
「式中初七日」の当日の流れ
- 葬儀会場にて葬儀・告別式を行う
- 初七日の法要を行う
- 出棺の儀を行い、火葬場へ搬送する
- 火葬・収骨を行う
- 会食(精進落とし)を行う
繰り上げ法要における3つの注意点

繰り上げ法要は一般的な葬儀・法要のスタイルと異なるため、執り行う際には注意点も踏まえておくことが大切です。ここからは、繰り上げ法要における注意点をご紹介します。
①あらかじめ親族間で相談しておく
繰り上げ法要を執り行う予定であれば、あらかじめ親族間で相談しておきましょう。繰り上げ法要を行うことは増えているものの、親族の中には葬儀の方法にこだわりがあったり、繰り上げ法要を受け入れられない方もいるかもしれません。
葬儀の際の思わぬトラブルを避けるためにも、事前に他の親族の理解を得てから行いましょう。
②必ず事前に葬儀社・寺院と打ち合わせをしておく
繰り上げ法要を行う場合は、必ず事前に葬儀社・寺院と打ち合わせを行った上で執り行いましょう。初七日や四十九日などの法要は、仏教の教えに基づいて行われるため、法要で読経などを行う寺院や僧侶からの承諾がないと実施できない場合があります。
また、土日や祝日に行う繰り上げ法要の場合、僧侶や葬儀社の予約が埋まっていることもあるため、打ち合わせはできるだけ早めにしておくとよいでしょう。
③地域の慣習を確認しておく
親族間やご近所でのトラブルを防ぐためにも、住んでいる地域の慣習もあらかじめ確認しておいてください。例えば北海道の場合、昔は交通機関が発達していなかったことから、繰り上げ法要だけでなく、四十九日や百箇日などの忌日法要を一緒に行う取越法要も一般的です。
一方で、住んでいる地域によっては、繰り上げ法要をよく思っていない場合もあるため、地域の人の失礼にならないように注意しましょう。
繰り上げ法要に関するよくある質問

ここからは、繰り上げ法要に関するよくある質問をまとめています。
繰り上げ法要に参列する場合の香典はどうする?
繰り上げ法要に参列する際の香典は、葬儀用とは別に法要用の香典を用意するという考え方が一般的ですが、近年では別で用意しないこともあります。
金額も一般的な葬儀と同じで、故人との関係性に合わせて包むようにしてください。尚、法要後の会食に参加する場合は、通常の香典の金額に加えて、5千~1万円程度上乗せして包むとよいでしょう。渡し方については地域差があるため、葬儀社に相談してみてください。
繰り上げ法要に香典返しは必要?
香典返しについては参列者が辞退する場合を除き必要です。葬儀と繰り上げ法要の香典を合計し、その額に対する香典返しを忌明け後に渡す方法や、葬儀と法要それぞれについて香典返しを用意する方法があります。
繰り上げ法要を行う際は、準備と手順をしっかり押さえましょう

この記事のまとめ
- 繰り上げ法要とは、初七日の忌日法要を葬儀当日にまとめて執り行うことを指す
- 繰り上げ法要は日程調整がしやすい点が大きなメリット
- 戻り初七日は葬儀・火葬の後、式中初七日は葬儀と火葬の間で法要を行う
- 繰り上げ法要では、葬儀当日は忙しくなりやすい点に注意が必要
繰り上げ法要は、葬儀当日にまとめて初七日法要を行える反面、事前準備や当日が忙しくなる傾向にあります。繰り上げ法要を行う際は、あらかじめしっかり準備と手順を確認した上で、故人や参列者に失礼がないように行ってください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。