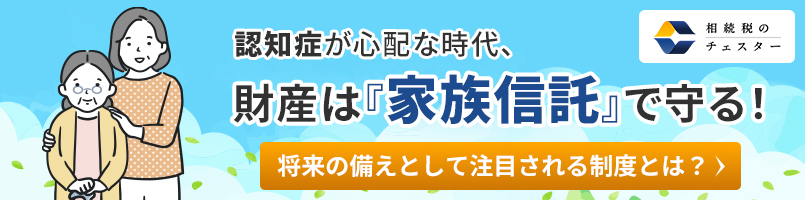「介護」と「介助」の違いとは?それぞれの種類・内容や注意点を解説

「介護」と「介助」は、日常や福祉の場面でよく耳にする言葉ですが、それぞれの違いについて正確に理解している人は多くないでしょう。介護と介助は、支援の目的や役割において違いがあります。本記事では「介護」と「介助」の違いや、それぞれの種類や具体的な内容などを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
「介護」と「介助」の違い

「介護」とは、身体的・精神的に弱った方が日常生活を快適に過ごせるよう支援し、生活全般を包括的にサポートすることです。介護の種類として食事や入浴の補助、体位変換などがあり、精神的ケアも含まれることが特徴です。
一方で「介助」は、特定の動作を補助する行為を指します。介護との違いは、支援範囲が限定的である点です。よって、介助は介護に含まれます。
介護と介助は、対象や支援内容において違いがあり、それぞれの役割を理解することで、より適切なサポートを選択できます。
「介護」でおこなう支援

介護でおこなう支援は身体介護と生活援助の2種類です。
身体介護
身体介護は、介護サービス利用者の日常生活の基本動作をサポートする支援です。身体介護の種類として、食事や入浴、排泄、着替えなどの介護が含まれます。浴槽への出入りの支援やトイレの使用の補助により、利用者の安全と快適さを確保します。
身体介護と介助の違いは、サポート範囲の広さや目的です。
注意点として、身体介護時は利用者のプライバシーを尊重し、負担軽減が重要になります。身体介護と生活援助の違いは、直接身体に触れる介護かどうかです。身体介護には専門的な技術が必要なため、研修を受講してからおこないます。
生活援助
生活援助は掃除や洗濯、料理、買い物などを通じて、利用者の日常生活を支える介護のことです。身体介護との違いは、生活援助が身体的なケアではなく、家事を中心におこなう点です。
注意点として、生活援助時はプライバシーを守り、希望やライフスタイルにあわせることが求められます。利用者によって必要な支援内容は異なるため、違いを理解して適切なサポートをお願いしましょう。
サポートしてもらう際は部屋の物の配置を変えないようお願いすることや、自身の嗜好や予算を考えて買い物をおこなってもらうなどの対応が必要です。生活援助は家事面のサポートに特化しており、利用者の体に直接触れてサポートをおこなう身体介護とは異なります。
「介助」でおこなう支援

介助でおこなう支援には、食事介助や排泄介助、入浴介助など、日常生活における動作の支援があります。それぞれの違いについて、適切に把握しておきましょう。
食事介助
食事介助は、利用者が安全に食事を摂るためのサポートです。食事を口元に運ぶ介助や姿勢の調整などが主な内容になります。
身体介護との違いは、食事介助が食事に特化した支援である点です。利用者が自分でできる動作は自分でおこなってもらい、自力では難しい動作を介助したり、安全な食事の準備をしたりします。支援方法は身体状況や環境によって異なります。
注意点として、嚥下障害のある方には食材の形状を工夫したり、とろみを加えた飲み物を提供したりするなど、誤嚥防止の対策が必要なことです。食事の好みや習慣を考え、味付けや食感の工夫も大切になります。
コミュニケーションを大切にして楽しい食事時間を提供することが、食事介助の大きなポイントです。
排泄介助
排泄介助は、利用者が安全で快適に排泄できるよう支援します。トイレへの移動やオムツ交換などが主な支援です。身体介護との違いは、排泄に特化したケアである点です。支援時にはプライバシーを尊重し、利用者がリラックスできる環境を作ることが求められ、利用者ごとに対応方法の違いがあります。
注意点として、声掛けは丁寧におこない、羞恥心を和らげる配慮が必要なことです。排泄後は清潔を保ち、皮膚が弱い方にはスキンケアをしてトラブルを予防します。尿や便の状態を観察することも重要で、健康状態の違いを見逃さないよう注意が必要です。
排泄介助は利用者によって必要な支援内容が異なるため、気になる方は介助者に確認してみてください。
入浴介助
入浴介助は、利用者が安全に入浴できるようサポートをします。介助の種類として浴槽への出入りや洗体、洗髪、着替えの補助などがあります。場合によっては全身を支えることも必要です。浴室の特徴を把握し、転倒防止のために手すりや滑り止めマットを用意したり、温度管理をしたりするなどの環境整備が重要です。
ほかの身体介護との違いは、入浴介助が衛生面だけでなくリラクゼーションを目的とする点にあります。注意点として、利用者によって支援内容が異なり、自分でできる部分を促しつつ、困難な動作については介助をおこない自立を支援します。
身体状況や入浴の好みの違いにあわせた対応も必要です。好きな香りの入浴剤や会話を取り入れると、心身ともにリラックスした時間になり、満足度を高められるでしょう。こうした配慮による違いが、利用者の快適さに大きく影響します。
歩行介助
歩行介助は、利用者が安全に歩行できるよう支援することです。身体介護との違いは歩行の支援に特化している点です。杖や歩行器の使用サポート、段差や坂道を歩行する際の補助などが含まれます。また、利用者が自分の力で歩くことを促し、自立を支援する点も大きな違いです。
介助時はバランスを保てるよう適切な姿勢をサポートし、転倒防止のために側について安全を確保します。屋外では天候や路面状況の確認も必要です。利用者の筋力や体力を考慮し、無理のないペースで進めることも大切です。
長時間の歩行が難しい場合は、休憩を取り入れて疲労を防ぐなど、状況の違いに応じた対応が求められます。
移乗・移動介助
移乗・移動介助は、利用者が車椅子からベッドや椅子へ移動する際に補助をおこなう支援です。身体介護との違いは、移乗や移動に特化している点にあります。利用者を安全に支えながら姿勢を整え、転落を防ぐ技術が求められます。
移乗・移動介助では、利用者が自分でできる動作を活用しつつ、支援するのがポイントです。車椅子に自力で座れる場合は動きを見守り、全身の支えが必要な場合は介助をおこないます。身体状況の違いに応じた柔軟な対応が必要です。
注意点は、心理的な不安を軽減するため、優しい声掛けや具体的な指示が求められる点です。「右に少し体を動かしましょう」などの明確な声掛けにより、安心して移乗・移動できる環境を作ります。利用者ごとの状態や移動方法の違いを把握すると、より安全で快適な介助ができるようになります。
更衣介助
更衣介助は、利用者が快適に衣服を着脱できるよう介助し、ボタンを留める、袖を通す、衣類を整えるなどが主な支援です。身体介護との違いは、更衣に特化している点で、利用者ごとの違いを理解して対応することが求められます。
寒い季節には防寒対策、暑い季節には通気性のよい衣類を選ぶといった工夫が必要です。利用者の好みやライフスタイルを尊重することで、心理的な満足感を高められます。
利用者とのコミュニケーションを通じて、必要なサポートの違いを確認し、適切な対応が必要です。個々の違いを意識した丁寧な介助が、利用者の快適さに結びつきます。
段階で異なる4つの介助

介助は、利用者の状態や自立度の違いにあわせておこないます。それぞれの段階における違いや支援方法を理解すると、利用者に安全で最適なケアを提供できます。
自立
自立を促す支援は、利用者が持っている能力を最大限に活用し、可能な限り維持することを目指します。過剰な介助を避け、利用者が自信を持って日常生活を送れるようなサポートが必要です。
朝の支度であれば、利用者が自分で歯を磨ける場合は見守り、困難な場合のみ介助をおこなう方法が効果的です。自立を維持するためには、本人が行動する機会を奪わないよう、時間に余裕を持ったスケジュールの組み立ても大切になります。
一部介助
一部介助は、利用者が自分でできる部分はそのままおこない、困難な動作に限って介助をおこなうことです。利用者の能力を最大限に活用しつつ、負担を軽減させることが目的です。
靴を履く際の介助であれば、靴を揃えておき、利用者が自分で足を入れられる場合は、動作を促します。食事介助では、スープやおかずを食べやすいサイズに切り分ける介助をおこない、自分で食べてもらうなどです。
一部介助では、利用者ができる部分を尊重しながら、必要な支援を提供するバランスが重要です。介助者は、利用者の能力を観察し、「どこまで自分でできるか」を見極めた上で適切にサポートをおこないます。
半介助
半介助は、利用者が一部の動作を自分でおこなえる場合に、動作を補う形の介助です。より広範囲の支援が必要な場合もありますが、利用者の意欲や能力を尊重し、一緒におこないながら行動を促します。
調理を一緒にする場合、利用者が野菜の洗浄や簡単な調理作業をおこない、介助者が包丁を使用する部分を担当するといった形があります。洗濯物を干す際には、利用者が洗濯物を取り出し、介助者が高い位置に干す作業を補助するなども考えられるでしょう。
全介助
全介助は、利用者がほとんどの動作を自分でできない場合の介助です。要介護度の高い方に対しておこなわれることが多く、日常生活全般にわたる支援が必要です。
食事介助や衣類の着脱、ベッド上での体位変換など、全身を対象としたすべての介助が挙げられます。入浴の際には浴槽への移動、洗体、髪を洗うといった一連の動作を完全にサポートします。
「介護」と「介助」の違いを理解して適切なサポートをお願いしましょう

この記事のまとめ
- 福祉の場面でよく耳にする「介護」と「介助」の意味は異なる
- 介護でおこなう支援は、身体介護と生活介護がある
- 介助でおこなう支援は、食事介助や排泄介助などがある
- 介助では、自分でできることはおこなってもらい、できないことを支援する
- 利用者の状態に合わせた介助方法が必要
「介護」と「介助」の違いを理解することは、利用者の日常生活の質を向上させるポイントとなります。それぞれの特徴や種類を把握し、利用者一人ひとりの状況や違いにあわせた支援が重要です。家族や福祉に従事する方たちのケアが利用者の自立を支え、よりよい日常生活を送る手助けとなるでしょう。