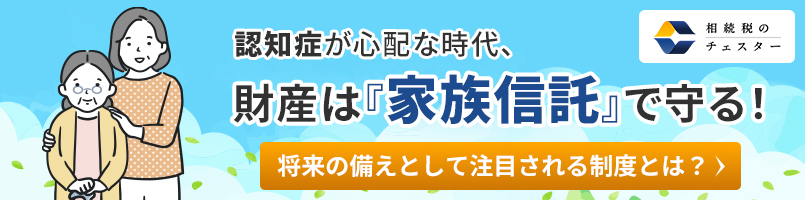親の介護をしないとどうなる?介護放棄が起きる原因やリスクを解説

親の介護をしないとどうなるのか、知らない人も多いのではないでしょうか。親の介護は子供がするものという考え方が多いですが、親との関係や介護者の体力などの理由によっては、親の介護をしないという選択肢もあります。本記事では、親の介護をしないとどうなるのかや、親の介護をしたくないときの対処法などについて紹介します。
親の介護は扶養義務に含まれる

そもそも、親の介護は法的な義務です。これは民法第877条に基づいており、直系血族間の扶養義務の一部として規定されています。この法律が存在する理由は、家族の絆を維持し、社会の安定を図るためです。親の介護は単なる道徳的責任ではなく、法律に定められた義務であることを認識し、自身の状況に応じた適切な対応を取ることが重要です。
ただし、直接的な身体介護をしない場合でも、経済的支援や介護サービスの手配なども介護に含まれます。では、親の介護を全くしない場合、どうなるのでしょうか。
親の介護をしないとどうなる?

親の介護をしないと、法律の観点や道徳的な側面、家族関係や社会的な側面からさまざまな影響をきたす可能性があります。まずは、親の介護をしないとどうなるか、具体的な状況や結果について解説します。
刑罰を科される場合がある
極端に親の介護をしないと、最悪の場合、刑罰の対象となる可能性があります。保護責任者遺棄罪(刑法第218条)などに該当する可能性があるためです。したがって、親の介護を完全にしないことは、法的リスクをともなうことを理解し、適切な対応を取ることが重要です。
扶養義務が免除されることがある
特殊な状況下では、親の介護をしないでよい可能性があります。親子関係が著しく悪化している場合や、子の経済状況が極めて厳しい場合など、特別な事情がある場合です。
例えば、長年虐待を受けていた子供は、成人後に親の介護をしなくてもよいと判断されることがあります。ただし、個別の状況に応じて慎重に判断されます。結論として、親の介護をしないことは可能ですが、それは極めて限定的な状況のみ認められるものです。
親の介護をしたくない理由

親の介護をしないとどうなるか気になった人の中には、親の介護をしたくないと感じている人もいるでしょう。親の介護をしたくないと感じることは決して珍しくなく、複雑な感情や原因、問題を反映しています。
ここからは、親の介護をしたくないと考える主な原因について、詳しく解説します。
心身の状態が悪い
介護者自身の健康状態がよくない場合、親の介護をしないという選択を考えるかもしれません。親の介護は身体的にも精神的にも非常に大変な仕事です。例えば、持病のある50代の子供が、認知症の親の介護を24時間求められる場合が挙げられます。このような状況では、介護者自身の健康悪化リスクが高まるため、親の介護をしたくないと考えても自然でしょう。
介護者の健康状態を考慮し、必要に応じて介護サービスの利用やほかの家族や兄弟姉妹との分担を検討することが重要です。
経済的負担が大きい
親の介護には多くのお金が必要になるため、家計を圧迫するという理由から介護をしないと決断する人もいます。しかしこの場合、介護をしないとどうなるのかを長期的な視点で考える必要があります。介護をしないことで、将来的により大きな経済的負担を強いられる可能性もあるためです。
適切な介護や予防的なケアがなされない場合、慢性疾患の悪化や新たな健康問題の発生リスクが高まります。結果として、より高度な医療処置や長期の入院が必要となり、医療費が大幅に増加する可能性が考えられるでしょう。身体の動きも悪くなりできないことが増えてきた場合は、より多くの介護費用が必要になります。
たとえば、月々10万円の介護費用が発生し、介護のために就労時間を減らさざるを得ない状況では、介護者の家計が著しく悪化する可能性があります。利用可能な経済的支援制度を積極的に活用し、長期的な介護の計画を立てることが重要です。
親との関係が悪い
親の介護をしたくないと考える原因に、過去の経緯や価値観の違いにより、親子関係が良好でない場合もあります。長年の感情の積み重ねや、互いの理解不足が要因で親子が不仲になることは多いです。このような状況での親の世話は、双方にとって大きなストレスとなるでしょう。
しかし、介護をしないことで、家族関係の悪化や社会的な批判など、さまざまな問題が生じる可能性があります。親の介護を始める前に、可能であれば関係改善を試みたり、第三者の介入を求めたりすることが必要です。
親の介護をしたくないときの対処法

親の介護をしたくないと感じたときは、ひとりで悩みを抱え込まずに適切な対処法を見つけることが重要です。介護は長期にわたる課題であり、個人の努力だけでは限界があります。ここからは、親の介護をしたくないときの具体的な対処法について詳しく解説します。
兄弟姉妹や親族と話し合う
親の介護をしないと決断する前に、家族間で介護の役割を分担することが重要です。ひとりに負担が集中することを防ぎ、持続可能な介護体制を作りましょう。定期的な家族会議を開き、それぞれができることを明確にすることをおすすめします。
例えば、長男が主に身体介護を担当し、長女が通院の付き添いをおこなうなど、具体的な役割分担を決めることで負担を軽減できます。介護をしないとどうなるのかについて家族全員で考え、役割分担を決めることで、ひとりで抱え込む負担を軽減できる可能性があるでしょう。
地域包括支援センターに相談する
どうしても介護をしたくない場合は、福祉の専門家のアドバイスを得ることが問題解決の糸口となります。地域包括支援センターは、高齢者の福祉の総合相談窓口として機能し、介護に関するさまざまな情報やサポートをおこなう機関です。介護をしないという選択肢だけでなく、ほかの可能性を探せます。
例えば、介護サービスの種類や利用方法が分からない場合、地域包括支援センターの福祉の専門家が個々の状況に応じた適切なアドバイスをしてくれます。介護者のメンタルヘルスケアについても相談可能です。親の介護に関する悩みや疑問がある場合は、まず地域包括支援センターに相談することをおすすめします。
要介護認定を受ける
親の介護をしないと決めた場合でも、要介護認定を受けることは重要です。市区町村の窓口に申請し、要介護認定を受けることで適切な介護サービスを利用できるようになります。介護をしないとどうなるのか、親の状態を客観的に評価しましょう。
例えば、軽度の認知症症状がある場合は要介護1や2、寝たきりに近い状態であれば要介護4や5といった具合に、状態に応じて認定が行われます。認定された要介護度に基づいて、利用できるサービスの種類や限度額が決まる仕組みです。
要介護認定を受けることで介護保険サービスを利用する権利が得られます。早めに認定を受けることで、必要なサポートを迅速に受けられるため、親の状態に変化が見られたら速やかに申請することをおすすめします。
介護サービスを利用する
介護サービスは、専門的な支援を提供し、介護者の負担を軽減するために設計されています。訪問介護やデイサービスなど、さまざまな介護サービスの利用が可能です。親の介護をしないと決めても、介護サービスを利用することで間接的に親の生活を支えられるでしょう。
例えば、親が週3回のデイサービスを利用することで、介護者は自分の時間を確保でき、リフレッシュする機会を得られます。訪問介護を利用すれば、ヘルパーが入浴や食事の介助をおこなってくれます。介護をしないとどうなるのか心配な場合、介護サービスを積極的に活用することで、介護の質を保ちながら介護者の負担を軽減することが可能です。
介護施設の入居を検討する
在宅介護が困難な場合は、介護施設への入居を検討しましょう。介護施設は、24時間体制の専門的なケアを受けられるというメリットがあります。特別養護老人ホームや有料老人ホームなどさまざまな種類の施設があり、それぞれ特徴が異なるため、親に合った施設を選びましょう。
例えば、認知症の症状が進行し常時見守りが必要な場合は、グループホームを選択することで親に合ったケアを受けられます。リハビリに力を入れたい場合は、介護老人保健施設を選ぶことも一つの方法です。
介護をしないとどうなるのか不安な場合、専門的なケアを受けられる施設は安心できる選択肢となります。本人の意思を尊重しつつ、家族で十分に話し合って決定しましょう。ただし、介護施設は入居待ちの状況もあるため、早めの情報収集と申し込みが大切です。
親の介護費用を抑える方法

親の介護にはさまざまな費用がかかり、経済的な負担が大きなトラブルとなることがあります。親の介護にかかる費用を軽減するための制度を活用することで、金銭の負担を軽減しつつ、必要な介護サービスを受けることが可能です。ここからは、親の介護費用を軽くするための主な方法について詳しく解説します。
高額介護サービス費
高額介護サービス費制度は、親の介護費用の負担を軽減するための重要な制度です。高額介護サービス費により、1ヶ月の介護保険サービスの利用者負担額が一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻されます。
例えば、一般的な世帯では月額44,400円が上限です。1ヶ月の介護サービス利用額が10万円だった場合、44,400円を超える55,600円が後日に払い戻されます。
高額介護サービス費を積極的に活用することで、経済的負担を過度に心配せずに必要な介護サービスが利用できます。制度の詳細や申請方法については、市区町村の窓口やケアマネジャーに確認しましょう。
高額医療・高額介護合算療養費
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の双方が高額になった場合の負担を軽減する仕組みです。年間の自己負担額が基準を超えた分が払い戻されます。医療と介護の両方のサービスを必要とする高齢者と、その家族の経済的負担を軽減するためのものです。
例えば、70歳以上の高齢者の年間の医療費と介護費の合計が60万円で、その世帯の所得に基づく限度額が56万円だった場合、超過分の4万円が払い戻されます。高額医療・高額介護合算療養費制度を利用することで、医療と介護の両面から必要なケアを受けつつ、経済的負担が抑えられます。
介護をしないとどうなるのか経済面で不安な場合、この制度は心強い味方となるでしょう。
特定入所者介護サービス費
特定入所者介護サービス費制度は、低所得の方が介護保険施設に入所した場合の食費と居住費の負担を軽減する仕組みです。所得に応じて自己負担額が設定され、基準額との差額が補助されます。経済的理由で必要な施設サービスを利用できないことを防ぐためのものです。
例えば、年間の収入が80万円以下の方は食費が日額390円に抑えられます。通常、食費や居住費は全額自己負担ですが、この制度により大幅に軽減されます。低所得の高齢者でも必要な施設サービスを利用しやすくなるでしょう。制度の利用には申請が必要なため、市区町村の窓口に相談しましょう。
介護をしないと決めた場合でも、親の生活を経済的に支援する方法の一つとなります。
親の介護をしないとどうなるかを理解し、まずは周囲に相談しましょう

この記事のまとめ
- 親の介護は扶養義務に含まれる
- 親の介護を全くしないと刑罰を科される場合がある
- 親の介護をしたくないのは、介護者の心身の状態や経済的な理由がある
- 親の介護をしない場合、家族と話し合ったり介護サービスの利用がおすすめ
- 親の介護費用を軽くするには、公的な制度を利用する方法がある
親の介護をしないことで、さまざまなリスクや問題が生じる可能性があります。親の介護は法的・道徳的責任をともなう重要な問題です。介護をしない場合、刑罰に至る可能性もあります。
親の介護をしたくないと思ったときには、家族や地域包括支援センターに相談し、利用可能な支援やサービスについて情報を集めましょう。介護保険制度を活用し必要に応じて施設入居も検討することで、介護の負担を軽減できます。
介護をしないとどうなるのか不安な場合は、専門家や家族と相談し、最適な解決策を見つけましょう。
介護職員として介護老人保健施設に勤務。
ケアマネジャー取得後は、在宅で生活する高齢者や家族をサポートする。
現在はWebライターとして、介護分野に関する記事を中心に執筆している。