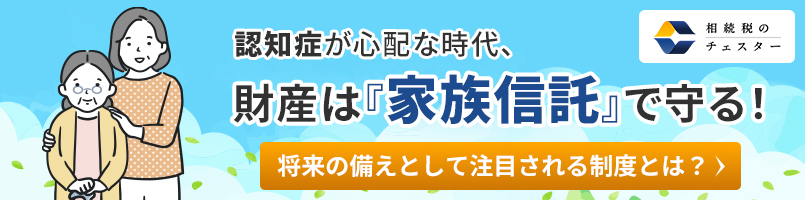在宅介護とは?受けられるサービス内容や注意点をまとめて解説

在宅介護という言葉を聞いたことはありますか?介護施設に入所して介護を受けるのではなく、要介護者を主に自宅で介護することを在宅介護といいます。本記事では、在宅介護サービスの費用や種類、利用時の注意点などを徹底解説します。
在宅介護とは

在宅介護とは、住み慣れた自宅で介護をすることをいいます。国としても「地域包括ケアシステム(※)」という考え方を提唱し、在宅介護の維持に向けた支援に取り組んでいます。
中でも介護保険制度は、生活の質の向上と家族の負担軽減を目的とし、在宅介護を支える中心的な制度となっています。
※地域包括ケアシステムとは
要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、さまざまな援助が一体的かつ総合的に提供される仕組み。
在宅介護のメリット

在宅介護を検討する場合、メリットとデメリットを理解することが重要です。まずは、在宅介護のメリットを紹介します。
在宅介護のメリット
- 住み慣れた自宅で生活できる
- 費用を抑えられる
- 自由度が高い
では、上記の三つをメリットとして挙げた理由を詳しく見ていきましょう。
住み慣れた自宅で生活できる
在宅介護は、住み慣れた自宅での暮らしを継続できることが最大のメリットです。
介護施設に入所すると、家族・友人・地域とのつながりが薄れてしまうことが心配です。特に高齢者は、居住環境が変わるストレスや孤独感で心身機能が低下してしまう恐れがあります。住み慣れた自宅での暮らしを続けられれば、安心して生活できるでしょう。
費用を抑えられる
在宅介護は施設と違い、費用が安い傾向にあります。「令和3年度 生命保険に関する全国実態調査」によれば、介護に要した月額費用は施設の場合平均12.2万円だったのに対し、在宅の場合は4.8万円でした。
家族の負担は増えるものの、介護にかかる月々の出費を抑えられる点は大きなメリットです。
自由度が高い
在宅介護は、必要性や意向に応じて多種多様なサービスを組み合わせた自分専用のケアプランでサービスを利用できる点が特徴です。
在宅であれば、施設の都合に合わせる必要もありません。自身の生活スタイルに応じた自由度の高い暮らしを続けられることも、在宅介護のメリットです。
在宅介護のデメリット

在宅介護には、以下のようなデメリットもあります。
在宅介護のデメリット
- 介護者にかかる身体的な負担が大きい
- 介護者のストレスがたまりやすい
- できる介護に限界がある
介護者にかかる身体的な負担が大きい
在宅介護の場合、介護サービスでカバーしきれない部分を家族が行なわなければなりません。特に夜間は対応可能な事業所も限られ、家族が対応を余儀なくされる場合もあるでしょう。
また、介護によって身体に負担がかかり、腰などを痛めてしまうことも少なくありません。身体介護の方法を学んだ有資格者とは違い、独自のやり方で介護を行うためです。
介護者のストレスがたまりやすい
在宅介護においては、精神的なストレスにも気をつけなければなりません。家という閉鎖的な空間での認知症の悪化や介護の手間は、介護者の精神的な負担につながるためです。
在宅介護のサービスを活用し、意識してリフレッシュしたりや気分転換をしたりするようにしましょう。
できる介護に限界がある
在宅介護には限界があります。なぜなら、設備やサービスに限界があるからです。
例えば在宅では段差が多く介護に適さなかったり、専門的な介護用品を準備することが困難だったりします。お金をかけて介護環境を整えようとしても限界があります。また、家族が介護のし方や認知症への対応方法を学んでいない場合も多く、介護のために仕事を休むのにも限界があります。
時が経つにつれ症状が重度化し、在宅介護に限界を感じた場合は施設入所を検討した方がよいでしょう。
在宅介護で受けられるサービスの種類と費用

在宅介護で受けられる介護保険サービスは、大きく5種類に分けられます。
在宅介護で利用できるサービスの種類
- 自宅に訪問してもらうサービス
- 施設に通うサービス
- 一定の期間宿泊するサービス
- 介護環境を整えるサービス
- 複合的なサービス
介護保険サービスには、その種類ごとに目的・内容・対象者・利用条件が違い、料金も異なります。在宅介護を無理なく続けるためには、生活上の困りごとに対応したサービスを効果的・効率的に組み合わせることが重要です。
この章では、それぞれの内容と費用を紹介します。
注:ここで紹介する費用は1単位=10円、自己負担割合1割の場合です(令和6年4月1日現在)。実際の料金はさまざまな条件によって異なりますので、あくまで参考としてご覧ください。
自宅に訪問してもらうサービスの場合
| 訪問系サービスの概要 | |||
|---|---|---|---|
|
名称 |
内容 |
費用 |
|
|
訪問介護 |
ヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や家事援助を実施。 公的介護タクシーも含む。 |
244円/回 ※身体介護20分~29分の場合 |
|
|
訪問入浴 |
自宅にて、組み立て式の浴槽などを使用した入浴介助を実施。 |
1,266円/回 |
|
|
訪問看護 |
看護師やリハビリ専門家が自宅を訪問し、医療ケアやリハビリを実施。 |
821円/回 ※看護師:30分~59分の場合 |
|
|
訪問リハビリテーション |
リハビリ専門家が自宅を訪問してリハビリを実施。 |
307円/回 ※1回あたり20分の場合 |
|
|
居宅療養管理指導 |
医師、薬剤師、歯科衛生士などが自宅を訪問し、在宅療養上の指導を実施。 |
514円/回 ※薬剤師の場合 |
|
|
居宅介護支援 介護予防支援 |
ケアプラン作成や各種介護相談、申請代行などを実施。 |
自己負担なし ※全額公費 |
|
|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
ヘルパーや看護師が定期巡回と随時対応サービスを実施する、24時間対応型の訪問サービス。 |
18,948円/月 ※訪問看護あり、要介護3の場合 |
|
|
夜間対応型訪問介護 |
ヘルパーが定期巡回と随時対応サービスを実施する、夜間専門の訪問介護。 |
989円/月+372円/回 ※定期巡回サービスのみの場合 |
|
施設に通うサービスの場合
| 通所系サービスの概要 | |||
|---|---|---|---|
|
名称 |
内容 |
費用 |
|
|
通所介護(デイサービス) |
心身機能の維持向上・閉じこもり防止・家族の負担軽減などを目的に、要介護者が施設に通う。 |
900円/回 |
|
|
通所リハビリテーション(デイケア) |
施設に通い、心身機能の維持向上を目的に専門的なリハビリテーションを実施。 |
1,039円/回 |
|
|
地域密着型通所介護 |
定員19名未満の小規模なデイサービス。 重度の医療ケアや認知症ケアに特化した月額制の「療養通所介護」という形態もある。 |
1,032円/回 |
|
|
認知症対応型通所介護 |
認知症ケアに特化した通所介護。 |
1,210円/回 |
|
※費用は通常規模・7〜8時間・要介護3の場合
なお、混同されがちですが、デイサービスは「主に介護」が目的で、デイケアは「専門的なリハビリテーション」が目的という違いがあるため覚えておきましょう。
一定の期間宿泊するサービスの場合
| 宿泊型サービスの概要 | |||
|---|---|---|---|
|
名称 |
内容 |
費用 |
|
|
短期入所生活介護 |
介護施設に一定期間入所し、各種介護・日常生活上の世話・機能訓練などを実施。
|
847円/日 ※ユニット型併設型・要介護3の場合 |
|
|
短期入所療養介護 |
病院・介護老人保健施設などの医療施設に一定期間入所し、医療ケア・リハビリ・各種介護などを実施。 利用のためには医師の指示が必要。 |
948円/日 ※老健ユニット型・基本型、要介護3の場合 |
|
介護環境を整えるためのサービスの場合
| 環境整備系サービスの概要 | |||
|---|---|---|---|
|
名称 |
内容 |
費用 |
|
|
福祉用具貸与 |
電動ベッド・車椅子・歩行器などの福祉用具がレンタルできるサービス。本人の生活の質の向上や介護者の負担軽減を図る。 |
杖:150円/月程度 電動ベッド:1,000円/月程度 ※料金は事業所が独自に設定 |
|
|
特定福祉用具販売 |
ポータブルトイレ、シャワーチェアなど一部の福祉用具について、購入額の7~9割を還付。 |
年間10万円分まで |
|
|
住宅改修 |
所定のバリアフリー化改修工事を実施した場合に、実施費用の7~9割を還付。 |
原則20万円分まで |
|
複合的なサービスの場合
| 複合的サービスの概要 | |||
|---|---|---|---|
|
名称 |
内容 |
費用 |
|
|
小規模多機能型居宅介護 |
通い・訪問・宿泊を一体的かつ柔軟に提供。ケアプランも事業所内のケアマネジャーが担当。 |
22,359円/月 ※集合住宅以外、要介護3の場合 |
|
|
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) |
小規模多機能型居宅介護の機能に、訪問看護も組み合わせたサービス。 |
24,481円/月 ※集合住宅以外、要介護3の場合 |
|
在宅介護で受けられるサービスの利用方法

在宅介護をする上で活用したいのが、介護保険サービスです。介護保険サービスを受ける流れをしっかり覚えておけば、必要になったときにすぐに対応できます。
在宅介護サービスを利用する流れ
在宅介護の利用を開始する方法は、以下の手順となっています。
在宅介護を開始する方法
- 要介護認定を受ける
- 結果に基づき、居宅介護支援事業所などと契約する
- ケアマネジャーからケアプランを作ってもらう
- サービス担当者会議に参加する
- サービス提供事業所と契約や打ち合わせをする
要介護認定は、住民票のある市区町村に申請します。申請の結果判明後にケアプラン作成を依頼することになるため、あらかじめ申請代行やケアプラン作成の対応が可能な地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に相談することがおすすめです。
どこに相談先があるか分からない方は、市区町村の介護保険担当窓口に問い合わせるか、自治体のホームページで調べてみましょう。認定後にケアプランの打ち合わせを行い、デイサービスなどの担当者も含めたサービス担当者会議が開催されます。そこで最終的にケアプランが確定したら、いよいよサービス利用の開始です。
在宅介護サービスを利用する際の注意点
在宅介護サービスを利用する際の注意点は、以下のとおりです。
在宅介護サービス利用時の注意点
- 利用回数と負担額のバランスを考える
- ケアマネージャーや事業所が合わないと感じたら、変えてもらうことも検討する
- サービス内容や利用条件があるため、しっかり説明を受ける
- 減免制度の対象になる場合は、積極的に活用する
在宅介護サービスは原則的として使った分だけ費用がかかるため、予算が決まっている場合は事前にケアマネジャーに伝えましょう。また、各種減免制度も存在するため、ケアマネジャーに確認しつつ利用できる制度はどんどん利用していきましょう。
在宅介護に限界を感じた場合の対処法
在宅介護に限界を感じたら、施設介護への移行も検討しましょう。ただし、入所申込をしてもすぐに受け入れてもらえるとは限りません。希望する施設が空くまでは別の施設に入所したり、入所希望施設に併設されたショートステイを練習目的で連泊利用したりして待機することも必要になります。
施設入所は決して「親を捨てる」ことではありません。無理や我慢をするとお互いの生活の質に悪影響が出るだけでなく、最終的には共倒れになる可能性があります。介護負担の部分はプロにお願いし、残された時間を有意義に過ごすことに重点を置くという考え方も一般的になっています。
在宅介護は専門家に相談しながら無理なく続けましょう

この記事のまとめ
- 在宅介護とは、要介護者の自宅での暮らしを維持しながら介護をすること
- 在宅介護のメリットとデメリットを知り、必要に応じて施設介護も検討する介護保険サービスは、それぞれ利用条件・目的・内容・費用に違いがある
- 在宅介護を始めるときは、要介護認定を受けて専門家に相談する
在宅介護は、住み慣れた環境で本人の意思を尊重しながらケアできる方法です。その一方、施設介護とは違って家族や近親者にさまざまな負担がかかるのも事実です。無理なく在宅介護を続けるためには、専門家に相談して介護保険サービスをはじめとした各種制度を活用することがポイントです。
介護が必要になったと感じたら、まずは早めに最寄りの地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に困りごとの内容を具体的に相談しましょう。各介護保険サービスの特徴を理解した上で、適切なサービスを利用することが重要です。