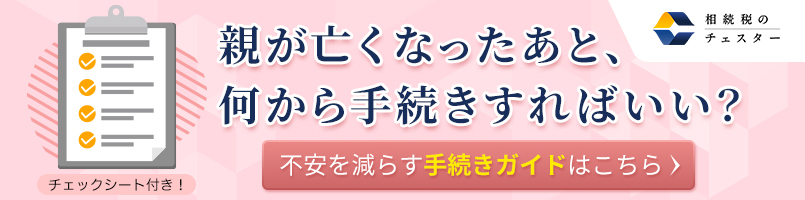神棚と仏壇を一緒に置くときはどうする?置く方角や場所を解説

神棚と仏壇はそれぞれ異なる対象を祀るためのものですが、一緒の場所に置くことはできるのでしょうか。本記事では、神棚と仏壇を一緒に置いてもよいのかや置くのに適した方角、一緒に置くときの注意点などをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
神棚と仏壇の違い

まずは、神棚と仏壇の違いについて解説していきます。
神棚
神棚とは、神道における神様を祀るためのものです。自宅の中に設置する神社としての役割があり、神棚の中には「宮形(みやがた)」を安置します。そして、神社で受け取った氏神様や天照大御神様、崇拝神社の神様の「お神札(おふだ)」を配置します。神棚のお供え物は、「神饌(しんせん)」と呼ばれるお酒や米、水、塩などが主流です。
神棚には、厄除けや家族の健康、家の繁栄、日々の恵みへの感謝などを込めてお参りします。お参りは1日のうちいつ行ってもよいとされていますが、朝と夕方に行うことが多いです。神棚へのお参りは、2回礼をして2回拍手をし、最後にもう一礼する「二拝・二拍手・一拝」で行います。また、神棚を新しく自宅に祀る場合は、神様への祈祷と「神棚奉賽(かみだなほうさい)」というお祓いを神社の神主に依頼するとよいでしょう。
仏壇
仏壇とは、自宅の中に設置する小さな寺院としての役割を担います。お寺を模して作られており、ご先祖の位牌やご本尊の仏像、掛け軸などが祀られています。また、仏壇の中には本堂の様式を模した「荘厳(しょうごん)」と呼ばれる飾りが施されています。水、ご飯、生花、ロウソク、線香の「五供(ごく)」と呼ばれるものをお供えします。
仏壇にお参りする理由としては、「仏様やご先祖を供養する」「仏壇にお参りすることで徳を積む」というものが一般的です。神棚同様、お参りはいつ行ってもよいとされていますが、起床後と寝る前に行うことが多いです。お参りの方法は宗派によって少し異なりますが、基本的には線香とロウソクに火をつけた後、おりんを鳴らして合掌・読経し、ロウソクを消すという流れで行われます。
また購入したばかりの仏壇には、仏様やご先祖の魂が入っておらず信仰の対象にはならないとされています。そのため、仏壇購入後は寺院に依頼して「魂入れ」という儀式を行う必要があります。
神棚と仏壇を一緒に置いてもよい?

神棚は神道の神様を、仏壇は仏教における仏様やご先祖を祀るものであり、信仰対象が異なります。そのため「一緒に置くべきではないのでは?」と思われる方も多いですが、同じ自宅内に置いても問題ありません。
ただし、神棚と仏壇を一緒に置く場合はいくつか注意点があるため、記事の後半で詳しく説明します。
神棚を置くのに適した場所・方角・向き

神棚と仏壇は、置くのに適した場所や方角、向きなどが異なります。二つを一緒に置く場合、それぞれの置き方に注意しましょう。
まずは神棚の最適な置き場所や方角を紹介していきます。
神棚を置くのに適した場所
神棚は、明るく清潔な場所や建物の最上階に置くのがよいとされています。なぜそれらの置き場所が適しているか、理由を詳しく見ていきましょう。
明るく清潔な場所
神様は穢れを嫌うため、神棚は明るく清潔な場所に置くべきとされています。暗く湿度が高い場所やトイレに近い廊下などは避け、太陽の光が入りやすく明るい部屋を選んで神棚を祀るようにしましょう。また、家族が集まりやすく毎日お参りしやすいところを選ぶのもポイントです。
建物の最上階
平屋以外の家に住んでいる場合は、建物の最上階に神棚を設置しましょう。神様を見下ろす形になる場所や、人が上を通る部屋などは避けるべきとされています。住宅の事情により最上階に神棚を配置するのが難しい場合は、「雲」「天」「空」と書かれた紙や彫刻を神棚の真上に貼りましょう。文字の書かれた紙ではなく、空や雲の写真・イラストで代用することも可能です。こうすることで「ここよりも上は天である」と考えられ、最上階に神棚を置けなくても失礼にはなりません。
神棚を置く方角・向き
神棚を祀る方角は、太陽が昇る東向きか、太陽が昇ったときに真っ先に光が入る南向きが適切だと考えられています。神棚に太陽の光を見せるように、自宅の西側か北側の壁に設置するのがおすすめです。ただし、直射日光が当たる場所は神棚が傷んでしまうため避けましょう。
仏壇を置くのに適した場所・方角・向き

神棚と同じく、仏壇を置く際も場所や方角、向きなどに注意する必要があります。ここからは仏壇の置き場所や方角について解説していきます。
仏壇を置くのに適した場所
仏壇は、和室や寝室、リビングなどに飾られることが多いです。それぞれの部屋が仏壇の置き場所として適している理由を詳しく紹介します。
和室
仏壇の置き場所として適しているのが和室です。自宅の和室に床の間や仏間がある場合、その部屋に置いて祀るのが最適でしょう。
床の間は古くから「ご先祖やご本尊を祀るための部屋」とされており、香炉や掛け軸が置かれていました。さらに、床が一段高い床の間は「自宅の中でも格式の高い場所」とされているため、仏壇の置き場所として最適です。床の間や仏間がない場合は、和室の一角に仏壇を設置しても問題ありません。
寝室
自宅に和室がない場合、寝室に仏壇を置くのもおすすめです。寝室は必ず人が出入りするため、忘れずに仏壇に手を合わせられます。また1日の始まりと終わりにゆっくり手を合わせられるという点でも仏壇を置くのに適しています。
ただし、寝るときに足が向く方角に仏壇を配置するのは、ご本尊やご先祖に対して失礼に当たりますので注意が必要です。
リビング
自宅に和室がなかったり、寝室に仏壇を置くスペースがなかったりする場合は、リビングに仏壇を置くのもよいでしょう。リビングは生活の中心であるため、家族が揃って手を合わせやすいのが特徴です。リビングに仏壇を置くことで、ご本尊やご先祖を供養することを忘れる心配がなくなります。
仏壇を置く方角・向き
仏壇を置く方角や向きにはさまざまな説があり、宗派によって設置する方角が異なるとされています。ここからは仏壇を置く方角を紹介します。
西方浄土説
仏壇を置く方角として「西方浄土説(さいほうじょうどせつ)」という説があります。これは、「仏様がいらっしゃる極楽浄土は西側にある」という考え方です。西方浄土説では仏壇を東向きに置き、極楽浄土がある西側に向かってご先祖やご本尊を拝みます。
南面北座説
仏壇を置く方角として、「南面北座説(なんめんほくざせつ)」という考え方もあります。これは、「目上の人は南向きに座る」という考え方に由来しています。南面北座説では、仏壇を部屋の北側の壁に沿って南向きに置き、北の方角にお参りする形になります。
春夏秋冬説
「春夏秋冬説(しゅんかしゅうとうせつ)」とは日本の四季と東西南北を結びつけた置き方で、以下のような表しがあると言われています。
春夏秋冬説の表し
- 東(春):万物の始まり
- 南(夏):実を結ぶこと
- 西(秋):収穫の時期
- 北(冬):物事を収めること
春夏秋冬説では、どの方角もなくてはならない大切なものであるため、仏壇をどの方向で祀っても問題ないとされています。自宅の事情に合わせて、設置しやすい方向で置いて構いません。
本山中心説
仏壇の置き方として、「本山中心説(ほんざんちゅうしんせつ)」というものもあります。これは、自身が信仰している宗派の総本山を拝めるよう、総本山がある向きに仏壇を配置する方法です。この説では、自宅と総本山の位置関係によって配置する方角が変わります。
神棚と仏壇を一緒に置くときの注意点

神棚と仏壇は一緒に置いても問題ないとされていますが、配置する際はいくつか注意しなくてはいけないポイントがあります。
向かい合わせで置かない
神棚と仏壇を一緒に置く場合、向かい合わせで置かないよう注意してください。向かい合わせで配置するのは「対立祀り」と呼ばれ、災いを招くとされているためです。
上下に配置するのは避ける
仏壇の真上に神棚を置くなど、上下に配置するのも避けましょう。上下に置くことで神様と仏様に優劣をつけてしまい、どちらに対しても失礼になると考えられているためです。
仏壇や神棚を置くのに向かない場所

ここからは、神棚や仏壇を置くのに不向きな場所を解説していきます。
神棚の場合
神棚は、汚れやすい場所やトイレ周り、キッチンや風呂場などの水回りには置かないようにしてください。これは、神様が穢れを嫌うためという理由です。また、廊下付近やドアの上など、頻繁に家族が出入りする場所も避けた方が無難です。
仏壇の場合
仏壇は、傾いている床や台には置かないようにしましょう。傾きが激しい場所に置くと、仏壇が破損したり変形したりする恐れがあるためです。また、仏具や金具が錆びたり変色したりする原因になるため、硫黄や塩分のある場所に置くのも避けてください。
神棚と仏壇を置く際は方角や場所注意しましょう

この記事のまとめ
- 神棚と仏壇は信仰とする対象が異なる
- 神棚と仏壇を一緒に置いても問題ない
- 神棚は、明るく清潔な場所や建物の最上階に、東か南向きで置くとよい
- 仏壇は和室や寝室、リビングなどに置くのがおすすめ
- 仏壇を置く方角には、西方浄土説、南面北座説、春夏秋冬説、本山中心説などの考え方がある
- 神棚と仏壇を一緒に置くときは、上下や向かい合わせで配置しないようにする
- 神棚を置く際は汚れやすい場所や水回りは避け、仏壇は傾きがない場所に置く
神棚は神道の神様を、仏壇は仏教における仏様やご先祖を祀るためのものであり、信仰対象が異なります。宗教が異なるため「一緒に置くべきではないのでは?」と思う方も多いですが、一緒に置いても問題ありません。ただし、神棚と仏壇を一緒に置く場合はいくつか注意点があるため、本記事を参考にしてください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。