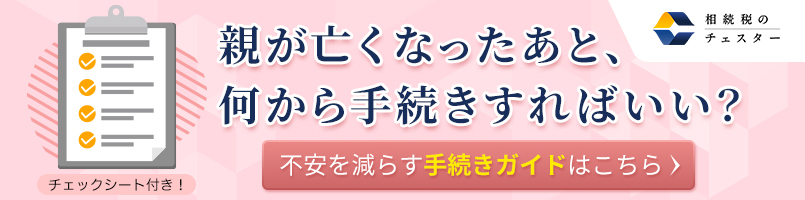遺品整理は四十九日の前にしてもよい?早めに整理するメリットや方法を解説

「遺品整理はなるべく早めに取り掛かった方がよい」とよくいわれますが、四十九日法要前に行っても問題ないのでしょうか?本記事では、遺品整理を四十九日前に行ってよいのかや、早めに取り組むメリットを紹介します。遺品整理をスムーズに進めるコツもまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
四十九日前に遺品整理をしてもよいのか

仏教においては四十九日法要を迎えるまでは「忌中」といわれ、結婚式への参列や旅行といったさまざまなことが制限されます。そのため、「四十九日までは遺品整理をやらない方がよいのでは?」と考える人もいらっしゃるでしょう。
しかし、仏教の教えにおいては、四十九日前に遺品整理をしてもよいとされています。故人が現世を彷徨っている四十九日の間に遺品整理をすることで、故人の心残りを断ち切れるとも考えられています。故人の冥福を祈るという意味でも、なるべく早めに遺品整理を行いましょう。
遺品整理を早めにするメリット

一般的に「遺品整理は早めに始めるとよい」といわれていますが、どのような理由があるのでしょうか。ここからは、早めに遺品整理に取り組むメリットを紹介します。
出費が減る
遺品整理を早めに行うと、出費が減るというメリットがあります。亡くなった人が賃貸住宅に暮らしていた場合、遺品整理が終わるまでは退去できないため、家賃などを払い続けなくてはいけません。
その他、スマートフォンやネットサービスの利用料などもかかってしまいます。早めに遺品整理を行い手続きを進めておくと、これらの出費を削減できます。
心の整理がつく
遺品整理をすることで心の整理がつくことも、メリットの一つです。遺品整理を先延ばしにしていると、相続や各種手続きなどもなかなか進まず、心が落ち着きません。
遺品整理に取り組むことで、不安が軽減されてゆっくり故人と向き合えるようになるでしょう。
忌引休暇で遺品整理を行える
忌引休暇を使用して遺品整理ができることも、早い時期に遺品整理に取り組むメリットです。両親や祖父母などの身近な人が亡くなった場合、忌引休暇を取得できます。
まとまった時間が取れるため、普段仕事が忙しい人でもスムーズに作業を進められるでしょう。
四十九日法要で遺品を形見分けできる
四十九日前に遺品整理を行うと、法要の際に遺品を形見分けできます。四十九日法要には、家族や親戚など故人との関係が深かった人が集まります。前もって遺品整理を行って、故人の思い出の品を見つけておくと、法要で親族が揃ったときに遺品を分けられます。親戚のもとに赴いて遺品を渡す必要がなくなり、手間が省けるでしょう。
形見分けを行う場合、どの遺品を誰に渡すか事前に書き出しておきましょう。家電や家具などは引き取りたい人がいないか確認し、譲渡前に手入れをすませておくことをおすすめします。衣服などを形見分けとして渡す場合はクリーニングをすませておきましょう。
四十九日前に遺品整理を行う際の注意点

遺品整理は四十九日前にしてもよいとされていますが、いくつか注意点があります。ここからは、四十九日前に遺品整理を行う際の注意点を解説しますので、作業前に確認しておきましょう。
他の遺族の同意を得る
四十九日前に遺品整理を行う場合、他の遺族の同意を得るようにしましょう。他の親族に何も伝えないまま勝手に遺品整理を進めると、「何か遺品を持ち出したのかも」「なぜ知らせてくれなかったのか」など、トラブルの原因になってしまいます。
親族と揉めることのないよう前もって遺族間で遺品整理について話し合い、全員の同意を得るようにしましょう。
相続放棄ができなくなることがある
遺品整理を行った場合、相続放棄ができなくなる恐れがあるため注意が必要です。遺品整理を行うと、故人の借金や財産の相続を認めたと判断されてしまいます。遺産を受け取れる一方、借金や負債も相続することになるため、相続放棄を検討している場合は十分注意してください。
大切なものを捨てないよう注意する
自分で遺品整理を行う場合、貴重品や大切な書類などを処分しないように注意しましょう。例えば、銀行口座といった金融関係の情報や、不動産の権利書、税金関係の書類などが挙げられます。これらの書類を誤って処分してしまうと、書類の再発行のために複雑な手続きを行わなければいけません。
また、遺産としての価値が高いものを処分してしまった場合、家族や親族とトラブルになる恐れがあります。自分ひとりで遺品整理を進めるのは避け、周りの家族や親戚と相談しながら整理を行いましょう。
遺品整理を行う方法

実際に遺品整理を行う場合、どの作業から着手すればよいのか迷ってしまうものです。ここからは遺品整理を行う方法や手順について詳しく解説しますので、作業の段取りを決める際の参考にしてみてください。
現場の様子を確認する
まず、遺品整理が必要な現場の様子を確認しましょう。どこの部屋から着手するべきか、不用品やゴミなどはどのくらい出るかなどを確認し、作業の段取りを決めてください。
他の親族と共に遺品整理を行う場合、一緒に作業を行う人と現場の状況を確認しに行くとよいでしょう。現場の状況を見た後は、整理時に必要になりそうな道具を準備して作業に備えます。
遺品整理をする時期を決める
現場の状況を確認できたら、遺品整理に取り組む時期を決めましょう。故人が賃貸物件に住んでいる場合、なるべく早めに遺品整理に取り掛かる必要があります。親族と予定が合う日を話し合い、片付けの日程と段取りを決定しましょう。
捨てるもの・残すものに分類する
遺品整理では、まず捨てるもの・残すものに分類します。故人との思い出が深いものや自分で使うもの、貴重品、写真などは残すものに分けましょう。
使用しないものやもう使えない家電などは処分するものに分類してください。処分するべきか判断できないものは一度保管しておき、他の家族と相談して決めましょう。
リサイクル品を仕分けする
処分するものの中から、リサイクル品を仕分けます。リサイクルショップに不用品を持ち込むと、処分費がかからない上に買い取ってもらえる場合があります。
リサイクルショップに持っていく時間がない場合、出張買取サービスやインターネットオークション、フリマアプリなどを利用するのもおすすめです。
不用品を処分する
リサイクルショップやフリマアプリで売れないものは、ゴミとして処分します。ゴミは燃えるゴミ・燃えないゴミ・リサイクルできるものなどに分け、自治体の回収サービスを利用して捨てると効率良く片付けられます。
機械類や大きな家具、家電などの処分方法が分からないものは、専門業者に相談するとよいでしょう。
清掃を行う
遺品を整理し終えたら、部屋の清掃を行います。故人が賃貸物件に住んでいた場合、原状回復を意識して掃除をしましょう。天井や壁など掃除が難しい場所は、専門業者に作業を依頼するのがおすすめです。
遺品整理をスムーズに進めるコツ

遺品整理ではさまざまな作業を行わなくてはいけないため、なかなかスムーズに整理が進まず悩む人も多いです。作業が思うように進まない人は、以下に紹介する遺品整理を進めるコツを参考にしてみてください。
複数人で作業を行う
遺品整理をなるべくスムーズに進めたい場合、複数人で作業に取り組むとよいでしょう。遺品整理をひとりで行う場合、荷物の量にもよりますがかなりの手間や時間がかかります。肉体的にも精神的にも負担が大きくなる上、親族とトラブルに発展する恐れもあります。
複数人で遺品整理を行うと、遺品を仕分ける人やゴミを処分する人、貴重品を探す人といったように作業を分担することができ、片付けをスムーズに進められるのでおすすめです。また、複数人であれば、貴重品を誤って処分してしまうリスクも減らせるでしょう。
業者に依頼する
不用品の処分や買取などを業者に依頼するのもおすすめです。大きく重たい家具や家電などは、捨てるのもリサイクルショップに持ち運ぶのも手間がかかります。専門の業者に処分を依頼することで、大幅に時間を節約できるでしょう。
重要な書類や貴重品を先に探す
遺品整理をスムーズに進めるコツとして、重要な書類や貴重品を先に探しておくことが挙げられます。故人の意向を確認するためにも、まずはエンディングノートや遺言状などがあるかを確認しましょう。
また、土地の権利書や銀行の通帳、健康保険証など死後の手続きに必要なものも回収しておくと後の作業が楽になります。先に貴重品を探しておかないと、遺品整理の作業中にうっかり捨ててしまうリスクが高くなるため注意が必要です。
遺品整理にはなるべく早めに取り掛かりましょう

この記事のまとめ
- 四十九日前に遺品整理をしても問題ない
- 早めに遺品整理に取り掛かかるメリットは、①出費が減る②心の整理がつく③忌引休暇を利用できる④四十九日法要で遺品を形見分けできる
- 四十九日前に遺品整理を行う場合は必ず他の遺族の同意を得て、大切なものを捨てないよう注意する
- 遺品整理を行うと相続放棄ができなくなる恐れがあるため注意する
- 自分でできない作業は、遺品整理業者に依頼するのもおすすめ
四十九日前に遺品整理を行うことで、故人への心残りを断ち切れるとされています。費用や手続きの面からも、四十九日前に遺品整理に取り掛かるとよいでしょう。今回紹介した遺品整理の手順やスムーズに進めるコツ、注意点などを参考にして、遺品整理を進めてみてください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。