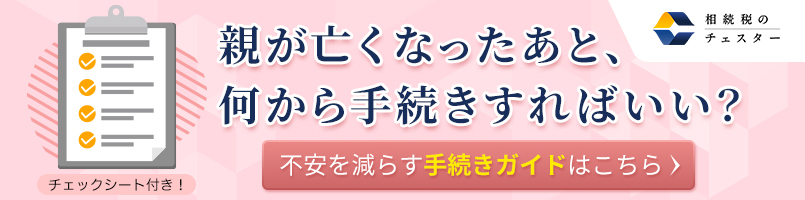墓石に刻む文字は?費用や書体などもあわせて紹介

墓石には名前や言葉が刻まれているのが一般的ですが、これらの文字には決まりはあるのでしょうか?本記事では、墓石に刻む文字の例を和洋それぞれに分けて紹介します。文字を彫る際にかかる費用や書体などもまとめています。参考にしてみてください。
墓石に刻む文字は決まっている?

墓石の「竿石」という部分には、文字が刻まれていることがほとんどです。宗教や墓石の種類によって使われることが多い文字はあるものの、墓石に刻む文字には明確な決まりはありません。どのような文字を入れるか、文字を入れる位置・彫り方などは自由に選べます。
和型墓石に刻む文字の例

和型墓石とは伝統的な日本の墓石の形で、一般的に石材を組み合わせた重厚感のあるデザインが特徴です。多くの場合、縦長の碑体に故人の名前や戒名を刻むスタイルが用いられます。基本的に墓石に刻む文字の種類に決まりはありません。しかし、和型墓石の場合は決まった文字を刻むことが多いです。ここからは、和型墓石に刻まれることが多い文字の例を紹介します。
家名
和型墓石には、家名が刻まれることが多いです。家名とは、「○○家先祖代々之墓」や「○○家」といった文字を指します。家名を入れることは家族のつながりを示すだけでなく、代々続く家系の歴史や絆を表す大切な意味があります。これらの家名は、最も目に入りやすい墓石の正面に彫るのが一般的です。
また、家名の彫り方や宗派によって異なります。例えば、禅宗の場合は家名の前に「〇」(円相と呼ばれる記号)を書くことがあります。真言宗や天台宗では、家名の前に「大日如来」を意味する梵字の「阿字」(「ア」ではなく梵字の形)という文字が刻まれます。
俗名
墓石に刻む文字の例として、俗名が挙げられます。俗名とは、故人の生きている時の名前のことです。宗教上の理由などで戒名を授からない場合は、戒名の代わりに俗名を刻むことがあります。
戒名・法号・法名
戒名や法号、法名も、墓石に刻まれることが多いです。戒名や法号、法名とは、故人が亡くなった後に与えられる名前のことを指します。本来は、生前に仏門に入った人に対して与えられるものでしたが、現在は逝去後に僧侶から与えられるのが一般的です。これらの文字を墓石に刻むことで、故人の成仏を願います。
没年月日・享年
墓石の側面には、没年月日や享年を入れることが多いです。没年月日は故人の命日のことで、和暦で刻まれるのが一般的です。享年とは、故人が亡くなった際の年齢であり、数え年で数えられます。
題目
お墓の側面には、題目が刻まれることもあります。題目とは、仏教のうち一部の宗派で勤行の際に唱えられる言葉のことです。宗派によって題目の内容は異なり、真言宗では「南無大師遍照金剛」、天台宗や浄土宗では「南無阿弥陀仏」、日蓮宗では「南無妙法蓮華経」となります。熱心な仏教徒だった方のお墓には、これらの題目が刻まれることがあります。
格言
墓石に刻まれる文字の例として、格言が挙げられます。故人が生前気に入っていた格言を入れることで、故人の人柄を表すことができます。格言は墓石の正面ではなく、側面や背面に刻まれることが多いです。
洋型墓石に刻む文字の例

洋型墓石とは、主に近代以降に日本で広まった西洋風の墓石で、比較的シンプルな形状が特徴です。従来の和型墓石と比べてデザインの自由度が高く、家名や戒名などの文字を刻むことが一般的です。
ここからは、洋型墓石に刻まれることが多い文字の例を紹介します。どういった文字を刻むことが多いのか知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
家名・戒名
洋型墓石でも、和型と同様に「〇〇家之墓」などの家名を刻むことが一般的です。また、故人の戒名や没年月日、生没年、俗名を刻むこともあります。複数人が入るお墓の場合には、それぞれの戒名を追加で彫刻するケースもあります。
文章
洋型墓石に刻む文字の例として、文章が挙げられます。洋型墓石は横に長いデザインが多いため、10文字程度の文章を刻むことが可能です。「ありがとう」「楽しかった」など、好きな言葉を刻みましょう。遺族から故人に対する言葉でもよいですし、故人の立場からの言葉を刻むのもおすすめです。
熟語
洋型墓石の場合、熟語を刻むことも多いです。故人が好きだった言葉や、故人の人柄を表すものなど、どのような熟語を選んでも問題ありません。例えば、「永遠」や「花鳥風月」などがあります。故人の希望があった場合は、その熟語を刻むことをおすすめします。
漢字1文字
洋型墓石の正面に、漢字1文字を刻むこともあります。「愛」「和」「光」など明るい意味を持つものや「空」「風」「海」といった自然を表す文字、「祈」「想」「念」などの故人をしのぶ言葉が彫刻される傾向にあります。
墓石に刻む文字の書体

墓石に刻まれる文字の書体に明確な決まりはなく、自由にデザインを決められるのが特徴です。ここからは、墓石によく使用される書体をご紹介します。ご遺族の意向や故人の希望に合わせて、どういった書体にするか検討してみてください。
楷書体
墓石の文字を刻む際によく使用されるのが、楷書体という書体です。楷書体は、文字を崩さずに、「とめ・はね・はらい」などをきちんと書くのが特徴です。読みやすく、和型・洋型を問わず墓石にふさわしい書体といえます。
ゴシック体
ゴシック体は、洋型墓石で使用されることが多い書体です。くっきりとした分かりやすい文字で、遠くから見た時によく目立ちます。
行書体
行書体とは、楷書体を崩したような雰囲気を持つ書体です。楷書体に比べて文字に丸みがあり、柔らかい印象を与えます。
隷書体
隷書体も、墓石に刻まれる文字に使用されることが多い書体です。隷書体はほかの文字に比べて少し横に長く、平たい形状という特徴があります。字の形がハッキリしているため、遠くからでも非常に読みやすい書体です。
草書体
草書体とは、行書体や楷書体を崩したような形状が特徴の書体です。文字を早書きする際に生まれた書体とされており、字画が省略されることも多いです。筆を流すように書くため、ほかの書体に比べて躍動感があるのが特徴です。
墓石の文字入れにかかる費用

墓石の文字入れにかかる費用は、彫刻の仕方や文字の彩色の有無、模様などによって異なります。こちらで紹介する費用を参考にして、どういったデザインにするか検討してみてはいかがでしょうか。
基礎彫刻
お墓を新しく建てる際は、家名や戒名・題目といった基礎彫刻を行います。基本的な文字彫りの相場は5万円~15万円です。どのような文字を刻むかによって費用が異なるため、見積もりの際に確認しておきましょう。
追加彫り
既にあるお墓に追加で文字を彫刻する場合、相場は3万円~5万円です。追加彫りに伴って墓石を移動させる必要がある場合は、先に魂抜きの儀式を行う必要があります。魂抜きを行う場合は、お寺へのお布施として3万円~5万円を準備しておきましょう。
また、彫刻が終わって再び墓石を元に戻す際には、魂入れも必要となります。こちらも3万円~5万円のお布施が発生するため、事前に準備しておいてください。
文字の彩色
故人や遺族の希望がある場合は、お墓に刻んだ文字に色を付けることも可能です。お墓に刻んだ文字を彩色する場合の価格は、1万円~3万円が目安です。
なお、生前に建てたお墓の場合、戒名や名前を朱色で刻むことがあります。これは「まだ生きていること」を意味し、没後に黒や白に塗り直す場合もあります。朱文字の扱いや塗り直しの時期については、墓石業者や寺院と事前に相談しておくと安心です。
模様の彫刻
文字以外にお墓に模様を入れる場合の価格は、10万円~20万円とされています。既に建立されているお墓に新しく模様を刻む場合は、5万円~15万円が相場です。模様を彫刻する場合、彫り方や位置、デザインによって価格が大きく変動します。前もって見積もりを出してもらい、予算内に収まるかどうか確認しましょう。
文字の削除
墓石に刻まれた文字を消す場合の価格は、方法によって異なります。石を削って文字を消す場合の価格は20万円~50万円です。文字の範囲や彫りの深さなどによって、価格は大きく異なります。文字をパテで埋めて消す方法は、1文字当たり1万円~3万円かかります。
墓石の文字の彫り方

墓石の文字の彫り方には、通常彫りや影彫り、線彫りなど複数の種類があります。彫り方によってそれぞれ特徴があり、文字の雰囲気や見え方などが異なります。お墓のデザインにこだわりたい方、故人の希望に合った墓石にしたい方は、彫り方ごとの違いも押さえておくとよいでしょう。
通常彫り
通常彫りは、お墓に文字を刻む際の一般的な彫り方です。文字を深くしっかり彫るのが特徴で、立体的かつ力強い印象に仕上がります。
また、彫刻の際には書道の筆致を意識し、線の太さや角度に強弱をつけることで、より美しく格調高い仕上がりになるのも特徴です。単に文字を刻むだけでなく、筆で書いたような流れや重みが再現されるため、職人の技術が仕上がりに大きく影響します。
影彫り
影彫りとは、点で文字を彫っていくという彫り方です。高度な技術が求められる彫り方であり、影彫りができる職人も限られているため、費用は高額になります。お墓のデザインにこだわりたい、芸術的な仕上がりにしたいという方におすすめの方法です。
線彫り
線彫りとは、薄い線を何本も入れて輪郭のみを彫るという方法です。線が多い分墓石のお手入れをする際の手間がかかりますが、その分個性的な仕上がりになります。文字はもちろん、模様やイラストを入れる際にも使われる彫り方です。
霞彫り
霞彫りは、文字の内側を彫りこまない代わりに輪郭をくっきりと彫る方法です。彫った後、文字にサンドブラストを吹き付けて仕上げるのが特徴で、他の彫り方に比べて高級感を演出できます。
浮き彫り
浮き彫りは、文字が浮かんでいるような仕上がりになるのが特徴です。文字自体を彫るのではなく、文字の周囲を彫ることで文字を浮き上がらせる技法です。立体感があり印象的な見た目になるため、文字はもちろん模様やイラスト、家紋を彫る際にも使用されます。
ただし、墓石の種類や状態によっては浮かし彫りができない場合もあるため、事前に確認が必要です。
墓石の文字を選ぶ際の注意点

墓石に刻む文字は基本的に自由に決められますが、覚えておきたい注意点もいくつかあります。ここからは、墓石の文字を選ぶ際の注意点について解説していきます。
不適切な言葉は避ける
まず不適切な言葉を使わないよう注意しましょう。不吉な言葉や忌み言葉などは、お墓参りに訪れた方を不快にさせる可能性があります。周囲への配慮を忘れず、刻む文字を決めるようにしましょう。
霊園や寺院の意向を確認する
墓石に刻む文字を決める際は、霊園や寺院の意向を前もって確認しておきましょう。霊園や寺院によってはお墓の文字やデザインに規制があることがあります。あらかじめデザインが決められている場合もあるため、墓地の契約前に確認しておくことが大切です。
言葉の著作権に注意する
言葉を墓石に刻む際は、著作権にも注意が必要です。例えば、故人が好きだった曲の歌詞を墓石に刻む場合は、その曲の著作権に配慮しなくてはいけません。トラブルを防ぐためにも、商標や著作権に問題はないかを確認してください。
書体や彫り方、価格を踏まえて墓石に刻む文字を決めましょう

この記事のまとめ
- 墓石に刻む文字に決まりはなく、基本的には自由に文字を決められる
- 和型墓石には、家名や俗名、没年月日、戒名、題目などが刻まれる
- 洋型墓石には、文章や熟語、漢字一文字を刻むことが多い
- 墓石に刻む文字の書体は、楷書体、ゴシック体、行書体、隷書体、草書体が選ばれる
- 墓石の文字入れにかかる費用は、彫刻の仕方や文字の色などによって異なる
- 墓石の文字の彫り方には、通常彫りや影彫り、線彫り、霞彫り、浮かし彫りなどがある
- 霊園や寺院の意向を確認し、言葉の著作権や不適切な言葉に注意する
墓石に刻む文字に明確な決まりはなく、故人や遺族が自由に文字を決められます。本記事で紹介した書体や彫り方、費用などを参考にして、どのような文字を墓石に刻むか検討してみてください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。