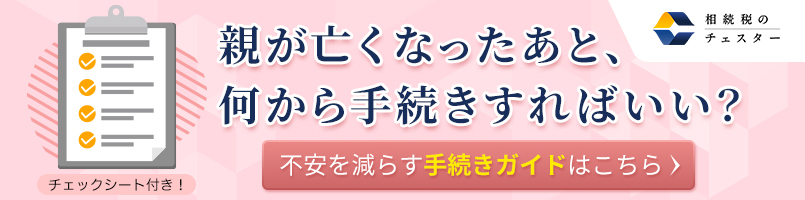弔問の手土産はどうする?選び方から渡し方までを解説

故人やご遺族の自宅へ弔問に伺う際、手土産を持参するべきかどうか迷う方も多いのではないでしょうか。本記事では、弔問時には手土産を持参するべきかどうかや、品物の選び方、おすすめの品物について解説します。渡し方のマナーもまとめているため、参考にしてみてください。
弔問に手土産は必要?

弔問の際、必ず手土産を持参しなくてはいけないという決まりはありません。しかし、お供え物として故人が好きだったものやお菓子などを手土産として渡すことで、故人への哀悼の気持ちやご遺族への気遣いの心を表すこともできるでしょう。そのため、弔問の際は多くの方が手土産を持参されています。
弔問の手土産の選び方

弔問の際に持参する手土産は、形式にとらわれず、故人を偲びご遺族の心情に寄り添う気持ちを込めたものを選ぶことが大切です。ここでは、弔問の手土産の選び方を紹介します。
ご遺族の負担にならないものを選ぶ
弔問の場では、ご遺族は心身ともに疲れていることが多いため、管理や保存に手間がかからないもの、置き場所を取らないものを選ぶと配慮が伝わります。大きすぎる物や扱いに困る品は避けましょう。
故人の好みに合わせて選ぶ
故人の好みに合わせるという選び方もおすすめです。生前故人が好んでいた食べ物や飲み物、花を手土産にすることで、故人への弔意を表せます。故人が好きだったものを受け取ったご遺族が、故人との日々を思い出すきっかけにもなるでしょう。
もし故人の好みが分からない場合は、ご遺族の家族構成や好みなどに合わせて手土産を選ぶのが無難です。
日持ちし、個包装されているものを選ぶ
弔問の際に食品を手土産として選ぶ場合は、日持ちするものを選びましょう。ご遺族は葬儀後の対応で多忙なことが多く、すぐに消費できるとは限りません。賞味期限が長く、常温で保存できるものは扱いやすいため、負担をかけにくい配慮になります。
また、個包装されている食品であればご遺族同士で分けやすく、少しずつ無理なく食べられるため、衛生面・実用面でも優れています。一人暮らしや高齢の方にも安心して受け取ってもらえるでしょう。
控えめで上品な包装を選ぶ
弔問の手土産は、華やかな包装ではなく、落ち着いた色味と簡素で品のある体裁を意識しましょう。白やグレー、淡い茶系などの落ち着いた色合いの包装紙や紙袋が適しています。過度な装飾やリボンは避け、控えめな印象を大切にすることが、ご遺族への思いやりにもつながります。包装に迷った場合は、仏事に対応している店舗に相談するのも安心です。
弔問の手土産に不適切な品物

ここからは、弔問の手土産には不適切な品物を紹介します。不適切な品物を弔問に持参するのは、故人やご遺族に対して失礼にあたります。弔問に伺う前に、手土産として持参するべきではないものを確認しておくと安心です。
派手なデザインのもの
弔問の手土産に不適切な品物として、派手なデザインのものが挙げられます。葬儀やお通夜、法要といった仏事には、落ち着いた色味のものが適しています。明るく派手な色味の品物は慶事を連想させるため、弔事ではなるべく避けるのが無難です。
壊れやすいもの・割れ物
壊れやすいものや割れ物も、弔問時の手土産には持参しない方が無難です。壊れやすい割れ物は、故人の自宅に伺う前に破損してしまう恐れがあるためです。陶器やガラス容器といったものも場所を取る上、ご遺族が捨てにくいと感じてしまうこともあるため、避けた方がよいでしょう。
忌み言葉に関するもの
忌み言葉に関係するものも、弔問時の手土産としては不適切です。例えば「4」や「9」は死や苦しみをイメージさせる不吉な数字とされています。4個や9個入りのお菓子や、これらの数字が名前に入っている品物は避けてください。
傷みやすいもの
手土産として食べ物を自宅に持参する場合は、傷みやすいものは避けてください。手土産を受け取ったご遺族が、その品物をすぐに食べるとは限りません。すぐに傷んでしまうものだと、ご遺族の口に入る前に賞味期限が切れてしまう可能性があります。
また、傷みやすいものを手渡した場合、「早くいただかなくては」とご遺族を焦らせることになりかねません。食べ物を手土産として持参する場合は、なるべく長持ちするものを選びましょう。
弔問の手土産におすすめの品物

ここからは弔問の手土産におすすめの品物を紹介します。具体的にどのような手土産がご遺族の負担にならないか知りたい方は、下記で紹介する品物を参考にして持参するお供え物を選んでみてください。
お菓子
弔問の手土産におすすめの品物として、お菓子が挙げられます。和菓子の場合はお饅頭や羊羹、おせんべい、どら焼きなどが選ばれる傾向にあります。洋菓子の場合は、クッキーやフィナンシェ、マドレーヌといった焼き菓子が定番です。
線香
線香も、弔問時の手土産におすすめしたい品物です。使用頻度が高いため、手元にあって困るものではなく、実用的な品として受け取っていただきやすいでしょう。香りの強さや煙の量などに配慮し、故人やご遺族の好みに合うものを選ぶのが望ましいです。
果物
果物も、弔問時の手土産に適した品物です。特に、梨やりんご、メロンなどの比較的保存しやすいものや、果物の盛り合わせなどが適しています。また、故人が生前好きだった果物や、季節のフルーツなども好まれます。一種類のフルーツではなく、果物の盛り合わせも人気です。
ただし、すぐに傷んでしまうものや常温保存が難しいもの、香りが強いものなどは避けた方がよいでしょう。
飲み物
お茶やコーヒー、紅茶などの飲み物も、ご遺族の負担になりにくく、気遣いが伝わる品としてよく選ばれます。小さいお子様がおられるご家庭には、ジュースを持参するのもおすすめです。
お花
生花も、故人への敬意を込めて贈る品としてふさわしい選択です。白を基調とした落ち着いた色合いの花を選ぶのが一般的ですが、故人の好みに配慮して淡い色味を取り入れることもあります。
花の種類は、菊、百合、胡蝶蘭、カーネーションなどが選ばれることが多いです。トゲのある花や香りの強すぎる花、毒を持つ植物は避けましょう。
弔問の手土産の渡し方

ここからは、弔問の手土産の渡し方について解説していきます。「手土産はどのタイミングで渡せばよいのか分からない」「手土産を渡す時、どのような挨拶をすればよいのだろう」などの疑問がある方は、ぜひこちらに目を通してみてください。
渡すタイミング
弔問した際に持参した手土産は、故人の自宅の玄関で渡すのが一般的です。この時、手土産は紙袋から出して相手に表書きが見える向きに持ちます。表書きとは、熨斗紙の上部に記される「御供」や「志」など、品物の用途や名目を表す文字のことです。相手が読みやすいように正面を向けて、両手で丁寧に差し出しましょう。
玄関先で手土産を渡すタイミングがなかった場合は、自宅の中でご遺族と軽く話をした後でも構いません。この時、勝手に仏壇へ品物を供えるのはマナー違反となるため注意が必要です。
渡す際の挨拶
手土産をご遺族に渡す際は、一言挨拶をするのが基本的なマナーです。「ささやかなものですが、どうぞお納めください」「○○様の御仏前にお供えください」と言葉を添えながら、品物を手渡ししましょう。
弔問の手土産の相場
弔問の手土産の金額相場は、3千円~8千円とされています。親族や近親者、友人、知人、職場関係者には3千円~5千円、恩師や親友といった特に親しい関係の相手には5千円~8千円の手土産を用意しましょう。1万円を超える品物を渡すと、ご遺族に気を遣わせてしまい負担になる恐れがあります。相手との関係に合わせた相場でお供え物を準備することが大切です。
弔問へ行く際の注意点

お通夜・葬儀の前後や法要などで弔問に行く際、いくつか注意しなくてはいけないポイントがあります。ここからは、弔問へ訪れる際の注意点を詳しく紹介します。ご遺族の負担にならないためにも、弔問の際の注意点をしっかりと押さえておきましょう。
長居はしない
弔問へ行った際は、長居しすぎないよう注意が必要です。特に故人が亡くなって間もない頃だと、ご遺族は精神的に疲弊している可能性があります。長々と居座るのは相手の負担になるため、できるだけ10分~15分ほどで切り上げましょう。
連絡なしで弔問するのは避ける
ご遺族に連絡をせず、いきなり弔問するのは避けてください。ご遺族にも事情や予定があるため、突然の弔問は迷惑になる可能性があります。事前に弔問に伺いたい旨を伝え、ご遺族の都合を確認してから日時を決めるようにしましょう。
派手な服装は避ける
弔問へ伺う際は、派手な服装は避けてください。故人が亡くなって、ご遺族は深い悲しみの中におられます。ご遺族の気持ちを汲み取り、ダークグレーやブラックなどの落ち着いたデザインの服で弔問しましょう。
葬儀に参列していない場合は香典を渡す
葬儀に参列できていない場合は、手土産と一緒に香典も渡しましょう。香典の金額は、3千円~1万円が相場とされています。ただし、前もってご遺族から香典を辞退したいと連絡を受けていた場合は、香典を持参する必要はありません。
作法を守って線香をあげる
弔問の際は、故人の仏壇に向かって線香をあげます。仏教の基本的な作法に倣って線香をあげましょう。ただし、宗派によって少しずつ作法が異なるため、事前に確認しておくと安心です。
弔問する際は、ご遺族や故人への心遣いが伝わる手土産を持参しましょう
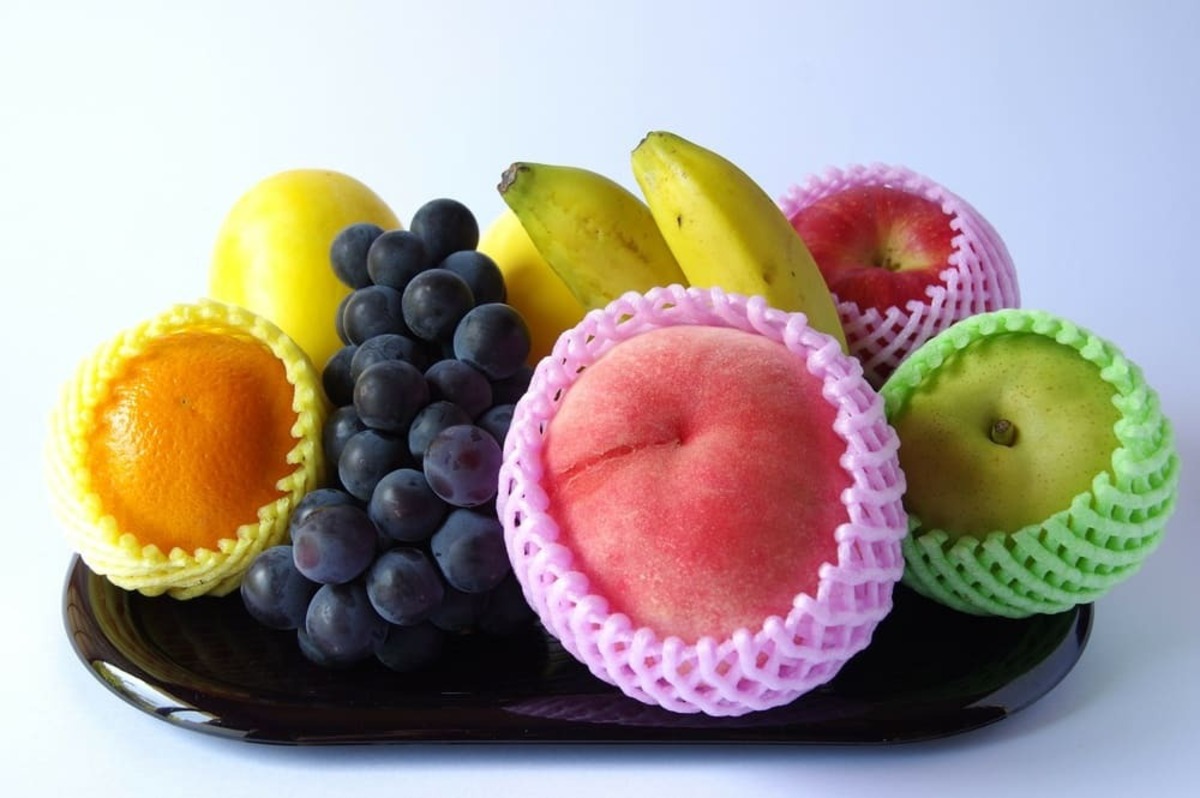
この記事のまとめ
- 弔問に行く際は、故人を想って手土産を用意するとよい
- 弔問の手土産には、ご遺族の負担や故人の好みを考え、日持ちして個包装されているものや控えめで上品な包装を選ぶ
- 派手なデザインのものや壊れやすい割れ物、忌み言葉に関するもの、傷みやすいものは弔問の手土産には不適切
- 弔問の手土産としておすすめなのが、お菓子や線香、果物、飲み物、お花など
- 弔問の手土産を渡す際は、渡すタイミングや挨拶に注意が必要
- 弔問の際は、長居はしない、連絡なしで弔問しない、派手な服装は避けるといったマナーに注意する
弔問の手土産は、形式ではなく「心を寄せる気持ち」を形にしたものです。何を選ぶか以上に、どのような気持ちで相手に渡すかが大切です。ご遺族が受け取りやすく、故人を静かに偲ぶことができる品を、慎み深く選ぶようにしましょう。
また、手土産を持参する際は、相手の状況や心情を思いやり、控えめで丁寧な振る舞いを心がけることも大切です。小さな配慮が、ご遺族の心の支えになることもあるかもしれません。本記事で紹介した渡し方のマナーや注意点も把握した上で、手土産を持参しましょう。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。