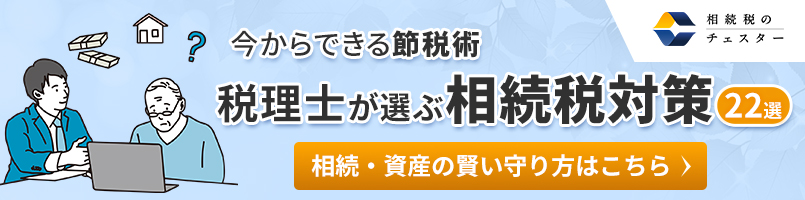年金は60歳からもらった方が賢い?メリットとデメリットを知っておこう

日本の年金制度では、65歳になれば老齢年金を受け取れるようになります。しかし、この老齢年金は一定の手続きをすることで60歳まで繰り上げて受給することが可能です。本記事では、老齢年金は60歳からもらうべきなのか、手続きやメリット・デメリットにも触れながら解説します。
60歳から年金をもらうこと自体は可能

まず、現在の年金制度上、60歳から年金をもらう(繰上受給する)こと自体は可能です。ここでは、具体的な手続きと、前提となる知識として年金の種類について解説します。
年金事務所に請求書を提出する
60歳から年金をもらうためには、年金事務所もしくは年金相談センターに所定の請求書を提出します。ただし、この手続きは原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金に対し、同時に行わなくてはいけません。
年金をもらう時期を65歳以降にする(繰下受給)の場合とは違い、どちらか一方だけを繰り上げることはできないため、注意が必要です。
【参考】年金の種類
理解を深めるための知識として、老後に受け取れる年金の種類について解説します。前提として、日本には法律によって全員が加入する公的年金と、企業や個人が自分の意思で加入する私的年金があります。そして、公的年金をさらに細かく分類すると、国民年金と厚生年金保険の2種類に分けることが可能です。
| 国民年金と厚生年金保険の違い | |||
|---|---|---|---|
| 国民年金 | 日本国内に住む20歳から60歳未満の人が加入する。20歳から60歳まで40年間保険料を納めると、原則として65歳から年金(老齢基礎年金)が受給できる。 | ||
| 厚生年金保険 | 会社員や公務員などが加入する。給与の一部から保険料を納めると、原則として65歳から年金(老齢厚生年金)が受給できる。 | ||
また、国民年金には以下の加入者区分が設けられており、65歳以降に受け取れる年金(老齢年金)の種類と密接に関係しています。
| 国民年金の加入者の区分と受け取れる年金の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
| 具体例 | 自営業者、農業者、学生および無職の方とその配偶者の方 | 会社員、公務員 | 会社員、公務員の配偶者かつ年収が130万円未満など一定の条件を満たす人 |
| 受け取れる老齢年金 | 老齢基礎年金 | 老齢基礎年金・老齢厚生年金 | 老齢基礎年金・老齢厚生年金 |
フリーランス・自営業などの第1号被保険者の場合、受け取れるのは老齢基礎年金のみとなります。そのため、自身で個人年金保険等を活用して老後資金を準備することが望ましいでしょう。
年金は60歳からもらったほうが賢い?2つのメリット

年金は60歳からもらったほうが賢いのかについては、さまざまな答えがあります。ここでは、年金を60歳からもらうことのメリットを解説します。
早期に安定収入が得られる
年金を60歳からもらうと、早期に安定収入が得られます。定年退職や役職定年などの理由により、60歳前後で年収が急激に下がることは決して珍しくありません。老齢年金の受給繰上げを選択すれば、年収が急激に下がるタイミングで給与以外の安定収入が得られます。
元気なうちに確実に受け取れる
年金を60歳からもらうことで、元気なうちに確実に受け取れます。繰上受給の手続きをしない限り、原則として65歳にならないと老齢年金は受け取れません。
しかし、持病があったり、余命宣告をされていたりなど、健康面での不安があり長生きが難しそうな場合、65歳になるまで待っていたら受け取れない可能性があります。65歳を迎える前に亡くなってしまった場合は、老齢年金が一切受け取れません。
存命中に確実に受け取れるという意味で繰上受給の手続きをし、60歳から老齢年金を受け取ることに一定のメリットはあります。
年金は60歳からもらったほうが賢いとはいえない?デメリット2つ
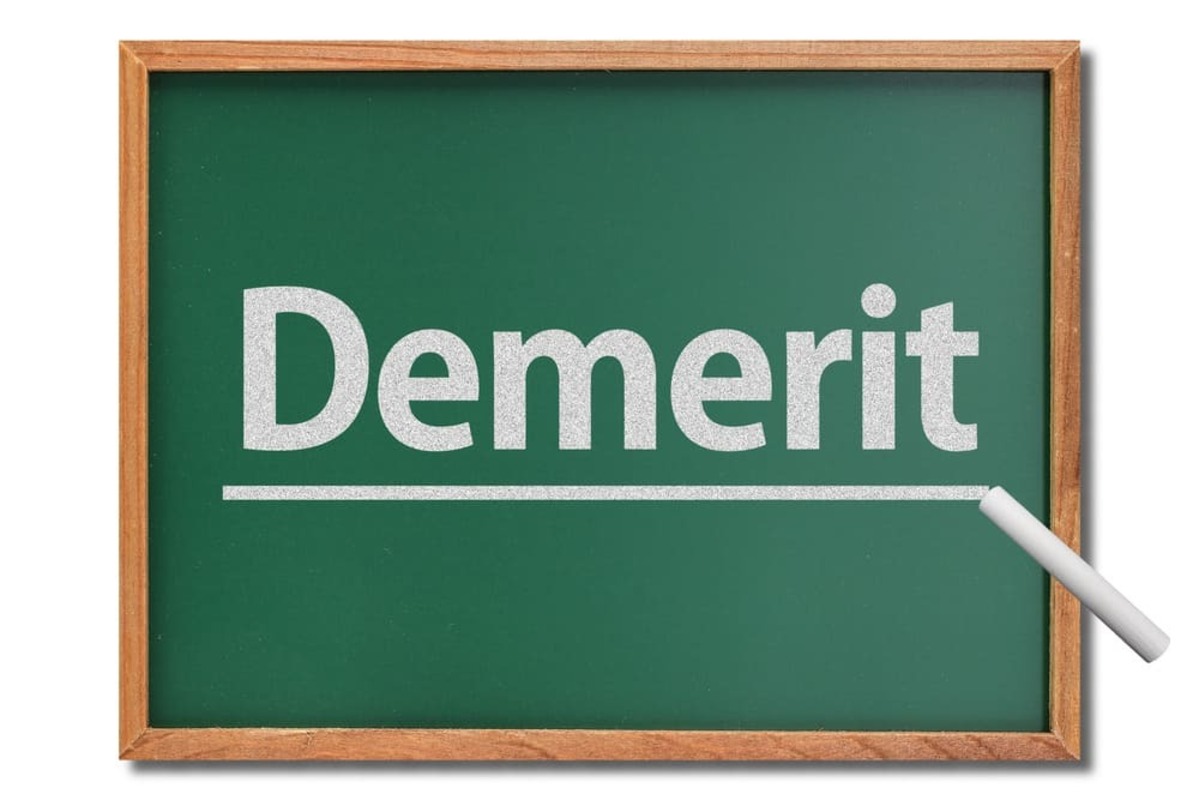
一方、「年金は60歳からもらったほうが賢いとはいえない」という声もあるのが事実です。ここでは、年金を60歳からもらうことに関するデメリットについて解説します。
毎月の受給額が減る
繰上受給をした場合、受け取れる老齢年金が1ヵ月あたり0.4%減額されます。老齢年金を60歳から繰上受給した場合、最大で24%減額されます。仮に、減額前に受け取れる老齢年金の月額が10万円だった場合、7万6,000円まで減るため要注意です。
なお、65歳以降に老齢年金の受給を繰り下げることにした場合、月額0.7%増額されます。受け取れる金額が増えるという意味では、できるだけ後で受け取るほうが賢いでしょう。
障害年金や遺族年金が受け取れないおそれが出る
60歳から年金を受け取ってしまうと、障害年金や遺族年金が受け取れないおそれがあります。年金には、支給理由の異なる年金は一緒に受け取ることができないという「一人一年金の原則」があるためです。
例えば、老齢基礎年金の繰上受給をすると、60歳から65歳の間に障害基礎年金の受給対象になったとしても、原則として障害基礎年金を請求できなくなる点に注意しなくてはいけません。また、遺族厚生年金についても、老齢基礎年金と同時に受給できないため、65歳になるまでは支給が打ち切られます。
年金を60歳からもらったほうが賢いといえる人の特徴
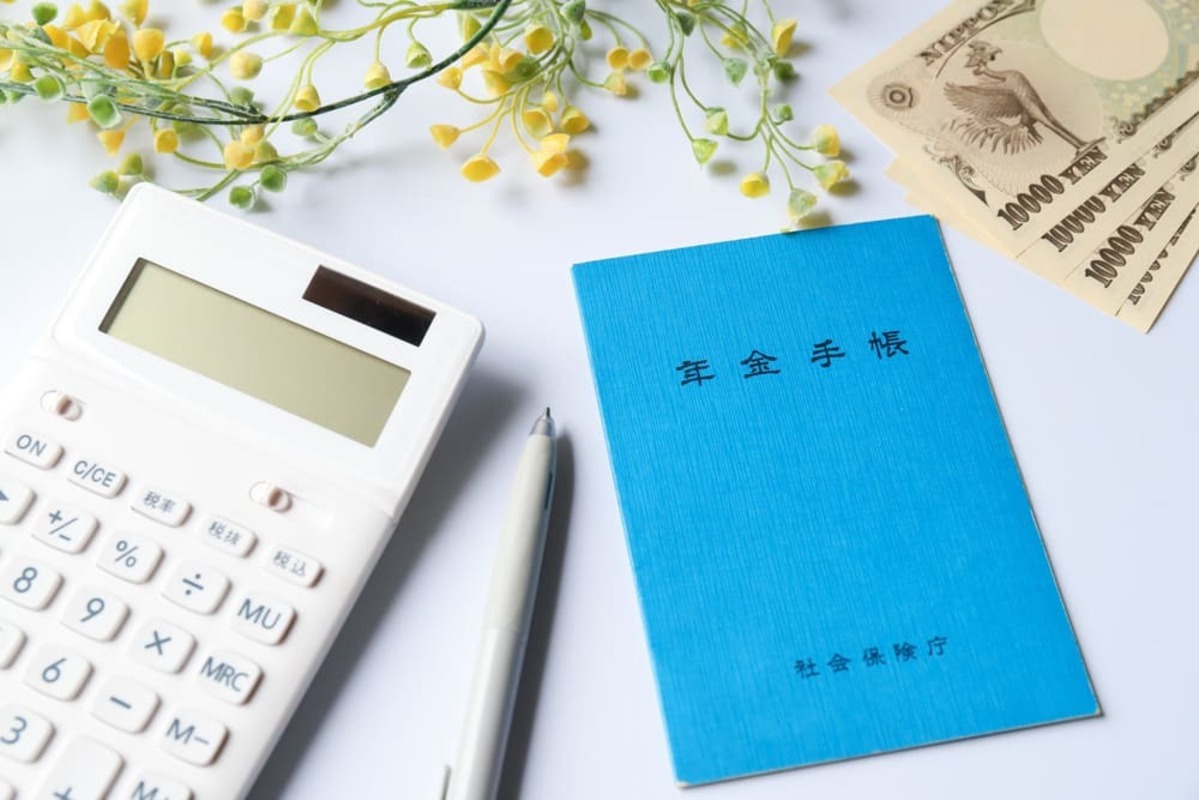
ここまでの内容を踏まえ、老齢年金を60歳からもらったほうが賢いといえる人の特徴について解説します。
事情があって働けず資産もない
実際のところ、60歳から年金を受け取るのが賢いといえるのは、事情があって働けず資産もない状態に限られます。健康上の理由や家族の介護など働けない事情があるなら、例え受け取れる額が減っても、60歳から受け取ることに一定のメリットはあるはずです。少なくとも、お金がないストレスを軽減できます。
年金を60歳からもらったほうが賢いといえない人の特徴
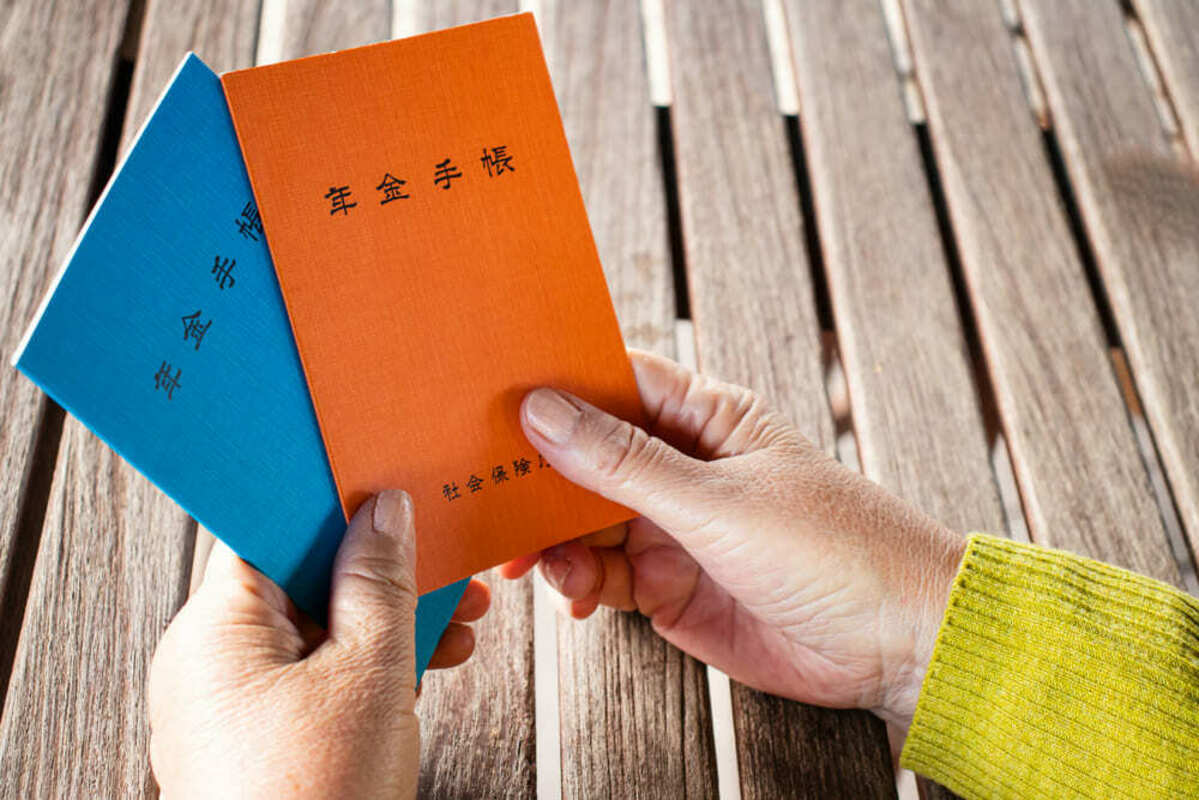
一方で、年金を60歳からもらうことで明らかに不利になるなら、もらわないのが賢い決断になるはずです。ここでは、年金を60歳からもらったほうが賢いといえない人の特徴を紹介します。
国民年金に任意加入しておきたい
国民年金に任意加入しておきたい場合は、老齢年金を60歳からもらうのは賢いとはいえません。国民年金の任意加入とは、国民年金保険料を支払った年数が短く、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間を満たしていないなど、一定の条件に当てはまる人が利用できる制度です。
60歳を過ぎても国民年金の保険料を払い続けると、老齢基礎年金をもらえるようになったり、年金の金額が増えたりします。しかし、繰上受給をする場合は任意加入ができなくなるため、注意が必要です。
寡婦年金を受け取っている
寡婦年金を受け取っている場合も、60歳から老齢年金をもらうのは賢いとはいえません。寡婦年金とは、夫が老齢年金をもらう前に亡くなったときに、妻が年金の一部を受け取れる制度です。
早くに夫を亡くしたなど、寡婦年金を受け取ることができる人が老齢年金の繰上受給を選択する場合は注意しなくてはいけません。寡婦年金の月額よりも、老齢年金の月額のほうが少なければ損してしまいます。
失業保険を受け取る予定
失業保険を受け取る予定の人も、60歳から老齢年金をもらうのは賢い選択とはいえないかもしれません。会社員、公務員として働いていて、厚生年金に加入していた人が退職した場合、条件を満たせば失業保険が受け取れます。
ただし、失業保険は老齢厚生年金と併給できない決まりであることに注意が必要です。なお、老齢基礎年金については併給ができます。まったくもらえなくなるわけではありませんが金額は減ってしまうため、その点を意識してどうするか考えましょう。
60歳過ぎても働きたい
60歳以降も働く予定の人も、繰上受給をすべきか慎重に考える必要があります。60歳以上の高齢者が働き過ぎると、老齢年金の一部もしくは全部が支給停止になりかねません。
在職老齢年金とは、60歳以降の高齢者について、勤務先から受け取る給与と年金の合計額が51万円(2025年度の場合)を超える場合、老齢年金(厳密には老齢厚生年金)の一部もしくは全額について支給停止される制度を指します。
せっかく繰上受給を選択しても、働き過ぎたら実際に受け取れる金額が減ってしまうことも考えられます。60歳以降も働く予定があるなら無理に繰上受給を選択しないとともに、65歳以降も働き過ぎて老齢年金を減らされないよう、賢い働き方を目指しましょう。
基本的に年金は60歳からもらわない前提でいましょう
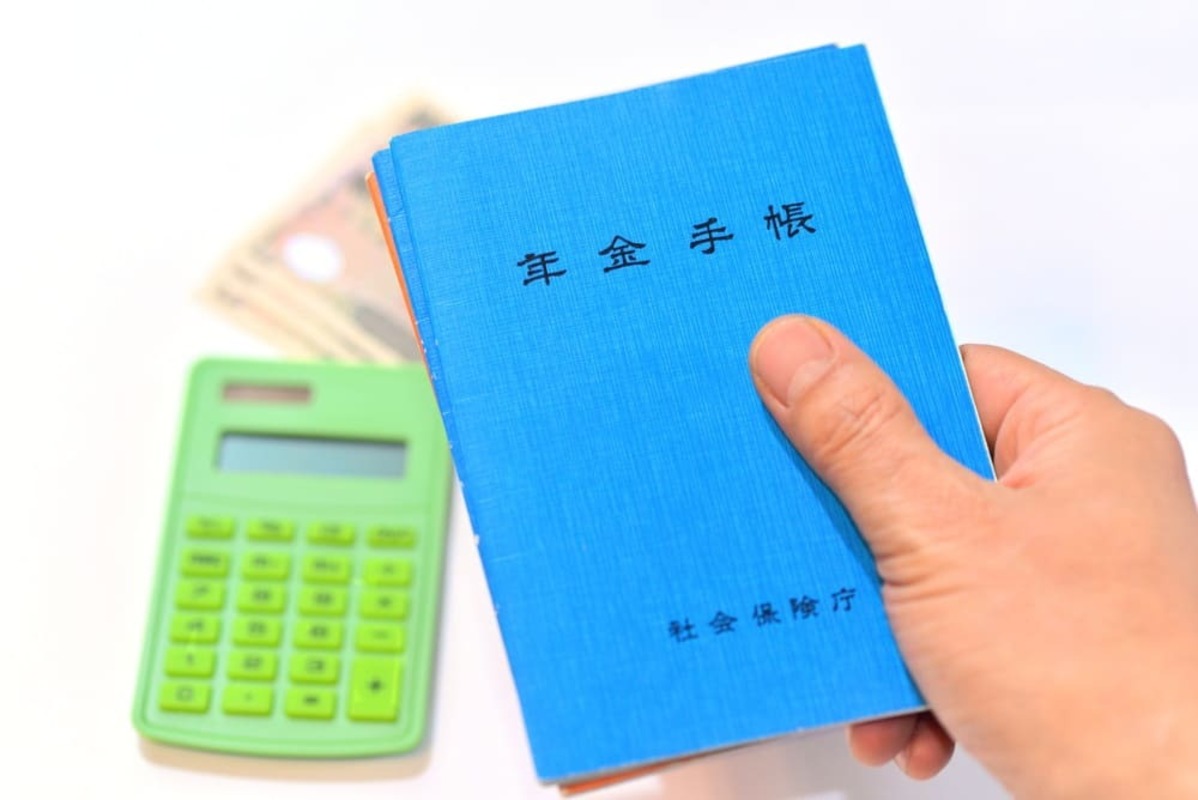
この記事のまとめ
- 年金を60歳からもらうメリットは「早いうちに確実に受け取れる」こと
- 一方で、1ヵ月繰り上げるごとに0.4%減額されるなどデメリットが大きい
- 大半の場合はデメリットがメリットを上回るため、年金をもらうのは65歳まで待つべき
- 年金を60歳からもらった方が賢いのは、健康上の理由などで働けず、預貯金などの資産もない場合
- 年金を60歳からもらわなくてすむよう、早いうちから対策を講じることが大切
60歳からもらわないと厳しい事情がないなら、65歳まで待ちましょう。また、65歳まで老齢年金をもらわなくて済むよう、早いうちから老後資金作りを始めるのが重要です。年金は「いつからもらうか」だけでなく、「どう備えるか」も大切なポイントです。将来を見据えて自分にとって最適な選択ができるよう、今から計画的に準備を進めていきましょう。
立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。