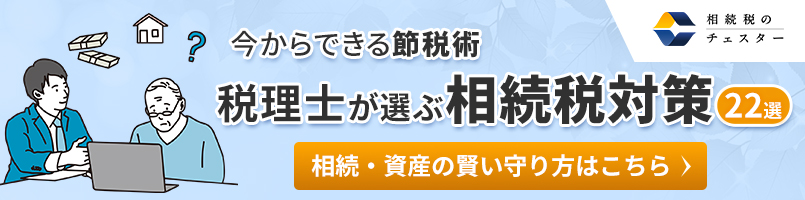相続税とは?誰が払うもの?税率や計算方法について分かりやすく解説!

相続税とは、故人の遺産を受け取る際に発生する税金のことです。相続税は故人の遺産を受け取った人が払うものですが、税率や計算方法は受け取る金額や故人との関係などによって大きく変わります。本記事では、相続税はどのような仕組みなのか、具体的な税率や計算方法などを解説します。
相続税とは相続を受けた人が払う税金

相続税とは、故人(被相続人)から財産を受け継いだ人(相続人)が支払う税金です。相続財産には、現金・預貯金、不動産、株式などが含まれます。相続税は、一定額を超えた財産に対して課税される仕組みで、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生します。
まずは相続税の控除額とはどのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
相続税の税率・控除額とは
相続税の税率には累進課税方式が採用されています。累進課税方式とは、受け取る財産の課税価格が高くなるほど税率が上がる仕組みです。
税率は10%から最高55%まで設定されており、以下のように財産の額に応じて段階的に税率が適用されます。
財産の額と相続税の税率の例
- 1,000万円以下…10%
- 3,000万円超~5,000万円以下…20%
- 1億円超…30%
また、相続税には基礎控除が適用され、相続財産が基礎控除額以下であれば課税されません。被相続人の配偶者や未成年者、障がい者には特別な控除制度があり、税負担が軽減される方法も用意されています。
相続税がかかる財産とは
相続税がかかる財産とは、以下のようなものです。
相続税がかかる財産の例
- 現金・預貯金
- 不動産(建物や土地)
- 株式・投資信託
- 生命保険金(一定額を超えた分)
- 死亡退職金
- 貸付金 など
これらの財産の評価額を合算し、基礎控除額を超えた部分に対して相続税が課されます。ただし、墓地や仏壇、位牌などの祭祀財産は相続税の課税対象外になります。
なお、生前贈与された財産も、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与であれば、相続開始前7年以内の贈与分が相続財産に含まれるため注意が必要です。
相続税の計算方法とは

相続税の計算方法は、まず相続財産の総額を算出し、基礎控除を差し引いた後、課税される遺産額に税率を適用して相続税を計算します。その後、相続人ごとの分割や各種控除を考慮して最終的な税額を確定します。
具体的な計算方法を見ていきましょう。
課税対象となる財産の総額を計算する
相続税の計算方法は、課税対象となる財産の総額を算出することから始めます。この際、不動産、預貯金、株式など、すべての資産を適正に評価し、合計額を算出しましょう。
不動産の評価方法としては、路線価や固定資産税評価額を基準に計算します。例えば、土地の評価は路線価方式または倍率方式を用いて行われ、建物は固定資産税評価額をもとに計算されます。
預貯金や株式の評価は、相続開始時点の市場価値が基準です。その他、生命保険金や死亡退職金なども相続財産に含まれる場合があります。これらの評価額を合計したものが「課税遺産総額」となります。
相続税の総額を計算する
相続税の総額を計算する際には、基礎控除をはじめとするさまざまな控除や特例を考慮しなければなりません。まず、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。相続財産の総額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税は発生しません。また、被相続人の配偶者が相続する場合には、配偶者の税額軽減が適用され、相続財産の総額が1億6,000万円以内なら相続税は発生しません。1億6,000万円を超えても、法定相続分までなら非課税となります。
さらに、未成年者が相続人となる場合には「未成年者控除」、障がい者が相続人となる場合には「障がい者控除」が適用され、それぞれ一定額の控除を受けられます。加えて「相次相続控除」という特例も存在します。過去10年以内に2回以上相続が発生した場合に、前回の相続税額の一部を控除できる制度であり、短期間に連続して相続が発生した際の税負担を軽減するための措置です。
このように、各種控除や特例を適用することで、相続税額を大幅に軽減することが可能です。
相続税を相続分で割り各種控除を受ける
相続税の総額を算出したら、その税額を各相続人の法定相続分に基づいて按分します。 法定相続分とは、民法に定められた相続割合のことであり、配偶者や子、親、兄弟姉妹などの相続人が、それぞれどれくらいの割合で財産を取得するかを決定する基準です。
相続税は、各相続人が取得する財産の割合に応じて計算されるため、最初に算出された相続税の総額を法定相続分に応じて分配した上で、各相続人の税額を確定します。その後、各相続人は自身の税額に対して適用可能な控除を受けます。例えば、配偶者が相続する場合には配偶者の税額軽減が適用されるほか、未成年者控除や障がい者控除などを適用することで、最終的な納税額を軽減できる仕組みです。
相続税で利用できる控除・特例とは

相続税を計算する際、さまざまな控除や特例を適用できます。ただし、控除や特例は相続人の状況や相続財産の種類によって異なるため、正しく利用することが大切です。それぞれの控除、特例とはどのようなものがあるのか詳しく解説します。
基礎控除
基礎控除とは、全ての相続に適用される控除です。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 2 = 4,200万円」で、相続財産がこの金額以下であれば相続税は課税されません。基礎控除が適用された後に残った相続財産に対して課税されるため、基礎控除をうまく活用すれば相続税が大きく軽減されます。
この控除額は相続人の数によって変動するため、相続人の人数を正確に把握することが大切です。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続する場合に適用される控除制度です。配偶者の税額軽減では、配偶者が相続する場合、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税が非課税となります。特に配偶者が相続する財産の額が大きい場合には、有効な仕組みといえるでしょう。
未成年者の税額控除
未成年者控除とは、相続人が未成年の場合に適用される控除です。未成年者控除では、未成年者が18歳に達するまでの年数に10万円を掛けた金額が控除されます。例えば、未成年者が相続人であり、18歳になるまで残り10年がある場合「10年×10万円=100万円」が控除されます。
※令和4年3月31日以前の相続または遺贈については、20歳に達するまでの年数が適用されます。
障がい者の税額控除
障がい者控除とは、相続人が障がい者である場合に適用される控除です。障がい者控除では、障がい者が相続する場合、85歳に達するまでの年数に10万円を掛けた金額が控除されます。
特別障がい者の場合は、控除額が20万円に増額されます。例えば、障がい者が相続人であり、85歳まで10年残っている場合、通常の控除額は「10万円×10年=100万円」です。特別障がい者であれば「20万円×10年=200万円」が控除される計算になります。障がい者が相続する際の税負担が軽減されるため、生活支援にもつながるでしょう。
相次相続控除
相次相続控除とは、相続が10年以内に2回以上発生した場合に適用される控除です。相次相続控除では、前回の相続税額の一部を新たな相続税額から差し引くことが可能です。
相次相続控除は、相続が繰り返されることで相続税の負担が増えないようにするための制度です。例えば、前回の相続で支払った相続税が200万円だった場合、その一部を次回の相続税から控除できるため、相続人の負担を軽減できます。
贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続前に贈与を受けていた場合に適用される制度です。生前に贈与税が課税されている場合、その贈与税額を相続税から差し引くことが可能です。
贈与税額控除を活用すれば、相続時に支払うべき税金を軽減できます。例えば、親から贈与を受けて贈与税を支払った場合、その贈与税額を相続税から控除し、二重課税を防げます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が住んでいた土地を相続する場合に適用される特例です。小規模宅地等の特例では、一定の条件を満たすことで、その土地の評価額が最大80%減額されます。
被相続人が居住していた自宅などに適用されることが多く、相続税の負担を大幅に軽減できます。例えば、家庭用住宅として使われていた土地が相続される場合、評価額を最大80%まで減額でき、相続税の負担を大きく減らせます。小規模宅地等の特例を適用するには、相続人がその土地に居住しているなどの条件があるため、条件を確認して申請することが大切です。
相続税を申告する際のポイントと注意点

相続税の申告には、いくつかのポイントと注意点があります。期限や申告の有無、被相続人との関係など、さまざまな点に注意し、正しく相続税を納められるように計算を進めましょう。相続税の計算や税制は非常に複雑なため、少しでも不明点がある場合は税理士に相談し、悩みや疑問を解消しておくと安心です。
相続税は10ヵ月以内に申告する必要がある
相続税は、被相続人の死亡を知った日から10ヵ月以内に税務署へ申告を行う必要があります。申告期限を守らない場合、納税額が増える可能性があります。相続が発生すると、遺産の調査や評価、必要書類の準備などが必要となるため、早めに税理士などの専門家に相談し、期限内に適切な申告を行ってください。
また、相続税の申告書の提出とともに納税もする必要があるため、税額の算定を早めに始めて、確実に申告と納税を終えるように心がけましょう。
相続財産が基礎控除以下なら申告は不要
相続財産が基礎控除額以下の場合、相続税の申告は不要です。基礎控除は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」によって算出されます。この基礎控除額を超えない場合、通常は相続税がかからないため申告する義務はありません。
しかし、基礎控除を超えなくても、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、特定の控除を適用する場合は申告が必要です。
相続税が2割加算される人がいる
被相続人の配偶者・子・父母以外の相続人(兄弟姉妹や孫など)は、相続税額に2割の加算がされるため注意しましょう。この加算制度は、相続人が一親等の血族または配偶者以外の場合に相続税の負担を増す仕組みです。兄弟姉妹や叔父叔母、甥姪などが相続する場合は相続税率が高くなり、最終的な税額が増加します。
相続税の申告をする際には、自身やほかの相続人と故人の関係を明確にし、税額を正確に計算しましょう。
まとめ

この記事のまとめ
- 相続税は、故人から財産を受け継いだ人が支払う税金のこと
- 相続財産には、預貯金、不動産、株式・投資信託、貸付金などが含まれる
- 相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ発生する
- 相続税は、受け取る財産の課税価格が高くなるほど税率が上がる
- 相続税には、基礎控除や配偶者の税額軽減、未成年者と障がい者の税額控除、相次相続控除、贈与税額控除、小規模宅地等の特例がある
相続税の計算はなかなか触れる機会が少なく、被相続人との関係によっても利用できる控除や特例が異なるため非常に複雑です。間違った申告をしたり、申告期限を守らなかったりすると相続税が余計にかかることもあるため、正しい申告を心掛けましょう。不明な点がある、相続人間で相続について問題が起きているなどの場合は、税理士などの専門家に相談することも大切です。
国税OB税理士(国税庁出身税理士)。
相続税を専門とする税理士法人チェスターのパートナー税理士。
国税在籍時には、2か所の税務署長、国税不服審判所で部長審判官、税務大学校で主任教授、
国税局訟務室で主任訟務官、さらには国税庁で審理担当課長補佐を歴任。
著書に「令和6年度版相続税・贈与税コンパクトブック」、「デジタル財産の税務」など多数。
また、「相続大辞典」、「税理士が教える相続税の知識」の記事監修も務める。