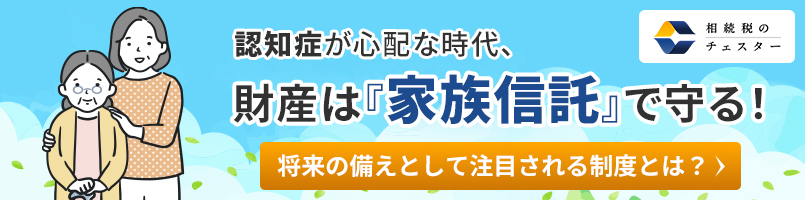ムース食とは?メリット・作り方・ほかの介護食との違いなどをまとめて紹介

介護食にはさまざまな種類がありますが、噛む力が弱くなった人に最初に試してほしい食事がムース食です。ムース食はほかの介護食と比べて、普通食に近い形の食事を摂れます。本記事では、ムース食とほかの介護食との違いやメリット・デメリット、作り方などを詳しく解説します。
ムース食とは

ムース食とは、普通食をすり潰したりミキサーにかけたりして軟らかくしたものを、とろみ剤などを使って成形した食事形態のことです。とても軟らかいため、噛む力や食べ物を口の中でまとめる力が低下した人、飲み込みが難しい人に適した食事です。
型を使って成形するため、見た目は普通食に近いものになります。普通食が難しく食事に介護が必要な高齢者の方などでも、美味しそうな見た目から食事を楽しめます。
ムース食とほかの介護食との違い
ムース食は数ある介護食の中の一つです。介護食には、ムース食のほかにきざみ食やミキサー食、ソフト食などがあります。それぞれに特徴が異なり、食べる方の状態に応じた食事を選択することが大切です。ここでは、ムース食とほかの介護食との違いについて解説します。
きざみ食
きざみ食は、普通食を刻んで細かくしたものです。ペースト状まで潰しているムース食と比較すると食べ物の大きさや固さ、食感も大きく異なります。きざみ食は、飲み込みには問題ないが、噛む力が低下している人に適した食事形態です。
刻んでいるだけなため、口の中でまとまりにくいナッツなどの固い食べ物は誤嚥を招く危険があります。そのため、唾液の分泌が少ない人には不向きです。
ミキサー食
ミキサー食は、普通食にだし汁やスープなど水分を加えてミキサーにかけ、ポタージュ状にした食事形態です。ミキサーにかけたものを固めていない点がムース食との違いです。噛む力が低下した人や飲み込みに不安のある人に適しています。
ミキサー食は基本的に液体状なため、高齢者や介護が必要な方にとってはむせやすい場合があります。そのような場合は、とろみ剤で粘度をつけて誤嚥を防ぎましょう。ムース食に比べると、粘度は低めです。
ソフト食
ソフト食とは、舌や歯茎で潰せる程度の軟らかさまで煮込んだり、蒸したりといった調理をした食事形態です。調理方法によっては普通食とほとんど変わらない場合もあります。飲み込みには問題ないが、噛む力が低下し、きざみ食では硬くて食べられない人に適しています。
食材によっては、食材そのものの形を活かした調理ができるため、ムース食とは見た目が異なっているのが特徴です。
ムース食のメリット

先述の通り、ムース食にはほかの介護食との違いがあり、ムース食を食べる人に合ったメリットがあります。ここでは、そんなムース食のメリットを紹介します。
見た目がよい
ムース食は、型を使って成形できるため見た目がよく、とても美味しそうな食事です。きざみ食やミキサー食では成形が難しいため、見た目のよさはムース食ならではのメリットといえます。
嚥下機能が低下しても美味しいものを食べたいという気持ちは同じです。介護食では食事の見た目で食欲を低下させてしまうという場合があります。その点、ムース食は見た目がよく、食べる人の気持ちを豊かにしてくれる食事です。
安全性が高い
ムース食は、安全性が高い点もメリットです。介護食を食べる際に最も注意が必要なのが、食べ物が誤って気管に入ってしまう「誤嚥」です。通常であれば、むせたり咳き込んだりすることで、入ってしまった食べ物が気管から排出されます。しかし、高齢者では上手く吐き出せず、誤嚥性肺炎など命に関わるリスクとなります。
その点、ムース食は口の中でまとまり食塊を作りやすいため、誤嚥しにくい食事形態です。きざみ食やミキサー食などのほかの介護食と比べても安全性が高いのがメリットです。
消化しやすい
ムース食は、消化しやすく消化器官への負担が少ない食事です。食材を全てミキサーにかけたりすり潰したりするため、食材の繊維も細かくなっています。消化しやすく、栄養素の吸収もしやすいため、消化機能の弱っている高齢者の方にとってムース食はお腹にやさしい食事です。
食事介助しやすい
とろみ剤と成形によって形がしっかり保たれるムース食は、一口分をすくって口に運ぶ作業がしやすく、介助しやすい食事です。自分で食べるにも負担が少ないため、自分で食べられるという自信にもつながります。そのような点も、ムース食のメリットといえます。
冷凍保存ができる
ムース食は、成形した食事をそのまま冷凍保存できます。食べるときには、常温に戻してしばらく置いておけば解凍できるため、とても便利です。多めに作って冷凍保存しておけば、忙しい時などでもすぐに食べられますし、調理の手間も省けます。
冷凍によって質感が変化してしまうことが少ないため、冷凍保存を活用できるのもムース食のメリットです。
ムース食のデメリット

ここまで、ムース食のメリットを紹介してきましたが、ムース食にはデメリットも存在します。ここからは、ムース食のデメリットを紹介します。メリットとデメリットを知り、食事に取り入れる際の参考にしてみてください。
調理に手間がかかる
すり潰した食事を成形することで、美味しそうな食事を作れることがムース食のメリットですが、この工程はとても手間がかかります。調理に手間がかかるという点が、ムース食のデメリットになります。
しかし、ムース食は先述の通り冷凍保存が可能です。時間のあるときに多めに作って保存しておくと、調理の手間も省けて便利です。ぜひ、冷凍保存を活用してみてください。
 ムース食|Amazon.co.jp
ムース食|Amazon.co.jp
食材本来の食感を感じにくい
ムース食は、食材を全てミキサーにかけたり潰してしまうため、食材の形は残りません。そのため、食材本来の食感を感じることが難しくなります。高齢者では「あの食材の、あの食感が好きだった」などという場合もありますが、食事の安全性を第一に考えた食事形態であることを理解しましょう。
噛む力、飲み込む力が著しく低下した人には不向き
ムース食は、噛む力や飲み込む力が低下したと感じ始めた初期段階に適しています。機能低下がさらに進み、嚥下機能が著しく低下した場合には、ムース食を舌で潰すことが難しくなります。すると、のどに詰まったり誤嚥したりする可能性が高くなってくるため、ムース食が適さなくなるのです。
嚥下機能の評価を定期的に行ったり、家族や食事を介助する方が被介護者をよく観察しながら、適切なレベルの食事を摂るようにしましょう。
ムース食の作り方

ここでは、ムース食の作り方を紹介します。基本は普通食をすり潰したり、ミキサーにかけてとろみ剤で固めるという手順で作ります。とろみ剤は、市販のもの以外にも片栗粉、ゼラチン、コーンスターチなどを使って作ることも可能です。
①食材をしっかりすり潰す
食材は、粒や繊維が残らないようにしっかり潰すことが重要です。なめらかなペーストにすることで、固めた後の食感もよくなります。繊維が残る場合には、一度ザルでこすと取り除けます。パサパサした食材を潰す時には、だし汁やスープなど水分を加えてなめらかな食感に仕上げましょう。
②個人の嚥下機能に適した固さにする
ペースト状にした食材を固める際には、個人の嚥下機能に適した固さにしましょう。軟らかすぎると、のどをスーッと通過してしまい誤嚥のリスクがあります。一方、固すぎるとしっかりと噛む必要が生じるため、ムース食のメリットを活かせません。
ムース食の固さの目安は、プリン程度の固さです。とろみ剤で調整しながら、プリンほどの固さになれば大丈夫ですが、個人に合った固さに調整しましょう。
③食材は個々にミキサーにかける
ムース食を作る際のポイントとして、食材を個々に潰したりミキサーにかけるのがおすすめです。全ての食材を一気にミキサーにかけてしまうと、味も色も、全てが混ざり合ってしまい、ムース食のメリットを活かせなくなってしまいます。
手間はかかりますが、一つひとつの食材ごとにミキサーにかけることで美味しいムース食になります。何を食べているのか見た目や香り、味から感じ取ることも食欲を増進させ、食事を楽しむことにつながります。
ムース食のおすすめレシピ

ここでは、ムース食のおすすめレシピを紹介します。味や見た目、栄養価にもこだわったおすすめのレシピです。ぜひ参考にしてご家庭で作ってみてください。
ハンバーグのムース
材料(1人分)
- ハンバーグ 60g
- コンソメスープ 45ml
- とろみ剤 適量
作り方
- 焼いたハンバーグを用意する
- ミキサーにハンバーグとコンソメスープを入れて攪拌(かくはん)する
- (2)を鍋に入れてひと煮立ちさせる
- とろみ剤を加えて混ぜる
- 型に入れて固めたら完成
普通食のハンバーグを、ミキサーでそのままムース食にした料理です。家族と同じものを食べられる喜びを感じてもらえるでしょう。成形後のハンバーグにケチャップをのせると、より見栄えがよくなります。
鮭のムース
鮭のムース(2人分)
- 鮭 2切れ
- 塩 小さじ1/4
- 片栗粉 少々
- だし汁 100ml
- とろみ剤 適量
作り方
- 鮭に塩をかけて10分おき、水分をふき取る
- 片栗粉をまぶして余分な粉ははたく
- 鮭の両面をフライパンで焼く
- 鮭をほぐし、骨と皮を取り除く
- ミキサーに(4)の鮭とだし汁を入れて細かくする
- とろみ剤を加えて混ぜる
- 成形して固めたら完成
骨や皮があることから敬遠されがちな魚料理も、ムース食にすることで食べやすくなります。だし汁をコンソメスープに変えると洋風の料理になるため、バリエーションを増やせます。
ほうれん草の白和え風ムース
材料(2人分)
- ほうれん草 40g
- 鶏ガラスープ 小さじ1
- 水 20ml
- とろみ剤 適量
- 生クリーム お好みで
- (A)豆腐 50g
- (A)練りごま 大さじ1/2
- (A)砂糖 小さじ1
- (A)塩 少々
作り方
- ほうれん草を軟らかくゆでて、ミキサーにかける
- (1)に鶏ガラスープ、水、とろみ剤、生クリームを加えてミキサーにかける
- 成形して固める
- 豆腐をすり潰し、(A)を混ぜ合わせる
- (3)に(4)をのせて完成
パサパサする葉物野菜は、だし汁やスープと一緒にミキサーにかけると食べやすくなります。豆腐は粒が残らないようしっかりすり潰すとより食べやすく、見た目もよくなります。
トマトのムース
材料(60g×4個)
- トマトジュース 80ml
- リンゴジュース 40ml
- 牛乳 100ml
- 卵黄 1個
- レモン汁 5ml
- はちみつ 5g
- 粉ゼラチン 2.5g
作り方
- ゼラチンは分量の4~5倍の水に振り入れ、湯せんにかけて溶かしておく
- ボウルに卵黄だけ入れて溶きほぐしておく
- 鍋にトマトジュース、リンゴジュース、牛乳を入れ、沸騰直前まで温める
- (2)のボウルにグラニュー糖を入れ混ぜ合わせ、さらにレモン汁、はちみつも入れて混ぜる
- (4)のボウルに(3)を2~3回に分けて入れて、その都度混ぜる
- 小鍋を少し温め直し、火を止めて(1)のゼラチンを入れて混ぜる
- (6)を氷水にあて、かき混ぜながら少しとろみがつくまで冷ます
- 別のボウルに生クリームを入れ、七分立て(軽くとろみがつく程度)まで泡立てる
- (7)に(8)の生クリームを2回に分けて入れ、その都度よく混ぜ合わせる
- 器にそそいで、冷蔵庫で30分くらい冷やし固めたら完成
間食は、高齢者に不足する栄養素を補給する役目があります。トマトジュースと牛乳を使ったムースは、たんぱく質やビタミンを補給できます。ムース食は、家族皆で食べても美味しい料理のため、ぜひ試してみてください。
ムース食のメリットを活かし、嚥下機能に合った食事を楽しみましょう

この記事のまとめ
- ムース食とは、普通食をすり潰してとろみ剤で固めた食事形態のこと
- 噛む力や飲み込む力が低下した高齢者に適しており、介護食の初期段階に試す形態としておすすめ
- ほかの介護食に比べて見た目がよく、安全性も高い
- 調理には手間がかかるが、冷凍保存が可能で作り置きできる
- ムース食を作る際は、食材をしっかり潰し、個人の嚥下機能に合った固さにする必要がある
噛む力や飲み込む力が低下しても、ムース食を取り入れることで見た目や味を楽しみながら食事をすることが可能です。嚥下機能を適切に評価しながら、個人に合ったムース食を取り入れましょう。
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業。
管理栄養士として病院に勤務し、患者様の栄養管理及び栄養指導に従事。
糖尿病患者や腎臓病患者を中心に、病状の進行を防ぐための食事指導を行う。食事と健康、美容に関する記事を中心に管理栄養士ライターとして活動中。