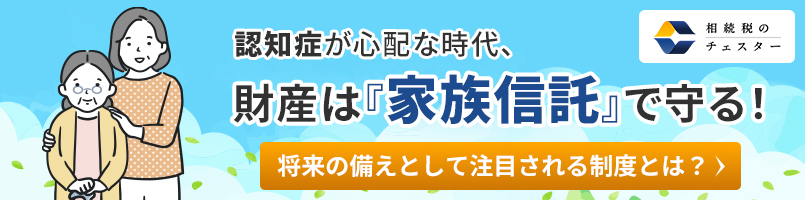認知症予防の脳トレには手遊びがおすすめ!認知機能が活性化する理由とは

認知症予防に脳トレがおすすめなのは有名ですが、手遊びも認知症対策に効果的であることをご存知ですか?本記事では、認知症予防のための手遊びや行なう際のポイントを解説します。手遊び以外の脳トレも紹介しますので、認知症予防に興味のある方は、参考にしてください。
脳トレで認知機能が活性化する理由

認知症予防の脳トレには、さまざまな種類があります。まずは、脳トレをすると認知機能が活性化する理由を解説します。
脳に刺激が与えられる
認知症を予防するには、継続的な脳トレが必要です。脳トレを行うことで脳内の血流がよくなり、脳が活性化されます。
例えば、なぞなぞや計算の脳トレは、感情や学習、記憶に関連する脳の部分へ刺激を与えます。
コミュニケーションの機会が増える
認知症予防の脳トレには、コミュニケーションの機会が増えるというメリットがあります。会社を退職したり仕事をやめたりすると、人との接触が減ってしまうことが多いです。その結果、精神的に不安定になったり認知症の症状が出たりする場合もあります。
脳トレにはひとりでできるものがあれば、複数で取り組むものも多いです。デイサービスなどの介護施設で行う認知症予防の脳トレなら楽しい時間が共有できるだけでなく、自然と会話も生まれます。コミュニケーションの機会となり、脳への刺激も増えるでしょう。
ストレス発散になる
高齢者になると加齢や持病などにより、さまざまなストレスを抱えやすくなります。手遊びなどの脳トレを日常的に行うことで、気分転換できるでしょう。ストレスを抱え込まないことが、認知症予防にもつながるため、手遊びを日常的に取り入れることはれっきとした認知症対策といえます。
認知症予防の脳トレにおすすめの手遊び10選

指先は「第二の脳」と呼ばれ、手遊びは脳へ刺激を与えられることが分かってます。手軽かつ場所を取らずに行える手遊びは、脳トレ初心者の方にもぴったりです。
ここからは、認知症予防の脳トレにおすすめの手遊びを10種類紹介します。指先を使いますが、どれも難しくないためぜひ試してみてください。
簡単にできる指体操
まずは、ひとりでもできる指体操を紹介します。
指折り体操
指折り体操の方法
- 両手をパーにして広げて、親指から1本ずつ順番に中へ折る
- 小指まで折って手がグーになったら、小指から1本ずつ広げる
指折り体操はリズムよく、声を出して指の名前を言いながら指を動かすことがポイントです。声出しと指を動かすことを同時にすると、脳によい刺激が与えられます。高齢になるにつれて、指が動かしづらくなるため、無理をせず一本ずつゆっくり行っていきましょう。
指回し体操
指回し体操の方法
- 両手の同じ指先を合わせる(親指と親指、人差し指と人差し指など)
- 両手の間にボールが入るような形に整える
- 親指から順番に、右回し左回しと指先をぐるぐる回す(他の指先は離さない)
指回し体操のポイントは、指を回すときに、指先同士が当たらないようにすることです。特に、中指と薬指を回すときには、ほかの指が離れやすくなります。指の感覚を感じながら、リズムのよい動きをするように心がけましょう。
最初は難しいと感じますが、慣れてくるとスムーズにできるようになります。
指離し体操
指離し体操の方法
- 両手を胸の前に出す
- 親指と親指、人差し指と人差し指など同じ指の腹を合わせる
- 親指から順に1本ずつ指を離す
ポイントは、ほかの指が離れないように気を付けることです。集中して体操をすると、脳機能の活性化につながります。
昔ながらの手遊び
ここからは、昔ながらの手遊びと認知症予防への有効性について紹介していきます。
あやとり
毛糸などのひもを輪にして、さまざまな形を作っていく手遊びです。2人でもできますが、ひとりでも可能です。歌いながら行うと、より脳機能の改善につながります。
お手玉
お手玉は、小さな袋を上に投げてキャッチする日本の伝統的な遊びです。一般的な遊び方を説明します。
お手玉の遊び方
- お手玉を用意する
- 片手に一つのお手玉を持つ(最初は片方の手で遊ぶ方法から始めるとよい)
- お手玉を軽く上に投げる(目の高さほどに投げるとよい)
- 投げたお手玉を、同じ手でキャッチする動作を繰り返す
- 両手に一つずつお手玉を持ち、一つずつ上に投げる動きを繰り返す
- 慣れてきたら、複数のお手玉を使ってリズムよく投げてキャッチを繰り返す
お手玉は、小さな布製の袋に豆や小さな粒が詰められた一般的なものを使います。手先の器用さや集中力が必要になり、認知症予防の脳トレの手遊びとなります。
じゃんけん
じゃんけんは、認知症予防の脳トレに役立つ遊びとして有効です。理由は以下のとおりです。
認知症予防の効果
- 相手の出す手を予測し、自分の手を素早く決める必要があるため、判断力の強化に役立つ
- 瞬時に勝敗を判定するため、脳の反応速度が向上する
- 相手と行う遊びであるため、他者とのコミュニケーションを通じて社会的つながりを保てる
じゃんけんは簡単で楽しく、脳トレにもなる遊びです。コミュニケーションの機会も増え、家族や友人とのつながりを深めるのに有効です。
歌いながらできる手遊び
認知症予防の脳トレには、歌いながらできる手遊びもあります。
むすんでひらいて
「むすんでひらいて」は音楽と歌に合わせて手をたたいたりグーパーしたりする手遊びです。慣れていない人は、ゆっくりしたリズムから始めるとよいでしょう。
あんたがたどこさ
「あんたがたどこさ」は椅子に座ったまま行う認知症予防の脳トレです。手をたたくタイミングを間違えたり手足がバラバラになったりする場合が多く、集中力が必要となります。真剣に取り組むことで、脳の活性化につながり認知症予防にもなります。
うさぎとカメ
うさぎとカメの歌に合わせて行う、認知症予防に有効な脳トレの手遊びです。指の動きはそれほど大きくありませんが、集中していないと間違ってしまうため、脳機能の改善が期待できる手遊びといえるでしょう。
幸せなら手をたたこう
「幸せなら手をたたこう」では、歌詞の内容に合わせて手をたたきます。身体を動かしながら脳トレにもなる手遊びです。次にたたく箇所を考えながら身体を動かすため、認知症予防になります。
手遊び以外にできる認知症予防の脳トレ5選

ここからは、手遊び以外にできる認知症予防の脳トレを紹介します。ひとりでできるものもあれば、複数人必要なものもあります。
間違い探し
認知症予防の脳トレとして「間違い探し」があります。間違い探しとは一般的に、並べられた2枚のイラストを見比べながら違っている箇所を探す作業のことです。
認知症予防として効果が得られる理由としては、以下のようなものが挙げられます。
認知症予防の効果
- 細部まで注意を払い、観察力を養える
- 正確な違いを見つけるには集中力が必要となり、間違い探しを繰り返すことで、集中力の持続や向上につながる
- 画像や絵の情報を記憶し比較しながら違いを見つけることは、脳の認知機能を活性化させる
手軽に始められて継続的に取り組みやすいため、認知症予防の脳トレとしておすすめです。
なぞなぞ
なぞなぞは、認知症予防の脳トレとして効果が期待できます。ひとりでもよいですが、複数人と行うとさまざまな意見が出て楽しくなるでしょう。
認知症予防の効果
- 言葉や状況に対する考えや想像力を必要とするため脳の思考力を養える
- 一度聞いた質問を覚えておき、それを解決するために頭の中でさまざまな情報を思い出す必要があるため記憶力の向上につながる
- ほかの人と一緒に行えばコミュニケーションが生まれ、社会的つながりを保つことで認知症予防に役立つ
認知症予防に効果的であり、継続的に取り組むことで脳の健康を保つ助けとなります。
将棋やオセロなど頭を使うゲーム
将棋やオセロも、認知症予防のための脳トレとして非常に効果的です。その理由について説明します。
認知症予防の効果
- 相手の動きを予測し、自分の一手をどのように展開するかを考えることにより、論理的な思考や長期的な視点を養える
- 過去の手やゲーム全体の流れを覚えておく必要がある。短期記憶や長期記憶の維持や改善につながる
- 次の手を考えるために集中力を維持する必要があり、集中力の持続や向上につながる
- 将棋やオセロは他の人とプレイするため社会的つながりを保ち、認知症予防に役立つ
将棋やオセロは認知症予防に効果的であり、ゲームとして楽しみながら脳トレに取り組むことができます。
計算問題
計算問題も、認知症予防の脳トレとして効果的です。その理由について説明します。
認知症予防の効果
- 数の移動や計算式の理解を必要とし、論理的思考を養うことができる
- 計算過程を頭の中で整理して結果を導くには、過去の数値や計算のステップを覚えておく必要があるため、記憶力の向上につながる
- 計算問題に取り組む際は正確な解答を出そうとするため、集中力の持続や向上につながる
ひとりでも取り組めるため、日常的に続けやすく、認知症予防に効果があります。日々の生活に取り入れることで、脳の健康を保てます。
足踏み体操
認知症予防のための脳トレとして、足踏み体操も効果的です。理由について説明します。
認知症予防の効果
- 足の動きと同時に手を使ったり、リズミカルに動かしたりするため、身体と脳の連動が必要で脳の活性化につながる
- リズムに合わせて左右の足を交互に上げる動作が多く、バランス感覚の強化に役立つ
- 足の動きだけでなく全身の筋肉を使うため、身体全体の健康改善に役立つ。運動は認知症予防や健康において重要な要素であり、脳トレの一環としても有効
認知症予防に効果的でも、続けられないと効果は期待できません。足踏み体操はテレビを見ながらでも簡単に継続できるため、日常生活に取り入れていきましょう。
認知症予防の脳トレに手遊びを行う際のポイント

認知症予防の脳トレを効果的に行うポイントについて、解説していきます。
毎日続ける
脳トレは、毎日続けることが大切です。楽しく続けられるように、まずはひとりでもできるものや手軽にできることから取り入れてみましょう。
コミュニケーションを取る
手遊びは複数人でコミュニケーションを取りながら行うことで、脳の活性化につながります。デイサービスなどでは脳トレをチーム対抗にすると、自然と会話する機会が生まれるでしょう。
徐々に難しくする
同じ手遊びを続けていると、効果が薄れる可能性があります。同じ種類でもリズムを変えたり、左右で違う動きをしたりして難易度を上げましょう。難易度を上げすぎるとやりたくなくなる可能性も出てくるため注意しましょう。
前後に体操をする
手遊びの前に準備体操で手指をほぐし、終わったら手首のストレッチなどでクールダウンしましょう。急に激しく手遊びをすると指を痛める可能性もあります。また、疲れを残さないことで、毎日継続しやすくなります。
認知症予防の脳トレに手遊びを取り入れてみましょう

この記事のまとめ
- 脳トレをすることで認知機能が活性化する
- 脳トレには手遊びが効果的
- 簡単にできる手遊びは継続しやすい
- 歌いながら行う手遊びは、認知機能がより多く活性化する
- 集団で行う脳トレは、他者とのコミュニケーションも取れる
脳トレの手遊びは、認知症予防に効果的です。高齢者が懐かしむ歌や遊びを取り入れると、脳が活性化し、記憶力の向上や認知機能の改善につながります。簡単に始められるため、手遊びを通して楽しみながら認知症予防に取り組めるでしょう。
介護職員として介護老人保健施設に勤務。
ケアマネジャー取得後は、在宅で生活する高齢者や家族をサポートする。
現在はWebライターとして、介護分野に関する記事を中心に執筆している。