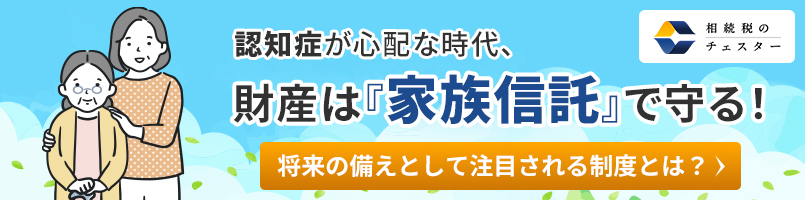認知症を予防する飲み物とは?摂取するべき有効成分や注意点を解説

認知症は、日常生活に支障をきたす病気です。その発症には生活習慣が関与するといわれており、特に食事は大きな影響を与えます。毎日口にする飲み物も例外ではなく、飲み物によっては認知症の予防効果も期待できます。本記事では、認知症予防に効果的な飲み物を紹介します。注意点も解説するため参考にしてください。
認知症とはどんな病気?

認知症とは、さまざまな病気によって脳の神経細胞の働きが徐々に低下し、記憶力や判断力が低下して社会生活に支障をきたす状態です。患者は65歳以上の高齢者に多いとされていますが、誰もが発症する可能性があります。
認知症には数種類のパターンがあり、発症の原因によって病名が異なります。血管性認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症などがありますが、最も発症確率が高いとされているのがアルツハイマー型認知症です。
アルツハイマー型認知症は生活習慣が大きく関与する
認知症の中で最も発症確率の高いアルツハイマー型認知症は、脳に「アミロイドβ」というたんぱく質が蓄積することが原因で発症するといわれています。アミロイドβは、全ての人の脳に存在するたんぱく質で、通常は代謝の過程で分解、排出されます。しかし、分解がうまくいかない場合、体内に蓄積していってしまうのです。
アミロイドβの蓄積は、運動不足や睡眠不足など不規則な生活習慣が原因で起こるとされています。蓄積したアミロイドβは、毒性の強い大きなたんぱく質に変化し、排出されにくくなります。この大きなたんぱく質によって、アルツハイマー型認知症が発症するのです。
アルツハイマー型認知症の発症には乱れた生活習慣が大きく関与しています。そのため、認知症予防には、日頃の生活習慣を見直し、規則正しい生活を送ることが大切です。
糖尿病ではアミロイドβが蓄積しやすい
アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβの蓄積には、生活習慣が大きく関わっています。さらに、生活習慣病である糖尿病の患者においては、よりアミロイドβが蓄積しやすいという研究結果が報告されているのです。
血糖値を下げるのに働くインスリンは、体内でインスリン分解酵素によって処理されています。このインスリン分解酵素には、アミロイドβを分解する働きがあります。しかし、糖尿病によって血液中のインスリン量が増えると、インスリン分解酵素はインスリンの分解で手一杯になるため、アミロイドβの分解ができません。
その結果、アミロイドβは分解されずに蓄積してしまいます。つまり、糖尿病を予防してインスリンの分泌量を正常に保つことが、認知症の予防につながるのです。
認知症予防に摂取するべき有効成分と含まれる飲み物

最近の研究で、認知症を予防するために有効な成分があることがわかってきています。中でも、カテキンやクロロゲン酸などのポリフェノールが有効とされ、私たちの身近な飲み物に含まれており手軽に摂取できます。ここでは、認知症予防に有効な飲み物とその成分について見ていきましょう。
緑茶:カテキン
緑茶に含まれる「カテキン」はポリフェノールの一種で、緑茶の苦味や渋味のもととなる成分です。カテキンには、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドβの蓄積を抑制する作用があります。また、カテキンは強力な抗酸化作用を持つため、脳細胞の酸化抑制にも役立つといわれています。
緑茶を飲むことで脳組織の委縮を抑制し、学習能力や記憶力の低下を防ぐ効果も期待できるとされ、認知症予防にも効果的です。
さらに緑茶には「テアニン」という成分も含まれています。テアニンはお茶のうまみ成分ですが、カテキンと同様に認知症予防効果が期待できます。テアニンが神経細胞を保護し、脳の血流を改善することで脳の機能を良好に保つのです。
コーヒー:クロロゲン酸
コーヒーにはポリフェノールの一種である「クロロゲン酸」が含まれています。クロロゲン酸にも強力な抗酸化作用があり、活性酸素による酸化を予防する作用があります。また、体内で脂肪の蓄積を抑える作用もあり、血管を健康な状態に保つのにも有効です。
赤ワイン:ポリフェノール
赤ワインに含まれているのは「アントシアニン」「レスベラトロール」という強力な抗酸化作用を持つポリフェノールです。特にレスベラトロールは、脳の血流量を増加させることで認知症の予防に有効とされています。1日250ml~500mlの赤ワインが、アルツハイマー型認知症の予防に有効という報告もあります。
赤ワインには神経細胞を刺激し、神経細胞を再生させる酵素の働きを高める作用もあるのです。脳の細胞同士を結び付けることで、高齢者の記憶力回復にも役立ちます。
ただし、赤ワインはアルコールです。適量を守り、休肝日も設けながらうまく取り入れましょう。
認知症を予防する飲み物を飲む際の注意点

認知症予防に効果的な飲み物を飲む際でも、注意しなければならない点もあります。ここでは、有効成分を含む飲み物を飲む際に気をつけたいポイントを紹介します。
認知症予防に効果的な飲み物でも、飲みすぎには注意
認知症予防に効果があるからといって、たくさん飲めばよいというわけではありません。飲み過ぎは体の負担になる場合もあるため、適量を飲むようにしましょう。
特にコーヒーや緑茶には、カフェインが含まれています。カフェインの摂りすぎは睡眠の障害になるため、飲み過ぎないようにしましょう。
飲むタイミングに考慮する
飲むタイミングにも注意が必要です。先述の通り、緑茶やコーヒーにはカフェインが含まれています。睡眠前に飲むと目が冴えて、睡眠を妨げてしまいます。朝や昼食後、活動を始める前に飲むと、頭もさえて効率的です。
コーヒーは砂糖やミルクを入れすぎない
認知症予防を目的としてコーヒーを飲む際、砂糖やミルクの入れすぎにも注意が必要です。認知症を予防するため積極的にコーヒーを飲んだとしても、砂糖やミルクのたっぷり入った飲み物を飲んでいては、血糖が上昇して糖尿病の原因となってしまいます。
コーヒーを飲む際にはブラックか、無糖のカフェオレなどを選ぶようにしましょう。また、市販のものはあらかじめ甘く味付けされているものもあるため、できる限りその場で淹れたコーヒーを飲むのがおすすめです。
認知症を予防するための生活習慣

認知症の発症には、生活習慣が大きく関与します。そのため、認知症を予防しながら健康的な生活を送るには、日々の生活習慣がとても大切です。ここでは、認知症を予防するための生活習慣のポイントを紹介します。
栄養バランスのよい食事を摂る
食事を摂ることは脳を刺激し、多くの機能を使うため認知症予防に効果的です。よく噛んで食べると、さらに脳へのよい刺激になります。また、食事の内容も大切で、栄養バランスの整った食事を適切な量食べることが理想です。特に、脳に必要な栄養素である魚油(DHA、EPA)をしっかり摂るように心がけましょう。
一方、肉の脂である飽和脂肪酸やショートニング、マーガリンなどのトランス脂肪酸は、認知症のリスクを上げるとされています。高齢者でも、スナック菓子やインスタント食品などを好む方はいますが、このような食品はできる限り食べないようにしましょう。
肥満を予防する
肥満もアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めるといわれています。そのため、日頃から肥満予防を意識して生活することも、認知症予防につながります。規則正しい食生活や運動習慣など、肥満予防はそのまま認知症予防のための生活習慣です。肥満にならないよう、意識しましょう。
塩分、糖分の摂り過ぎに注意する
食習慣の中では、塩分や糖分の摂り過ぎに注意が必要です。特に高齢者では、塩分、糖分の摂り過ぎが認知症以外の病気の引き金にもなる場合があります。
塩分の摂り過ぎは、高血圧による脳梗塞のリスクになります。また、糖分の摂り過ぎは糖尿病や耐糖能異常を引き起こし、結果的にどちらも脳血管型認知症やアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めます。塩分や糖分の摂り過ぎには、十分注意しましょう。
適度な睡眠、適度な運動を心がける
運動習慣は、認知症の発症リスクを低下させるといわれています。特に、ウォーキングなどの軽い有酸素運動が効果的です。運動不足を感じている方は積極的に運動を取り入れ、体を動かしましょう。運動の目安は、週3回以上の頻度で継続して行うことが大切です。無理のない範囲で続けることを意識してみましょう。
さらに、睡眠習慣も認知症の発症に関与するとされています。長すぎる、もしくは短すぎる不適切な睡眠は、認知症を発症するリスクを高めます。高齢者では、早寝早起きを心がけ、7時間~8時間を目安に質のよい睡眠をとるようにしましょう。就寝前のスマホ操作は睡眠の質を低下させるため、控えてください。
認知症予防に効果的な飲み物を取り入れ、認知症を予防しましょう

この記事のまとめ
- 認知症とは、脳の神経細胞の働きが徐々に低下することで記憶力や認知能力が低下して、日常生活に支障をきたす病気である
- 認知症にはいくつかの種類があり、中でもアルツハイマー型認知症が最も発症率が高いとされている
- アルツハイマー型認知症は、アミロイドβというたんぱく質が蓄積することで生じる
- 認知症予防には、カテキンやクロロゲン酸、ポリフェノールを含む飲み物が効果的
- 認知症予防のため、栄養バランスの整った食事や適度な運動、適度な睡眠を心がける
認知症は生活習慣の改善によって予防が可能な病気です。本記事で紹介した内容を参考に、予防に効果的な飲み物や生活習慣を取り入れ、健康維持に役立ててみてください。
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業。
管理栄養士として病院に勤務し、患者様の栄養管理及び栄養指導に従事。
糖尿病患者や腎臓病患者を中心に、病状の進行を防ぐための食事指導を行う。食事と健康、美容に関する記事を中心に管理栄養士ライターとして活動中。