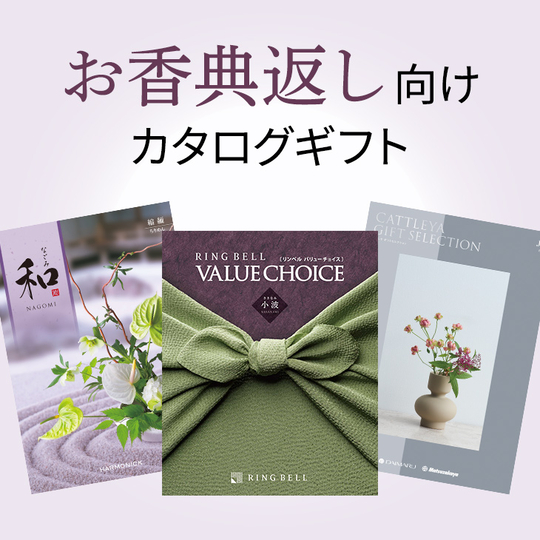弔電のお礼はどうする?お礼状の例文やマナーを解説

葬儀の弔電をいただいたときはお礼を伝える必要があります。しかし、どのような方法でお礼を伝えるべきか分からないという方もいるでしょう。本記事では弔電のお礼の方法やお礼状の例文、マナーについて解説します。
弔電を受け取ったときのお礼の方法

弔電とは、事情によってお通夜や葬儀に参列できない方が弔意を伝えるために送る電報のことです。弔電を受け取った遺族側は、送った相手に対して後日お礼をする必要があります。しかし、どんな方法でお礼をすべきか分からない方もいるでしょう。ここでは、お礼の方法について解説します。
弔電のお礼はお礼状で伝える
弔電を受け取ったときのお礼は、お礼状で伝えるのが一般的です。本来は弔電を送ってくれた相手に直接面会し、お礼の言葉を伝えるのがもっとも丁寧な方法ですが、今ではお礼状を送ることが多くなっています。
似ているものに会葬礼状がありますが、会葬礼状はお通夜や葬儀に参列していただいた方に渡すお礼状であり、弔電を送っていただいた方に送るお礼状とは別物のため注意しましょう。
また、弔電のみをいただいたときにはお礼の品は不要です。お礼の品を送る方が丁寧に思えるかもしれませんが、相手に気を遣わせてしまい、かえって失礼にあたることもあるため用意しなくて構いません。
弔電と一緒に香典を受け取った場合は香典返しを送る
弔電と一緒に香典や供花、供物を受け取った場合は、お礼の品として香典返しを忌明け後に送ります。香典返しの相場は、いただいた品の3分の1~半額が一般的です。
送る品物は、お菓子やお茶、タオル、洗剤などといった消え物と呼ばれる消耗品を選びましょう。
相手の好きな物、誰でも使いやすく便利な物、相手方の家族構成などを意識して香典返しの品物を選ぶと喜ばれるでしょう。また香典返しには、お礼状を添えて送るのがマナーとなっているため、忘れないよう注意が必要です。
弔電を受け取ったときに送るお礼状に含めたい内容

葬儀の弔電を受け取ったときに送るお礼状を書く際には、いくつか含めたい内容があります。お礼状に何を書けばよいか分からない方も、以下の内容を意識すると書きやすいでしょう。
故人の名前
弔電のお礼状に必ず含めたいのが故人の名前です。誰の葬儀の弔電に対するお礼状なのかが一目で分かるよう、お礼状の冒頭部分に記載しましょう。
書き方は、故人の名前の前に「故」、後に「儀」の文字を入れて「故〇〇(故人の名前)儀」や「亡き祖父〇〇(故人の名前)儀」などと記載します。会社から出すお礼状の場合は「弊社△△(役職)〇〇(故人の名前)儀」と記載するようにしましょう。
弔電をいただいたお礼
弔電をいただいたお礼も、必ず記載しましょう。お通夜や葬儀には参列できないものの、多忙の中で弔電の手配をしていただいたことへの感謝の気持ちを記します。
「御多忙にもかかわらず弔電を賜りましたこと厚く御礼申し上げます」や「御心のこもった弔電を賜り誠にありがとうございます」などと記載しましょう。
略式であることのお詫び
弔電のお礼はお礼状をもって伝えるのが一般的ではありますが、先述の通り、もっとも丁寧な方法は直接お会いしてお礼を伝える方法です。お礼状の送付はあくまでも略式となるため、お詫びを記載します。
「本来であれば直接お会いして御礼を申し上げるべきところですが略儀ながら書中をもちまして失礼いたします」などと記すとよいでしょう。
差出人の名前
誰からの弔電のお礼状であるかが伝わるように、差出人の名前を最後に記載します。差出人の名前は喪主の名前を記載します。
実際に差出人が喪主でない場合など、別の人の名前を記載したい場合には喪主との連名にします。また、喪主の名前の後に「親族一同」と記載することもあります。弔電を送ってくれた相手と親族ぐるみで関わりがある場合などは検討するとよいでしょう。
弔電を受け取ったときに送るお礼状の例文

ここからは、弔電を受け取ったときに送るお礼状の例文を紹介します。相手別に例文を用意しているので、どんな文章を書くべきか分からないという方は参考にしてください。
個人に送るお礼状の例文
このたびは 故 東博太郎(故人の名前)儀の葬儀に際しまして ご丁重な弔電を賜り厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして 滞りなく葬儀を相営むことができました
亡き父にかわり 生前の御厚情に深く感謝申し上げますとともに 今後も生前と変わらぬ御厚誼を賜りますよう お願い申し上げます
本来であれば直接お会いして御礼をお伝えすべきところ 略儀ながら書中をもちまして失礼いたします
令和◯年◯月◯日
住所
喪主 東博一郎 親族一同
会社に送るお礼状の例文
拝啓
亡き父 東博太郎(故人の名前)儀の葬儀に際しまして ご多忙中にもかかわらず皆様からご丁重な弔電を賜りましたこと 厚く御礼申し上げます
おかげをもちまして 葬儀をつつがなく済ませることができました
出社は来週の初めを予定しております
本来であれば皆様に直接お会いしてお礼を申し上げるべきところですが 略儀ながら書中をもってのご挨拶とさせていただきます
敬具
令和◯年◯月◯日
住所
喪主 東博一郎
親しい間柄の人へ送るお礼状の例文
このたびは 亡き祖父 東博太郎(故人の名前)儀の葬儀に際しまして 心温まるご丁寧な弔電をいただき誠にありがとうございました
おかげをもちまして つつがなく葬儀を営むことができましたことをご報告いたします
突然のことで家族一同驚きましたが △△(相手の名前)さんからいただいた温かいお言葉に励まされました
祖父も△△さんからのお言葉をいただき さぞ喜んでいることと存じます
お近くにいらした際には ぜひお立ち寄りいただき 祖父との思い出話などお教えいただきたく存じます
今後も変わらぬご指導とご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます
本来であれば直接お目にかかってお礼をお伝えしたいところですが 略儀ながら書中にて失礼いたします
令和◯年◯月◯日
住所
喪主東博一郎 親族一同
弔電のお礼状におけるマナー

最後に、弔電のお礼状においてのマナーを紹介します。
お礼状は葬儀後一週間以内に送る
弔電を受け取ったときのお礼状は葬儀後一週間以内に送るよう心がけましょう。
大切な人を亡くし、心身ともに疲れている中でお礼状を手配するのは大変なため無理はせず、かといって遅すぎると失礼にあたるため、できるだけ早く送るよう意識しましょう。お礼状を送るのが遅くなってしまった場合は、文面にお礼が遅くなったことのお詫びを記載することも大切です。
一般的には手紙やはがきで送る
弔電を受け取ったときのお礼状は、手紙やはがきで送るのが一般的です。弔電に対するお礼状であることを意識して、白やグレーなどの落ち着いた色や、無地または蓮の花などが入ったシンプルなデザインのものを用意しましょう。
はがきの場合は、郵便局で手に入れられる弔事用のデザインが施されたはがきや切手を使用するとよいです。手紙の場合は、便箋だけでなく封筒も注意します。「不幸が重なる」ことを連想させる二重封筒は避け、一重封筒を使いましょう。茶封筒はカジュアルな印象を与えるため、フォーマルな場面で使える白無地の和封筒を用意することも大切です。
また、弔電を送ってくれた相手とよほど親しい間柄である場合や、相手の住所が分からない場合にはメールや電話でお礼を伝えても構いません。
ただし、メールは相手によっては失礼と捉える方もいるかもしれません。そのため「メールでのお礼となってしまい大変申し訳ございません」などのお詫びのメッセージも必ず記載しましょう。
 お礼状の封筒・便箋|Amazon.co.jp
お礼状の封筒・便箋|Amazon.co.jp
縦書きで記載する
弔電のお礼状は縦書きで記載するのがマナーです。横書きはカジュアルな印象を与えてしまう可能性があるため避けた方がよいでしょう。
お礼状は印刷と手書きのどちらでも失礼にはあたりませんが、手書きの方がより丁寧です。手書きの場合、縦書きに慣れていないと縦のラインがずれてしまうこともあるため、時折全体を見ながら書き進めていくと綺麗に仕上がりやすいでしょう。
時候の挨拶は書かない
一般的な手紙とは異なり、弔電のお礼状では時候の挨拶は省略します。時候の挨拶を記載した方が丁寧に思えるかもしれませんが、簡潔に本題に入りましょう。
「拝啓」や「敬具」などの頭語と結語は記載してもしなくてもマナー違反ではないため、記載するかどうかは書き手が自由に決めてよいでしょう。しかし記載する場合は、必ず頭語と結語の両方をセットで記載するよう注意が必要です。
句読点は使わない
弔電を受け取った際のお礼状には、句読点は使用しません。普段の文章の感覚で思わず句読点を使用してしまわないか心配な方は下書きをすると安心です。句読点を使いたい部分には空白や改行をして対応しましょう。
弔電を受け取ったときには葬儀後一週間以内にお礼状を送りましょう

この記事のまとめ
- お通夜や葬儀に弔電を受け取ったときにはお礼状を送るのが一般的
- 一番丁寧なお礼の伝え方はお礼状ではなく直接会ってお礼を伝えること
- 弔電と一緒に香典をもらった場合は香典返しを送る
- お礼状に含めたい内容は故人の名前や弔電をもらったお礼などを記載する
- お礼状に何を書けばいいか迷ったときには例文を参考にすると書きやすい
- 弔電のお礼状におけるマナーには葬儀後一週間以内に送るなどがある
お通夜や葬儀に弔電を受け取ったときにはお礼状を用意します。お礼状は感謝の気持ちが伝わるよう、マナーに注意しましょう。お礼状にどんなことを書けばよいか分からない場合は、本記事で紹介した例文を参考にしてみてください。
2006年に葬儀の仕事をスタート。「安定している業界だから」と飛び込んだが、働くうちに、お客さまの大切なセレモニーをサポートする仕事へのやりがいを強く感じるように。以来、年間100件以上の葬儀に携わる。長年の経験を活かし、「東京博善のお葬式」葬祭プランナーに着任。2023年2月代表取締役へ就任。