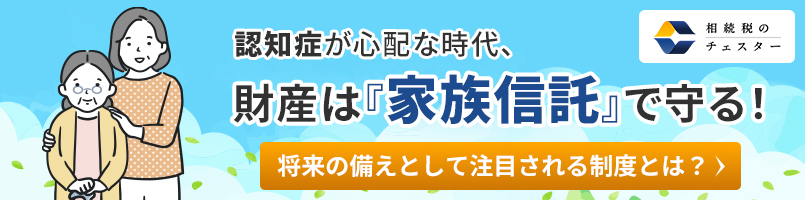認知症による徘徊の対策7つ!介護者に活用してほしい方法や負担を軽減するアイテムなどを解説

家族の中に認知症の人がいる場合、「徘徊」が大きな課題となっている家庭も多いのではないでしょうか?徘徊は迷子や事故にあう恐れがあり、介護者の大きな精神的・身体的負担となります。本記事では、認知症による徘徊の原因や具体的な対策法、介護者の負担を軽減するアイテムを解説していきます。
認知症による徘徊とは

認知症による徘徊は、認知症の症状の中でも介護者にとって大きな負担となります。本人は自分自身の目的を果たすために外へ出ているつもりで、無意識に歩いているわけではありません。しかし、途中で自身がどこへ向かっているのか分からなくなり、迷子になってしまうのです。
徘徊は、自宅へ戻れなくなり行方不明になる恐れや、交通事故に遭う危険が伴います。介護者は認知症の人の安全を確保すべく見守りや介助を行う必要があるため、大きな負担を抱えることになるでしょう。
徘徊を予防するには、生活環境を整えることや本人の行動パターンの理解が重要です。また、もし迷子になった場合でもすぐに見つけられるように、工夫や対策をする必要があります。
認知症による徘徊の原因

認知症による徘徊の原因は、下記の三つと言われています。
認知症による徘徊の原因
- 身体的原因
- 精神的原因
- 環境的原因
徘徊の原因を特定して適切に対応することで、徘徊を防止できる場合があります。ここからは、認知症による徘徊の原因について詳しく説明していきます。
身体的原因
認知症による徘徊の原因の一つが、病気や身体的な不調です。認知症が進行していくと、自分の訴えを人に伝えることが難しくなります。
例えば、トイレに行きたいという基本的な欲求を言葉で表現ができないため、何も言わずにその場から離れようとすることがあります。また、お腹が空いて何か食べたくてもどうしたらよいのか分からず、外へ出てしまうこともあります。
このように、体調不良や欲求不満が徘徊へとつながることも考えられるため、日常的な健康管理や体調の確認が必要です。
精神的原因
精神的な要因も、認知症による徘徊の大きな原因のひとつです。例えば、もう退職しているのに「会社に行かないといけない」と、昔通っていた職場に行こうと外出する場合などが考えられます。また既に子供は独り立ちしているのに「子供を迎えに行かないといけない」と思い込み、夕方になると外出しようとする人もいます。
デイサービスを利用していても、夕方になると「家に帰りたい」「自宅まで送ってくれるの?」と落ち着かなくなる人もいます。これらの場合、不安や焦り、ストレスが原因と考えられます。
精神的な不安から徘徊が始まりそうになったときは、本人の気持ちを否定せずに受け止めることが大切です。本人の話を傾聴しながら、興味をそらしたり一緒に歩いたりすることも効果的です。
環境的原因
認知症による徘徊には、環境的な原因も大きく関係します。急な環境の変化や混乱しやすい環境は、ストレスや不安を増大させるため注意が必要です。
例えば、家具の配置が変わったことで「いつもと違う場所にいる」と感じ、家を出てしまうことがあります。また、外出先で自分がどこにいるのか分からなくなり、ひとりで歩き始めようとする場合もあります。
このように、環境の変化により徘徊が始まることを理解し、本人にとって安心できるような環境を整え、徘徊による危険を軽減しましょう。認知症の人が安心できる環境にするためには、家具の配置を変えないことや照明の明るさを適切にする、騒がしくしないなどの対応がおすすめです。
認知症による徘徊の具体的な対策法

ここからは、認知症による徘徊の具体的な対策法を説明します。
①生活パターンを知る
認知症の人の生活パターンの把握は、徘徊の予防に効果的です。睡眠時間や食事の好み、趣味など日々の生活習慣を理解することで、徘徊の傾向が把握しやすくなり本人に合わせた支援ができます。
例えば、夜間に徘徊する傾向がある場合、日中の活動量を増やして適度に疲れさせることで認知症の人は夜間によく眠れるようになります。生活パターンに合わせた対策ができれば、不安やストレスが軽減でき、徘徊を抑制できるでしょう。
②趣味や役割を見つける
認知症の人に趣味や役割を持ってもらうのは、徘徊の対策に効果的です。日常の中で役割があると自己肯定感が高まり、生活が充実していきます。
例えば、ガーデニングや簡単な家事、手芸など本人が楽しんで参加できる活動を見つけましょう。充実感のある作業や役割を持つことで「ここにいても大丈夫」という安心感が生まれ、不安やストレスを軽減できます。
③身体を動かす
徘徊するからと言って、認知症の人をじっと座らせておくのは逆効果です。エネルギーが発散できずに、徘徊のきっかけになる場合があります。適度な運動はストレス解消になり、心地よい疲労感も感じられるためおすすめです。夜間の安眠にもつながり、夜眠れずに外出したくなる衝動も改善する可能性があるでしょう。
また、散歩は足腰の筋力を鍛えることができ、トレーニングにもなります。どの程度の運動なら日常的に行ってよいか医師に確認をし、適切に行うことが大切です。
④体調を整える
認知症の人は体調管理をすることが大切です。体調不良になると、徘徊につながる場合があります。脱水傾向になり頭がぼーっとしたり、便秘で不快な状態だったりすると、本人はどうしたらよいのか分からず精神状態が不安定になり、徘徊へつながる可能性もあるのです。
体調が整うと徘徊したい衝動が落ち着くことがあるため、日頃からの体調管理は大切です。
⑤一緒に外出する
徘徊を無理に引き止めようとすると、余計に興奮してしまう場合があります。この場合、一緒に出かけることで気分転換になりストレス解消につながるでしょう。
本人の表情が穏やかになってきたら、景色を見ながら会話をしたり公園のベンチに座ってお茶を飲んだりすることもおすすめです。一緒に外出をすれば、本人が興味を持つ場所や立ち止まって休憩する場所など、徘徊した場合の行動も把握できるでしょう。
⑥地域と連携する
認知症の人の徘徊が始まったら、地域の人に協力を求めましょう。認知症の人の介護をひとりで行うのは大変で、精神的負担も大きいです。近所の人やお店などに本人の様子を話しておくことで、徘徊した際に見つけてもらえる可能性が高くなります。
また、行方不明者が出た際に、登録している携帯電話に一斉通知するネットワークを作っている自治体もあります。行方不明になったときのために市区町村や地域包括支援センターに相談し、登録しておくとよいでしょう。
⑦介護サービスを利用する
介護サービスを利用すると、日中の活動量が増えます。また、介護職なら認知症に対する知識を持っているため、適切なケアを受けられます。特にデイサービスやデイケア、ショートステイなどの利用は介護者が本人と距離を置くことができるため、気分転換にもなるでしょう。
認知症による徘徊への負担を軽減する対策アイテム

ここからは、認知症による徘徊で介護者の負担が軽減するアイテムを紹介します。
GPS端末を付ける
GPS端末の利用は、徘徊対策に有効な手段です。常に履いている靴に取り付けたり、外出する際に持っていくバッグに入れたりしましょう。GPS端末があればどこにいるのか把握ができるため、行方不明になったときに早く見つけられる可能性が高くなります。
ドアセンサーや人感センサーを設置する
徘徊対策で、ドアセンサーや人感センサーを活用する方法もあります。
ドアセンサーは、ドアが開くと反応して音が鳴ります。人感センサーは、人の動きを感知すると音や通知で知らせてくれるものです。本体から音が鳴るだけでなく、携帯電話に通知される機能が付いているものもあるため、離れた場所でも異変を知ることができます。
靴や持ち物に名前を書く
認知症の症状が進むと、自分の名前や住所が言えなくなる場合があります。誰かに発見された場合、身元が分かるものを身につけておくことで連絡しやすくなるため、靴や下着、財布やバッグなどに氏名や連絡先を記入しておくとよいでしょう。
認知症による徘徊が発生したときの対応方法

認知症による徘徊が発生したとき、介護者としてどのように対応すればよいのか事前に知っておくことが大切です。ここからは、正しい対応方法について解説していきます。
話を傾聴する
認知症の人が徘徊をしているときは、不安が大きく興奮している場合もあります。そのようなときに「心配したでしょ!」「どこにも行かないでって言ったよね!」などと強い口調で責めると、本人は余計に混乱します。
認知症の人はなぜ叱られたのかを忘れても、叱られて悲しい気持ちになったことは覚えていることが多いため、家族に対して悪い感情が残らないよう優しく声をかけましょう。
気をそらせる
徘徊の目的から気をそらすのも、有効な対応方法の一つです。認知症の人の徘徊は、周りから見ると目的もなく歩いているように見えます。しかし、本人にとっては「会社に行く」「畑に行く」などしっかりと目的を持っています。
そのようなとき、「今、車を呼んだのでお茶でも飲みましょう」「外は暑いので公園のベンチで休みましょう」などと声かけすると、徘徊の目的を忘れて素直に家に戻る場合も多いです。このように、本人の気分を変えることも効果的でしょう。
無理に止めようとしない
徘徊をしている最中に無理に止めさせると、認知症の人にとっては自分の目的が達成されず消化不良となり、連れ戻したとしてもすぐに徘徊を再開してしまう場合があります。
そのため、無理に徘徊を止めるのではなく、認知症の人と一緒に歩くことがおすすめです。一緒に歩くと安全を確保しながら徘徊の欲求を満たすことができ、歩いたことで身体的な疲労も出てくるため徘徊がおさまることが多いです。
警察に連絡する
認知症の人が行方不明になったら、すぐに警察へ連絡しましょう。「いつか戻ってくる」と考えて対応せずにいると、遠い場所に行ってしまう恐れがあります。また、認知症の人の単独での徘徊は交通事故にあったり脱水症状になったりするなど危険を伴います。冬であれば、夜間の気温低下により命が危険にさらされる場合もあるでしょう。認知症の人が行方不明になった場合は早急に対応することが大切です。
認知症による徘徊の対策法や対応方法を押さえて要介護者を見守りましょう

この記事のまとめ
- 認知症による徘徊は、介護者にとって大きな負担となっている
- 徘徊をしている本人は目的があって歩いている
- 認知症による徘徊の原因は、身体的・精神的・環境的原因の三つがある
- 認知症による徘徊の対策は、①生活パターンを知る②趣味や役割を見つける③身体を動かす④体調を整える⑤一緒に外出する⑥地域と連携する⑦介護サービスを利用する
- 認知症による徘徊の対策として、GPS端末やドアセンサーなどのアイテムを活用するのがおすすめ
- 認知症による徘徊が発生したときには、無理に止めようとせず話をよく聞いたり気をそらせる
認知症による徘徊は、介護者にとって常に心配の種です。いつ家を出ていってしまうか分からないため、常に気を張っている必要があります。徘徊を減らすには、本人の生活パターンを理解し、体調を整え、日々の生活の中で役割を持ってもらうことが効果的です。
GPS端末やドアセンサーのような徘徊対策のアイテムの使用や、介護サービスの利用などにより、介護者の負担が軽減され本人の安全も守ることができるでしょう。
介護職員として介護老人保健施設に勤務。
ケアマネジャー取得後は、在宅で生活する高齢者や家族をサポートする。
現在はWebライターとして、介護分野に関する記事を中心に執筆している。