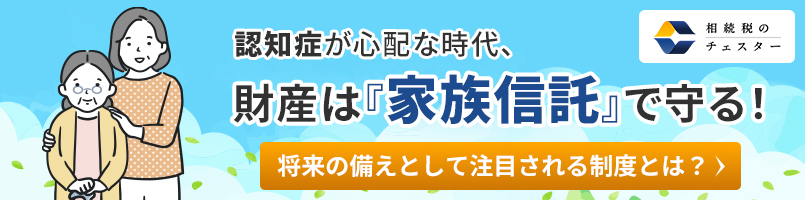高齢者の食事で大切なポイント|食品の選び方や食習慣などの注意点を押さえよう

高齢者は咀嚼機能が低下して食事量が減ったり、味覚が鈍くなることで濃い味付けを好むようになるなど、食事の栄養バランスが偏る傾向にあります。健康を維持するためには栄養不足にならないようバランスのよい食事を摂ることが重要です。本記事では、高齢者の食事のポイントやおすすめの食品を紹介します。
高齢者の食事で生じる問題点

高齢者は身体機能の低下や環境の変化によって食事量の減少やそれに伴う栄養不足などが生じやすくなります。ここでは、高齢者の食事で起こりやすい問題点について解説します。
加齢による噛む力、飲み込む力の衰え
高齢者は加齢や病気の影響で、嚙む力や飲み込む力が低下してきます。これは嚥下(えんげ)障害と呼ばれ、食べ物をうまく飲み込めなくなることで、食欲減退につながります。必要な食事量が減るため、気付かぬうちに栄養不足や脱水症になってしまう場合もあります。
孤食が増え、食事が簡素化する
近年、ひとり暮らしの高齢者の増加に伴い、食事をひとりで摂る「孤食」も増加しています。孤食では、自分の好きな物ばかり食べる傾向があり、栄養バランスが崩れやすくなります。また、自分だけのために食事の用意をするのが面倒という理由から、食事が簡素化することも少なくありません。
さらに孤食は食べる楽しみが失われ、欠食が多くなったり、食欲が出ずに食事量が減ることもあります。時には家族や友人と一緒に食事をする機会を作ったり、楽しい環境で食事ができるように周りがサポートすることも必要です。
味覚が鈍くなる
高齢になると、舌や口腔内にある味蕾(みらい)と呼ばれる、味を感じる細胞が減少します。新生児に比べ高齢者の味蕾は約半分になるとされ、味を感じにくくなります。今までと同じ食事でも物足りなさを感じるのは味蕾の減少によるものです。
味覚が鈍くなると濃い味付けを好み、塩分やカロリーの過剰摂取につながります。塩分やカロリーの摂り過ぎは高血圧や肥満の原因になり、動脈硬化や心筋梗塞など生活習慣病のリスクが高まるため注意が必要です。濃い味付けの食事ではなく、素材の旨味を活かした食事に慣れることが大切です。
栄養素が不足しがちになる
高齢者は食事量の減少に伴い、必要な栄養素が不足しがちになります。栄養が不足すると身体に必要なエネルギーや筋肉、皮膚、内臓などをつくるたんぱく質やビタミンが不足し、低栄養に陥ります。高齢者の低栄養は筋肉量の減少や運動能力の低下につながり、生活の質を落とす原因になるため、注意が必要です。
次に、高齢者にとって不足すると問題がある栄養素について解説します。これらの栄養素が不足しないように、毎日の食事を意識してバランスのよい食事を心がけましょう。
たんぱく質
たんぱく質は、身体の構成に必要不可欠な栄養素です。食事の総量が減った高齢者でも、食事から摂取すべきたんぱく質の量は、若い世代と変わりません。たんぱく質は内臓や皮膚の他に、神経伝達物質の材料でもあるため、不足すると思考力の低下にも影響します。
さらに、たんぱく質の不足は筋肉量にも影響するため注意が必要です。筋肉が減少することで、日常的な活動に必要な運動能力の低下につながります。また、運動能力が低下すると食欲も減退し、食事量が減るといった負の連鎖に陥ります。そのため、たんぱく質は食事からしっかり摂る必要があります。
ビタミン類
ビタミン類は、体のさまざまな機能を調整する働きを担う、生命活動の維持に必要不可欠な栄養素です。人の体内では合成できないため、食事から摂取する必要があり、不足すると欠乏症が起こるため、意識して摂る必要があります。
バランスのよい食事を摂っていれば、ビタミンが極端に不足することはありません。しかし、食事量の減った高齢者では、特に動物性食品に含まれるビタミンD、Eが不足しやすい傾向にあります。
ビタミンDは骨粗鬆症の予防に、ビタミンEは強い抗酸化作用により生活習慣病の予防や老化防止に効果があります。ビタミンDは魚類やきのこ類に、ビタミンEは卵、種実類、豆類などに多く含まれているため、これらの食材を意識して摂りましょう。
ミネラル類
ミネラル類の中でも、高齢者では特にカルシウムの摂取が重要です。カルシウムが不足すると、骨が弱くなり骨折して寝たきりになってしまうなど、生活の質を落としかねません。ミネラルは緑黄色野菜や乳製品に多く含まれているため、意識して摂るようにしましょう。
食物繊維
食物繊維は整腸作用や血糖値、コレステロール値の低下作用などが期待できる栄養素です。生活習慣病予防のために進んで摂りたい食材ですが、食物繊維を含む食材は野菜や果物、きのこ類、海藻類などの硬い物や噛みにくい物が多く、高齢者は不足しがちになります。
食物繊維が不足しないために、これらの食材は柔らかく煮たり細かく刻むなどの工夫をして食事に取り入れるようにしましょう。
高齢者が食べやすい食品・食べにくい食品

ここからは、高齢者が食べやすい食品と食べにくい食品を紹介します。食事を摂りにくい時には食べやすい食品を食べて栄養補給に努めましょう。
食べやすい食品
以下にまとめたような食品は比較的食べやすい食品です。ポイントは、誤嚥(ごえん)しないこと。栄養不足にならないためには、このような食品をうまく利用して食事量を保つようにしましょう。
高齢者が食べやすい食品
- とろみのある食品:お粥、カレー、シチューなど
- のどごしのよい食品:ゼリー、プリン、茶わん蒸しなど
- 口の中でまとまりやすい食品:うどん、フレンチトーストなど
- 適度な水分、油分のある食品:マヨネーズ和え、あんかけ料理など
食べにくい食品
噛む力や飲み込む力が低下すると、以下のような食品は食べにくいと感じます。誤嚥や窒息などのリスクもあるため食べる際は注意しましょう。
高齢者が食べにくい食品
- パサパサしていて水分の少ない食品:パン、ゆで卵、カステラ、高野豆腐など
- ベタベタして粘り気の強い食品:もち、団子など
- のどに張り付きやすい食品:海苔、葉物野菜など
- 噛み切れにくい食品:タコ、イカ、こんにゃく、肉のスジなど
- 酸味の強い食品:酢の物、柑橘類、オレンジジュースなど
高齢者の食事で工夫すること

加齢に伴う身体的な変化は誰にでも起こることです。だからといって、食事をしないわけにもいきません。そのため、高齢者の食事では身体の変化に合わせて食事の内容を工夫することがポイントです。
栄養バランスのよい食事を摂る
高齢者の食事では栄養バランスの整った内容を心がけて、必要な栄養素を摂取しましょう。バランスのよい食事とは、主食、主菜、副菜のそろった食事です。
主食になる炭水化物は活動のエネルギー源となります。炭水化物が不足すると低血糖になりやすく、めまいや、集中力の低下につながります。主菜はたんぱく質がメインの食べ物となるため、不足すると栄養不足になるリスクが高まります。高齢者の食事では、主菜も欠かさず食べましょう。
副菜は野菜、海藻、きのこ類などビタミンや食物繊維を多く含む食べ物です。これらも高齢者の身体の調整機能を正常に保つために必要な栄養素なため、食事に摂り入れるよう意識しましょう。
食事の調理方法を工夫する
食事は調理方法によっても食べやすさが変わります。高齢者が食べにくい食材でも、調理方法を工夫することで食べやすくなるため、参考にしてみてください。
噛みやすくする
硬くて噛みにくい食材は、調理して噛みやすくしましょう。肉は繊維を断ち切るようにカットしたり、よく叩いて柔らかくすると食べやすくなります。野菜は一口大にカットしたり、柔らかくなるまで煮込むことで噛みやすくなります。歯茎でつぶせるくらい柔らかくなると、食べやすくなります。
飲み込みやすくする
食材を飲み込みやすくすることも大切です。サラサラした液体にはとろみをつけます。バラバラした食材はマヨネーズなど油脂成分を使ってまとめることで食べやすくなります。また、パンのようなパサパサの食材は口の中の水分を奪われて食べにくいため、牛乳に浸すなど水分を含ませると食べやすくなります。
また、高齢者が主食でご飯を食べる際には、全粥や軟飯がおすすめです。まとまりやすく食べやすいのもポイントですが、全粥や軟飯は水分も多く含むため、脱水予防にも効果的です。
食事中の姿勢に注意する
高齢者が食事を摂る際には、姿勢も重要です。誤嚥のリスクを避けるために、正しい姿勢で食事を摂る必要があります。座ることができる人は、椅子に座って食事を摂るのが理想的です。
深く腰掛けた状態で、足が床につき、膝が90度に曲がることを意識しましょう。上半身は軽く前かがみで、顎を少し引くようにします。椅子にもたれて上向きや真正面を向くと、のどから気管への角度が直角になり、食べ物が気管に入りやすくなるため注意が必要です。
食欲のない時は無理に食べようとしない
ここまで食事量が減ることが問題だと述べてきましたが、食欲がない時には無理して食べる必要はありません。無理して食べることがストレスになったり、食べることがプレッシャーになって食欲がさらに減退することもあります。食べたくない時には無理に食べないようにしましょう。
食事量が確保できない場合は、間食に栄養のある物を食べたり、食べたいと思った時に食べるようにしましょう。食欲が湧く方法として、たまには自分の好きな物を思い切り食べることもよいでしょう。
美味しく食べるための食事習慣

ここまで述べたように、食事量の減少には高齢者ならではの理由があります。加齢によるものもあり、自然なことではあるものの、低栄養のリスクを避けるためにも食事は美味しく楽しく食べたいものです。ここでは、高齢者が食事を美味しく食べるためのポイントを解説します。
適度な運動を取り入れる
運動は、身体機能の向上だけでなく、ストレス解消や生活習慣病の予防など健康維持に効果的なメリットが多くあります。また、程よく身体を動かすことで代謝が良くなり胃腸の働きが良くなります。食欲が増進し、食事量の増加も期待できます。
ストレスをためない
胃は自律神経によってコントロールされているため、強いストレスによって消化吸収の働きが悪くなります。それにより、胃もたれや胃のムカつきなどの不調が現れます。高齢者で食欲がわかない場合、ストレスが原因である場合もあります。
ストレスは胃以外にも身体のさまざまな働きに影響します。できる限り、ストレスをためない生活を心がけて、精神的にも健康な状態を目指しましょう。
良質な睡眠をとる
良質な睡眠をとると、心も身体も十分に休養ができます。睡眠不足は身体の疲労が取れないだけでなく、自律神経にも影響を与えます。睡眠不足によって自律神経が乱れ、胃腸が正常に働かなくなることで食欲低下、胃もたれ、胃痛、便秘、下痢といった不調が現れる可能性もあります。
高齢者は睡眠の質の低下により、眠りが浅くなって何度も目を覚ましてしまうことがあります。良質な睡眠を取るために、食事は就寝3時間前に終え、湯船につかってリラックスするなどの工夫をして身体を十分に休養させてあげましょう。
高齢者は食事量の減少や栄養バランスの偏りに注意しましょう

この記事のまとめ
- 高齢者の食事では、嚥下機能の低下や食事環境の孤食化、味覚の変化などにより健康を害する問題が生じやすい
- 食事量の減少によって、高齢者はたんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維などの栄養素が不足するため意識して摂取する
- 加齢による嚥下機能の低下によって食べにくい食材がでてくるため、食べやすく調理するとよい
- 高齢者の食事は調理方法や食べる時の姿勢に気を付け、栄養バランスのとれた食事を心がける
- 食事を美味しく食べるために、適度な運動、ストレスをためない、質のよい睡眠をとることも大切
高齢者の食事では、加齢に伴うさまざまな変化によって起こる問題を考慮し、個人にあった食事を摂ることが大切です。特に、食事量の減少による栄養不足には十分注意し、低栄養にならないよう注意する必要があります。
今回紹介した高齢者が食べやすい食品、食べにくい食品を理解し、必要量を満たした食事を心がけてみてください。また、調理方法や食事環境、姿勢など高齢者が食べやすくなるポイントを押さえ、健康的な食生活を送りましょう。
武庫川女子大学生活環境学部食物栄養学科卒業。
管理栄養士として病院に勤務し、患者様の栄養管理及び栄養指導に従事。
糖尿病患者や腎臓病患者を中心に、病状の進行を防ぐための食事指導を行う。食事と健康、美容に関する記事を中心に管理栄養士ライターとして活動中。