DIEwithZEROに学ぶ、終活支援の新たな視点 よりよく生きるための終活に、葬儀社がどう寄り添うか

これまで終活は、遺言書の作成やエンディングノートの記入、仏壇やお墓の準備、資産の整理といった、“ 死に備える行為” として捉えられてきた。「残された家族に迷惑をかけたくない」「きれいに片づけておきたい」といった意識が出発点となっている場合が多い。しかし今、終活のあり方が静かに変化している。「どう死ぬか」よりも「どう生きるか」に関心を向ける人が増えているのだ。その流れを後押しする一冊が、世界的ベストセラーとなった『DIE WITHZERO』(ビル・パーキンス著)である。
思い出こそが最大の“資産”である
著者は、人生における“時間・体力・お金”という限られた資源を、どのように使い切るかを問う。「人生は思い出の総量で決まる」「経験にこそ価値がある」といった言葉が象徴するように、単に資産を残すのではなく、体験に投資することが、人生の満足度を高める鍵であると説いている。
「子どもが小さいうちに旅行する」、「体力があるうちにやりたいことに挑戦する」、「大切な人に想いを伝える」といった行動が、人生を“豊かに使いきる”ための本質であるとされている。
終活を「これから」の話に変えるために
この価値観は、葬儀社が担う終活支援や、生前葬といったニーズにおいても、重要なヒントとなる。相談者がこれまでの人生を整理すると同時に、これからの人生を見つめ直す機会を提供することは、葬儀社の新たな役割と言えそうだ。
そのためには、葬儀の形式や費用、事務的な流れを説明するだけでなく、人生に寄り添う問いかけを用意することが効果的である。たとえば、以下のような質問が対話の入口となる。
質問例
- これまでの人生で「やってよかった」と感じたことは何か
- 今の体力でしかできないことに挑戦するとしたら何か
- ご家族にどのような思い出や言葉を残したいか
- 最後に誰とどのような時間を過ごしたいか
こうした問いを通じて、会話は形式から感情へ、そして信頼へと深まっていく。
人生の伴走者”という新たなポジション
葬儀社が「その人らしい人生を支える存在」になることは、結果として事前相談や顧客との関係性の質を高め、地域で選ばれるブランドづくりにもつながる。
また、『DIE WITH ZERO』の視点は、家族の関わり方にも影響を与える。「親には元気なうちに何をしてほしいか」、「遺産をどう残すか」ではなく、「今、生きているうちにどんな経験を共有できるか」というテーマは、終活を“家族全体の対話の場”へと広げる。
葬儀社にとって、こうした終活支援は“情報提供”ではなく、“対話を生む場”の創出である。人生を振り返り、これからに希望を見出す人に伴走する存在として、葬儀社が果たせる役割はこれまで以上に大きい。
終活支援を“事業”として育てる視点

終活へのニーズは年々高まりを見せており、葬儀社にとっては相談機会の入り口としてだけでなく、信頼関係の構築やサービス拡張のチャンスとして捉えることができる。終活セミナーや生前相談をきっかけに、仏壇・墓地・相続・保険・身元保証といった周辺サービスと連携した提案へとつなげることで、顧客との長期的な関係性を築くことが可能である。
その際に重要となるのが、「商品説明」だけで終わらせないことだ。人は“納得して生きたい”という深い欲求を抱えている。「なぜ今、終活なのか」、「その人にとって何が“思い出の投資”になるのか」。そうした本質的な問いを共に考える姿勢こそが、顧客の信頼を生み、結果として地域に根ざしたブランドの強化にもつながっていく。
本書は“終活を支える人”にも力をくれる
『DIE WITH ZERO』は、単なるマネー本ではなく、人生観を再構築する“哲学書”である。限られた人生をいかに豊かに使いきるか。その視点は、葬儀社としての提案力にも深みを与えてくれる。
終活とは、「死に備えること」ではなく、「よりよく生ききるための第一歩」である。
この本は、終活に携わるすべての人に、自らの人生のあり方を問い直すきっかけを与えてくれるだろう。ぜひ一度、手に取っていただきたい。きっと、相談者との対話の質が変わる一冊になるはずだ。
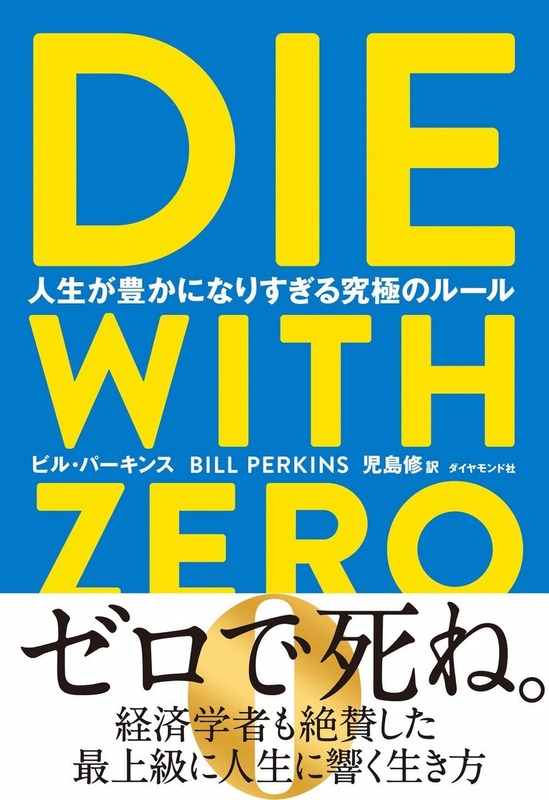
『DIE WITH ZERO』(ビル・パーキンス著/ダイヤモンド社)
「 死ぬときに最も後悔しない人生」とは何かを問い直すベストセラー。お金・時間・体力のバランスに着目し、「経験に投資し、思い出を最大化せよ」と説く。人生の最適な“ 使いきり方” を提示し、働きすぎや先送りの人生に一石を投じている。


















