【世界の葬祭文化24】中国で広がる「日本式介護」最新事情 ~介護サービスは「おもてなし」と技術力で勝負~

世界に先駆けて超高齢社会を迎えた日本が「介護の先生」として世界から注目されています。とくに、急速な高齢化に直面するアジア諸国では、日本の介護技術や運営ノウハウへの期待が高まり、中でも中国では、日本の事業者が続々と現地に進出し、「日本式介護」の旗印のもとで着実な成果を上げています。今回は、なぜ日本の介護技術が世界から求められているのか、その要因と中国での具体的な展開事例をご紹介します。
世界が注目する日本の介護技術

世界各国で高齢化が進む中、豊富な実戦経験を持つ日本の介護サービスは、国際的に高く評価されています。日本は2000年に介護保険制度をスタートさせ、20年以上にわたって試行錯誤を重ねてきました。その結果、自立支援を重視したケアマネジメントシステムや、利用者一人ひとりに寄り添う個別ケア、そして何より「おもてなし」の精神に基づいたホスピタリティの高いサービスが確立されたのです。
様々な分野の国際規格を策定し、その普及を促進することで、世界貿易の活性化に貢献している国際標準化機構(ISO)では、2025年中に介護サービスの質や安全性に関する国際規格を策定する予定ですが、そこでも日本の基準が大きく反映されると期待されています。これは日本の介護サービスが世界標準として認められている証といえるでしょう。介護という「究極のサービス業」も、今や立派な輸出産業になっており、「技術立国ニッポン」の新たな顔といえるのかもしれません。
中国の高齢化は日本を上回るスピードで進行中
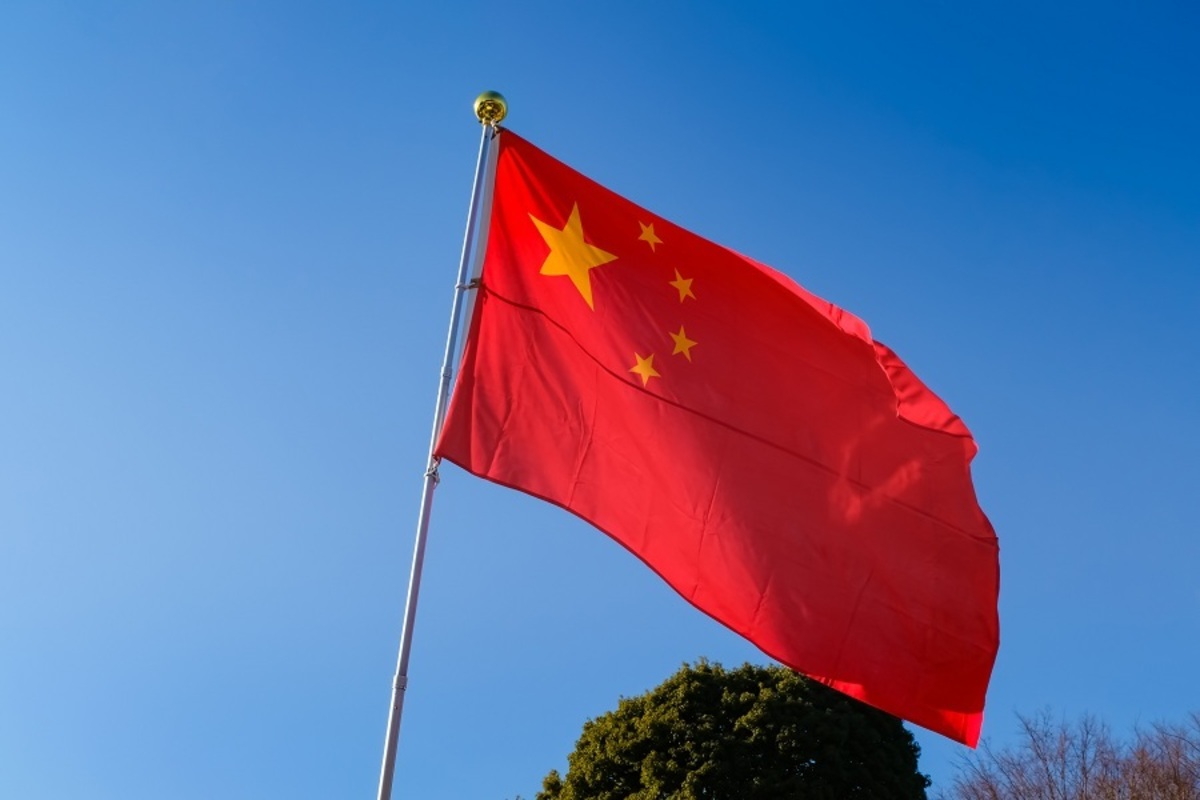
中国の高齢化は、まさに「シルバー・ドラゴン」とでも呼ぶべき勢いで進んでいます。2023年末の時点で、65歳以上の人口は2億1,676万人(全体の15.4%)に達し、国連の予測によれば2050年には30.9%まで上昇するとされています。日本を上回る高齢化のスピードに中国政府も計画的に対応。2013年には「高齢者産業元年」として外資企業を含む民間資本の参入を積極的に奨励する政策を打ち出しました。
ただし、中国の介護事情は日本とは大きく異なります。最も特徴的なのは、在宅介護の比率の高さです。上海市では「9073モデル」(在宅90%、コミュニティ7%、施設3%)、北京市では「9064モデル」を掲げており、日本の在宅6割・施設4割とは対照的です。
その背景にあるのは「養児防老」(子どもを育てて老後に備える)という伝統的な価値観でしょう。中国高齢協会の調査では、87.3%の高齢者が在宅ケアを希望し、介護施設を選んだのはわずか7.7%でした。この文化的背景を理解せずに中国市場に参入すると、思わぬ落とし穴にはまりかねません。
介護サービスは「おもてなし」でQOL向上

日本の介護サービスの最大の特徴は、たんなる「お世話」ではなく「生活の質(QOL)向上」を目指している点でしょう。これは技術的な優位性というより、むしろ「おもてなし」の精神から生まれるサービスの質の違いです。
中国で訪問介護事業を展開するアースサポート株式会社の事例が、この違いを如実に物語っています。同社が上海市で提供している認知症対応のデイサービスは、中国の長期介護保険の適用対象外にもかかわらず、リピート率が非常に高いのです。理由は明快で、通所前後で認知症症状の緩和が実感できるからです。
また、同社の訪問入浴サービスも興味深い事例です。3名の専門スタッフによって介助を行うため、利用料金は高額ですが、利用者の満足度は極めて高いといいます。まさに「高くても価値がある」サービスの典型例といえるでしょう。
中国の高齢者や家族にとって、介護サービスは「目に見える変化」があってこそ価値を感じられるもの。日本式の丁寧なケアや専門的なアプローチは、まさにこのニーズに応える強力な武器になっているのです。
認知症ケアにも「目に見えるサービス」を
中国では2~3年前まで認知症の人への対応といえば精神病院に入院するぐらいしか選択肢がありませんでしたが、メディカル・ケア・サービス株式会社は、中国で計10か所の高齢者向け施設を運営し、特に認知症ケアの分野で独自のポジションを確立しています。同社の中国法人の取締役によれば、中国の介護施設の多くでは、認知症専門フロアと一般フロアのサービス内容に大差がありません。
そこで同社は、現地スタッフに日本のサービス手法を一から教育し、日本に近いレベルのサービスを提供することで差別化を図りました。利用料金は高めに設定しましたが、入居前後の変化を家族に実感してもらうことで、口コミでも良い評判が広がっているといいます。
「入居者の変化を目に見える形で示すことが最重要」という言葉は、中国市場で成功するための金言かもしれません。技術やノウハウだけでなく、それを「見える化」する力が求められているのです。
●福祉用具は技術力と専門資格で勝負
介護サービスだけでなく、福祉用具分野でも日本企業の技術力が光っています。中国では2018年から福祉機器のレンタルサービスの試行が始まり、全国35か所の試行拠点で累計11万3,000点の機器が貸し出され、延べ91万6,800人がサービスを利用しています。
日本製の福祉用具の強みは、「耐久性」と「使い勝手の良さ」です。日本では介護保険制度のもとで長年レンタルサービスが展開されているため、不特定多数の利用者に何度も貸し出されます。そうした環境に適した、組み立てや搬送がしやすく、耐久性に優れた製品の数々は中国市場でも高く評価されています。
興味深いのは、株式会社ヤマシタの取り組みです。同社のスタッフは上海市リハビリ福祉用具協会の専門相談員の資格を取得したうえで、顧客に最適な福祉用具を提案しています。中国では福祉用具の専門知識を持つ人材が少ないため、この資格は大きな差別化要因になっています。
立ちはだかる制度の壁と現地適応の課題

もちろん、中国での事業展開は順風満帆ではありません。最も大きな課題は制度面での違いです。まず、介護保険制度が「道半ば」の状況です。現在49都市で長期介護保険制度が試行されていますが、給付対象者やサービス内容が限定的で、多くのケースで利用者の自己負担が重くなります。日本のように、要介護度に応じて幅広いサービスが補償される制度とは異なっているのです。
また、中国では土地の多くが国有地であるため、外資企業が単独で事業を展開するのには限界があります。その場合、現地企業との合弁が必要になりますが、介護に関する十分な知識やノウハウを持つ中国企業を見つけるのが難しいという問題があります。
さらに、介護施設事業を取り巻くバリューチェーンが、まだ整備されていないことも課題になっています。日本では運営事業者、施工業者、設備業者、調剤薬局などの分業化が進んでいますが、中国ではこうした環境がないため、企業が単独で施設の建設から設備導入、職員採用、営業まで、すべてを手掛ける必要があり、大規模な投資が必要になるのです。
ロングライフグループの中国事業の担当者は、「単に日本のやり方をそのまま導入するのではなく、現場の細かいところから中国の事情に合わせて柔軟に対応しなければならない」と強調します。
世界に広がる「日本品質」の介護サービス

こうした課題を乗り越えながら、日本の介護事業者は着実に中国市場での地歩を固めています。重要なのは、単に技術や設備を提供するだけでなく、「サービスの価値」を現地の人々に実感してもらうことでしょう。
中国の在宅介護大手企業の創業者は、日本に留学して介護を学んだ経験を持ち、同社のサービスに日本のきめ細かい介護や自立支援の理念を取り入れています。全国60以上の都市に280以上のナースステーションを展開する同社の成功は、日本式介護が中国でも通用することを証明しています。
今後、世界的な高齢化の進展とともに「日本品質」の介護サービスへの需要はさらに高まることが予想されています。IoTやAIなどの最新技術と、おもてなしの心に基づくホスピタリティを組み合わせた日本独自の介護ソリューションが、世界各国の高齢者の生活の質向上に貢献する大きなチャンスであり、同時に、日本の介護業界にとって新たな成長の可能性を示す希望の光になるかもしれません。

















